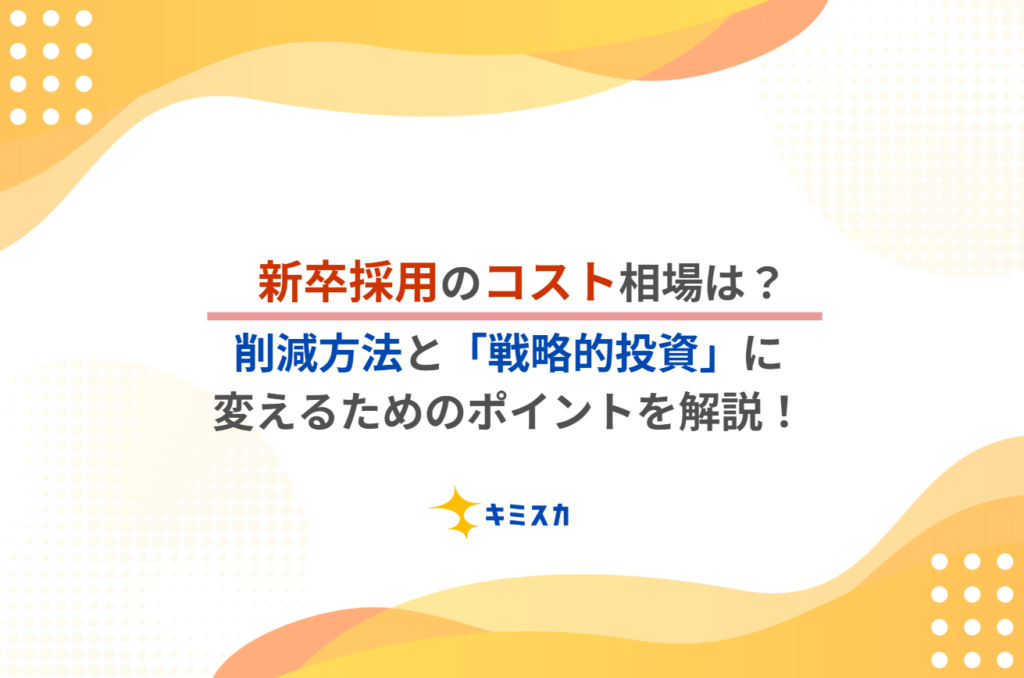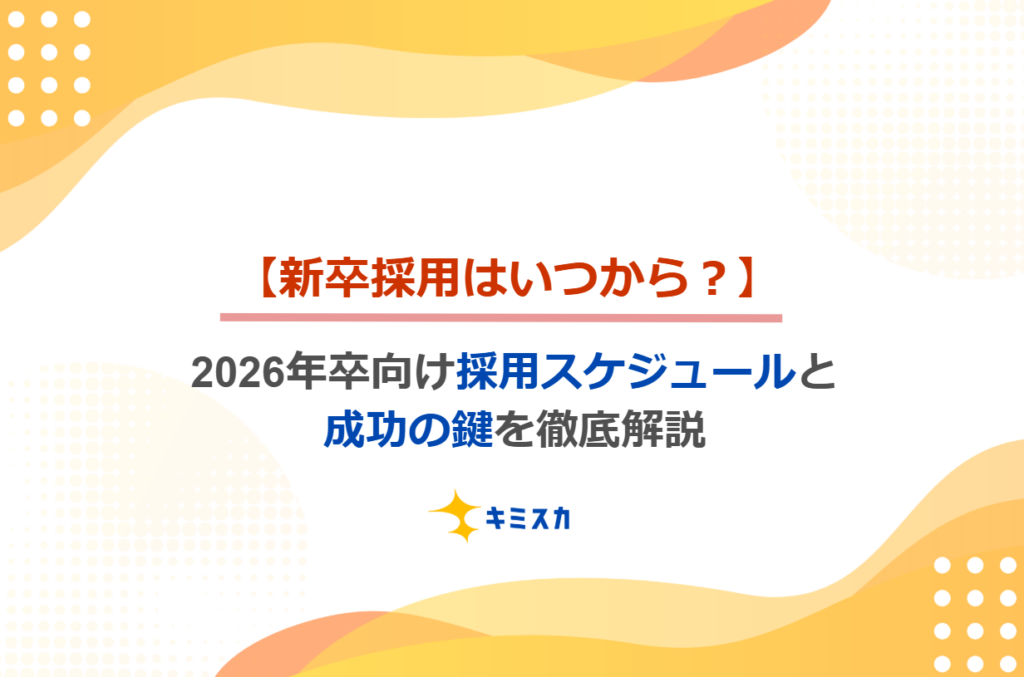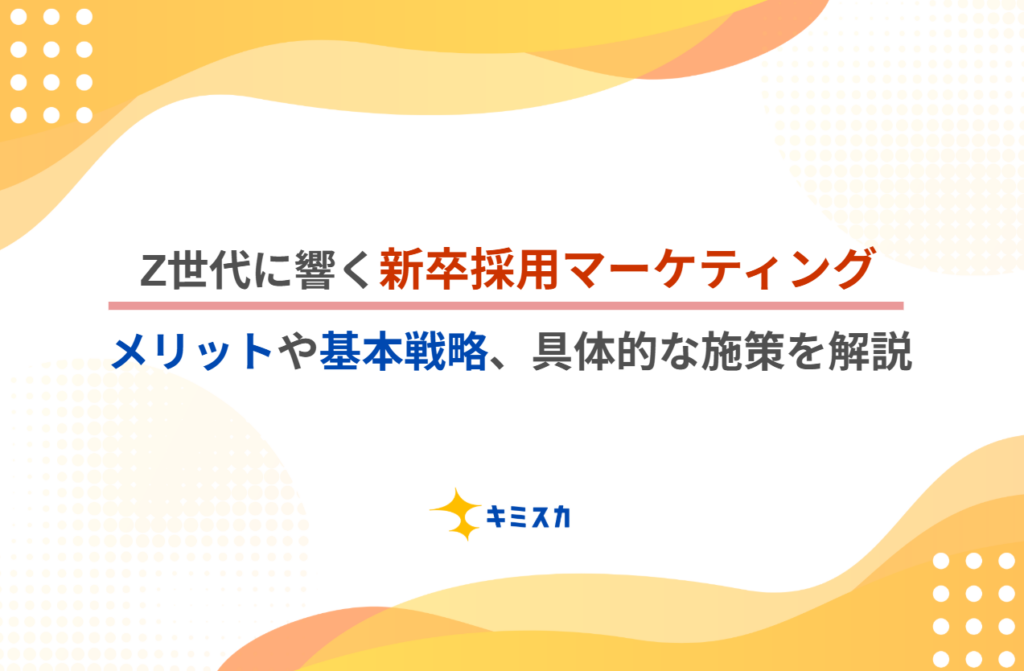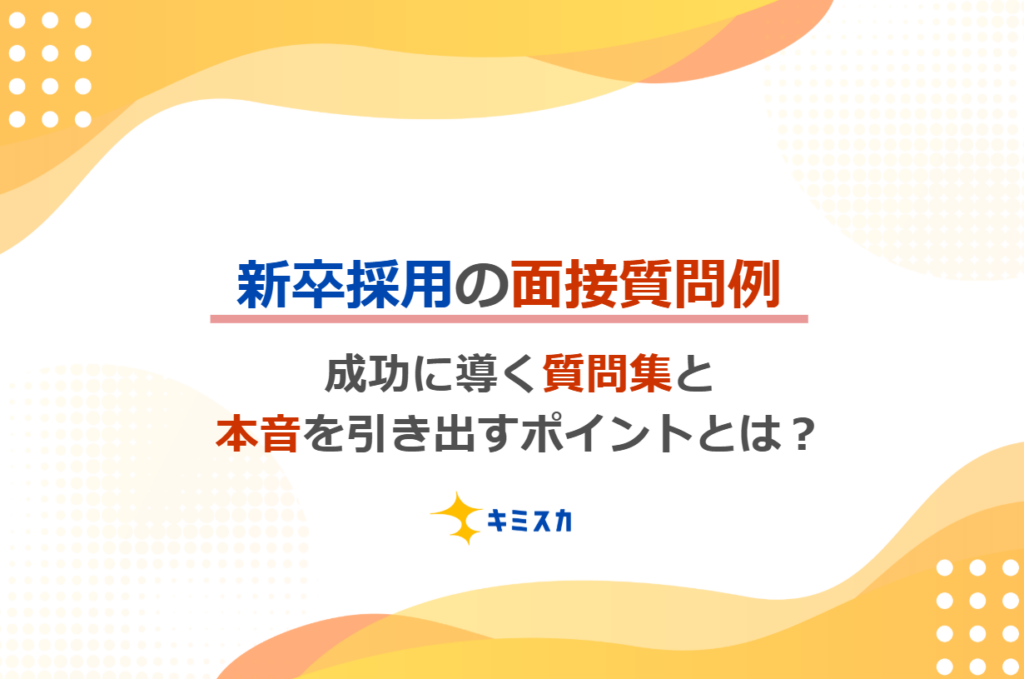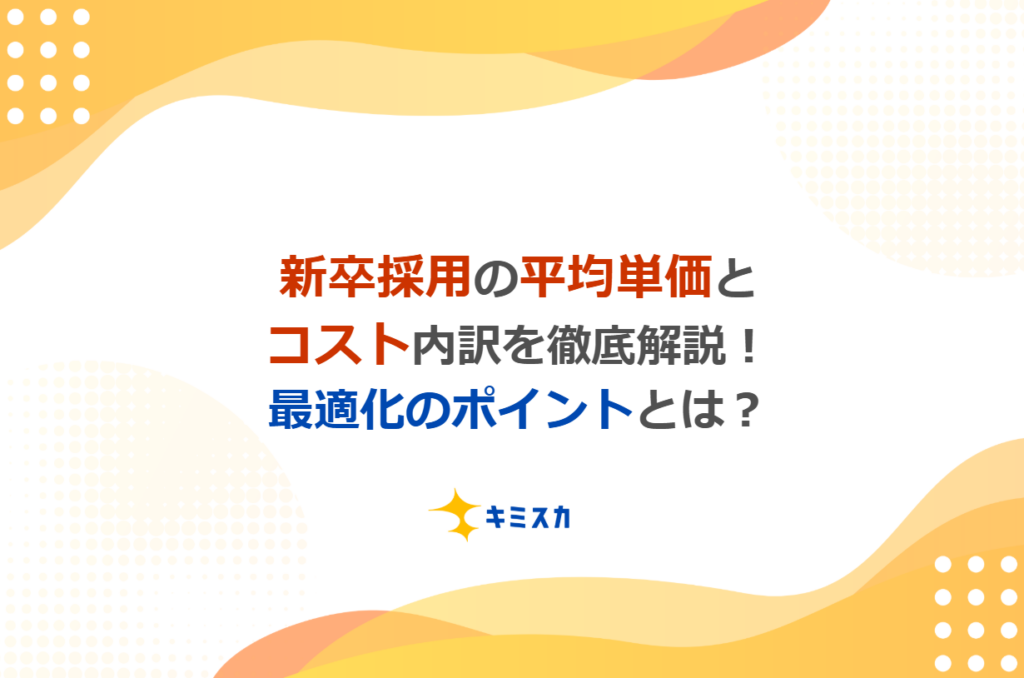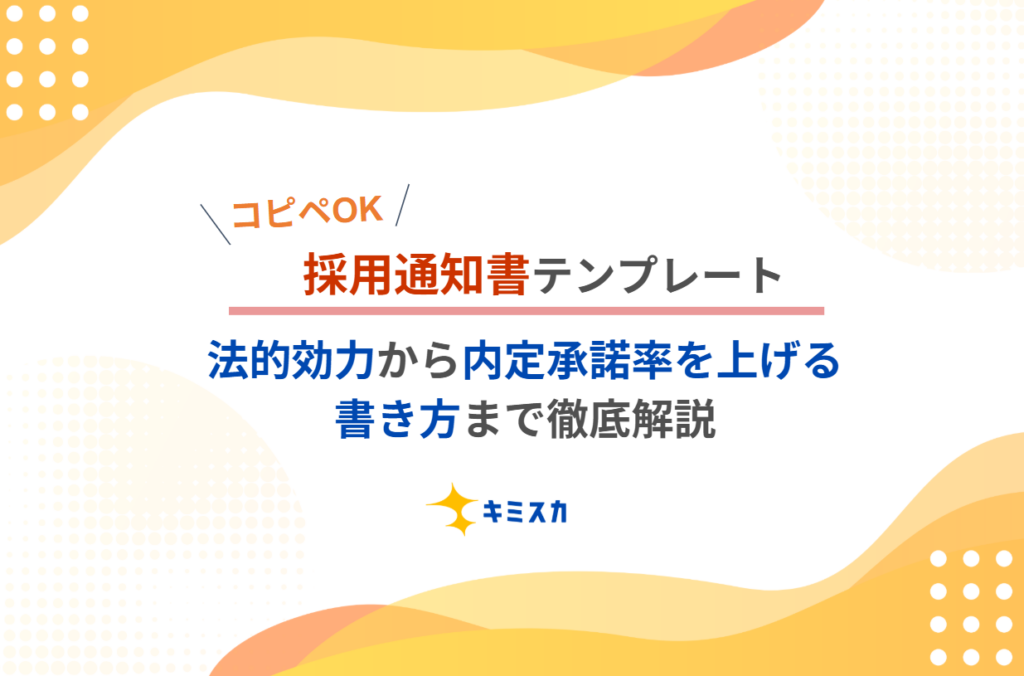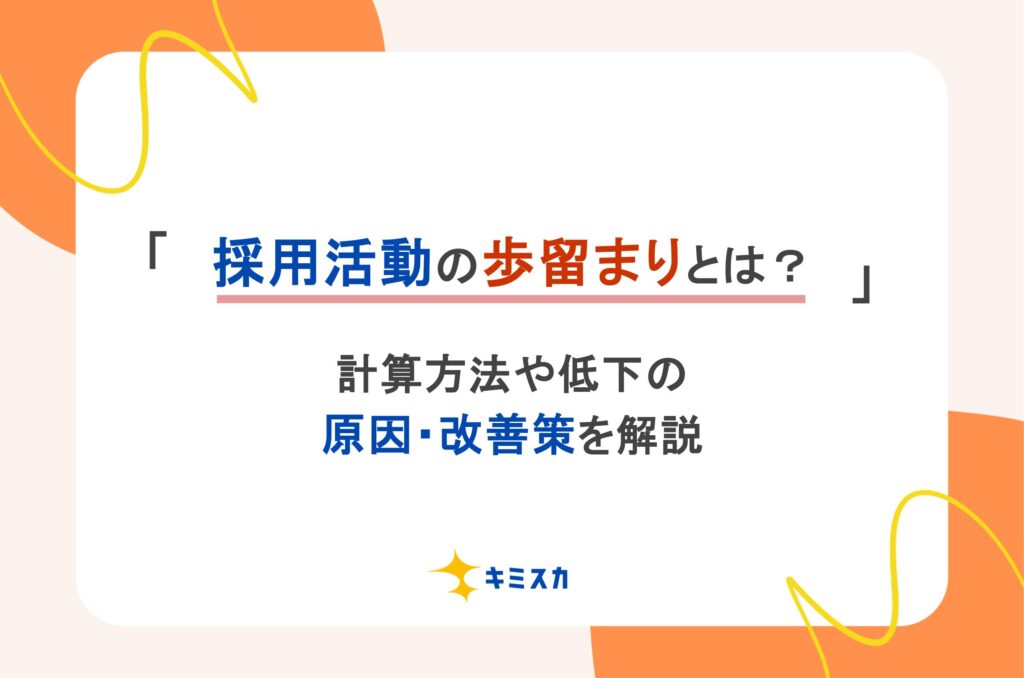
採用活動の現状把握や課題特定に欠かせない指標が「歩留まり」です。歩留まり率が高ければ効率的な採用活動であると判断できますが、低い場合は改善の余地があるかもしれません。
本記事では、採用活動における歩留まりの概要や計算方法をはじめ、歩留まり率が低下する原因や改善策を紹介します。企業の採用活動を成功させるためにも、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。
採用担当者なら知っておきたい「歩留まり」とは?
採用活動における「歩留まり」とは、応募から内定承諾までの採用フローのなかで、応募者が各ステップを進む割合のこと。表現としては、「歩留まり」「歩留まり率」と呼ばれますが、正しく活用できるようそれぞれ意味を把握しておきましょう。
・歩留まり:採用フローのなかで次の過程に進んだ人の割合
・歩留まり率:歩留まりを「%」で表したもの
歩留まり率が高い場合、選考・内定を辞退した人や不合格となった人が少なく、歩留まり率が低い場合は、辞退者や不合格者が多いと判断できます。
ただ、歩留まり率の低下が採用活動の失敗を意味するわけではありません。例えば、内定者の質を重視するためにあえて選考基準を厳しく設定している場合は、歩留まり率が低くなるケースもあります。
歩留まり率をどう評価するかは企業によって異なりますが、採用活動の現状把握や課題特定に役立つ指標であると捉えておきましょう。
採用の歩留まり率を計算する方法
歩留まり率は、以下の式で求めることができます。
「選考通過数」÷「選考対象数」×100
例えば、二次面接で30人中15人が通過した場合は「15÷30×100」となるため、二次面接の歩留まり率は「50%」です。
歩留まり率は採用活動のステップごとに算出するため、計算には「採用フローの洗い出し」「受験者の数」「応募者の数」を把握しておく必要があります。歩留まり率をどこまで詳しく計算するのかは企業ごとの判断に委ねられますが、一例として以下の項目を参考にしてみてください。
【採用過程別「歩留まり率」の計算式】
| 受験率 | 受験者数÷エントリー数×100 |
| 説明会予約率 | 予約者数÷エントリー数×100 |
| 説明会参加率 | 参加者数÷予約者数×100 |
| 書類通過率 | 書類選考通過者数÷エントリー数×100 |
| 面接通過率 | 面接通過者数÷面接受験者数×100 |
| 内定率 | 内定者数÷応募者数×100 |
| 内定承諾率 | 内定承諾者数÷内定者数×100 |
なお、同様の計算式で辞退者数の割合を求めることも可能です。以下の式では、算出した数値が大きいほど選考途中や内定の辞退者数が多いことを示しています。
【辞退者数を求める場合の計算式】
| 途中辞退率 | 途中辞退者数÷応募者数×100 |
| 内定辞退率 | 内定辞退者数÷内定者数×100 |
どの段階で辞退者が出たのかを把握する際は、途中辞退率の計算式を活用してみても良いでしょう。
【新卒・中途】採用における歩留まり率の平均
ここまで採用活動における歩留まりに関する基本情報を紹介しましたが、どの程度の歩留まり率が平均的なのか気になる方もいるでしょう。
そこで、ここからは新卒・中途に分けて歩留まり率の平均を紹介します。あくまでも参考として捉え、自社にとって最適な採用活動を検討してみてください。
新卒採用の歩留まり率の平均
まずは新卒採用の歩留まり率がどの程度あるのか、就職みらい研究所が発表した『就職白書2024』データ集をもとに見てみましょう。
| 平均人数 | 歩留まり率 | |
| プレエントリー | 1770.9人 | - |
| 書類選考 | 281.3人 | 15.88%(選考参加率) |
| 面接 | 136.5人 | 48.52%(書類選考通過率) |
| 内々定・内定出し | 45.2人 | 33.11%(面接通過率) |
| 内定 | 24.4人 | 8.67%(内定率) |
「内定率」と「内定承諾率」の歩留まり率を混同しないように注意しましょう。上記データの場合、内定率は「24.4÷1770.9×100=8.67%」で算出しましたが、内定承諾率は「24.4÷45.2×100=53.98%」となります。
中途採用の歩留まり率の平均
続いて、中途採用における歩留まり率の平均を「株式会社マイナビ 中途採用状況調査2024年版(2023年実績)」のデータをもとに見ていきましょう。
| 平均人数 | 歩留まり率 | |
| 応募 | 77.9人 | - |
| 面接 | 37.8人 | 48.52%(面接参加率) |
| 内定出し | 23.9人 | 63.22%(面接通過率) |
| 内定 | 21.8人 | 27.98%(内定率) |
なお、中途採用の内定承諾率は「91.2%(21.8÷23.9×100)」と、高くなる傾向にあります。中途採用の場合は、希望する職種・企業が明確になっているケースが多くありますが、選考が長引くと他者へ流れてしまう可能性がある点には注意が必要です。
採用の歩留まり低下を招く主な原因6つ
ほかの企業と同じように採用活動を行っていても、採用の歩留まりが低下してしまうケースも少なくありません。もちろん、選考基準を厳しく設定しているために歩留まり率が低くなっていることもありますが、応募者の辞退が多い場合は原因を探り、改善する必要があります。
そこで、ここでは歩留まりの低下につながる主な原因を6つ紹介します。自社に当てはまるものがないか、それぞれ確認していきましょう。
1.就活生へのレスポンスが遅かった
選考の進捗に関する連絡をはじめ、応募者からの問い合わせに対する返信が遅くなると、不信感から選考辞退につながる可能性があります。特に、新卒採用では学生が複数の企業に応募している場合が多く、レスポンスが遅くなることでマイナスの印象を持たれるかもしれません。
例えば、一次面接の結果が出るのに1ヶ月以上もかかると、就活生は「対応が遅い」「選考に落とされたのでは?」と感じてしまうでしょう。もちろん、採用担当者が対応しきれない場合もあるので、人員の補充やレスポンスを早める仕組みづくりを検討したほうが良いかもしれません。
2.内定出しが競合他社よりも遅かった
レスポンスが遅くなるケースと同様に、内定出しが遅くなることで歩留まり率が低下してしまう場合もあります。
人手不足の昨今は人材獲得競争が激化しているため、複数社の内定を獲得している応募者は少なくありません。また、就活生は内定をもらった企業の中から内定承諾先を決めるので、内定出しのタイミングが遅くなる企業は不利になってしまうでしょう。
3.公開情報と実情にギャップがあった
就活は企業側だけが就活生を見極めているのではなく、企業と応募者が互いにマッチするかどうかを確かめています。応募者は企業研究や採用サイトといった公開情報から企業側に対するイメージを持ちますが、会社説明会や面接などを通じてギャップを感じると、選考の途中で辞退することも珍しくありません。
例えば、「リモートワーク環境を整備」と紹介している一方で、従業員のほとんどが出社していると、マイナスの印象につながるでしょう。こうしたギャップがあると、選考途中での辞退だけでなく内定辞退の原因になる可能性もあります。
このように、応募者を集めるために自社のことをよく見せすぎてしまうと、歩留まりが低下しかねません。業務内容をはじめ職場環境や社風など、就活生が魅力に感じるポイントそれぞれ違いますが、公開情報と実情にギャップがある場合は、発信する情報の見直しを検討してみましょう。
4.応募者がミスマッチや不信感を覚えた
公開情報と実情の乖離がなくとも、応募者がミスマッチや不信感から選考を辞退する場合もあります。これは、自社の採用条件に合わない人材が応募してくるケースに見られ、企業の求める人物像が不明確なことが主な原因です。
例えば、企業の求める人物像やスキルと、応募者の能力や希望にミスマッチが生じると、「自分には合わない」と感じ辞退することもあります。また、応募者が面接官の態度や質問内容に不信感を抱くと、「この会社とは合わないかも」と選考辞退するケースも少なくありません。
企業によっては面接に慣れていない人が面接官を務めるケースもありますが、応募者と丁寧なコミュニケーションを徹底することを意識することが重要です。
その「ミスマッチや不信感」は、採用プロセス全体の設計に根本原因があるかもしれません。候補者との全ての接点で一貫した価値を提供し、信頼を勝ち取るための「全体設計」の考え方を以下の資料で解説します。
5.応募者が家族や友人から辞退を勧められた
新卒の就活や転職活動では、応募者が家族や友人に意見を求めることは珍しいことではありません。そこで、企業に関するネガティブな要素があると、周囲から「そこはやめたほうがいい」と促されることがあります。例えば、福利厚生や待遇を他社と比較されたり、インターネット上の口コミを見てネガティブなイメージを持たれたりすると、家族や友人が辞退を勧めることもあるでしょう。
もちろん、最終判断を下すのは応募者本人ですが、企業はこうした周囲の影響を受ける可能性があることを把握しておくことが大切です。そのうえで応募者をはじめ、家族や友人が安心できる情報を発信するなどの対策を講じましょう。
6.自社の魅力が伝わっていなかった
労働時間が短かったり有給取得率が高かったりと、労働者にとって魅力的な要素を持つ企業であったとしても、その魅力が伝わらなければ応募者の関心を引くことは難しいでしょう。特に新卒採用では学生が多くの企業情報に触れるため、特徴やインパクトのある情報を発信しなければ、競合に流れてしまう可能性があります。
自社だけの魅力は応募者にとっての志望動機にもなり得るため、どういった魅力があるのか整理することが大切です。そして、採用ページやSNSなどを活用し、企業の雰囲気や強みを視覚的に伝えることで、歩留まり率の向上を図れるでしょう。
採用の歩留まりが低下しやすいフェーズと対策法
採用活動は会社説明会や書類選考、面接などのフェースがありますが、特に歩留率の低下に注意すべきフェーズがあります。解決すべき課題点は企業ごとに異なりますが、ここでは歩留まりが低下しやすいフェーズと対策法を確認していきましょう。
エントリー~説明会参加
まずは、応募者がエントリーしたにも関わらず、説明会の予約や参加へと進まないケースです。たしかに就活生にとってはエントリー自体のハードルが低いため、少しでも興味のある企業があれば複数社にエントリーすることも少なくありません。
歩留まりが下がってしまう理由としては、他社と比較して魅力に欠けていたり、説明会の案内が遅かったりしたために、他社に流れてしまうことも考えられます。
このフェーズで歩留まりが低い場合は、応募者が参加しやすい時間帯に説明会を開催したり、応募者の興味を引く案内文を送ったりといった対策を検討してみてください。もしも、説明会予約が入っているにも関わらず、当日の参加率が低い場合は、前日にリマイドメールを送付して参加を促しても良いでしょう。
書類選考~1次面接
続いて、書類選考を通過してから一次面接にかけてのフェーズも歩留まりが下がりやすいです。書類選考は面接ほどハードルが高くないために多くの応募者が書類を提出しますが、書類選考を通過してから本格的に考える人もいるため、歩留まり率が低下することがあります。
このほか、書類選考の結果が出るまでに時間がかかってしまうと、応募者の興味が薄れてしまう可能性もあるでしょう。応募者にとって面接は事前準備が必要なので、このフェーズの歩留まり率を改善するのであれば、迅速な連絡と面接日程の柔軟さを意識するのがおすすめです。
内定出し~入社
内定出しから入社にかけても歩留まり率が低下しがちなフェーズです。内定辞退者が出たことで選考活動の再開が必要となるケースもあるため、人事担当者にとっては特に気になるポイントでしょう。
優秀な人材ほど複数社の内定を獲得している可能性が高いため、歩留まり率が低くなってしまうのは仕方のないことだと考えるかもしれません。しかし、このフェーズで歩留まりが低下していても改善の余地があります。競合他社にはない魅力をアピールするほか、内定者向けの連絡やイベント開催を行うなど、内定者へのフォローを十分に行うことが大切です。
内定辞退の根本対策は、内定後のフォローだけでは不十分です。応募から内定まで、候補者の意欲を育て続ける一貫した「体験」を設計しませんか?そのための戦略と戦術をこの一冊に凝縮しました。
採用の歩留まりを改善するためのポイント
最後に、採用の歩留まりを改善するために押さえておきたいポイントを9つ紹介します。
・採用活動の期間を短くする
・企業が発信する情報を見直す
・面接の時間・方法は柔軟に行う
・面接官の教育を行う
・内定者には手厚いフォローを行う
・母集団の質にこだわる
・採用手法を見直す
・採用活動を通じて動機付けを行う
・学生との接点を増やす
歩留まり率を改善させることで採用活動が成功に近づくケースもあるため、人事担当者はここで紹介する内容を参考にしてみてください。
採用活動の期間を短くする
新卒採用の場合は1年近く採用活動を行うケースも珍しくありませんが、採用活動を行う期間は企業によって異なります。ただ、選考の期間が長すぎてしまうと、応募者が他社の内定を獲得した際に選考を辞退する可能性があるため注意が必要です。
そこで、選考期間を短縮できないか検討してみましょう。例えば、各選考の期間を見直して迅速に対応できる仕組みを整えたり、面接の日程をまとめて設定したりすることで、選考期間を短縮できるかもしれません。また、合否の結果が出るまでに時間がかかっている場合は、評価プロセスの効率化を図ってみても良いでしょう。
企業が発信する情報を見直す
企業が発信する情報を見直すことで、採用における歩留まりの低下を改善できる場合もあります。というのも、応募者は企業からの情報をもとに自分とのマッチ度を確かめたり、志望度を高めたりするため、魅力的な情報を発信することで選考途中の離脱を防げます。
企業の特徴や働く魅力が具体的に伝わるものであれば、応募者の関心を引くことができるでしょう。例えば、採用サイトやSNSで先輩社員の声や業務内容をまとめたコンテンツを発信したり、会社説明会で仕事のやりがいや職場の雰囲気を現場社員から伝える時間を設けたりと、自社の魅力を伝える施策を検討してみてください。
面接の時間・方法は柔軟に行う
新卒・中途に関わらず、面接の時間や方法に柔軟性を持たせることも重要なポイントです。というのも、応募者は仕事や学業と並行しながら選考に臨んでいるケースも多いため、面接の日時によっては選考辞退を判断する可能性もあります。
また従来の面接方法では、面接前後のフェーズで歩留まりが低くなったり、優秀な人材を取りこぼしたりすることもあります。オンライン面接の導入をはじめ、平日の夜や週末に面接の枠を設けるなど、応募者が面接を受けやすい体制を整えてみましょう。
面接官の教育を行う
応募者のなかには、面接官とのやりとりを通じて企業に対する不信感を抱くケースも少なくありません。特に不適切な質問をしたり横柄な態度を取ったりすると、ネガティブな印象を抱いて選考辞退することもあります。そのため、面接官を務める人には教育実施や事前の情報共有などを行いましょう。
面接官の教育とあわせておすすめしたいのが、面接官マニュアルの作成です。面接時のルールや質問内容をはじめ、評価項目や合格基準を明記しておくことで、初めて面接官を務める人でも円滑に面接を進められます。
以下の記事では、面接官マニュアルの必要性や記載すべき項目、具体的な作り方などをまとめています。採用活動の効率化や面接の平準化を図りたい場合は、ぜひ参考にしてみてください。
内定者には手厚いフォローを行う
内定を出したにもかかわらず、内定承諾や入社までの時期に離脱されるのは、企業にとって大きな損失となります。内定者へのフォローが不十分だと、他社に流れたり入社意欲を失ったりする可能性があるため、特に注意が必要です。
内定者向けのフォローイベントを定期的に開催して、企業・先輩社員との接点を増やす、メンター制度を導入して内定者が気軽に相談できる環境を整えるなどの施策を検討してみましょう。
母集団の質にこだわる
多数の応募がある一方で、選考の通過率が悪いために歩留まりが低い場合は、母集団の質にこだわりましょう。良質な母集団形成に取り組めば、採用活動の効率化や入社後のミスマッチ防止などにつながります。また、マッチ度の高い人材が多く集まるため、応募者の選考通過率が高まるでしょう。
母集団の形成は、採用活動の目的を明確にするほか、ターゲットの設定や採用計画の立案などが必要です。各プロセスの詳細は以下の記事で詳しくまとめているので、母集団形成にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
質の高い母集団は、待っていても集まりません。ターゲットの心を掴み、惹きつけるための採用活動を「全体設計」する視点が不可欠です。その具体的な手法を以下の資料で詳しく解説しています。
採用手法を見直す
歩留まりが低い場合は採用手法を見直してみるのも一つの手です。近年は、以下に挙げたようにさまざまな採用手法があるため、どれが効果的なのかわからない人事担当者も少なくないでしょう。
・就活サイト
・就職イベント
・人材紹介
・ダイレクトリクルーティング
・リファラル採用
・SNS採用 など
上記のなかで歩留まり改善におすすめな採用手法は、ダイレクトリクルーティングです。学生からの応募を待つ従来の方法とは異なり、自社の求める人材に対して企業側からアプローチできるため、歩留まりの改善につながります。
採用活動を通じて動機付けを行う
応募者の入社意欲が高いほどに選考を辞退する可能性が低くなるため、採用活動を通じて動機付けを行うことも歩留まり改善につながります。
例えば、面接中に応募者のキャリアプランや価値観をヒアリングし、それに合致した自社の魅力を伝えてみても良いでしょう。また、採用サイトや会社説明会などでは広く浅い情報発信になる場合もあるため、マッチ度の高い人材に対して面談や座談会の場を設けるなど、個人にアプローチをかけるのもおすすめです。
学生との接点を増やす
新卒採用では特に学生との接点を増やすのがおすすめです。なぜなら、学生は企業との接点が多くなるほどに入社後のイメージを具体的に持ち、入社意欲の向上につながるためです。
インターンシップで実務や職場環境を体験してもらうほか、オンラインイベントを開催して広く交流しても良いでしょう。このほか、学生の相談窓口を設けてコミュニケーションを図るのも効果的です。
歩留まりを分析して効果的な採用活動を行おう
採用活動における歩留まりは、応募から内定承諾までのステップごとに何人が進んだのかを把握できる指標のこと。選考の厳しい企業では歩留まりが低くなることもありますが、選考辞退により歩留まりが低くなっている場合は、改善の余地があるかもしれません。
歩留まりを確認することで、採用活動の効率化や課題点の把握を行いやすくなるため、採用活動をブラッシュアップしていくためには欠かせない視点といえるでしょう。
本記事で紹介したように、歩留まりの改善にはさまざまな方法がありますが、採用手法を見直す場合はダイレクトリクルーティングサービス「キミスカ」を活用してみてください。認知度が高くない企業であっても質の高い母集団を形成でき、自社とマッチする人材の抽出から内定者フォローまで幅広い機能を備えています。
このほか、採用活動に関するお困りごとがございましたら、ぜひキミスカまでお問い合わせください。