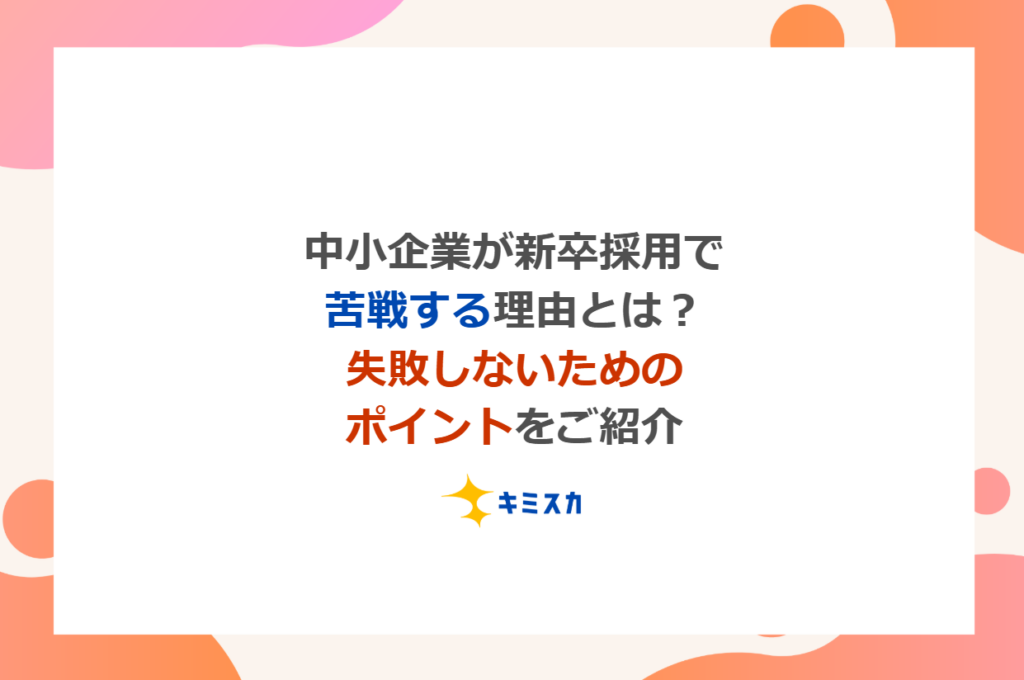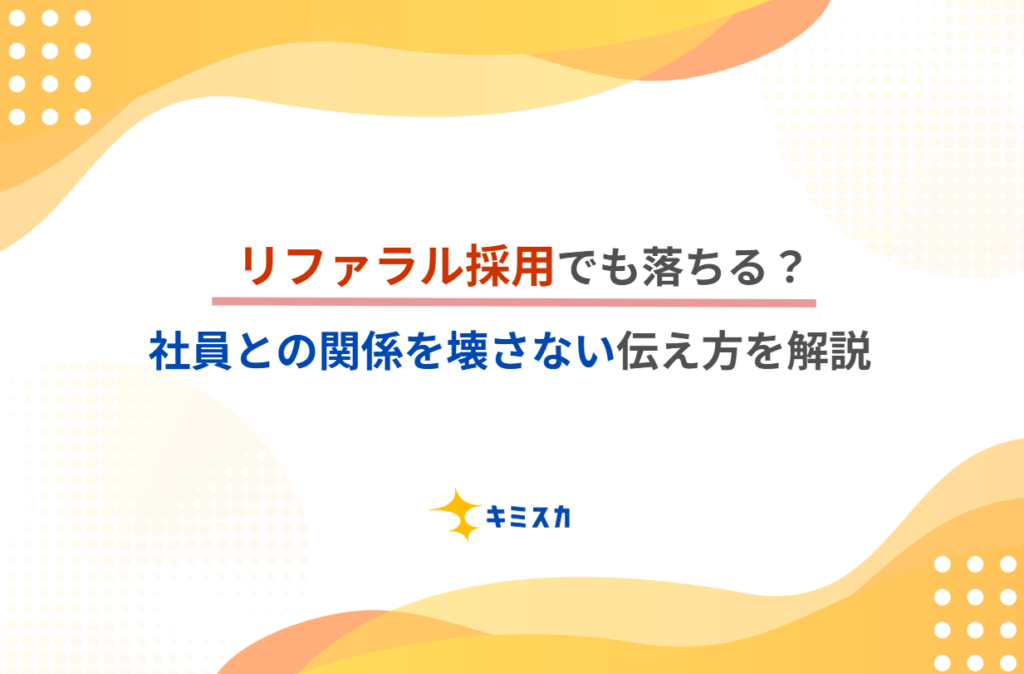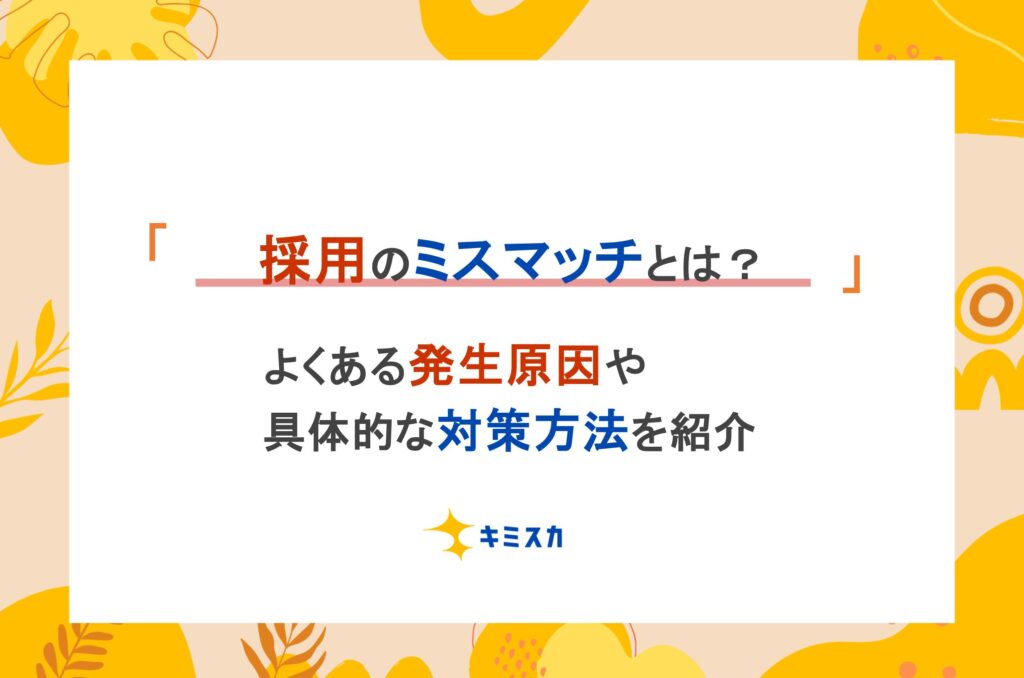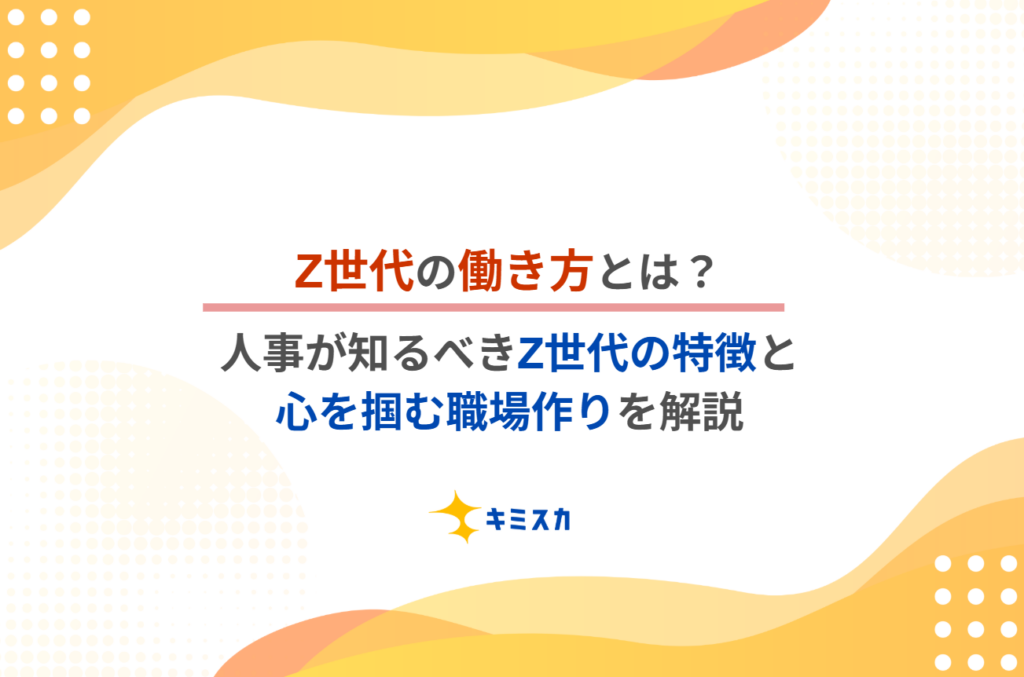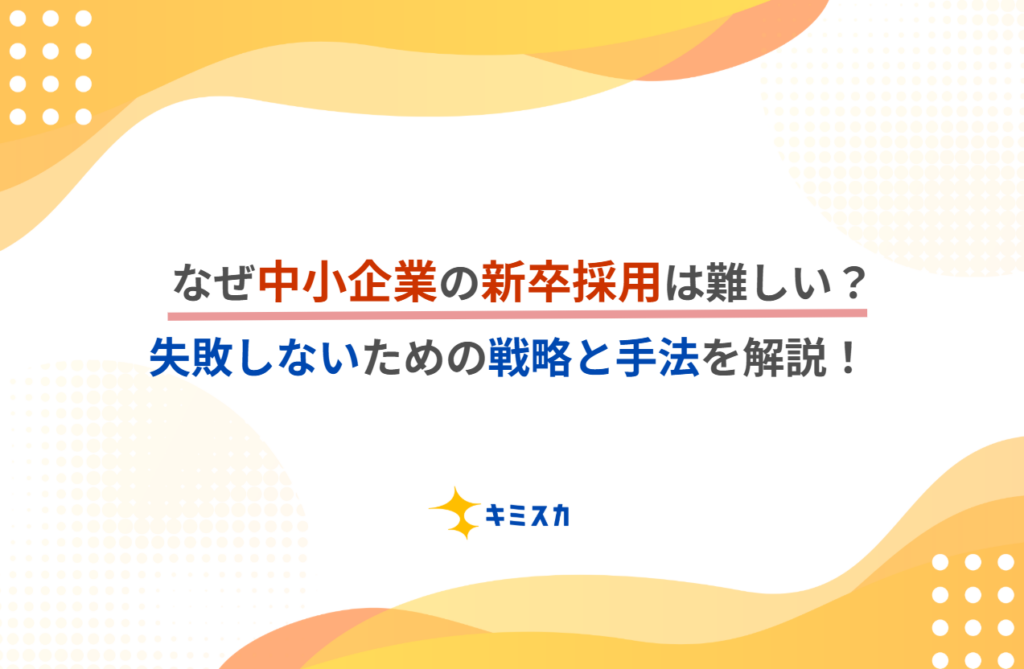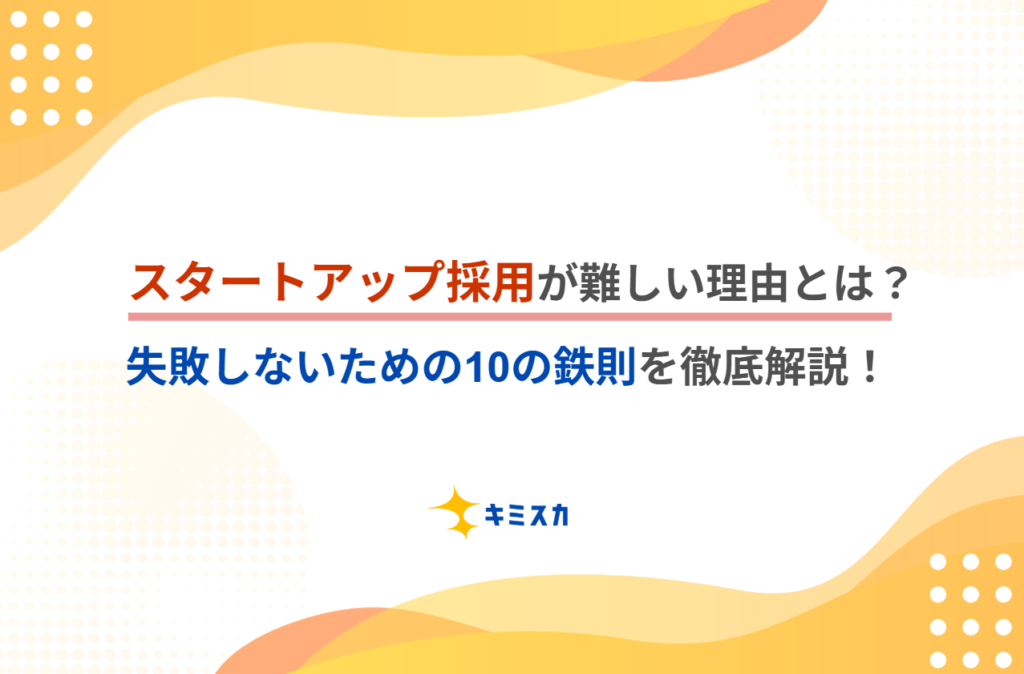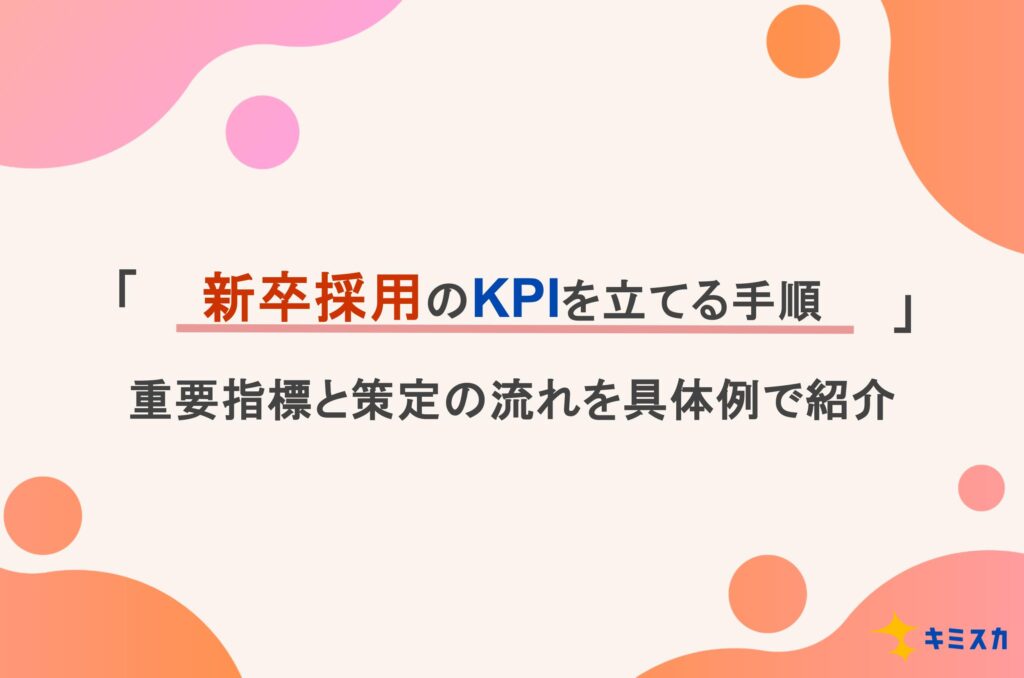
KPIは、最終的な目的(KGI)を達成するために必要となる中間目標です。新卒採用では、KPIを適切に設定することで、採用活動の成果を最大化し、効率的な目的達成を実現しやすくなります。
この記事では、新卒採用におけるKPIの重要性や設定手順、具体的な指標の一例をわかりやすく解説します。事例や実践的なヒントを押さえて、自社の採用活動に役立てていきましょう。
採用活動のKPIとは
採用活動のKPI(Key Performance Indicator)とは、採用目的を達成するために必要となる中間目標です。採用活動の目的に加えてKPIも設定することで、採用プロセスを効率的に管理でき、活動の進捗を評価したり軌道修正を行ったりすることが可能になります。
まずは、KPIに関する基本的な知識を身につけていきましょう。
KPIとKGIの違い
KPI(Key Performance Indicator)とは、特定の目的に対する成果を測る指標で、短期的な進捗を把握するのに適しています。一方でKGI(Key Goal Indicator)は、最終的な目的を指しており、長期的な成功の達成度を示す指標です。
これだけを聞くとわかりにくいと感じるかもしれませんが、KGIを達成するために必要な行動や成果を定めたものがKPIだと考えておくとよいでしょう。例えば、KGIが「年度末までに〇名採用する」ことである場合、「1か月間で面接を〇回実施する」「書類応募数○件」などがKPIの一例として挙げられます。
KPIの具体例
新卒採用における具体的なKPIとして、以下のような指標が考えられます。
・説明会参加者数
・一次面接通過率
・内定承諾率
・採用コスト(1人当たり)
・内定者の定着率
上記のような指標を活用することで、採用活動のパフォーマンスを可視化し、目的達成に向けた最適な行動を取れるようになります。
ただし、採用活動の目的や採用手法によって必要になるKPIの指標は大きく異なります。新卒採用で重要なKPIについては後述するので、自社に適したKPI設定に活かしてみてください。
採用活動でKPIを設定するメリット
採用活動でKPIを設定すると、以下のようなメリットが得られます。
・採用活動の進捗を管理できる
・採用活動の成果を評価・改善できる
・社内で連携しやすくなる
ここでは、各メリットの詳細を見ていきましょう。
採用活動の進捗を管理できる
KPIを設定しない場合、「このまま進めて目的を達成できるのか」「どれくらい目的に近づいているのか」を把握することができません。
特に、新卒採用ではエントリー受付や説明会実施、面接選考、内定出しなど複数のプロセスが同時進行します。そのため、進捗を管理するための指標をいくつか用意しておかなければ、採用が計画通りに進んでいるのかを把握することが難しくなるのです。
採用活動を計画的に進めるには、各プロセスの進捗状況を管理することが欠かせません。KPIを設定して進捗を「見える化」することで、現状と目的との乖離を把握することが大切です。
採用活動の成果を評価・改善できる
KPIを活用することで、採用活動の各ステージでの成果を正確に把握できるようになります。その結果、施策の成果を評価したり改善策を立案したりしやすくなるというメリットが生じます。
例えば、面接通過率が低いことがわかれば、「応募者の選考基準を見直す」という具体的な改善策が見えてくるかもしれません。こうした評価と改善のプロセスを繰り返すことで、採用活動の精度を向上させられるのです。
もしKPIの数値が悪化しているなら、根本の原因は採用活動の「設計」そのものにあるかもしれません。小手先の改善ではなく、採用プロセス全体を最適化する「全体設計」の考え方を、以下の資料でご確認ください。

社内で連携しやすくなる
複数の部門が採用活動に関わる場合、各部門が共通の目標を持っていなければ、進捗が滞ったりすれ違いが起きたりする可能性があります。
一方で、明確かつ小刻みに目標を設定しておけば、各部門が何を目指すべきかを明確に認識できるようになります。KPIをもとに目的や行うべきことを分解していくことで、各部門の役割や目指すべき成果が見えてくるでしょう。
さらに、進捗状況を数値で共有すると、部門間でのコミュニケーションを活性化できるというメリットもあります。部門を超えた協力体制が構築されれば、採用活動全体の効率化が目指せるでしょう。
新卒採用のKPIを設定する手順
新卒採用のKPIは、以下の手順で設定できます。
1.KGIを決める
2.歩留まり率を把握する
3.採用チャネルごとに採用戦略を立てる
4.KPIツリーを作成する
5.設定したKPIを検証する
各プロセスの詳細について説明します。
1. KGIを決める
KPIを設定する前に、まずKGI(Key Goal Indicator)を明確にしておきましょう。KGIは、採用活動全体の最終目的を示すものです。「年度末までに新卒採用で30名の内定者を確保する」など、具体的かつ測定可能な内容にすることが大切です。
KGIをもとに各プロセスで必要になる成果(KPI)を設定することで、一貫性のある採用計画を立てやすくなります。KPIはKGIに大きく左右されるので、慎重に設定していきましょう。
そのKGI達成への道筋を、一貫したストーリーとして描き出すのが「全体設計」です。
感覚的な採用活動から脱却し、戦略的にゴールを目指すための設計図を、この資料で手に入れませんか。

2. 歩留まり率を把握する
採用活動を成功させるためには、各プロセスの歩留まり率を正確に把握することが欠かせません。歩留まり率とは、特定のプロセスから次のプロセスへ進む応募者の割合を示す指標で、以下の計算式で算出されます。
| 歩留まり率 (%)=(次のプロセスに進んだ人数÷現在のプロセスの人数)×100 |
例えば、説明会に100人が参加して、そのうち50人がエントリーシートを提出した場合、歩留まり率は「(50÷100)×100=50%」ということになります。同じように、各プロセスでの歩留まり率を計算していくことで、現実的な数値目標を設定しやすくなります。
歩留まり率は、一般的な業界データを参考にすることも可能です。しかし、KPIの精度をより高めたい場合は、自社の過去の採用データをもとに算出することがおすすめです。
3. 採用チャネルごとに採用戦略を立てる
複数のチャネルを活用して採用活動を進める場合は、それぞれの特性に応じた戦略を立てることが大切です。
例えば、大学と提携して採用活動を行う場合は、ターゲット大学の選定や訪問計画を具体化し、現地説明会の集客を行わなければいけません。一方、求人広告やSNSを活用する場合は、ターゲット層の行動データを活用して最適なタイミングで情報を発信することで、エントリー数の最大化を目指す必要があります。
このように、採用チャネルによって必要なアクションや予算、最適なKPIは大きく異なるのです。そのため、チャネル別に採用戦略を立てることが、リソース配分の最適化や採用効率の向上につながります。
4. KPIツリーを作成する
KPIツリーとは、採用活動の目的(KGI)を分解し、各ステージで必要になる具体的な行動やプロセスを可視化した図のことです。歩留まり率とチャネルごとの採用戦略をふまえたうえで、KPIツリーを作成していきましょう。
例えば、「内定者10名」というKGIに対して「最終面接参加者20名」というKPIを設定したとします。KPIツリーでは「最終面接参加者20名」というKPIもさらに分解して、「インターンシップ経由10名」「二次面接経由10名」といったように、KPIを木の枝葉のように段階的に展開していくのです。
ポイントは、分解したKPIを具体的なタスクに落とし込むことです。アクションと数値目標を明確化し、枝葉の末端から目標を達成していくことで、最終的にKGIの達成につなげられます。
5. 設定したKPIを検証する
KPIを設定したあとは、「SMARTの法則」にもとづいて妥当性を検証していきましょう。SMARTの法則は、設定したKPIが具体的かつ達成可能な目標であるかを確認するための判断基準となるものです。
具体的に、以下のような視点で評価を行っていきます。
| 項目 | 説明 | 具体例 |
| Specific(具体的) | 目標が具体的で、誰が何をするべきかが明確か | 「説明会参加者数を100名にする」→「5月中に〇〇大学で説明会を実施し、100名の参加者を確保する」 |
| Measurable(測定可能) | 成果が数値やデータで測定可能か | 「エントリー数を増やす」→「エントリー数を前年比20%増加させる」 |
| Achievable(達成可能) | 実行可能で現実的な目標か | 「半年で内定者を100名確保する」→「12か月で内定者を100名確保する」 |
| Relevant(関連性がある) | 採用活動全体の目的に関連しているか | 「採用ページの閲覧数を増やす」→「閲覧数を増加させ、エントリーに結びつける」 |
| Time-bound(期限が明確) | 期限が設定されており、目標達成までの期間が明示されているか | 「参加者数を増やす」→「6月末までに説明会参加者数を100名にする」 |
このようにSMARTの法則を基準にKPIを見直すことで、採用活動の目標を現実的かつ成果に直結するものにブラッシュアップできます。採用活動開始後も、この基準に沿って定期的に検証を行い、必要に応じてKPIを修正・調整していくことが大切です。
【段階別】新卒採用で重要になる主要なKPI
新卒採用では、具体的にどのようなKPIを用いて進捗や成果を管理していけばよいのでしょうか。ここでは、新卒採用で重要になる主要なKPIを段階別に紹介します。
エントリー
エントリー段階では、学生の興味・関心や行動を評価する指標の活用がおすすめです。
・説明会予約率:案内を受けた学生のうち、説明会を予約した割合
・説明会参加率:予約した学生のうち、実際に説明会に参加した割合
・プレエントリー数:企業に対して興味を示した学生の数
・エントリー数:実際に応募手続きを行った学生の数
・有効応募率:エントリー数のうち、必要な応募条件を満たしている学生の割合
この段階では、企業に対する学生の関心度合いやエントリー意欲を把握することが重要です。上記のような指標を用いることで、採用広報や母集団形成が成功しているかを評価しやすくなります。
選考
選考段階では、応募者の進捗や通過率を管理して、効率的に選考できているかを評価する指標の活用がおすすめです。
・書類提出率: エントリーした学生のうち、書類を提出した割合
・書類選考通過率: 提出された書類のうち、次のステージに進んだ割合
・面接設定率: 書類選考通過者のうち、面接の日程を設定した割合
・面接参加率: 面接を設定した学生のうち、実際に参加した割合
・通過率: 各選考ステージ(一次面接、最終面接など)を通過した割合
選考段階では、応募者の質を高める施策や選考プロセスの効率化が求められます。特に重視したいのが、「通過率」です。この指標を用いることで、選考基準や選考手法の課題発見・改善が可能になります。
内定
内定段階では、学生の意思決定や採用活動の成果を測る指標を活用しましょう。
・内定率: 最終選考を通過した学生のうち、内定を出した割合
・内定承諾率: 内定を提示した学生のうち、実際に承諾した割合
・内定辞退率: 内定提示後に辞退した学生の割合
・入社率: 内定を承諾した学生のうち、実際に入社した割合
ここで重要になるのが、データを活用しながら内定辞退の理由を分析して、入社率向上に向けた改善を行うことです。自社の課題を発見できれば、競合企業との差別化や学生の満足度向上を実現するヒントが得られます。
採用後
採用活動は、「学生が入社すれば終わり」ではありません。採用後も以下のような指標を用いて、採用人材や採用活動全体の質を評価することが大切です。
・早期離職率: 入社後3年以内に離職した新卒社員の割合
・採用成功率: 目標人数に対してどれだけ自社が求める人材を採用できたかを示す指標
・平均選考期間: 応募から内定に至るまでの平均的な期間
・チャネル別応募者数・内定率: 各採用チャネルからの応募者数と内定獲得率
・歩留まり率: 各選考ステージ間での移行率
採用後のデータ分析は、次回以降の採用活動の改善に直結します。長期的な視点で採用活動を振り返ることで、より採用戦略をブラッシュアップしていけるでしょう。
コスト評価
次回以降の採用活動のリソース配分を最適化するために、コストに関する以下の指標も活用しましょう。
・採用チャネルごとの費用対効果: チャネルごとにかけたコストと成果を比較
・応募単価: 応募者1人あたりの平均コスト
・1人あたりの採用単価: 内定者1人あたりの平均コスト
コスト評価のデータが得られたら、できるだけ費用対効果の高いチャネルや施策にリソースを集中させましょう。効率的な予算配分が、採用活動全体の効率アップにつながります。
新卒採用のKPI設定を成功させるポイント
新卒採用のKPI設定を成功させるために、以下のポイントを意識しましょう。
・KPIに優先順位をつける
・達成期限を設ける
・リアルタイムで管理する
・KPI達成・未達成の要因を分析する
・必要に応じて見直す
どのようなことなのか、詳しく説明します。
KPIに優先順位をつける
企業ごとに採用目的が大きく異なるのと同じように、重要なKPIは一社一社異なります。また、KPIが多すぎると管理の負担が増え、効果的な進捗管理が難しくなる可能性があります。そのため、自社のKGIに直結するKPIを絞り込み、優先順位をつけながら活用することが大切です。
例えば、大量採用を目指すなら「エントリー数」や「選考時の通過率」、少数精鋭なら「有効応募率」や「採用成功率」を重視するとよいかもしれません。採用チーム全体でKPIの優先順位を共有し、重要な指標にリソースを集中させることで、効率的な採用活動を実現しやすくなるでしょう。
達成期限を設ける
KPIを設定するときは、数値目標だけでなく「いつまでに何を達成するのか」も明確にしておきましょう。具体的な期限がなければ、進捗管理が曖昧になり、採用活動のペースが乱れる可能性があるためです。
例えば、「今月末までにプレエントリーを50件獲得する」といった期限付きの目標を設定しておくと、達成度合いを把握しやすくなります。このように期限を決めておくことで、スケジュールの優先順位が明確になり、必要なリソースやタスクを適切に管理できるようになります。
リアルタイムで管理する
KPIの進捗はプロセスが終わったあとではなく、常時管理しましょう。リアルタイムで進捗を把握することで、いち早く問題を発見でき、その場で改善できるためです。
例えば、説明会の開催が終わってから「今回は参加者が予定より少なかったな」と分析しても、あとから状況を好転させることはできません。一方で、参加受付時にリアルタイムで申し込み状況を把握しておけば、「急いで広告を配信しよう」「SNSで告知しよう」といった対策を講じることが可能となります。
素早く課題の発見と改善を繰り返すことで、着実に採用活動のKGIに近づけるようになるのです。
KPI達成・未達成の要因を分析する
KPIを評価するときは「目標を達成できた・できなかった」だけでなく、その要因も一緒に分析しましょう。
目標を達成できた場合は、成功の要因を特定し、次回の採用活動に活かします。一方で、達成できなかった場合は、計画や施策にどのような課題があったのかを深掘りして、改善策につなげていきます。
KPIを管理・評価するときに最も重要なのは、「なぜその結果になったか」を知ることです。結果と要因をセットで把握することで、自社にとっての「採用活動の勝ち筋」を見つけやすくなるでしょう。
その「勝ち筋」を、再現性のある仕組みとして構築するのが「全体設計」です。「なぜ上手くいかなかったのか?」の分析から一歩進み、「どうすれば勝てるか?」の答えをこの資料で見つけてください。

必要に応じて見直す
設定したKPIは絶対的なものではないので、採用状況や市場環境に応じて柔軟に見直しましょう。特に、目的と現実に乖離がある場合や、経済状況の変化といった外的要因が影響している場合は、KPIを調整して現実的な計画に軌道修正していく必要があります。
KPIの見直しを行ったあとは、「修正したKPIがKGIと整合性を保てているか」を確認しましょう。また、何度もKPIを修正したり根拠なく主観で変更したりすることは避けてください。
新卒採用のKPIを設定するときの注意点
新卒採用のKPIを設定するときは、以下の3点に注意が必要です。
・数字にこだわりすぎない
・定量的な指標だけにとらわれない
・採用条件を引き下げない
どのようなポイントを意識すればよいのか、詳しく紹介します。
数字にこだわりすぎない
KPIは、目的達成のための手段でしかありません。KPIの数値達成に追われてしまうと、本来の採用活動の意義を見失ってしまい、採用チームのモチベーションが低下したり柔軟な発想が制限されたりする可能性があります。
例えば、「エントリー数を前年の1.5倍にする」という目標で考えてみましょう。この場合、単にエントリー数を増やすことだけを追求すると、ターゲット層が広がりすぎて応募者の質が低下するリスクがあります。
KPIは、あくまで活動の方向性を示す指標です。採用チームが目的意識を持って対応できるように、柔軟に運用する姿勢が求められます。
KPIという「点」の改善に留まらず、採用活動という「線」そのものをデザインしませんか?数字の先にある「採用の質」を高めるための「全体設計」の考え方を、以下の資料で解説します。

定量的な指標だけにとらわれない
KPIを設定するときは、「測定可能かつ定量的な目標」が基本となります。しかし、採用活動においては、応募者の質や企業との相性といった定性的な要素も重要です。定量的な指標だけにとらわれ、本当に自社が必要とする人材を確保できない状況に陥ることは回避すべきです。
選考の際は、応募者の定性的な部分を評価する方法も考えておきましょう。例えば、面接の評価項目に「コミュニケーション能力」「価値観の一致度」といった要素を組み込むことが有効です。
採用条件を引き下げない
KPIの達成を優先するあまり、妥協して採用条件を引き下げることがないように注意しましょう。例えば、「内定者30名」という目標に固執して選考基準を緩めてしまうと、結果的に企業に適合しない人材が増え、早期離職率の上昇や生産性の低下を招くリスクが高まります。
採用条件は、企業の価値観や目標にもとづいて設定された重要な基準です。短期的な目標達成のために変更することは避け、長期的な視点で採用活動を進めるべきです。
採用の本質を見失わないように、KPIはあくまで補助的な役割を果たすものとしてとらえましょう。
KPI設定で新卒採用を成功させよう!
新卒採用におけるKPIの設定は、採用活動全体を効率化するために欠かせないプロセスです。
しかし、KPIは単なる指標であり、目標達成の手段に過ぎません。設定したKPIを最大限に活用するためには、自社の採用目標や戦略にマッチする指標を見極め、優先順位をつけながら柔軟に運用することが大切です。
「KPIを管理して効率的に採用活動を進めたい」「KPI管理の手間を軽減したい」という企業におすすめなのが、ダイレクトリクルーティングサービス「キミスカ」です。
「キミスカ」では、独自の逆採用型プラットフォームを通じて、企業のニーズにマッチする学生を効率的に発見し、スカウトを送付できます。豊富なデータ分析機能をご利用いただけるので、採用活動の各段階でのKPIを効率的に管理しやすくなります。
採用活動の目的を達成するために、ぜひ「キミスカ」をご活用ください。
キミスカのサービスについては、こちらで詳しくご覧いただけます。