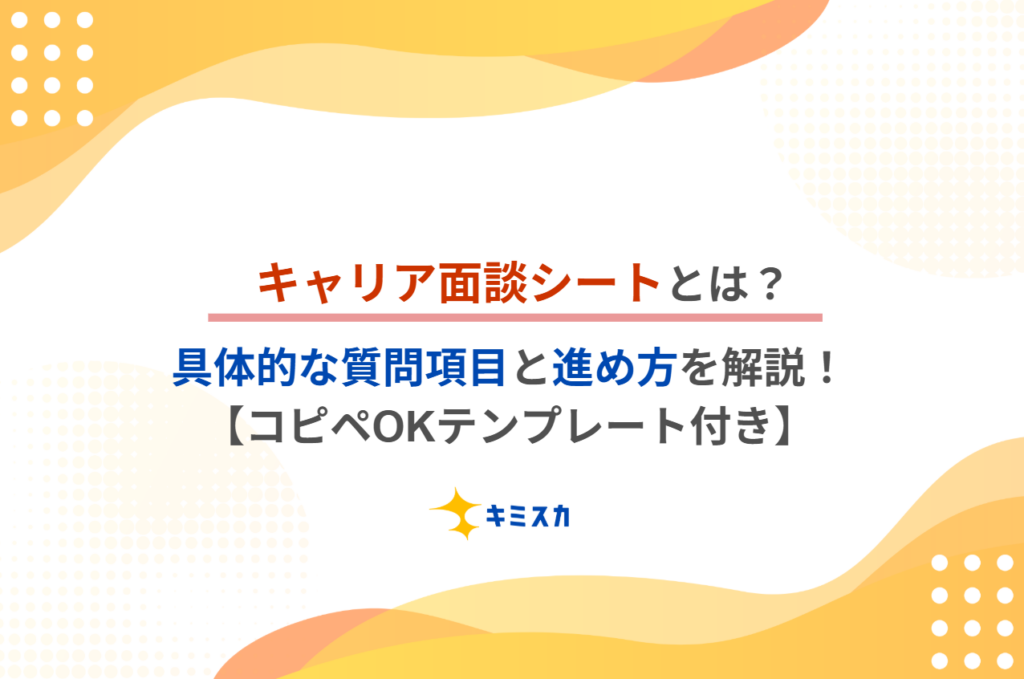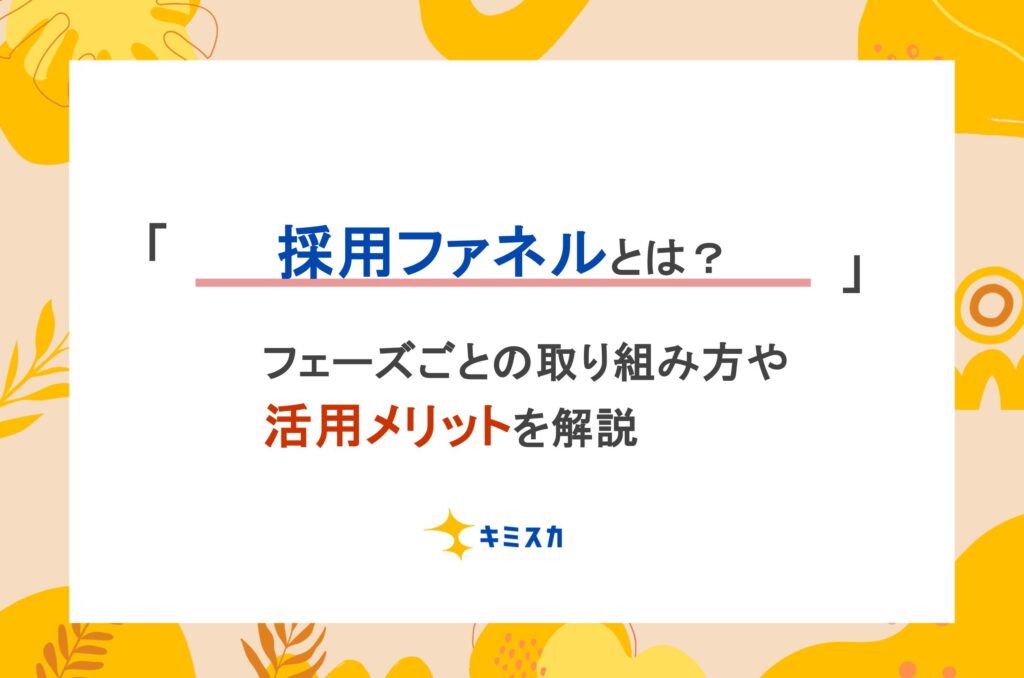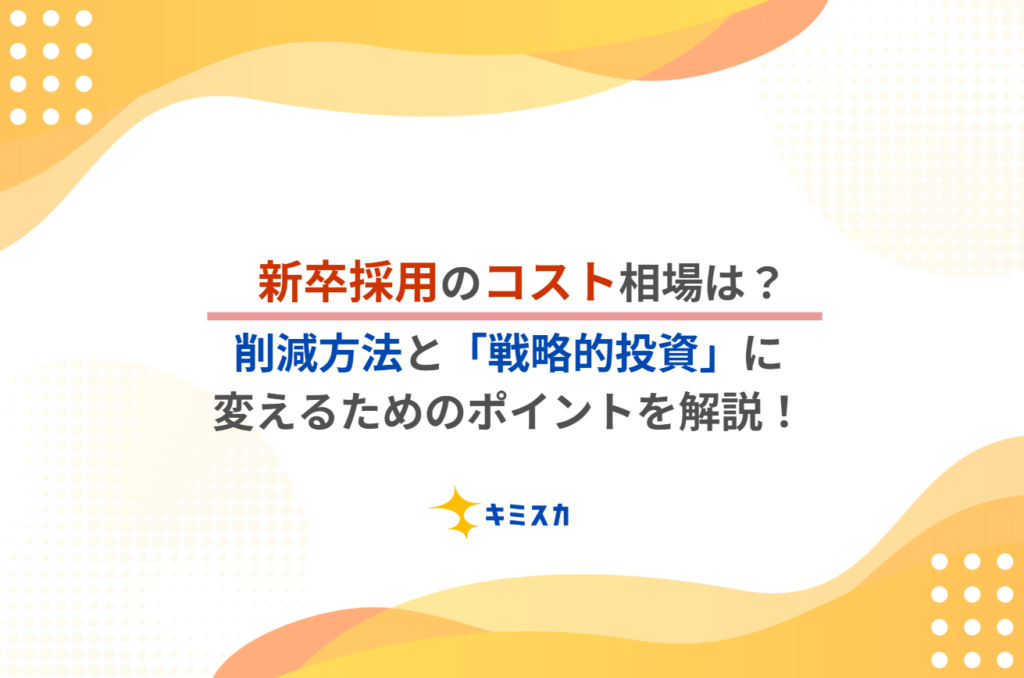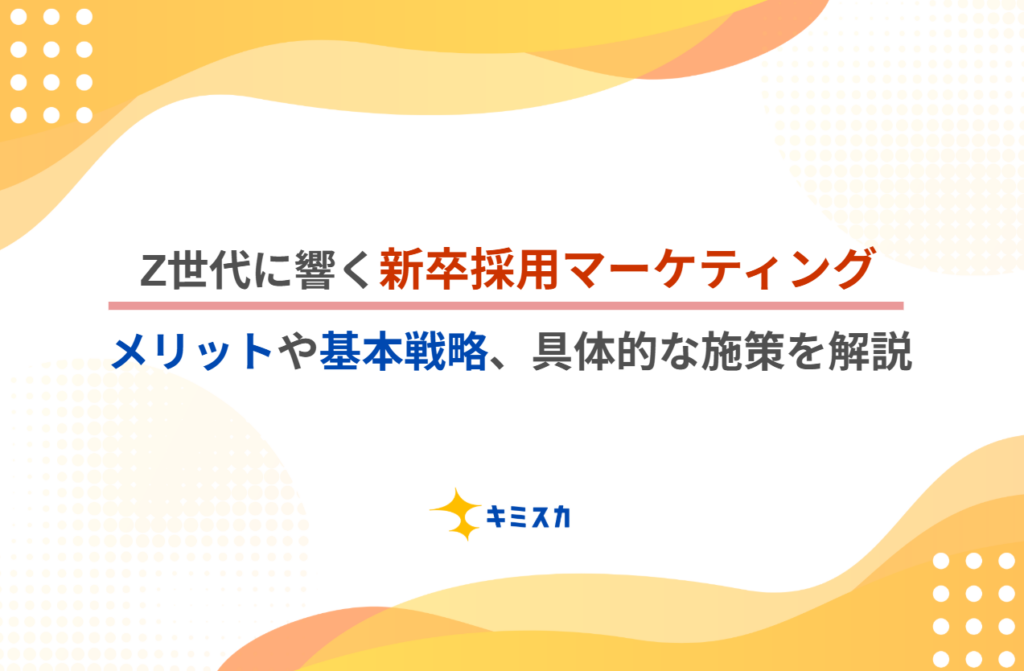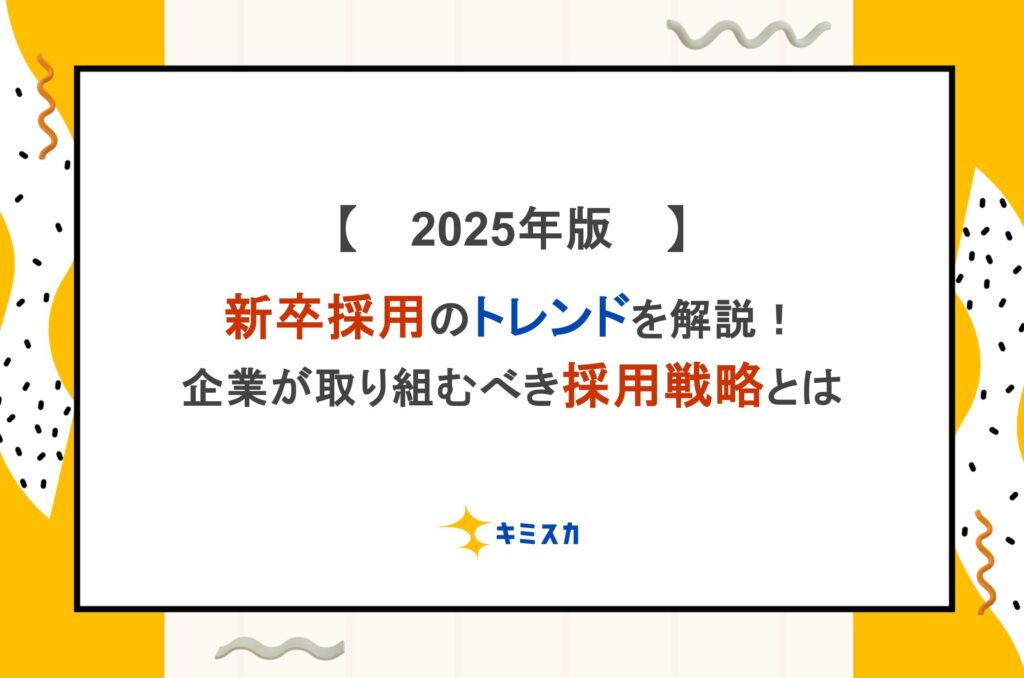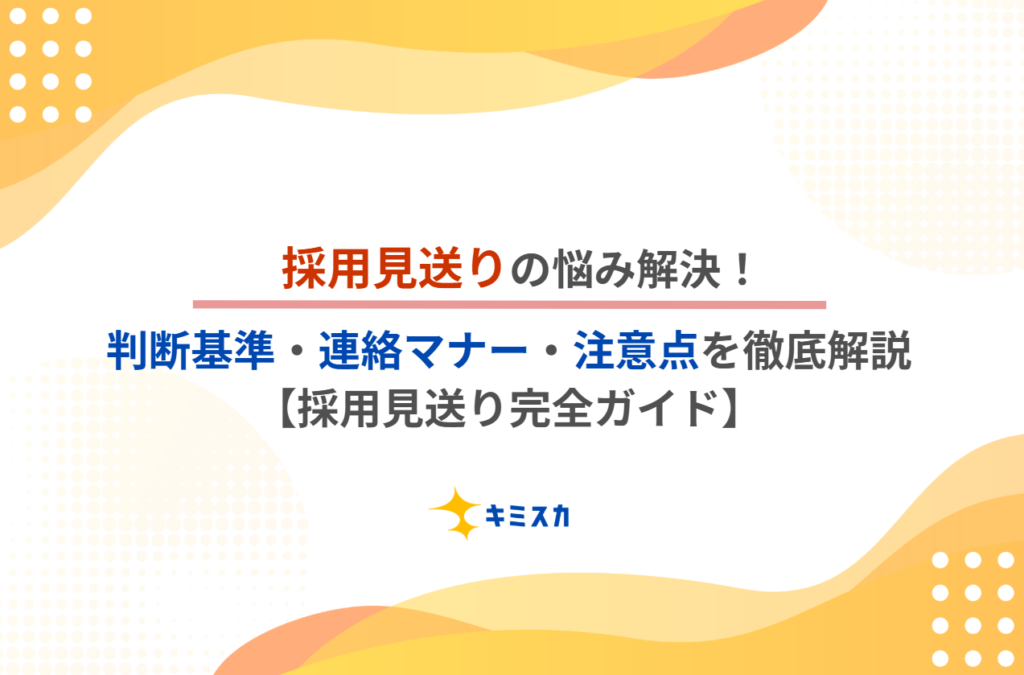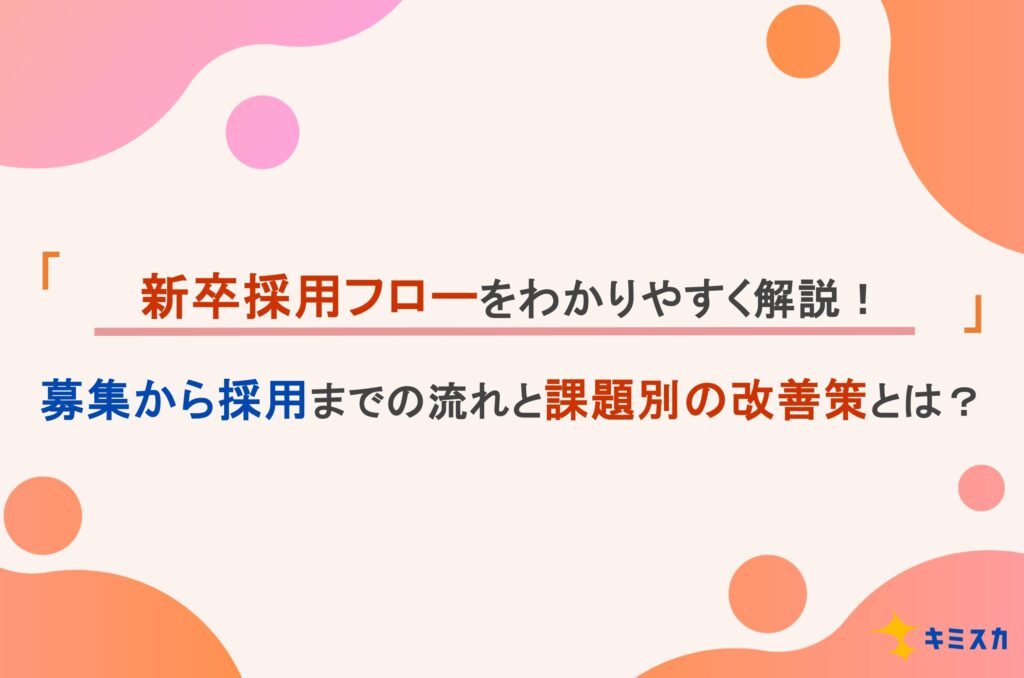
採用フローとは、応募者の募集(母集団形成)から選考、内定までの一連の流れのことです。通年募集が一般的な中途採用と異なり、新卒の採用フローには特徴があるため、正しい流れを知っておくことが大切です。
この記事では、新卒の採用フローについて詳しく紹介します。各プロセスのポイントやよくある課題の解決方法を知って、自社に合った採用フローの策定を目指しましょう。
【新卒採用】基本の選考フロー
新卒採用の基本的な選考フローは、以下のとおりです。
以下では、各選考フローの詳細を見ていきましょう。
1. 採用戦略を策定する
まずは、採用活動全体の指針となる採用戦略を立てましょう。
「ほかの企業がこうだから」「よくわからないし、例年どおりでいいか」と、明確な目的や方針がないまま採用戦略を立てることは避けてください。自社の経営戦略や事業計画にひもづいた採用戦略を立てることが、新卒採用を成功させる近道です。
戦略策定では、以下の要素について明確化しましょう。
・採用人数と職種
・採用予算
・求める人材要件
・選考スケジュール
・実施体制
ポイントは、単に不足した人材を確保するだけではなく「なぜその人数が必要か」「どのような人材を採用すべきか」という本質的な戦略まで策定することです。現場の管理職も巻き込んで策定することで、より実効性の高い戦略を立てやすくなります。
新卒採用を成功させる戦略の立て方とは?具体的な手順やフレームワークを紹介
とはいえ、「実効性の高い戦略と言っても、何から手をつければ…」とお悩みではありませんか?
その戦略策定の全プロセスを体系的にまとめた「全体設計」の解説資料をご用意しました。まずはこの資料で、自社の採用戦略の骨子を固めましょう。
2.応募者を集める
採用戦略を策定できたら、応募者を集める「母集団形成」を行いましょう。母集団形成の際は、ただ情報を発信するだけではなく「採用市場における自社のブランディング」を意識して取り組みます。
近年の新卒採用は売り手市場の傾向があるので、学生に企業を好きになってもらったり憧れてもらったりすることができなければ、応募や入社してもらうことは困難です。特に、新卒市場では企業の第一印象がその後の志望度や熱意に大きく影響するため、早い段階から戦略的にアプローチする必要があります。
広報活動・プレエントリー
就活生との最初の接点となる広報活動では、自社の魅力を端的に伝えて興味を抱いてもらうことが何よりも重要です。近年は、学生の情報収集手段が多様化しているので、複数のチャネルを活用することも検討してみましょう。
例えば、以下のような広報活動が考えられます。
1.就活ナビサイトで、業界内での差別化ポイントを明確に示して興味を喚起する
2.自社サイトへ誘導して、企業理念や具体的な仕事内容を詳しく知ってもらう
3.SNSで、社員の生の声や職場の日常的な雰囲気を伝えて親近感を抱いてもらう
4.オウンドメディアで、企業の想いや取り組みを具体的に知ってもらう
この段階では多くの接点を設けることよりも、ターゲットとなる学生へ確実にリーチすることを意識しましょう。質の高い母集団を形成できれば、採用にかかるコストや手間を削減できます。
また、学生がエントリーしてくれるのを待つだけではなく、自社を知ってもらえるように積極的に働きかけたり、学生とコミュニケーションを取ったりすることが重要です。
会社説明会
プレエントリーや本エントリーをした学生に対して、より深い理解を促すための説明会を実施します。ここでのコミュニケーションは、選考への参加意欲に大きく影響します。
例えば、次のような内容の説明会が効果的です。
・事業戦略や将来のビジョンを具体的に説明する
・若手社員との座談会セッションを行う
・配属後のキャリアパスを明確に提示する
・質疑応答の時間を十分に確保する
・フォローアップ面談を実施する
特に重要なのは、企業側からの一方的な情報提供で終わらせないことです。学生との対話を通じて相互理解を深め、安心して次のステップに進める関係性を構築しましょう。
3. 選考を行う
新卒採用における選考は、単に合否を判定するだけの場ではなく、企業と学生が相互理解を深める重要な機会になります。近年は選考方法の多様化が進んでいますが、基本となるのは書類選考と面接です。
ここでは、各選考のポイントについて説明します。
書類選考
エントリーシートや履歴書は、応募者の基本的な適性や志望度を確認するための重要なツールです。企業によっては、適性検査を行うこともあります。
書類選考を行うときは、次のようなポイントを意識しましょう。
・評価基準の明確化
・スキルや資格の確認
・求める人物像に合ったエントリーシートの設問設計
ここで意識したいのは、学生の優劣を評価するのではなく、自社との相性を見極めたり面接での深掘りポイントを見つけ出したりすることです。特に、志望動機やガクチカからは応募者の価値観や考え方を読み取りやすいので、しっかりと確認しておきましょう。
面接
面接は、応募者の適性や人物像を直接確認できる、選考プロセスの中でも核となるプロセスです。
「集団面接→個別面接」へと段階的に進めていくのが一般的な流れですが、グループディスカッションやグループワークを行うこともあります。集団面接では基礎的なコミュニケーション能力や協調性を、個別面接では価値観や志望度をより深く確認しましょう。
面接で自社にマッチする人材を見極めるには、事前の準備が不可欠です。まずは面接官の選定と評価基準の統一を行い、各面接で重点的に確認しておきたい項目を明確にします。
面接後は評価会議を実施して、書類選考や適性検査の結果も含めてさまざまな視点から合否を検討しましょう。
4. 内定を出す
内定は採用プロセスの最終段階ですが、決して「内定を出して終わり」ということではありません。むしろ、ここからが本当の意味での採用活動のスタートともいえます。
特に、売り手市場が続いている昨今は、内定辞退を防ぐための戦略的なフォローが不可欠です。ここでは、内定出しと内定者フォローで意識したいポイントを見ていきましょう。
内定出し
選考を通じて自社にマッチする人材が見つかった場合は、内定通知を行いましょう。
内定を伝えるときは、次のようなポイントを意識してみてください。
・入社後の具体的なキャリアプランを提示する
・配属予定部署や待遇について明確に説明する
・入社までのスケジュールを共有しておく
・内定承諾までの期限を設定しておく
内定を出したからといって、必ずしも承諾してもらえるわけではありません。内定辞退時に繰り上げする余地を残しておくために、希望する人数から内定承諾をもらえるまで、繰り上げ候補者への不採用の連絡は待ちましょう。
内定者フォロー
内定から入社までの期間は、学生が他社の選考を継続している可能性が残されているので、丁寧な対応が求められます。定期的なコミュニケーションを通じて、入社への意欲を維持・向上させましょう。
具体的には、社内報や業界情報の共有、内定者同士の交流会の開催、配属予定部署の社員との面談などが有効です。特に最近は、SNSや社内チャットツールといったオンラインツールを活用したフォローが増えています。
内定者一人ひとりの状況や性格に応じて、適切なコミュニケーション方法を見極めましょう。
【手法別】新卒の採用フローとポイント
企業の規模や業界、求める人材像によって、最適な採用フローは異なります。
ここでは代表的な採用手法とそれぞれの採用フローについて説明します。
オーディション型
オーディション型は、多くの企業が取り入れている最も一般的な採用手法で、先述した基本の採用フローが該当します。
オーディション型は、幅広い応募者を集められる一方で、求人情報が他の企業に埋もれやすい点に注意が必要です。自社を学生に知ってもらうには、求人ページの作り込みや広告オプションの活用など、認知度を高める工夫が求められます。
特に中小企業は、いかに自社の強みを大々的にアピールして、大手企業と差別化を図れるかが、新卒採用の成功を左右するポイントとなります。
オファー型
オファー型は、ダイレクトリクルーティングやスカウト採用とも呼ばれる、近年注目度が高まっている手法です。企業が欲しいと思う学生に自らアプローチするので、量より質を重視した採用活動を行いたい企業に向いています。
オファー型の採用フローは、次のとおりです。
1.ダイレクトリクルーティングサービスに求人情報を掲載する
2.学生にオファーを送る
3.オファーを承認した学生がエントリーする
4.説明会や面談を開催する
(インターンシップを開催する場合もある)
5.書類選考・面接を実施する
6.内定通知を行う
7.入社
オファー型を採用するときは、ターゲットの明確化や興味を引くスカウトメッセージの作成、スピード感のある対応が重要となります。メリットが多い一方で、戦略的・計画的に実施しないと期待する成果を得られない場合がある点に注意が必要です。
インターンシップ型
2025年度以降、一定の要件を満たすインターンシップに参加した学生の情報を、採用選考時に活用できるようになりました。そのため、インターンシップを実質的な採用活動の場として活用する企業が増えています。
インターンシップ型の採用フローでは、職場体験を通じて学生の適性を見極めると同時に、企業の魅力を深く理解してもらうことができます。特に、以下のような企業の場合は、インターンシップ型を取り入れてみるとよいでしょう。
・業務体験で魅力が伝わりやすくなる職種・企業
・じっくりと時間をかけて人材を見極めたい企業
・独自の企業文化や価値観を重視する企業
インターンシップ型の採用フローは、次のとおりです。
1.インターンシップを企画する
2.企業情報やインターンシップ情報を公開する
3.インターンシップのエントリー受付と選考を実施する
4.インターンシップを実施する
5.ナビサイトなどに求人情報を本公開する
6.本エントリーを受け付ける
7.書類選考・面接を実施する
8.内定通知を行う
9.入社
企業によっては、長期インターンがそのまま内定に直結する場合もあります。インターン型の採用を成功させるには、ただ職場体験をさせるだけではなく、業界や仕事内容に魅力を感じてもらえるコンテンツを提供する必要があります。
また、インターンシップの企画・運営には相当の工数が必要です。受け入れ可能な人数も限られるため、他の採用手法と組み合わせながら実施することが一般的です。
大学提携型
大学提携型は、大学のキャリアセンターや研究室、OB・OGと連携して採用活動を進める手法です。特に専門性の高い人材を採用したい企業や、地域に根ざした採用を行いたい企業に適しています。
1.提携したい大学にアポイントを取る
2.大学に訪問する
3.大学掲示用の求人票を作成する・学内セミナー等に参加する
4.説明会を開催する
5.エントリーを受け付ける
6.書類選考・面接を実施する
7.内定通知を行う
8.入社
大学提携型を取り入れると継続的な求人掲示が可能になり、安定した採用活動につながる可能性があります。
ただし、連携できる大学の数には限りがあるので、母集団の規模が限定される傾向にあります。また、大学と良好な関係を継続するために、採用した学生のフォローや定着にも尽力することが大切です。
新卒採用フローの決め方
採用市場や就活生の動向は、年々変化しています。そのため、採用活動を成功させるには、自社の状況や目的に合わせて採用フローを最適化することが大切です。自社に適した新卒採用フローの決め方を、詳しく見ていきましょう。
1. 採用目標を設定する
まずは、採用活動における目標を設定しましょう。
採用目標の設定では、「何人採用するか」という最終的な目標だけではなく、それを実現するために必要な中間目標(KPI)を設定する必要があります。例えば、「エントリー数50件」「内定承諾率70%」といった中間目標が考えられます。
特に重要なのは、現場の管理職を巻き込んで目標設定することです。現場の従業員は実際に新卒社員と働く立場なので、必要な人材像を熟知しています。
また、採用後の育成計画や定着施策まで見据えた、長期的な採用目標を設定することも大切です。
2. 求める人物像を明確にする
求める人物像は、採用活動の基盤となるものです。選考基準があいまいなまま採用活動をスタートすると、評価基準がバラバラになったり、本来必要な人材を見逃したりするリスクが高まります。
おすすめなのは、はじめに企業の経営理念や事業戦略から理想の人物像を導き出して、それを具体的なスキルや行動特性に落とし込むことです。「コミュニケーション能力が高い」という抽象的な表現ではなく、「相手の意見を積極的に聞き、建設的な提案ができる」というように、実際の業務場面に即した定義づけを行いましょう。
このように、欲しい人材を具体化することで、選考時の評価基準が明確になり、より精度の高い選考活動が可能になります。
そして、その「求める人物像」に一貫してアプローチする採用フローを作るための手法が「全体設計」です。
人物像定義からメッセージ策定、選考体験の設計までを網羅したガイドブックを、以下より無料でダウンロードいただけます。
3. 具体的なスケジュールを立てる
母集団形成から内定者フォローまでのすべてのプロセスを見据えて、具体的な採用スケジュールを策定していきましょう。近年は、新卒採用を取り巻く環境が大きく変化しているので、「自社はどうなのか」「今年度はどうなのか」を意識しながらスケジュールを立てていく必要があります。
重要なのは、自社の繁忙期や人的リソースを考慮したうえで、現実的に実現可能なスケジュールにすることです。例えば、「面接を担当する管理職の業務が集中する時期は避ける」「説明会は閑散期の〇月に実施する」というように、採用活動以外の業務を考慮することが大切です。
新卒採用フローによくある課題と対処
新卒採用の現場でよくある課題として、以下のようなものが挙げられます。
・専門性の高い・優秀な人材を確保できない
・知名度がなく認知してもらえない
・自社のターゲットに応募してもらえない
・内定・選考を辞退する学生が多い
・採用コストが高い
ここでは、上記の課題への対処法について詳しく見ていきましょう。
【課題1】専門性の高い・優秀な人材を確保できない
就活ナビサイトや合同説明会など、従来型の採用手法に頼っているだけでは、ターゲットにリーチできなかったり有名企業に埋もれてしまったりする可能性があります。専門性の高い学生や優秀な学生など、倍率の高い人材が欲しい場合は、「応募者を集める」段階で企業から積極的にアプローチすることが大切です。
この課題を解決するには、ただ学生を待っているだけではなく、ダイレクトリクルーティングサービスなどを活用して積極的に学生を獲得しに行く姿勢が重要となります。特に理系学生の場合、研究室単位での就職活動も多いため、大学の就職課や研究室との関係構築も検討してみるとよいかもしれません。
【課題2】知名度がなく認知してもらえない
知名度が低い企業の場合、コストをかけて広告を大量に出しても、有名企業に学生の関心を奪われやすい傾向にあります。この場合は、認知度の低さを逆手に取った「狭く深いアプローチ」が有効です。
具体的には、地域・業界に特化した小規模イベントへの出展や、エントリー者との1on1面談の実施など、じっくりと自社の魅力を伝える採用活動に注力しましょう。また、社員のリアルな声や職場の雰囲気を発信するなど、大手にはない等身大のコミュニケーションを心がけることで、着実な母集団形成が可能になります。
【課題3】自社のターゲットに応募してもらえない
「応募数は多いのに、求める人材が見つからない」という場合は、採用フローの初期段階である採用戦略の見直しが必要です。採用活動では、採用戦略をもとに広報活動や選考方法を考えていくことになるので、前提条件が間違っているとミスマッチが起きやすくなります。
まずは、自社の事業戦略やビジョンから、必要な人材要件を明確化しましょう。そのうえで、ターゲットとなる学生が普段どのような情報に触れ、どのような企業に興味を持っているのかを徹底的にリサーチします。
このような入念な分析をもとに広報活動や選考方法を設計すれば、求める人物像に近い母集団を形成しやすくなるでしょう。
この「入念な分析と設計」を、フレームワークを用いて効率的に行う方法をまとめたのが、資料「新卒採用を成功に近づける全体設計のやり方」です。
「ターゲットとのズレ」という課題を根本から解決したい方は、ぜひご活用ください。
【課題4】内定・選考を辞退する学生が多い
内定・選考を辞退する学生が多い企業は、学生とのコミュニケーションが不足している、もしくは質の高い母集団を形成できていないことが原因です。この課題の背景には「学生とのエンゲージメント不足」という共通点があります。
解決には、選考プロセス全体にコミュニケーションの機会をできるだけ多く盛り込むことが有効です。
例えば、選考の段階で1on1の面談時間を設けたり内定者同士の交流会を開催したりすると、企業への理解と共感を深められます。また、早い段階から配属予定の部署の社員との接点を作ると、入社後のイメージを抱いてもらいやすくなるので、意欲の維持・向上効果が得られるでしょう。
【課題5】採用コストが高い
採用コストが高い場合やコストに見合った成果が得られていない場合は、採用期間や利用する媒体・ツールを見直す必要があります。
例えば、以下のような工夫をするとコストを抑えやすくなります。
・ダイレクトリクルーティングサービスを利用する
・掲載媒体を絞り込む
・短期集中型の採用フローにする
・ストック型の自社コンテンツを活用する(オウンドメディアなど)
・無料のSNSを活用する
・オンラインツールを活用して説明会・選考を実施する
特におすすめなのが、最初からターゲットを絞って直接アプローチするダイレクトリクルーティングサービスの活用です。掲載料や広告費を抑えながら、自社の求める人材へ効率的にリーチできるため、費用対効果の最大化を目指せます。
ダイレクトリクルーティングサービスのメリットについては、こちらの資料で紹介しています。あわせてご覧ください。
新卒採用フローの策定・活用を成功させるコツ
新卒採用フローの策定・活用を成功させるために、以下のコツを意識しましょう。
・自社に合った採用フローを見つける
・募集職種によって採用フローを使い分ける
・学生目線で実現可能かチェックする
・評価と改善を行う
それぞれどのようなことなのか、詳細を説明します。
自社に合った採用フローを見つける
今回紹介した採用フローは基本的なものであり、企業の文化や業界の特性、採用の目的によって最適な採用フローは異なります。企業によっては、「書類選考を行わない」「独自の試験を行う」など、自社ならではの選考フローを策定することもあるでしょう。
大切なのは、他社の成功事例をそのまま流用するのではなく、自社の状況や採用したい人材像に合わせてカスタマイズすることです。また、採用活動を通じて得られた学生の反応や選考結果のデータをもとに継続的な改善を行うことで、より効率的かつ効果的な採用戦略に磨き上げていくことも意識してみてください。
募集職種によって採用フローを使い分ける
採用フローを設計するときは、職種ごとの特性を考慮しましょう。なぜなら、営業職や技術職、事務職など、それぞれの職種で求められるスキルや適性は大きく異なるためです。
例えば、技術職の採用では、専門的なスキルテストや実務に即した課題解決型の選考を実施するとよいでしょう。一方、営業職では、コミュニケーション能力や主体性を重視した選考プログラムを盛り込むとよいかもしれません。
また、同時に複数の職種で採用活動を行う場合は、選考プロセスの運用管理も重要になります。各職種の選考状況を一元管理しつつ、職種ごとの評価基準や選考方法の違いを明確にすることで、より精度の高い人材確保が可能になります。
学生目線で実現可能かチェックする
採用フローを設計するときは、「企業側の都合が優先されていないか」というポイントに気をつけましょう。例えば、「エントリーから選考までの期間が短すぎる」「面接可能な日程が限定的すぎる」など、学生の立場からすると参加が難しい設計になっていることがあります。
多くの学生は複数の企業を並行して検討しており、授業やサークル活動との両立も必要です。そのため、選考への参加のしやすさは、応募を決める重要な判断材料のひとつになります。
採用活動のスケジュールを立てるときは、以下のように柔軟な対応を心がけましょう。
・オンラインと対面の選択制を導入する
・土日の面接枠を設ける
・予備日を確保しておく
また、各選考段階における所要時間や準備に必要な期間なども、学生生活を考慮のうえ設計することが大切です。
評価と改善を行う
採用フローの改善には、データにもとづいた戦略的なアプローチが不可欠です。「なんとなく手応えがよかったから今後もこうしよう」「よくわからないから去年と同じようにやろう」という、感覚的な判断で次年度の採用活動を進めることは避けましょう。
戦略的なアプローチには、評価と改善が欠かせません。そのために必要なのが、各プロセスにおける具体的なKPIです。
・説明会参加者の応募率
・エントリー率
・面接通過数
・各選考段階での選考辞退の数と理由
上記のような指標を用いて詳細な分析を行うことで、採用フローのどの段階に課題があるのかが明確になります。
特にチェックしておきたいのは、「最終的に入社を決めた学生が、どの採用チャネルからの応募で、選考でどのような評価を得ていたのか」という点です。この分析結果をもとに、効果の高い施策へ重点的に投資することで、採用の質と効率を両立させやすくなります。
新卒採用フローを見直して採用活動を成功させよう
新卒採用フローは、採用活動だけではなく、企業の成長を左右する重要な要素です。単に人材を確保するだけでなく、その後の人材育成や組織の成長を考慮しながら計画を立てていく必要があります。
本記事で解説した採用フローの見直しと計画立案にすぐに使える「全体設計」のフレームワークを、以下の資料で詳しく解説しています。
自社の採用フローに課題を感じている方は、ぜひこの資料から改善の一歩を踏み出してください。
近年は、就活生の価値観やコミュニケーション方法が多様化しているため、従来型の採用フローでは十分な成果を上げることが難しくなってきました。そのような採用市場で効率的かつ効果的な採用活動を実現するには、キミスカのようなダイレクトリクルーティングサービスの活用が不可欠です。
キミスカを導入することで、採用コストを抑えながら、自社に最適な人材にピンポイントでリーチすることが可能です。また、導入企業の採用成功を実現するために、専門スタッフによるコンサルティングも実施しています。
採用フローや採用手法を見直したい企業は、お気軽にキミスカまでご相談ください。