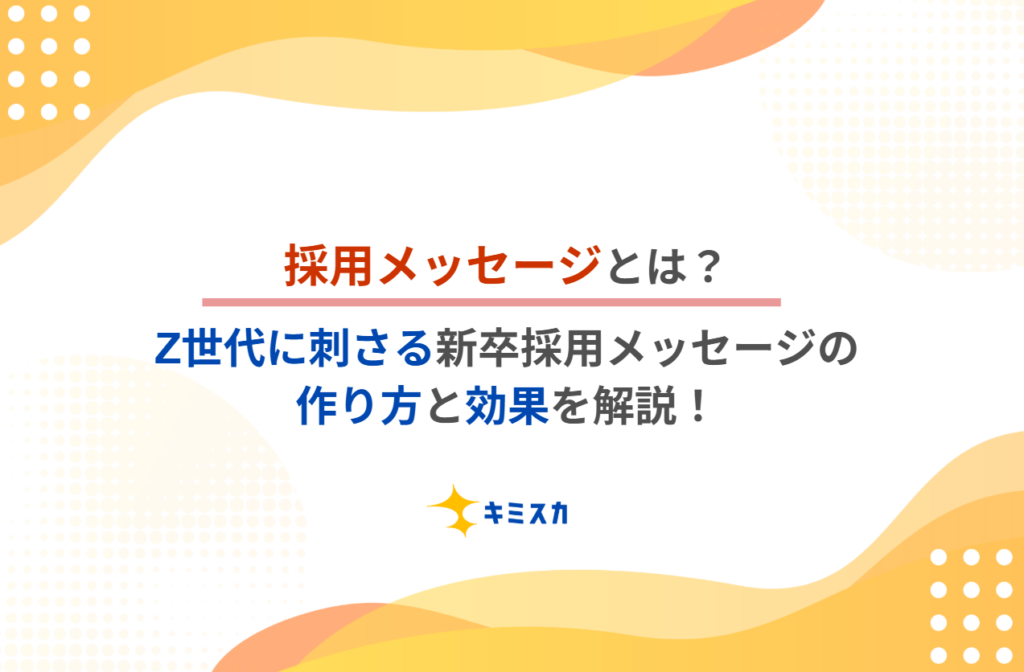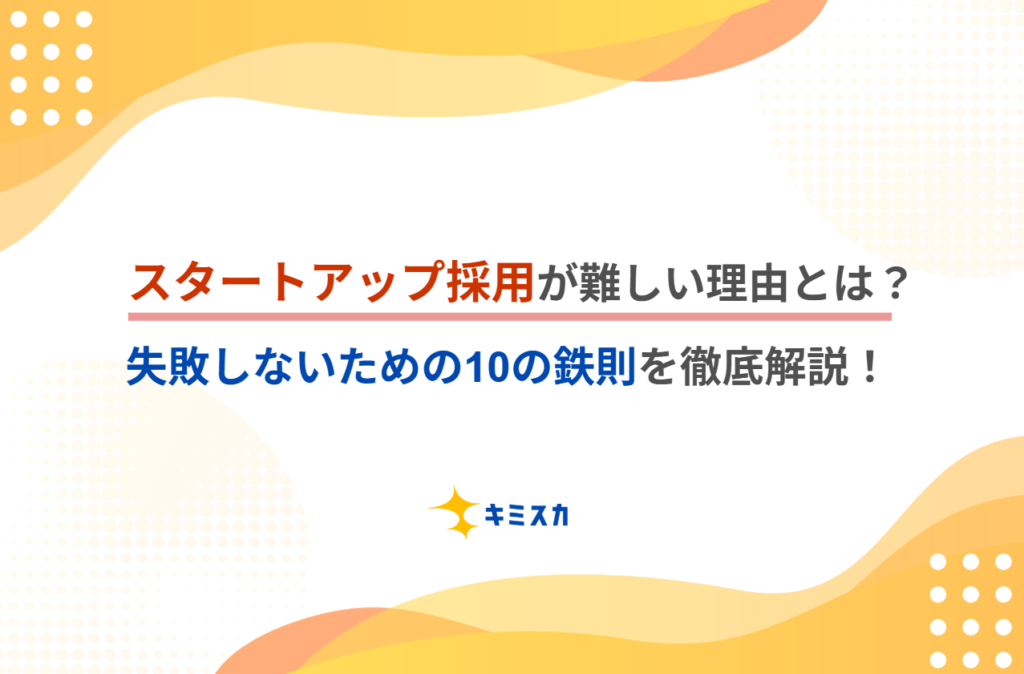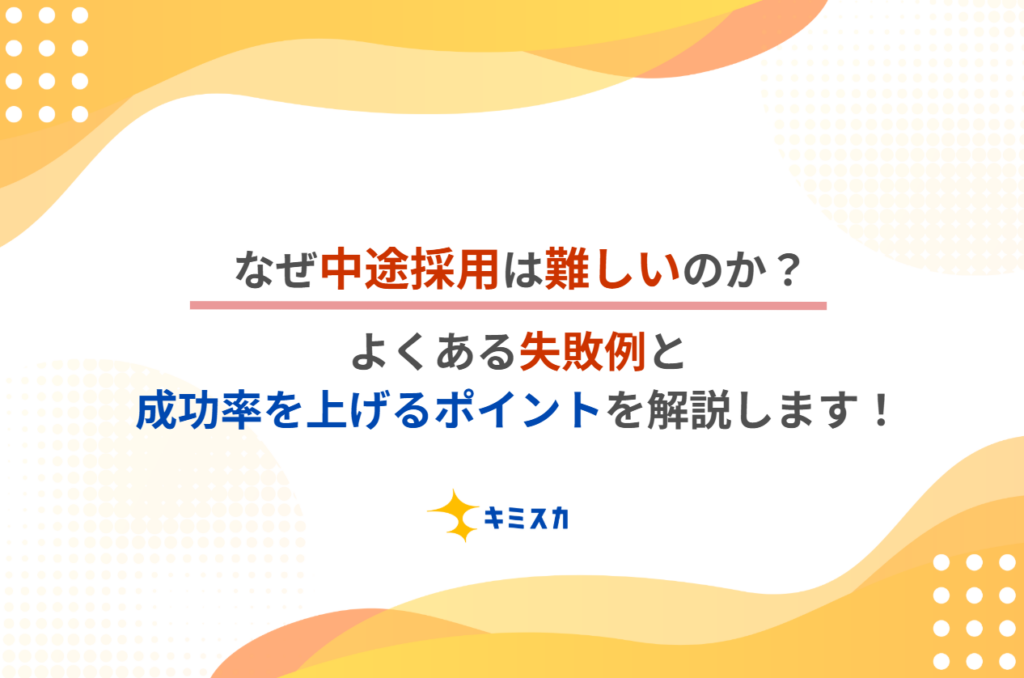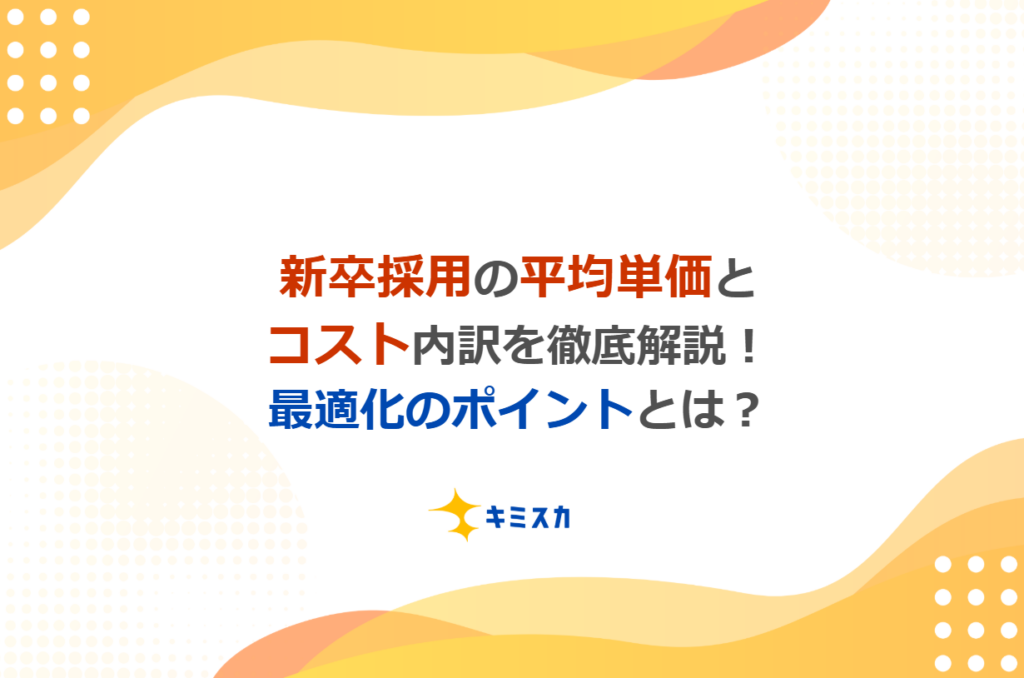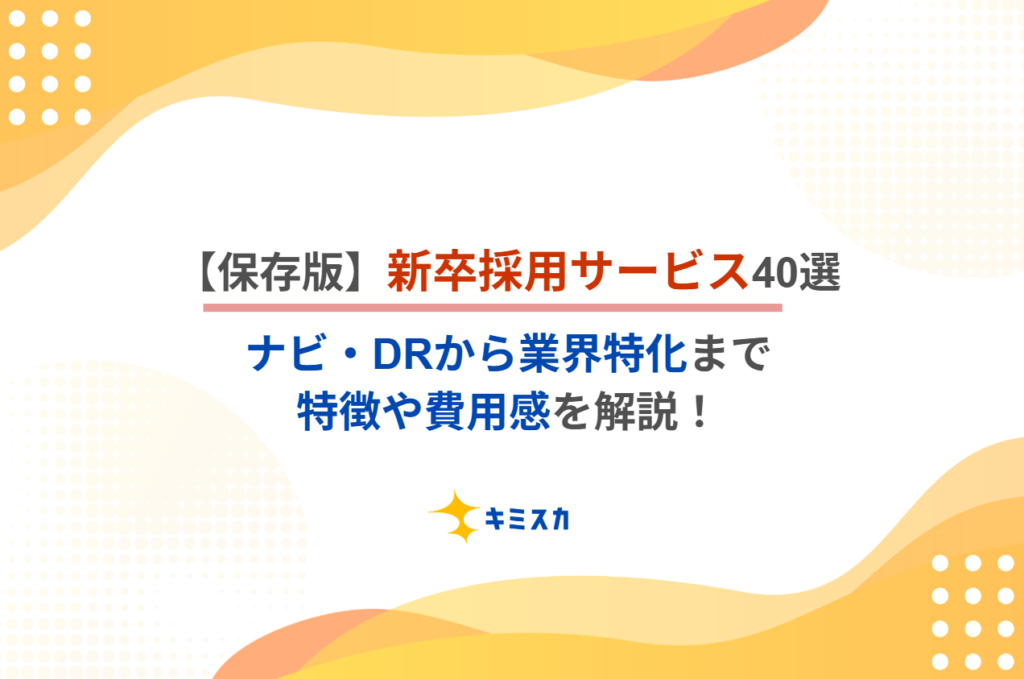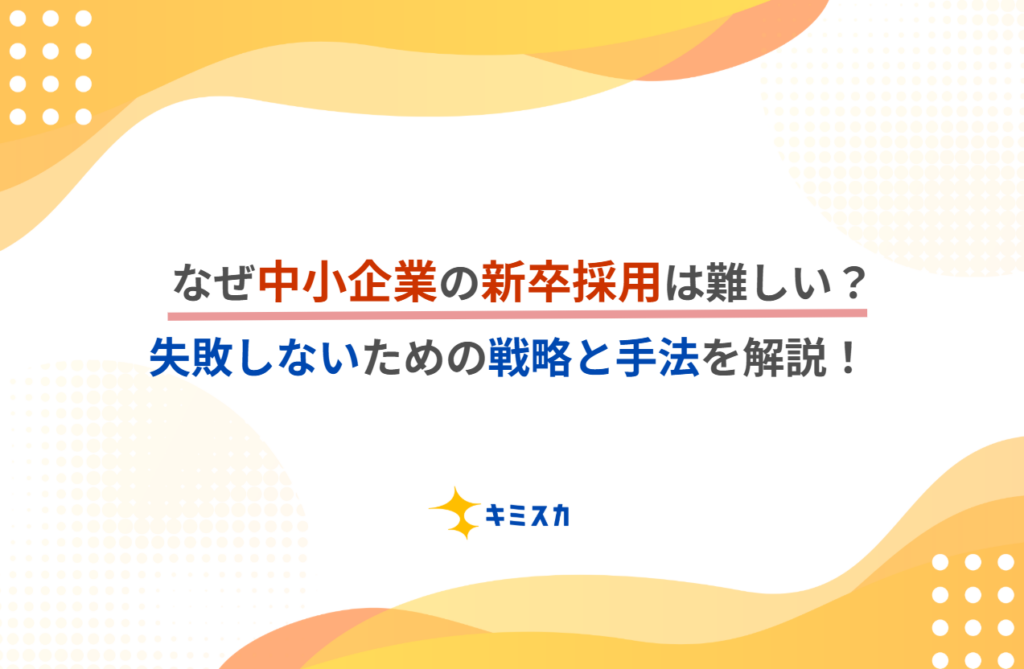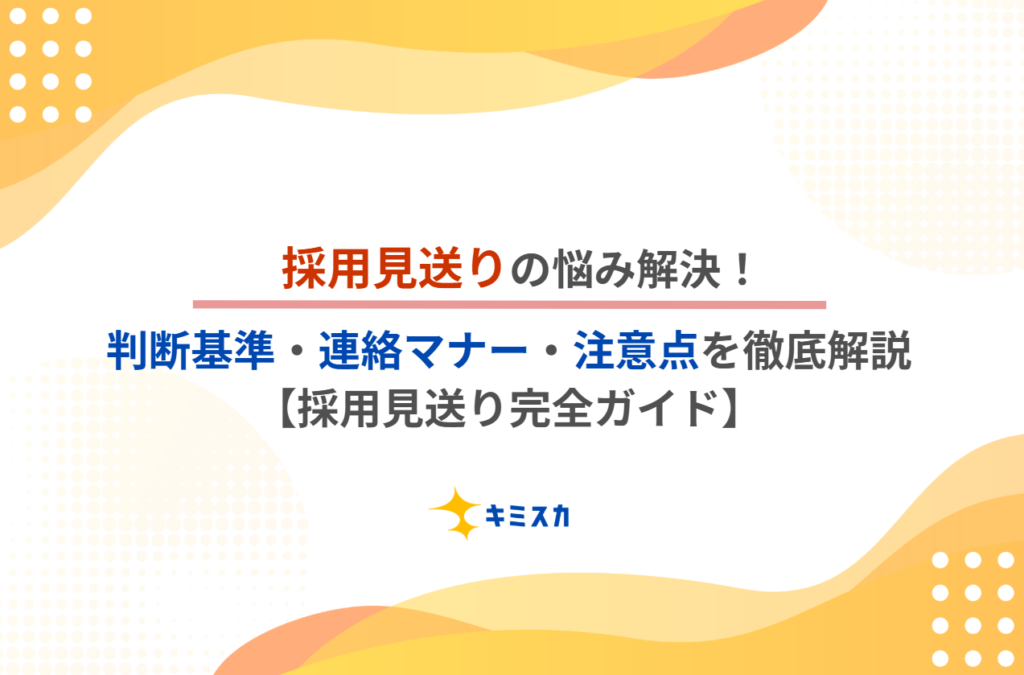
採用見送りの連絡、お悩みではありませんか?
「採用見送りの連絡、どうすれば失礼なく伝えられるだろう…」
「お祈りメールの書き方が分からない」
「見送り理由って伝えるべき?」
新卒採用を担当する中で、候補者への見送り対応は避けられないものの、多くの疑問や不安がつきまといます。
不適切な対応は企業の評判低下や将来の採用活動への悪影響にも繋がりかねません。
この記事では、採用見送りの判断基準から、候補者に好印象を与える連絡マナー(メール例文付き)、法的注意点、そして「サイレントお祈り」などのNG対応まで徹底解説します。自信を持って誠実な見送り対応をすることで、採用活動の質と企業イメージ向上につなげていきましょう。
採用見送りとは?意味と企業が取るべき対応
まずは、採用見送り(不採用)の意味と重要性、企業が取るべき対応について見ていきましょう。
採用見送り(不採用)とは
採用見送りとは、文字通り、採用選考プロセスにおいて、候補者の採用を見合わせる、つまり「不採用」と判断することを指します。
多くの場合、「不採用」という直接的な言葉を避け、「今回は採用を見送らせていただくことになりました」「貴意に沿いかねる結果となりました」といった、より丁寧な表現で候補者に伝えられます。これは、候補者の心情に配慮し、企業の印象を悪化させないための工夫でもあります。
なぜ丁寧な採用見送りが重要なのか
採用見送りの連絡は、単なる結果通知ではありません。その対応一つで、企業の評判や将来の採用活動に大きな影響を与えかねない、非常に重要なプロセスです。
候補者体験の向上
近年、採用活動において候補者体験の重要性が高まっています。
たとえ不採用という残念な結果であっても、連絡が迅速かつ丁寧であれば、候補者は「きちんと対応してもらえた」「誠実な会社だ」と感じてもらえます。逆に、連絡が遅れたり、ぞんざいな対応をされたりすると、「候補者を大切にしない会社だ」という強いネガティブな印象を与えてしまいます。
優れた候補者体験を提供することは、採用市場における企業の競争力を高める上で不可欠です。丁寧な見送り対応は、そのための重要なステップと言えます。
企業の評判・ブランドイメージ維持
採用見送りを受けた候補者は、その企業の対応について、友人や知人に話したり、就職活動関連の口コミサイトやSNSに書き込んだりする可能性があります。不誠実な対応や、いわゆる「サイレントお祈り(連絡なし)」は、企業の評判を著しく低下させるリスクがあります。
「連絡が全く来なかった」「メールの内容が冷たかった」「理由も教えてくれず不親切だった」といったネガティブな口コミは、瞬く間に広がり、今後の採用活動において優秀な人材からの応募を遠ざける原因となりえます。逆に、丁寧な対応を受けた候補者は、たとえ不採用でも企業に対して好意的な印象を持ち、ポジティブな情報を広めてくれる可能性もあります。
将来的な候補者・顧客になる可能性
今回採用を見送った候補者が、数年後にスキルや経験を積み、再び自社の採用に応募してくる可能性があります。また、その候補者が自社の製品やサービスの顧客になる可能性も十分に考えられます。
もし採用見送りの際に不快な思いをさせてしまっていたら、将来的な採用機会やビジネスチャンスを失うことになりかねません。逆に、丁寧な対応で良い印象を残せていれば、将来的に良好な関係を築ける可能性が広がります。
採用活動は、短期的な視点だけでなく、長期的な視点で候補者との関係性を捉えることが重要です。丁寧な見送り対応は、未来への投資とも言えるのです。
法的リスクの回避
採用選考においては、性別、年齢、国籍、信条、社会的身分などを理由とした差別的な取り扱いは、法律で禁止されています(男女雇用機会均等法、職業安定法など)。不採用通知の内容や伝え方によっては、候補者から差別的な選考が行われたと受け取られ、トラブルに発展するリスクもゼロではありません。
面接で聞いてはいけないことについて、こちらの記事『採用面接で「聞いてはいけないこと」とは?採用担当者が知っておくべきタブーと質問例について解説します!』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください!
採用見送りを伝える基本的なマナーと方法
採用見送りの重要性を理解したところで、次に具体的な連絡のマナーと方法について解説します。
タイミング、連絡手段、そしてそれぞれの手段に応じたポイントと例文を見ていきましょう。
選考結果はいつまでに連絡すべきか
選考結果の連絡は、可能な限り迅速に行うのが理想です。具体的な日数については、企業の選考プロセスや応募者数によって異なりますが、一般的には以下の期間を目安とすると良いでしょう。
- 書類選考:応募書類到着後、1週間〜10日以内
- 面接:面接実施後、1週間以内
重要なのは、選考プロセス開始前や各選考ステップの冒頭で、候補者に対して「結果連絡の時期(目安)」を事前に伝えておくことです。「〇月〇日までにご連絡します」「結果に関わらず、〇営業日以内にメールにてご連絡します」といった具体的な告知があれば、候補者は安心して結果を待つことができます。
約束した期日がある場合は、必ずその期日までに連絡するようにしましょう。
遅れる場合の対応
多数の応募があった、あるいは社内での最終調整に時間がかかるなど、やむを得ず事前に伝えた期日までに連絡できない場合もあります。その際は、放置するのではなく、必ず候補者に連絡が遅れる旨とその理由、そして改めて連絡する時期(目安)を伝えるようにしましょう。
「現在、慎重に選考を進めており、最終決定まで今しばらくお時間を頂戴しております。〇月〇日までには改めてご連絡させていただきます」といった中間連絡を入れるだけでも、候補者の不安は軽減され、誠実な印象を与えることができます。遅れることが確定した時点で、速やかに連絡することが重要です。
見送りの連絡手段
採用見送りの連絡手段としては、主に「メール」と「電話」が用いられます。
メールでの連絡
メールは、多くの候補者に一括で、かつ時間を問わず送信できる効率的な手段です。また、通知内容が文章として残るため、「言った・言わない」のトラブルを防ぐ効果もあります。丁寧な文章を作成すれば、誠意を伝えることも可能です。
ただし、一方的な通知になりやすく、候補者の心情を直接うかがい知ることが難しいという側面もあります。誤字脱字や不適切な表現がないか、送信前によく確認することが重要です。
電話での連絡
電話は、候補者一人ひとりに直接、丁寧な口調で結果を伝えられるため、より誠意が伝わりやすい方法と言えます。特に、最終選考まで進んだ候補者や、企業として特に配慮したい候補者に対しては、電話での連絡が適している場合があります。
候補者の反応を直接感じ取ることができ、簡単な質問であればその場で答えることも可能です。ただし、候補者が電話に出られない場合や、時間帯を選ぶ必要がある、担当者のコミュニケーションスキルが求められるといったデメリットもあります。また、会話の内容が記録として残りにくい点も考慮が必要です。
見送り連絡のポイント
ここでは、最も一般的な連絡手段である「メール」と、丁寧さが求められる「電話」について、具体的なポイントと例文を紹介します。
メールの書き方と例文
メールで見送りを伝える際は、丁寧さ、明確さ、そして候補者への配慮が求められます。
件名
件名は、候補者が一目で何のメールか理解できるように、具体的かつ簡潔に記載します。「選考結果のご連絡/株式会社〇〇」のように、会社名と用件を入れるのが一般的です。多くのメールに埋もれないよう、分かりやすさを心がけましょう。
本文の冒頭
本文の冒頭では、数ある企業の中から自社に応募してくれたことへの感謝を伝えます。「この度は、弊社の新卒採用にご応募いただき、誠にありがとうございました」「先日は、お忙しい中、面接にお越しいただき、重ねて御礼申し上げます」といった言葉を添えましょう。
感謝の言葉
感謝の言葉に続けて、選考結果を伝えます。ここでは、曖昧な表現は避け、採用を見送る旨を明確に、しかし丁寧な言葉で記述します。「慎重に選考を重ねました結果、誠に残念ながら、今回は貴意に沿いかねる結果となりました」「今回は採用を見送らせていただくことになりました」といった表現が一般的です。
見送り理由(任意)
見送り理由をメールに記載するかどうかは、企業の判断によります。もし記載しない場合は、「誠に申し訳ございませんが、選考内容の詳細につきましてはお答えいたしかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます」といった一文を添えるのが一般的です。
もし簡潔に触れる場合は、客観的かつ候補者を不必要に傷つけない表現を心がけます。
応募書類の取り扱いについて
応募時に提出された書類(履歴書、エントリーシートなど)の取り扱いについて明記します。個人情報保護の観点から、返却するのか、責任を持って破棄するのかを明確に伝える必要があります。「お預かりした応募書類につきましては、弊社規定に基づき、責任を持って破棄させていただきます」「ご提出いただきました応募書類は、後日ご返却いたします」のように記載します。
結びの言葉
最後に、候補者の今後の活躍を祈る言葉で締めくくります。形式的であっても、この一文があるかないかで印象は変わります。「末筆ではございますが、〇〇様の今後のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます」といった定型文を用います。
署名
メールの最後には、送信者である企業名、部署名、担当者名、連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)を明記します。これにより、候補者は誰からの連絡かを確認でき、必要に応じて問い合わせることができます。
見送りメールの例文
メールで見送りを伝える際の例文をご紹介します。丁寧かつ簡潔に要件が伝わるようなメールが好ましいです。
件名:選考結果のご連絡/株式会社〇〇
〇〇様
この度は、弊社の採用選考にご応募いただき、誠にありがとうございました。
また、先日はお忙しい中、一次面接にお越しいただき、重ねて御礼申し上げます。
慎重に選考を重ねました結果、誠に残念ながら、今回は貴意に沿いかねる結果となりました。
ご期待に沿えず大変申し訳ございませんが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、誠に恐縮ですが、選考内容の詳細に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承ください。お預かりいたしました応募書類につきましては、弊社規定に基づき、責任を持って破棄させていただきます。
末筆ではございますが、〇〇様の今後のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。
————————————————–
株式会社〇〇
人事部 採用担当
〒XXX-XXXX 東京都〇〇区〇〇 X-X-X
TEL: XX-XXXX-XXXX
Email: recruit@xxxx.co.jp
————————————————–
電話での伝え方と注意点
電話で見送りを伝える場合は、メール以上に丁寧な対応が求められます。以下の点に注意しましょう。
事前準備(伝える内容、静かな環境)
伝えるべき内容(応募への感謝、選考結果、今後の書類の扱いなど)を事前にメモしておくと、落ち着いて話せます。また、周囲の雑音が入らない静かな環境から電話をかけるようにしましょう。相手に失礼なく、話に集中できる環境を整えることが大切です。
候補者への配慮(時間帯など)
候補者の都合を考えずに、いきなり結果を伝えるのは避けましょう。まず、「株式会社〇〇の採用担当〇〇と申します。ただいま、〇分ほどお時間よろしいでしょうか?」と相手の都合を確認します。
もし都合が悪そうな場合は、改めてかけ直す旨を伝えましょう。かける時間帯も、常識的な範囲内(就業時間内や、学生であれば授業時間を避けるなど)に配慮が必要です。
伝えるべきことの要点
電話では、まず応募への感謝を伝え、その後、残念ながら採用を見送る旨を明確に、しかし穏やかな口調で伝えます。長々と話すのではなく、要点を簡潔に伝えることを意識しましょう。「この度はご応募いただきありがとうございました。慎重に検討を重ねましたが、誠に残念ながら、今回は採用を見送らせていただくことになりました。」のように伝えます。
冷静かつ丁寧な口調
電話では声のトーンが直接伝わります。早口になったり、事務的な冷たい口調になったりしないよう、落ち着いて、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。相手への敬意と、残念な気持ちを伝える誠実なトーンが大切です。
質問への対応準備
電話の場合、候補者から不採用の理由などを質問される可能性があります。どこまで答えるか、どのように答えるかを事前に社内で決めておき、準備しておく必要があります。
「申し訳ございませんが、選考内容の詳細はお伝えできない決まりとなっております」と丁寧にお断りする場合や、差し支えない範囲で簡潔に伝える場合など、対応方針を明確にしておきましょう。不用意な発言はトラブルの元になる可能性があるため注意が必要です。
採用見送り理由を伝えるメリット
採用見送りの連絡において、多くの担当者が頭を悩ませるのが「見送り理由を伝えるかどうか、伝えるとしたらどのように伝えるか」という点です。
まずは、不採用理由を伝えるメリットを見ていきましょう。
候補者の納得感向上
具体的な理由(たとえ簡潔なものであっても)が伝えられることで、候補者はなぜ自分が不採用になったのかを理解しやすくなります。理由が全く分からない状態よりも、納得感を得やすくなり、結果を受け入れやすくなる可能性があります。
「何が足りなかったのか」を知ることで、今後の就職活動に活かそうと前向きに捉える候補者もいるでしょう。
企業イメージの向上(誠実さ)
理由を正直に、かつ丁寧に伝える姿勢は、候補者に対して「誠実な企業だ」「一人ひとりに向き合ってくれている」というポジティブな印象を与える可能性があります。たとえ不採用であっても、企業への好感度が高まり、将来的に良好な関係を築けるかもしれません。
口コミサイトなどで「理由をきちんと説明してくれた」といった好意的な評価につながることも考えられます。
採用見送り理由を伝えるデメリット・リスク
一方で、不採用理由を伝えることには、以下のようなデメリットやリスクも存在します。
伝え方による誤解やトラブル
理由の伝え方によっては、候補者に誤解を与えたり、反論されたりする可能性があります。特に、抽象的な表現や主観的な評価は、「納得できない」「不当な評価だ」と感じさせてしまうリスクがあります。また、候補者を不必要に傷つけてしまう可能性も考慮しなければなりません。
具体的なフィードバックの難しさ
候補者一人ひとりの詳細な評価内容や、他の候補者との比較に基づいた具体的なフィードバックを提供することは、時間的にも労力的にも大きな負担となります。また、面接官の主観や評価の機微に関わる部分を、誤解なく的確に言語化することは非常に難しい作業です。
法的リスクの可能性
最も注意すべきは法的リスクです。伝えた理由が、性別、年齢、信条、障がいなど、法律で禁止されている差別的な選考理由と受け取られかねない表現であった場合、訴訟などのトラブルに発展するリスクがあります。「社風に合わない」といった曖昧な理由も、場合によっては客観性に欠けるとして問題視される可能性もゼロではありません。(参考:厚生労働省「公正な採用選考の基本」)
見送り理由を伝える際の判断基準
上記メリット・デメリットを踏まえ、見送り理由を伝えるかどうか、どのように伝えるかは慎重に判断する必要があります。
企業の方針を確認する
まず、自社として不採用理由の開示について、どのような方針を持っているかを確認しましょう。全社的に「理由は原則として開示しない」と定めている場合もあれば、「問い合わせがあった場合には、可能な範囲で回答する」としている場合もあります。採用担当者個人の判断で動くのではなく、必ず組織としての方針に従う必要があります。
伝える場合の内容と表現方法
もし理由を伝える方針である場合、あるいは個別の問い合わせに対応する場合でも、伝える内容は慎重に検討する必要があります。以下の点を考慮しましょう。
- 客観的な事実に基づくか?:スキル、経験、資格など、客観的に判断できる要素に限定するのが安全です。
- 応募職種との関連性は?: 求められるスキルや経験とのギャップなど、職務遂行能力に関連する理由に留めるべきです。
- 差別的な要素はないか?:法律で禁止されている項目に抵触する可能性がないか、細心の注意を払います。
- 表現は適切か?: 候補者を不必要に傷つけたり、誤解を与えたりするような表現は避けます。
「〇〇さんの能力が低い」ではなく、「今回のポジションで求める〇〇の経験が、より豊富な方を優先させていただきました」のような、相対的な評価やポジションとの適合性に焦点を当てた表現を検討します。
やってはいけない採用見送りの注意点:「サイレントお祈り」はNG
丁寧な対応が求められる採用見送りですが、一方で絶対に避けるべき対応があります。それが「サイレントお祈り」です。
サイレントお祈りとは?
サイレントお祈りとは、企業が採用選考で不採用とした候補者に対して、合否の連絡を一切行わないことを指します。「お祈りメール(不採用通知メール)」すら送らず、候補者は結果を知らされないまま放置される状態です。
連絡をしない理由としては、「連絡の手間を省きたい」「応募者が多すぎて対応しきれない」「単なる連絡漏れ」などが考えられますが、どのような理由であれ、候補者にとっては非常に不誠実な対応と受け取られます。
サイレントお祈りが企業にもたらす悪影響
サイレントお祈りは、単に候補者に不快感を与えるだけでなく、企業にとって以下のような深刻な悪影響をもたらします。
企業イメージの大幅な低下
連絡をしないという行為は、「候補者を軽視している」「不誠実な会社だ」という印象を強く与え、企業のイメージを著しく損ないます。候補者は、自分が時間と労力をかけて応募し、選考に参加したにも関わらず、結果すら知らされないことに憤りや失望を感じるでしょう。
SNSでの悪評拡散リスク
現代では、就職・転職活動に関する情報は、口コミサイトやSNSを通じて瞬時に拡散されます。サイレントお祈りを受けた候補者が、その経験を「〇〇社はサイレントだった」「連絡なしで最悪」といった形で書き込む可能性は非常に高いです。こうしたネガティブな情報は、他の求職者の目に触れ、「この会社に応募するのはやめよう」という判断につながりかねません。
優秀な人材の機会損失
一度サイレントお祈りを受けた候補者は、その企業に対して強い不信感を抱きます。たとえ将来、その候補者がスキルアップし、企業が求める人材像に合致するようになったとしても、過去の不誠実な対応が原因で、二度とその企業に応募しようとは思わないでしょう。これは、将来の優秀な人材獲得の機会を自ら放棄していることに他なりません。
候補者の不信感増大
サイレントお祈りは、特定の企業だけでなく、採用市場全体に対する不信感を助長する可能性もあります。「どうせ連絡なんて来ないだろう」と考える候補者が増えれば、採用活動全体の健全性が損なわれることにもつながりかねません。
必ず連絡を入れる体制を構築する
上記のような悪影響を避けるためにも、採用選考の結果は、合否に関わらず、必ず全ての候補者に連絡する体制を構築・徹底することが不可欠です。
応募者が多い場合など、連絡作業が負担になることもあるかもしれませんが、企業の信頼を守り、将来の採用活動を成功させるためには、避けては通れない重要なプロセスです。誠実な対応を積み重ねることが、結果的に企業の利益につながります。
- 連絡漏れを防ぐ仕組み:応募者管理システム(ATS)などを活用し、誰にいつ連絡したかを確実に管理する。
- 担当者への教育・周知:採用に関わる全ての担当者が、結果連絡の重要性を理解し、サイレントお祈りは絶対に許されないという認識を共有する。
- テンプレートの準備:迅速かつ効率的に連絡できるよう、事前に不採用通知メールのテンプレートを用意しておく。
- 連絡期日の設定と遵守:候補者に伝える連絡期日を設定し、それを遵守する。遅れる場合は必ず中間連絡を入れる。
採用見送り後の対応:将来につながる関係構築
採用見送りの連絡をしたら、それで終わりではありません。見送り後の対応も、企業の印象を左右し、将来の採用活動につながる可能性があります。
ここでは、応募書類の取り扱いと、タレントプールの活用について解説します。
応募書類の適切な取り扱い
候補者から預かった履歴書やエントリーシートなどの応募書類は、個人情報に該当します。そのため、個人情報保護法の規定に則り、適切に取り扱う義務があります。
主な対応としては、「返却」または「破棄」のいずれかとなります。いつまでに破棄するかについても、社内規定で明確にしておくと良いでしょう。
タレントプールの活用
タレントプールとは、過去に応募があった候補者(採用見送り者を含む)や、イベントなどで接触した潜在的な候補者の情報をデータベース化し、継続的にコミュニケーションを取る仕組みのことです。
これには以下のようなメリットがあります。
- 採用コストの削減:新たに求人広告を出したり、人材紹介を利用したりするコストを抑えられます。
- 採用期間の短縮:すでに企業に関心を持っている層にアプローチできるため、選考プロセスを短縮できる可能性があります。
- 優秀人材の確保:タイミングが合わずに採用を見送った優秀な人材に、適切なタイミングで再アプローチできます。
- 採用ブランディングの向上:継続的な情報提供により、候補者の企業への関心を維持・向上させることができます。
タレントプールへの登録案内方法
不採用通知を送る際に、候補者の同意を得た上で、タレントプールへの登録を案内することができます。
例えば、「〇〇様のこれまでのご経験やスキルは大変魅力的であり、今後、別のポジションでご活躍いただける可能性もございます。もしよろしければ、弊社のタレントプールにご登録いただき、今後、適合するポジションがオープンになった際に、優先的にご案内させていただけませんでしょうか?」といった形で、ポジティブに打診します。
その際、どのような情報が配信されるのか(採用情報、イベント情報、企業ニュースなど)、配信頻度、登録解除がいつでも可能であることなどを明記し、候補者が安心して登録できるように配慮することが重要です。必ず本人の明確な同意を得るようにしましょう。
再アプローチのタイミングと方法
タレントプールに登録してもらった候補者に対しては、定期的に企業の最新情報や関連する可能性のある求人情報を配信し、関係性を維持します。そして、候補者の経験やスキルにマッチする新たなポジションが生まれた際に、個別にアプローチを行います。
再アプローチの際は、「以前ご応募いただいた際の〇〇のご経験が、今回の新しいポジションに活かせると考え、ご連絡いたしました」のように、過去の応募内容を踏まえた上で、なぜ今回連絡したのかを具体的に伝えることが重要です。一方的な求人案内ではなく、候補者への関心を示すパーソナルなコミュニケーションを心がけましょう。
まとめ
この記事では、「採用見送りとは何か」から始まり、その重要性、具体的な連絡マナーと方法、理由の伝え方、避けるべきNG対応、そして見送り後の関係構築まで、幅広く解説しました。
採用見送りは、候補者にとっては残念な結果ですが、企業にとっては候補者体験を向上させ、企業ブランドを守り、将来の採用機会へと繋げるための重要なコミュニケーションの機会でもあります。連絡のタイミング、方法、内容、そしてその後の対応一つひとつに心を配ることが、企業の信頼を築き、長期的な成長に貢献します。
特に「サイレントお祈り」は、企業の評判を著しく損なうため、絶対に避けなければなりません。合否に関わらず、応募してくれた全ての候補者に誠意を持って連絡する体制を整えることが、採用活動の基本です。
この記事を参考に、丁寧で誠実なコミュニケーションの積み重ねを意識していきましょう。