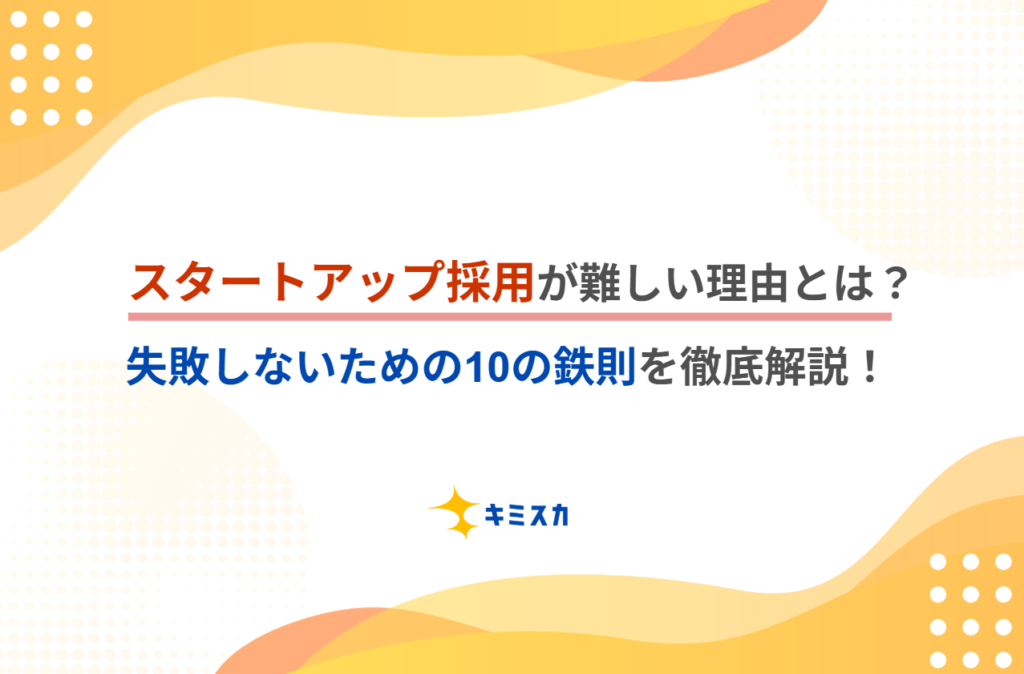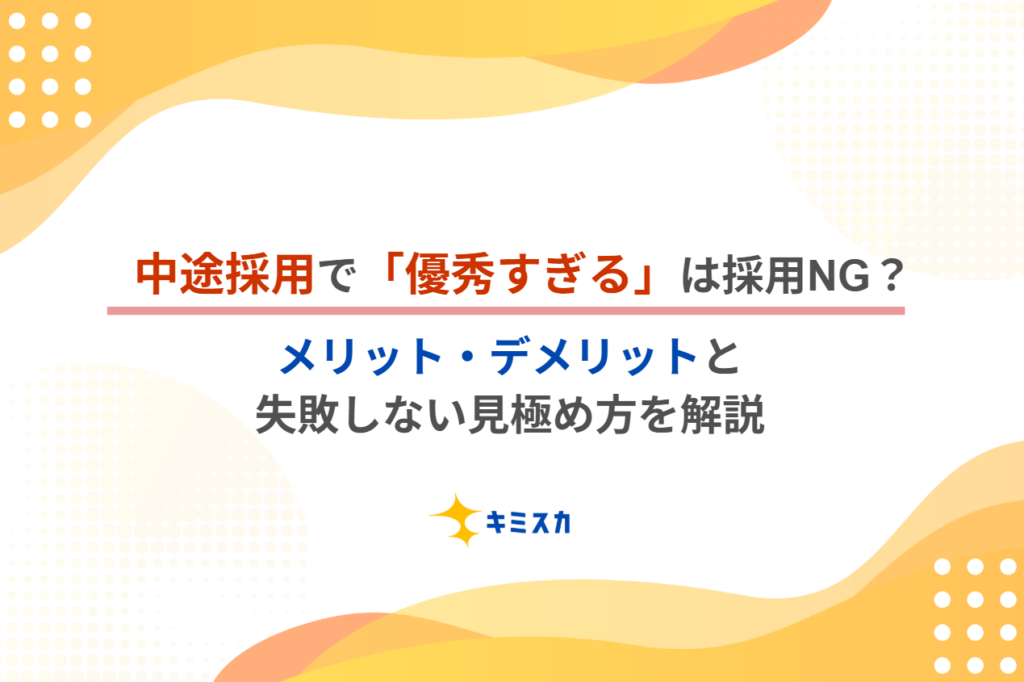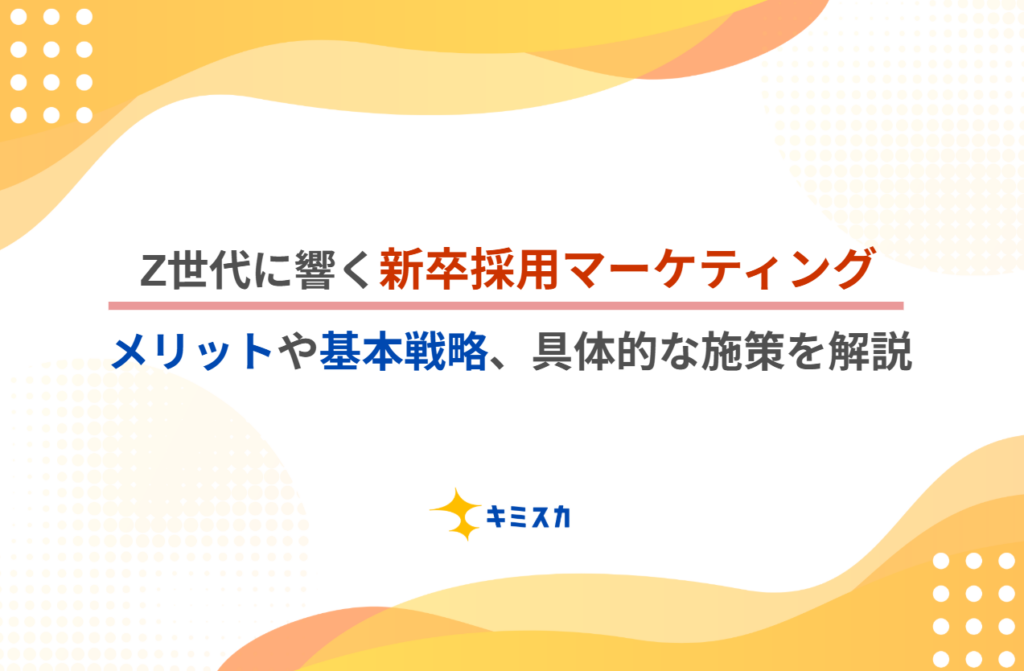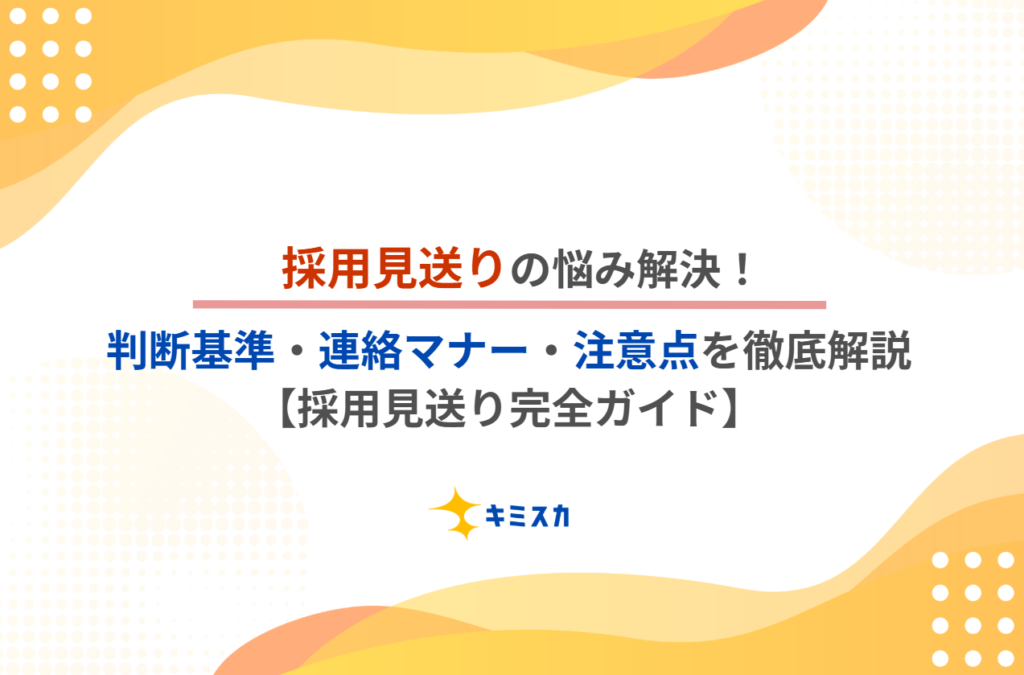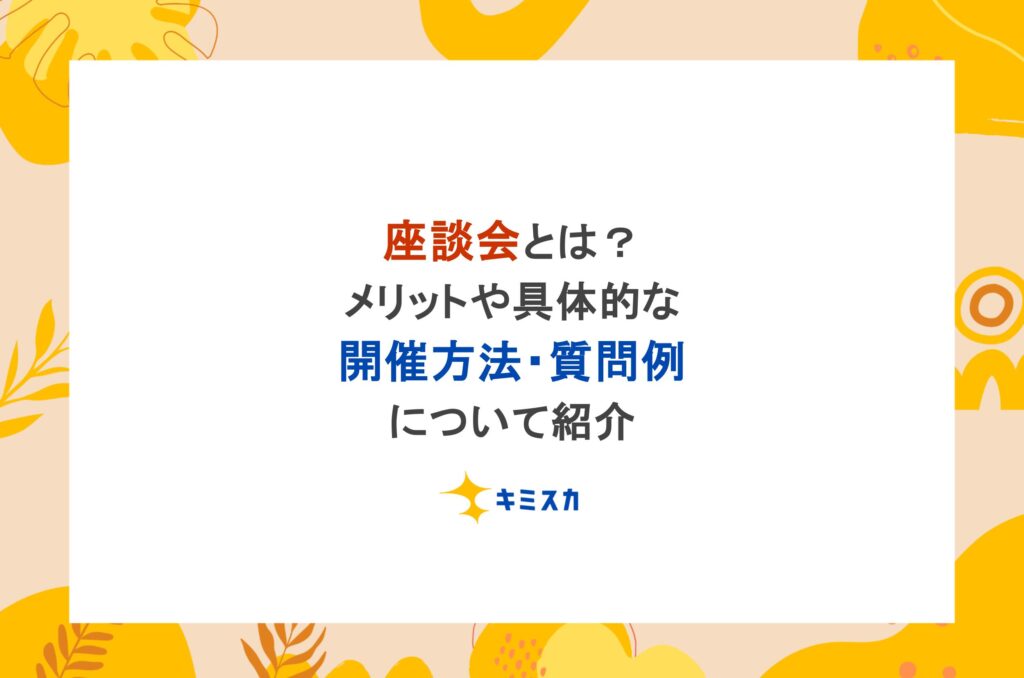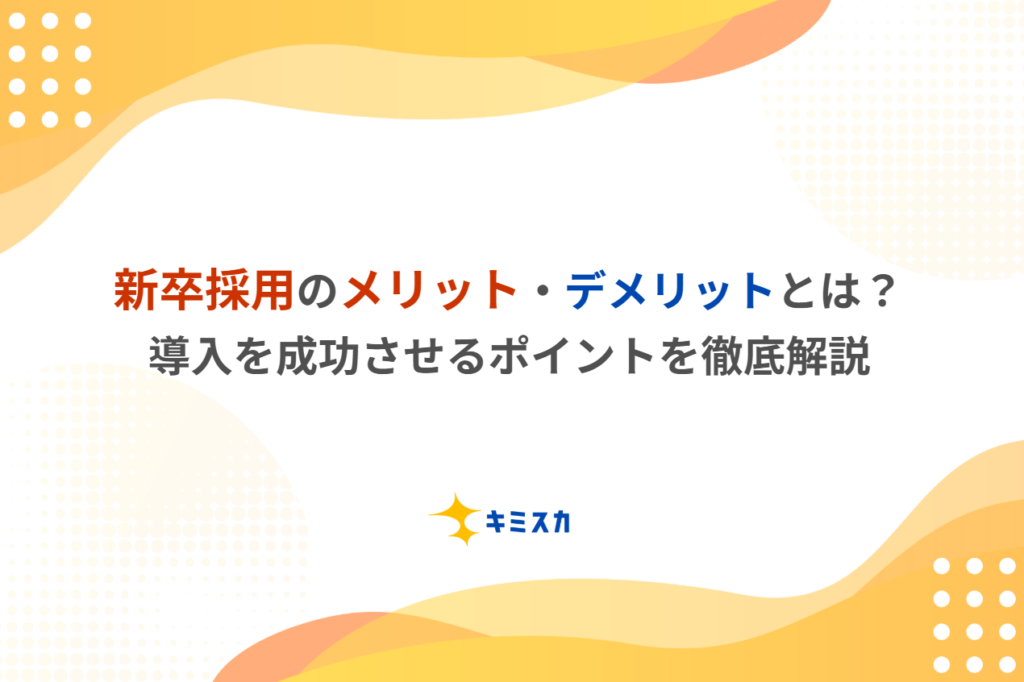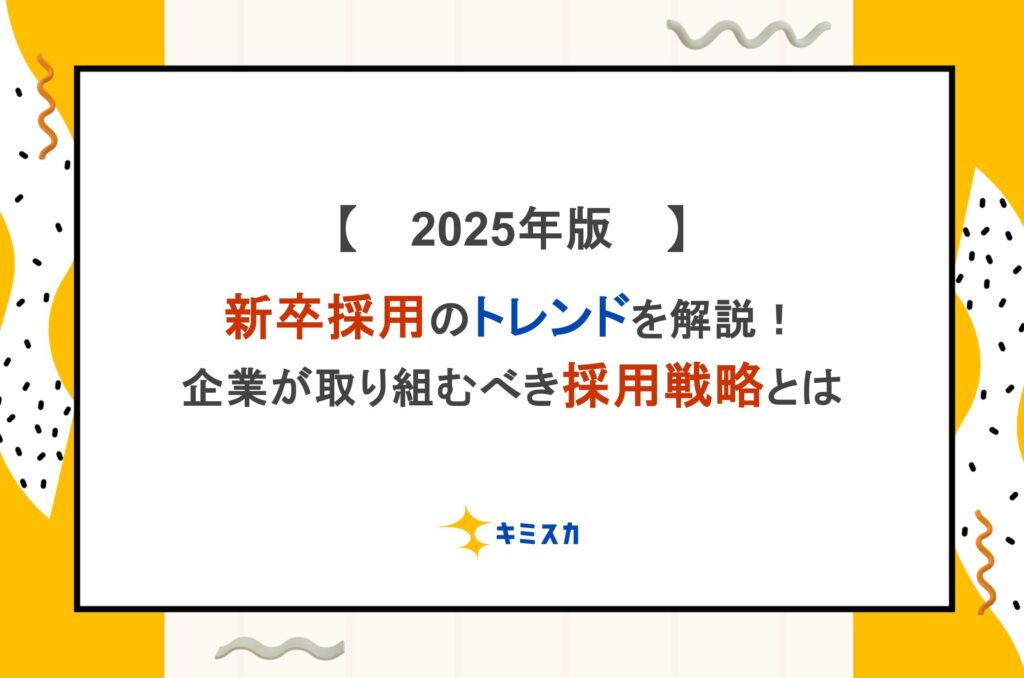
新卒の採用活動を効果的に行うためには、最新のトレンドを押さえておく必要があります。採用スケジュールは例年と異なることも多く、特に政府や経団連の要請が関係する場合があるほか、新しい採用手法が普及することもあるため、さまざまな観点からトレンドを把握しておくことが重要です。
そこで今回は、新卒採用における最新トレンドを詳しく解説します。就活生の価値観の変化や注目を集める採用手法、近年の動向に合わせた新卒採用の施策など、新卒採用を成功させるために欠かせない情報を確認しておきましょう。
26卒の新卒採用スケジュール
26卒の新卒採用スケジュールは25卒と大きく変わりませんが、どういった流れで進んでいくのか把握しておきましょう。ここでは、26卒のケースを例に大学3年6月からの流れを紹介します。
【6~9月】サマーインターンシップの開催
6~9月は大学3年生がサマーインターンシップに参加し始める時期です。
内閣府が2022年に発表した「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査結果について」によると、1Day仕事体験を含むインターンシップに一度でも参加したことがある学生は72.8%という結果が出ています。アフターコロナの現代では、さらに多くの学生がインターンシップに参加すると予想され、25卒からは採用直結型インターンが政府公認になったため、インターンシップ開催を積極的に行う企業も増えてくるでしょう。
インターンシップを開催する場合は、学生のニーズに応じたプログラムを実施することが重要です。この時期は志望企業が定まっていない学生も多いため、学生がキャリアビジョンを明確にできる内容が望ましいでしょう。
なお、インターンシップの設計方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
【10~12月】オータム・ウィンターインターンシップの開催
インターンシップを秋や冬に実施する企業も少なくありません。ただ、この時期になると就活に向けた準備を進める学生も多く、自己分析や業界研究などを通じて志望する業界・企業を絞り始めます。また、外資系企業をはじめ、総合商社や日系金融などでは早期に選考を行う場合もあり、すでに選考を受け始めている学生がいるのも実情です。
産学協議会の「産学協働による自律的なキャリア形成の推進」では、採用広報が解禁となる3月まで、採用活動へのエントリーに関する案内をインターンシップで取得した連絡先に送ることはできない規定となっています。また、政府や経団連が要請している採用活動スケジュールは、「採用広報解禁」が3月1日以降、「採用選考活動」が6月1日以降となっていますが、強制力がないために企業によってスケジュールが異なることも把握しておきましょう。
秋・冬のインターンシップは長期での実施が難しい場合があるため、1日で完結する「オープンカンパニー」や1週間程度のプログラムを行う「短期インターンシップ」などの実施も検討しておくことが重要です。
【1~2月】インターン参加者へのフォロー・採用選考の準備
1〜2月は、インターンシップに参加した学生に対してフォローを行ったり、3月から始まる採用選考の準備を進めたりしましょう。1〜2月は大学の後期試験が始まる時期なので、多くの学生が学業に注力する傾向にあります。そのため、学生への連絡は試験が落ち着くまで控えたり、頻度を減らしたりといった配慮が必要です。
ただ、インターンに参加した学生に対して全く連絡しないのも避けましょう。いつでも視聴できるセミナー動画の案内や、春休み前にオンライン座談会を開催するなど、この時期のフォローでは学生が参加しやすい方法を工夫し、企業への関心を維持することが重要です。
【3~5月】説明会の開催・広報活動
3月1日は採用広報の解禁日となるため、人事担当者が特に忙しくなる時期です。採用ナビサイトや自社の採用ページに求人情報を掲載したり、パンフレット配布やDM送信したりと、企業ごとにさまざまなアプローチを行うようになります。
また、産学協議会の規定に従う企業であれば、インターン参加者に対して採用広報に関する連絡が可能です。リアルやオンラインで会社説明会を行う企業もあれば、合同説明会に出展して広報活動を行う企業もあり、人事担当者は多忙を極めることとなるでしょう。
ただ、企業の中には5月までに面接を開始するところも少なくありません。新卒採用の準備を始める時期は企業ごとに異なるため、自社の新卒採用スケジュールを立てたい場合は、以下の記事を参考にしてみてください。
【6~9月】選考の実施から内定フォローまで
3月1日に採用広報が解禁されたあと、6月1日からは選考活動が解禁となります。
面接やグループディスカッションなどの選考をすることになりますが、人事担当者だけでなく現場社員や役員のスケジュール調整が必要です。次年度の採用活動としてサマーインターンシップも開催する場合は、人事担当者の負担が大きくなるでしょう。
また、6月はインターンシップ参加者へ採用選考についての案内を送れる時期なので、企業によっては選考・サマーインターンシップ開催・インターン参加者への連絡を並行することになります。面接の一部をオンラインで実施するなど、選考の効率化を図るのも検討しておきたいポイントです。
大学4年の6〜9月は夏季休暇もあるため、就活に力を入れる学生は少なくありません。就活生のなかにはすでに複数社の内定を獲得し、承諾する1社以外は辞退するケースもあります。内定辞退を回避するためのアプローチも必要ですが、理系学生などは卒業論文の制作などで忙しくしている可能性もあるため、連絡方法や内容には十分に配慮しましょう。
【10~2月】内定式・内定者研修
多くの企業では10月に内定式を開催するため、この年の採用活動も一段落がつきます。もちろん、企業独自の日程を設定している場合や採用スケジュールの都合で11月以降に内定式を開催するケースもあります。
また、入社する4月までに内定者研修が実施されますが、ライトワークスの調査「ライトワークス、近年の内定者と企業を対象にした「内定者研修に関する調査結果」を発表 ~内定者研修を成功させるポイントは、「知りたい」「自信を持ちたい」「繋がりたい」を満たすこと~」では、内定者研修を実施している企業は75%に上り、大多数の企業が実施していることがわかります。
すでに内定を獲得した学生のなかには、社会人になることへの不安を感じている人も少なくありません。そこで内定者研修では、不安解消や入社までのモチベーション維持、入社後に活躍するための知識・スキルの習得などを目的にしたプログラムを実施するのが重要です。
【学生・企業】新卒採用における今後の動向
26卒の採用スケジュールについて紹介しましたが、これからの新卒採用は企業・学生でどのような動きが見られるのでしょうか。ここでは、学生と企業それぞれの動向予測を紹介します。
新卒採用のトレンドは常に最新の情報を押さえておく必要がありますが、以下の情報を参考に自社に最適な採用計画を立ててみてください。
新卒採用|学生の動向
まずは学生の動向について紹介します。学生が就活を始めるタイミングや説明会・選考を受ける方法など、詳しく見ていきましょう。
【学生】就活の開始時期は大学3年6月までが大半
株式会社ワンキャリアが25卒の学生向けに行った調査「【調査レポート】25卒振り返り 入社志望度が最も上がるのは面接期間中」では、学生の7割以上が大学3年の6月までに就活を開始していると回答しています。
また同調査では、6月はサマーインターンシップへのエントリーが最も集中する時期であり、平均で11社以上(中央値8社)のエントリーを行っていることがわかりました。一方、秋・冬のインターンシップへのエントリーは9〜10月に集中していますが、エントリー数の平均は6.62社(中央値3社)となっており、夏よりも減少傾向にあるようです。
大学生の動き出しが早いのは、選考の早期化が関係していることが考えられます。本選考にエントリーする時期は大学3年の3月が21.1%ですが、それより前にエントリーしている学生は半数以上に及んでいるのが実情です。
そのため、26卒以降も夏のインターンシップ参加を機に、本格的に就活を開始する学生が多くいることが予測されます。
【学生】オンラインとオフライン共に需要がある
新型コロナウイルスの影響もあり、近年はオンラインで説明会を開催したり面接を行ったりする企業も多くなってきました。学生にとっても、移動の負担が減ったり気軽に参加できたりといったメリットがあるため、26卒以降の新卒採用でもオンラインへのニーズがあることが予想されます。
実際、株式会社ワンキャリアの「【調査レポート】最速|26卒早期層の就活動向 ~6割以上の学生が選考全体で対面を希望~」を見てみると、説明会はオンラインでの参加を希望する学生が過半数を占めています。ただ、インターンシップをはじめ、本選考や最終面接ではオフライン(対面)を希望する学生が多くいることは把握しておきましょう。
業界研究や企業研究といった情報収集を目的としている場合はオンライン形式、企業の雰囲気を直接確かめたい場合はオフライン形式に需要があります。こうしたニーズを汲み取って説明会開催や選考を行えば、良質な母集団形成や学生の志望度向上などにつながる可能性もあるでしょう。
新卒採用|企業の動向
26卒からは選考の早期化に合わせて学生が早く動き出し、オンラインで説明会を受けて効率よく就活を進めていくことが予測されます。こうした就活生のトレンドに応じて、企業はどういった行動を取るのが効果的なのでしょうか。
ここからは、新卒採用における企業の動向予測を紹介します。26卒以降の採用計画を立てる場合の参考にしてみてください。
【企業】採用活動の開始時期は早期化の傾向にある
株式会社ベネッセ i-キャリアが実施した「企業の新卒(25卒・26卒)採用計画実態調査」を見てみると、25卒を対象にした採用活動の開始時期は24年の3月が最多の24%となっていました。ただ、それよりも早い23年10月から翌年2月に採用活動を進める企業は合計で46.7%と半数近くにも及びます。
また、26卒は25年3月に採用活動を行う予定の企業は最多の13.2%ですが、2024年内に採用選考の実施を予定している企業の割合が増加しているため、選考早期化の傾向はさらに強まる可能性があります。
優秀な学生が大学3年の3月時点ですでに内定を獲得しているケースも珍しくないため、新卒の採用活動をいつから始めるかは慎重に検討しましょう。
【企業】オープンカンパニーの実施率が高まっている
先ほど取り上げた株式会社ベネッセ i-キャリアの調査「企業の新卒(25卒・26卒)採用計画実態調査」では、オープンカンパニーやインターンシップに関する調査結果も掲載されています。25卒にオープンカンパニーを実施した企業は58%と過半数に上りますが、翌年の26卒では、「実施予定あり」「実施検討中」を含めると74.9%となっており、25卒より増加する可能性が高いでしょう。
一方、25卒では夏と秋冬に5日以上のインターンシップを実施した企業は18%であり、内訳は夏が6%、秋冬が12%です。26卒では実施予定の割合が21.5%と微増だったため、近年はインターンシップよりもオープンカンパニーに注力する傾向にあるかもしれません。
オープンカンパニーは大学3年生だけでなく、1・2年生とも接点を持てるのが最大のメリットです。オープンカンパニーで入手した学生情報は採用活動に利用できませんが、早期に学生と接点を持っておけるために採用活動時の母集団形成につなげられます。もちろんインターンシップ開催にもメリットがあるため、自社に合った手法を吟味することが大切です。
【企業】オンラインを積極的に活用する企業も増加
学生のニーズに合わせるかのように、オンラインを積極的に活用する企業も増えてきました。「企業の新卒(25卒・26卒)採用計画実態調査」でも、会社説明会や個別相談会は対面よりもオンラインで行う企業のほうが多い結果となっています。ただ、職場見学やワークショップ型の仕事体験は対面で実施する企業が多かったため、企業の雰囲気を直接感じてもらい入社意欲の向上につなげたい意図があるのでしょう。
説明会や選考をオンラインで実施するのは、企業にとってもメリットがあります。採用コストや効率化につながりやすいため、対面のみで採用活動を進めている企業はオンラインを取り入れてみるのもおすすめです。
説明会はオンライン・対面の2つを実施したり、一次面接のみオンラインで実施したりと、オンライン・対面を組み合わせることで選考参加のハードルを下げ、採用活動の効率化を図れるでしょう。
新卒採用手法のトレンド【4選】
これまでの新卒採用は、就職サイトを活用したり大学に求人票を出したりといった手法が用いられてきましたが、近年は新しい手法を取り入れている企業も少なくありません。具体的にどういった方法で新卒採用を行っているのか、ここでは新卒採用のトレンドとして押さえておきたい4つの採用手法を見ていきましょう。
1.ダイレクトリクルーティング
「攻めの採用」とも呼ばれているダイレクトリクルーティングは、求職者に対して企業が直接アプローチする採用手法のことをいいます。求人広告や人材紹介といった従来の手法では、採用のミスマッチが起きるケースも少なくありませんでした。しかし、ダイレクトリクルーティングで企業が就活生のスキルや適性にもとづいてアプローチすることで、ミスマッチを防ぎやすくなります。
ダイレクトリクルーティングでアプローチできるのは、サービスに登録している学生に限定されているため、できるだけ学生の登録者数が多いサービスを選ぶのがおすすめです。
2.リファラル採用
リファラル採用とは、企業の従業員に知人や友人を紹介してもらう採用手法のことです。紹介者である社員が、求職者の人柄や能力と企業の求める人物像を擦り合わせたうえで紹介してくれるため、カルチャーフィットしやすい点が特徴といえます。
また、リファラル採用は紹介者にインセンティブを支払うだけで採用につなげられるため、採用コストを抑えてマッチ度の高い人材を採用したい場合に向いているでしょう。ただ、既存社員に通常業務と並行して人材を紹介してもらうため、候補者を集めづらい点には注意が必要です。
3.SNS採用
近年はInstagramやXといったSNSを活用した採用手法にも注目が集まっています。自社のSNSアカウントを作成し、企業の魅力や価値観を発信することで、学生に興味・関心を持ってもらうのが主な目的です。SNSでは広く情報発信できるだけでなく、個別に連絡を取ることも容易なので、手軽に始められる手法といえるでしょう。
求人広告などでは企業情報の発信方法が限られているケースもありますが、SNSであれば文章・動画・画像を載せられるため、発信できる情報の自由度が高いのも嬉しいポイントです。
4.ミートアップ
ミートアップは2015年ごろから実施企業が増えてきた採用手法です。交流会や勉強会など直接交流する場を設け、座談会や現場社員とのコミュニケーションを通じて企業の社風や魅力を伝えます。
選考を意識してしまうと学生は緊張することもありますが、ミートアップであれば気軽に参加できるため、学生の人柄や本音を引き出したい場合には効果的な手法といえるでしょう。また、ミートアップは低コストで開催できるほか、企業のブランディングやファン作りにもつながるため、母集団形成や長期的な目線で実施する価値があります。
ただ、ミートアップは企画・開催に労力がかかり、内容によっては人手やスケジュール調整が必要になります。さらに、就活生が必ず参加してくれるとは限らないため、SNSなどで情報発信して集客を行う必要があることも把握しておきましょう。
新卒採用のトレンドをもとに最適な採用戦略を検討しよう
新卒採用におけるトレンドは年度ごとに変わることも珍しくなく、効果的な採用活動を行うためには常に最新の情報を集めておく必要があります。特に近年は労働力人口の減少にともない人材獲得競争が激化しており、採用広報解禁の3月1日よりも前に選考を開始する企業も少なくありません。また、SNS採用のように従来にはなかった採用手法も広まっていることもあり、優秀な人材をどのように獲得すればよいか悩む方もいるでしょう。
「新卒採用の最新情報を入手したい」「採用活動で相談相手が欲しい」という場合は、キミスカまでご相談ください。キミスカは新卒採用に特化したダイレクトリクルーティングサービスで、豊富な機能が搭載されているほか、カスタマーサクセスが徹底サポートします。分析データを活用したコンサルティングも実施しているため、企業にとって最適な提案をいたします。
キミスカの資料はこちらよりダウンロード可能です。