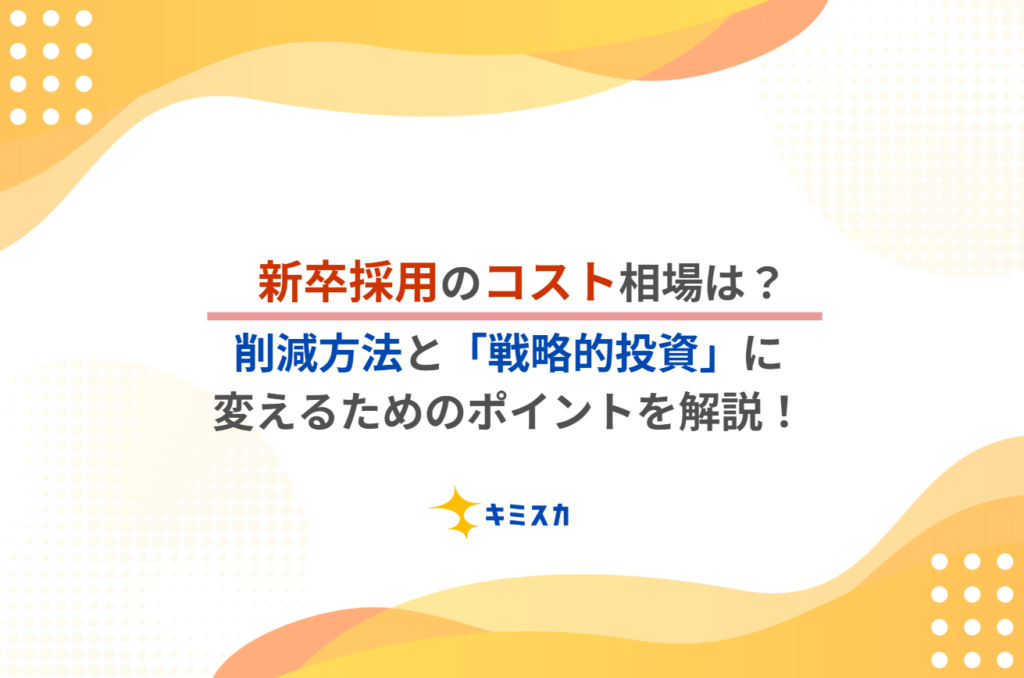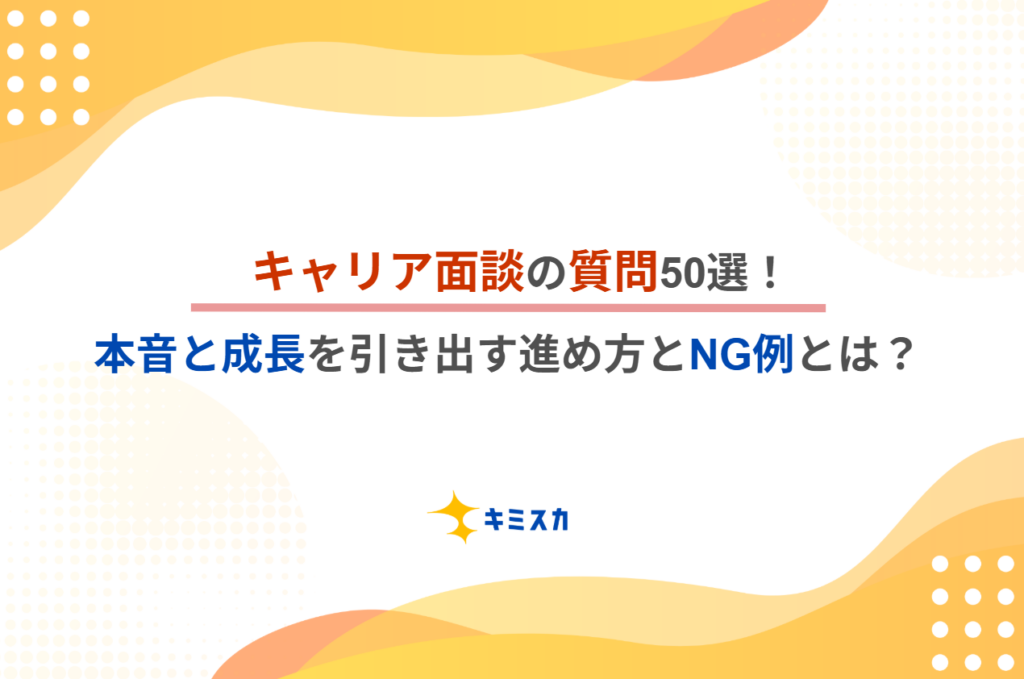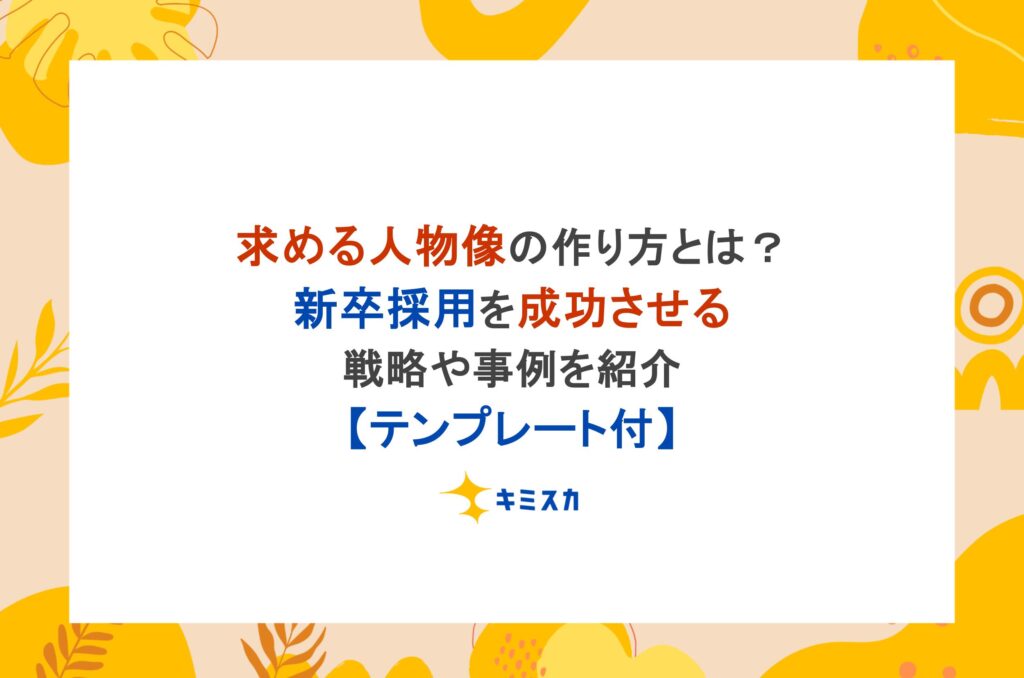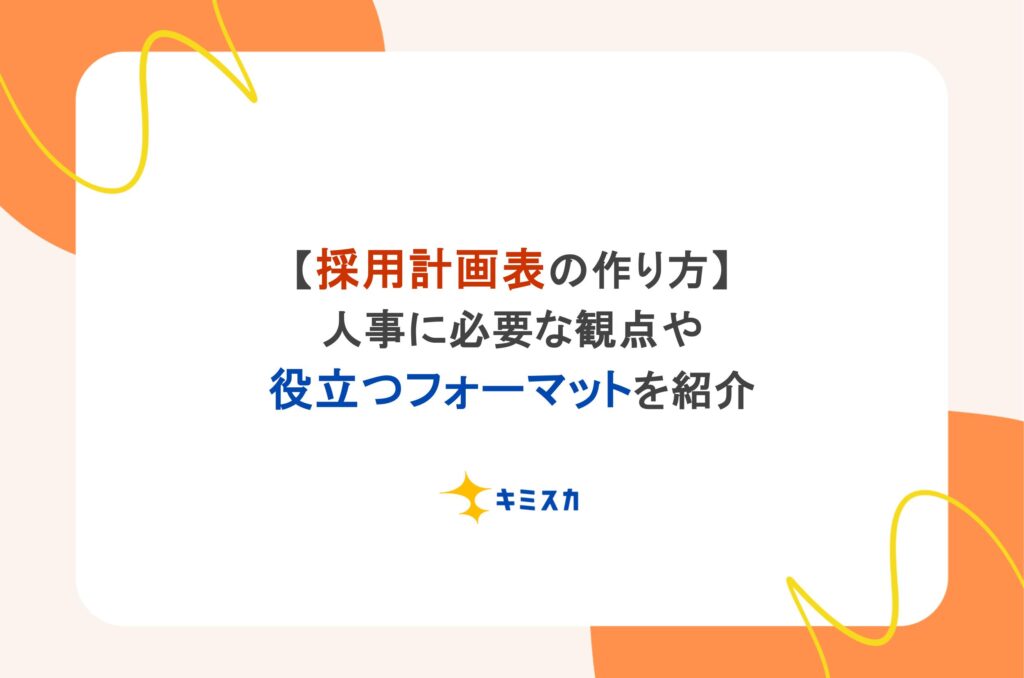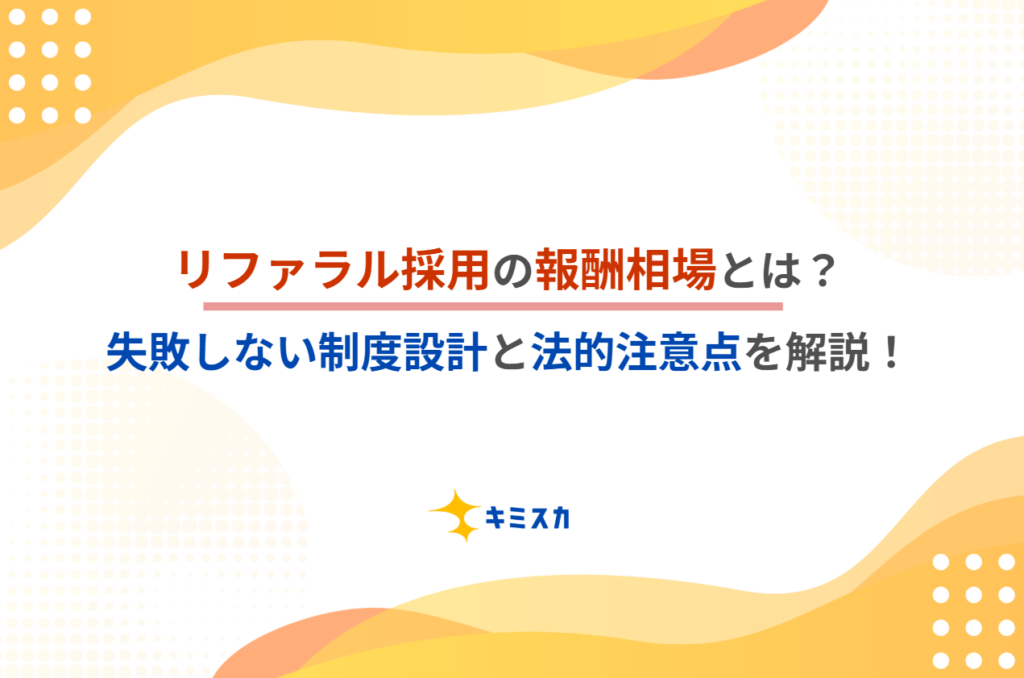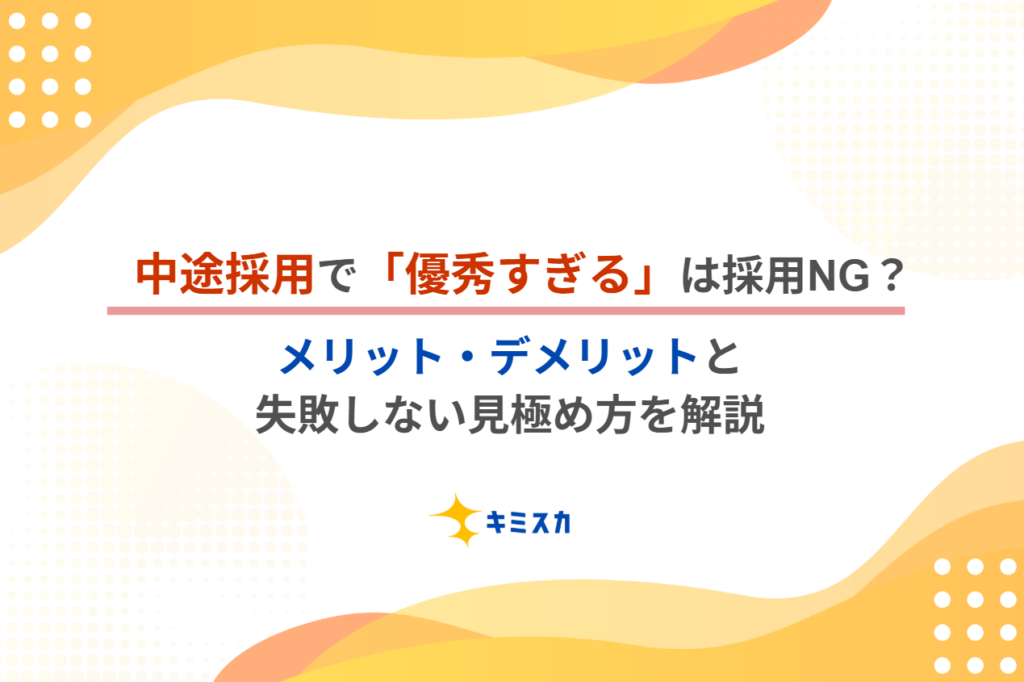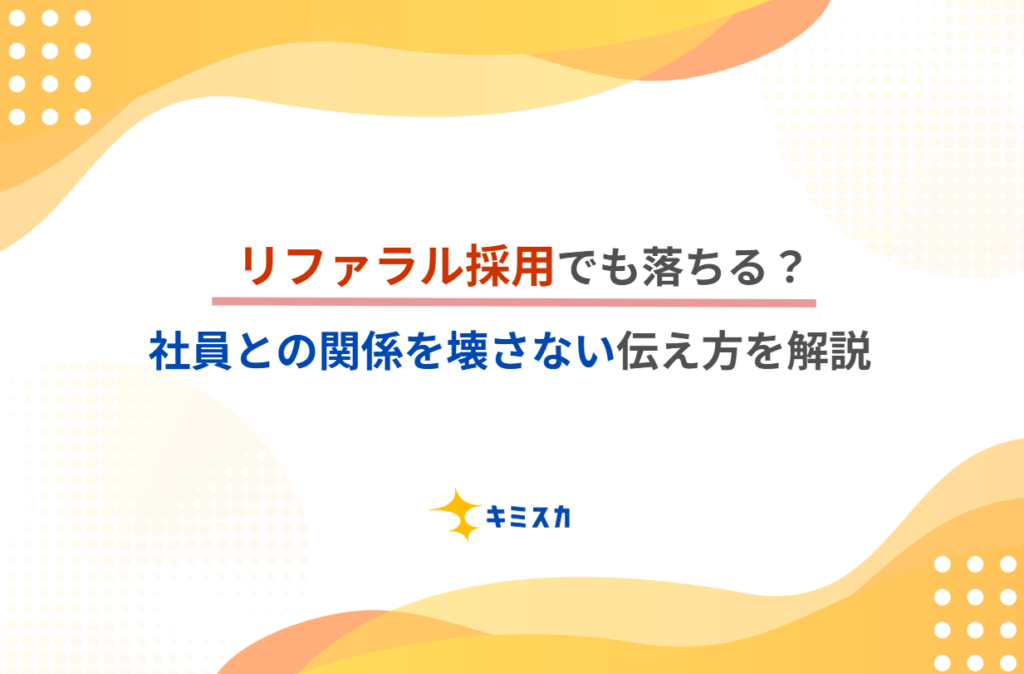
「社員がせっかく紹介してくれた候補者だが、残念ながら今回は見送りたい…」
「不採用にした場合、紹介してくれた社員との関係が気まずくならないだろうか…」
リファラル採用は、優秀な人材と出会える非常に有効な採用手法ですが、その一方で、紹介された候補者を不採用にする際の対応は、人事担当者にとって最も神経を使う業務の一つではないでしょうか。
この記事では、そんなデリケートな場面で人事担当者が取るべき対応を、具体的なステップとコミュニケーションのポイントを交えて体系的に解説します。
リファラル採用でも「落ちる」ことはある?
まず大前提として、リファラル採用であっても候補者が不採用になる、つまり「落ちる」ことは、決して珍しいことではありません。むしろ、健全な選考プロセスを経ていれば、当然起こり得ることです。この点を社内、特に紹介者となる社員に正しく認識してもらうことが、制度運用の第一歩となります。
リファラル採用における選考通過率の目安
リファラル採用は、一般的な公募に比べて選考通過率が高い傾向にあるのは事実です。社員が自社の文化や求める人物像をある程度理解した上で紹介するため、初期段階でのミスマッチが少ないからです。しかし、最終的な内定承諾に至る割合は、決して100%ではありません。データは様々ですが、応募から内定に至る割合は20%~30%程度とも言われており、多くの候補者が選考過程で不採用になっていることが分かります。
なぜ「紹介だから受かる」とは限らないのか
リファラル採用の目的は、あくまで「自社にマッチする優秀な人材と出会う機会を増やす」ことであり、「縁故採用」とは全く異なります。厚生労働省が打ち出している「公正な採用選考の基本」にもあるように、企業は、事業を成長させるために、客観的かつ公平な基準で採用の可否を判断する責任があります。
もし紹介という理由だけで採用基準を甘くしてしまうと、入社後のミスマッチやパフォーマンス不振に繋がり、かえって紹介者と候補者、そして会社の三者全員が不幸になる結果を招きかねません。
ちなみに、リファラル採用と混同されることがある「縁故採用」とは、企業の役員や社員などの縁故者を通じて、人材を採用する手法のことです。詳しくは『縁故採用はトラブルのもと?導入前に知るべき4つのリスクと対策・メリットを解説!』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。
リファラル採用で候補者を不採用にする主な理由
では、具体的にどのような場合に、紹介された候補者が不採用となるのでしょうか。企業がリファラル採用で候補者を見送る際の、正当かつ一般的な理由を4つ解説します。
1. スキルや経験のミスマッチ
最も多い理由が、候補者のスキルや経験が、募集ポジションで求められる要件と合致しないケースです。紹介者が候補者の人柄を高く評価していても、実際の業務遂行に必要な専門知識や実務経験が不足している場合は、不採用の判断となります。特に専門職や管理職の採用では、このスキル要件が非常に重要視されるため、シビアな判断が下されることが多くあります。
2. カルチャーフィットへの懸念
スキルや経験は十分であっても、企業の文化や価値観、チームの雰囲気と合わない(カルチャーフィットしない)と判断される場合も不採用の理由となります。例えば、チームワークを重んじる社風の中に、個人プレーを好む候補者が入ると、組織全体のパフォーマンスを損なう可能性があります。候補者本人にとっても、カルチャーが合わない環境で働くことは大きなストレスとなるため、これは双方にとって重要な判断基準です。
3. 給与など条件面でのミスマッチ
候補者が希望する給与や待遇と、企業が提示できる条件が折り合わないケースです。特に優秀な人材ほど、現在の給与水準も高い傾向にあり、中小企業にとっては提示できる条件に限界があることも少なくありません。双方にとって納得のいく条件が見つからない場合は、残念ながら不採用という結論に至ります。これは、どちらが悪いというわけではなく、純粋な条件の不一致と言えるでしょう。
4. 面接時の言動やマナーの問題
基本的なことですが、面接時のコミュニケーションや態度、マナーに問題があると判断された場合も、不採用の理由となり得ます。紹介された候補者であっても、選考プロセスにおける一人の応募者です。社会人としての基本的な受け答えができなかったり、企業のビジョンに対して否定的な態度を示したりした場合は、スキル以前の問題として、採用が見送られることがあります。
【人間関係を壊さない】不採用を伝える5つのステップ
リファラル採用で不採用を決定した際、最も重要なのは「伝え方」とその「順番」です。このプロセスを誤ると、社員の信頼を損ない、制度そのものを揺るがしかねません。ここでは、人間関係を壊さずに、誠実な対応を行うための具体的な5つのステップを解説します。
STEP1. 社内で不採用の最終意思決定と理由を固める
まず、関係者(面接官、人事、役員など)の間で、不採用とする最終的な意思決定を行います。そして、その結論に至った理由を、誰が見ても納得できる客観的な言葉で明確にまとめておきます。「なんとなく合わない」といった曖昧な理由ではなく、「〇〇のスキルが、今回のポジションで必須の要件に達していなかった」など、事実に基づいたロジックを固めることが、この後の全てのステップの土台となります。
STEP2. 紹介者への伝え方を準備する
次に、紹介してくれた社員へ、いつ、誰が、どのように伝えるかを準備します。メールやチャットだけで済ませるのではなく、可能な限り、対面やビデオ会議で直接伝えるのが望ましいでしょう。伝えるべき内容(感謝、結論、客観的な理由、今後の期待)を事前に整理し、どのような質問が来そうかを想定して、回答を準備しておきます。この準備が、誠実な対応に繋がります。
STEP3. 紹介者へ先に、かつ丁寧に経緯を伝える
最も重要なステップです。候補者本人に結果を通知する「前」に、必ず紹介者の社員へ先に伝えましょう。友人である候補者から「不採用の連絡が来た」と知らされる前に、会社から直接経緯を聞くことで、紹介者は「自分は尊重されている」と感じることができます。この順番を間違えるだけで、社員は「梯子を外された」と感じ、会社への不信感を抱きかねません。伝える際は、次の章で解説するポイントを押さえ、丁寧に行ってください。
STEP4. 候補者本人へ誠実に不採用を通知する
紹介者への伝達が終わったら、速やかに候補者本人へ不採用の通知を行います。この連絡は、紹介者を介さず、必ず人事担当者から直接行うのが鉄則です。友人である紹介者に不採用を伝えさせるようなことは、絶対にあってはなりません。通知の方法は、企業のルールに則って行いますが、丁寧さと誠実さを心がけることが、紹介者の顔を立てることにも繋がります。
STEP5. 紹介者への感謝と今後の協力依頼を伝える
一連の対応が終わった後、改めて紹介者へ感謝の意を伝え、今後の協力をお願いしましょう。「今回は残念な結果になりましたが、〇〇さんの人脈は大変魅力的だと改めて感じました。今後も、弊社に合いそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひ積極的にお声がけいただけると嬉しいです」と伝えることで、紹介者は自分の行動が会社から評価されていると感じ、次の協力へのモチベーションを維持できます。
紹介社員への伝え方で押さえるべき重要ポイント
5つのステップの中でも、最もデリケートなのが紹介社員への伝達です。ここでのコミュニケーションを丁寧に行うことが、信頼関係を維持し、リファラル採用制度を継続させるための鍵となります。具体的なポイントをトーク例と共に解説します。
1. 感謝の気持ちを最初に伝える
結論を切り出す前に、まずは「会社の採用活動に協力してくれたこと」への感謝を、真摯な言葉で伝えましょう。「〇〇さん、先日は素晴らしいご友人をご紹介いただき、本当にありがとうございました」という一言があるだけで、相手はポジティブな気持ちで話を聞く体制を整えることができます。協力してくれたこと自体が、会社にとって非常に価値のある行為であることを、最初にしっかりと伝えることが重要です。
2. 不採用の客観的な理由を誠実に話す
次に、結論と理由を簡潔に伝えます。ここでは、候補者の人格を否定するような主観的な表現は避け、あくまで「募集ポジションの要件」と「候補者のスキル・経験」を照らし合わせた結果としての、客観的な事実を誠実に話すことが重要です。「〇〇さんのご経歴は素晴らしかったのですが、今回募集しているポジションで必須となる△△という実務経験が、少しだけ要件と異なっておりました」のように、事実を淡々と、かつ丁寧に説明しましょう。
3. 紹介者の貢献を評価し、今後の協力を依頼する
不採用というネガティブな結果で終わらせず、紹介者の貢献を改めて評価し、未来への期待を伝えることで、ポジティブな締めくくりを意識します。「今回は要件が合わず採用が叶わなかったですが、〇〇さんのような方と繋がっている△△さんの人脈は、弊社にとって大変貴重です。今後もぜひ、積極的なご紹介をお願いします」と伝えることで、紹介者のエンゲージメント低下を防ぎ、次回の協力へと繋げることができます。
紹介者へ伝える際のトーク例
紹介者へ採用見送りを伝える具体的なトーク例を記載します。テンプレ感が出すぎるのも味気ないためバランスが難しいですが、簡潔に「御礼・事実・理由」を伝えましょう。
【御礼】〇〇さん、お時間いただきありがとうございます。先日ご紹介いただいた△△さんの件ですが、まずはお力添えいただいたこと、本当に感謝しています。ありがとうございました。
【事実(結果)】社内で慎重に選考を進めさせていただいたのですが、誠に申し上げにくいのですが、今回はご縁を見送らせていただくことになりました。
【理由】△△さんのご経歴やスキルは非常に魅力的だったのですが、今回募集しているポジションで特に重要となる××という領域のご経験が、弊社の求める要件と少しだけ異なっており、苦渋の決断となりました。
【御礼】ただ、△△さんのような優秀な方と繋がっている〇〇さんのネットワークは、弊社にとって大変貴重だと改めて感じました。今後も、もし弊社に合いそうな方がいらっしゃいましたら、ぜひ積極的にお力添えいただけると嬉しいです。引き続き、よろしくお願いいたします。
候補者本人への誠実な不採用通知のポイント
紹介社員への伝達が終われば、次は候補者本人への通知です。たとえ不採用であっても、候補者は大切な社員の友人・知人です。通常の選考以上に、誠実で丁寧な対応を心がける必要があります。
1. 紹介者経由ではなく、企業から直接連絡する
不採用の通知を、紹介者である友人に依頼するのは絶対に避けるべきです。これは、企業の責任を紹介者に転嫁する行為であり、最も信頼を損なう対応と言えます。採用の可否を判断したのは企業であり、その責任において、人事担当者から候補者本人へ直接、かつ速やかに連絡するのがビジネスマナーです。
2. 感謝と期待を伝えつつ、簡潔に結果を通知する
通知の際は、まず応募してくれたことへの感謝を伝えます。その上で、「〇〇様の素晴らしいご経歴を拝見し、社内で慎重に検討を重ねましたが、誠に残念ながら、今回はご期待に沿いかねる結果となりました」というように、敬意を払いながらも簡潔に結論を伝えます。曖昧な表現で期待を持たせるようなことは避けましょう。
3. 不採用理由は具体的に伝えないのが原則
通常の選考と同様、リファラル採用においても、候補者本人に具体的な不採用理由を伝える必要はありませんし、伝えるべきではありません。理由を伝えることで、かえって候補者を傷つけたり、不要なトラブルに発展したりするリスクがあるからです。「選考の結果、総合的に判断し」といった定型的な表現に留めるのが一般的です。もし食い下がられた場合も、具体的な言及は避け、丁寧にお断りしましょう。
【予防策】そもそもミスマッチな紹介を防ぐには?
今回のようなデリケートな事態を未然に防ぎ、リファラル採用制度をより良く運用していくためには、継続的な改善が不可欠です。最後に、今後のミスマッチな紹介を防ぐための3つの改善策をご紹介します。
1. 紹介を依頼する際に、選考基準を明確に伝える
そもそも、求める人物像と大きく異なる候補者が紹介されるのは、社員が「どのような人材を求めているか」を正しく理解していないことが原因です。紹介を依頼する際には、単に「営業職が足りない」と伝えるだけでなく、「〇〇業界での法人営業経験が3年以上あり、新規開拓が得意な方」というように、必須要件(Must)と歓迎要件(Want)を具体的に、かつ明確に伝えることが重要です。
採用基準については、こちらの記事『「採用基準」の重要性とは?具体的な設定方法とメリットを解説!』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。
2. リファラル採用でも通常選考と基準は変えないと周知する
「紹介だから受かりやすい」という誤解が社内に広まると、安易な紹介が増え、選考の質が低下します。全社員に対し、「リファラル採用は、あくまで優秀な候補者と出会うための『きっかけ』であり、選考プロセスや基準は、通常の公募と一切変わらない」ということを、日頃から明確に周知徹底しておくことが、制度の健全な運用に繋がります。
リファラル採用の制度設計や注意点については、こちらの記事『リファラル採用の報酬相場とは?失敗しない制度設計と法的注意点を解説!』で解説しておりますので、合わせてご覧ください。
3. 紹介者への定期的な情報共有とフォローを行う
紹介があった後は、選考の進捗状況を、紹介者へ定期的に報告しましょう。「来週、一次面接です」「現在、最終選考の結果待ちです」といった簡単な情報共有があるだけでも、紹介者は「自分の紹介を、会社が丁寧扱ってくれている」と感じ、安心することができます。こうしたこまめなフォローが、最終的に不採用という結果になったとしても、紹介者の納得感を高める上で非常に効果的です。
まとめ
本記事では、リファラル採用で候補者が不採用になった際の、人事担当者が取るべき具体的な対応について、網羅的に解説してきました。
リファラル採用における不採用対応で最も重要なのは、紹介してくれた社員への最大限の配慮と、誠実なコミュニケーションです。適切な手順と丁寧な対話を心がけることで、人間関係を損なうことなく、むしろ社員との信頼関係を深め、リファラル採用という素晴らしい制度をさらに活性化させることが可能です。
今回の内容が、皆様のデリケートな悩みを解決し、健全な採用活動を推進するための一助となれば幸いです。