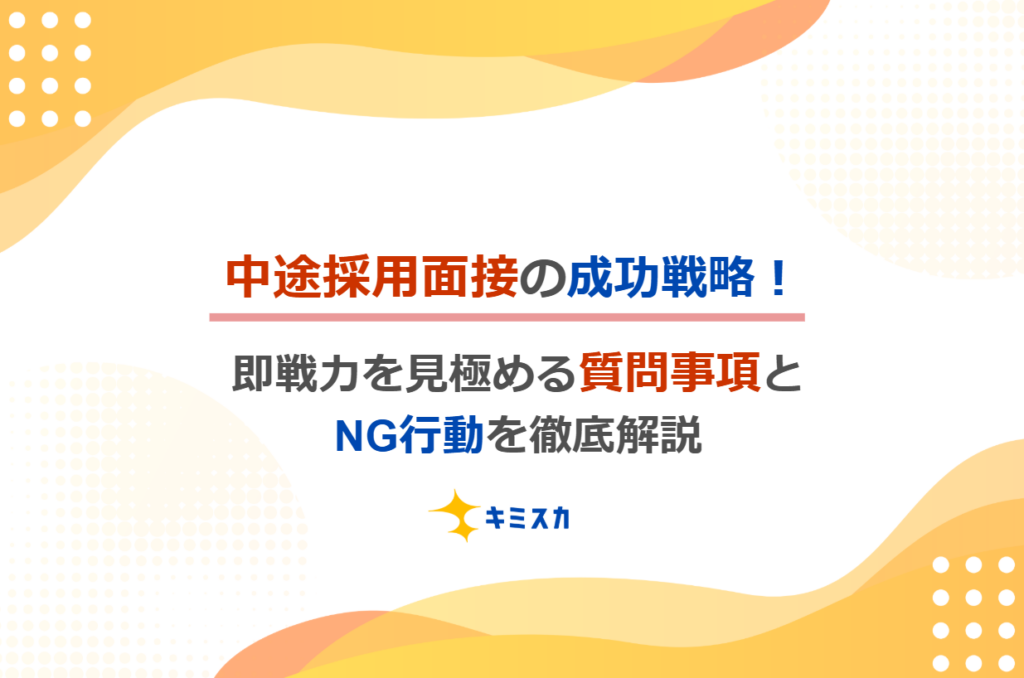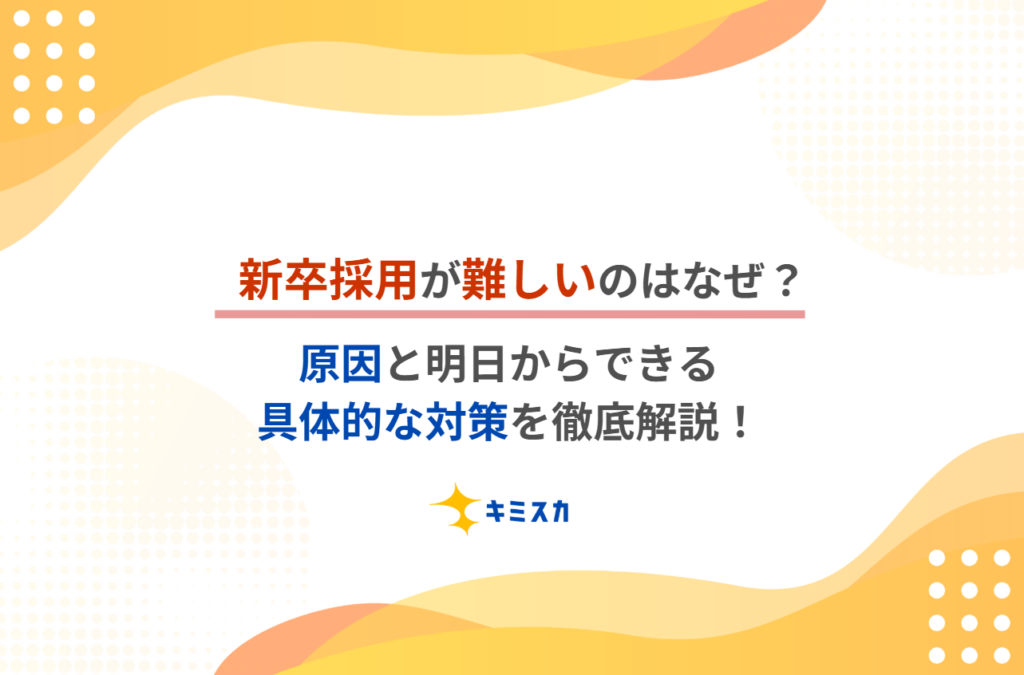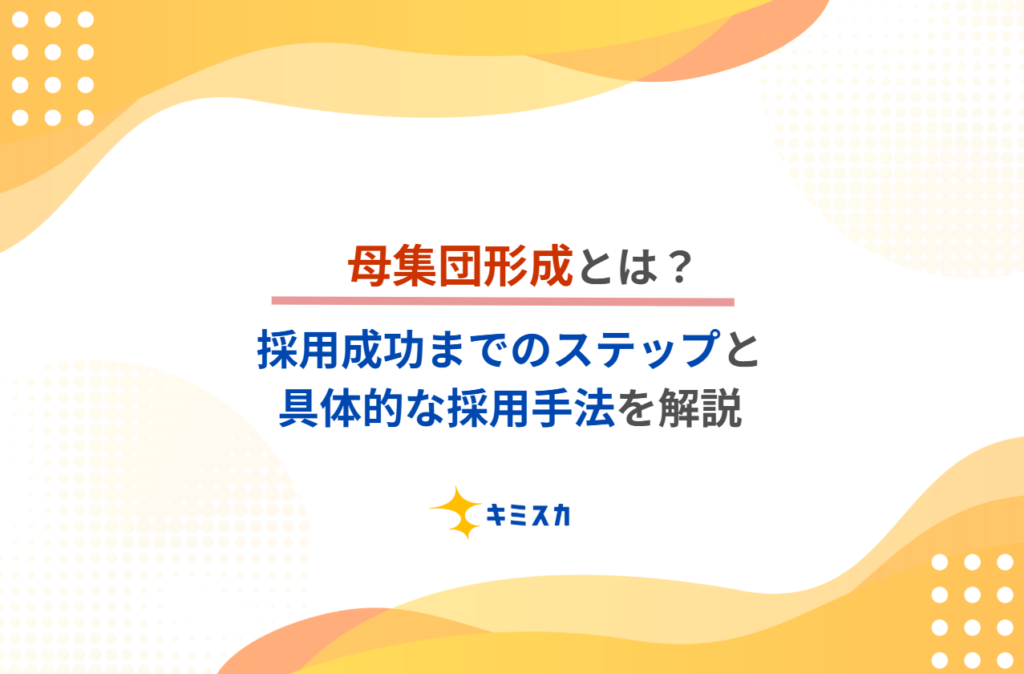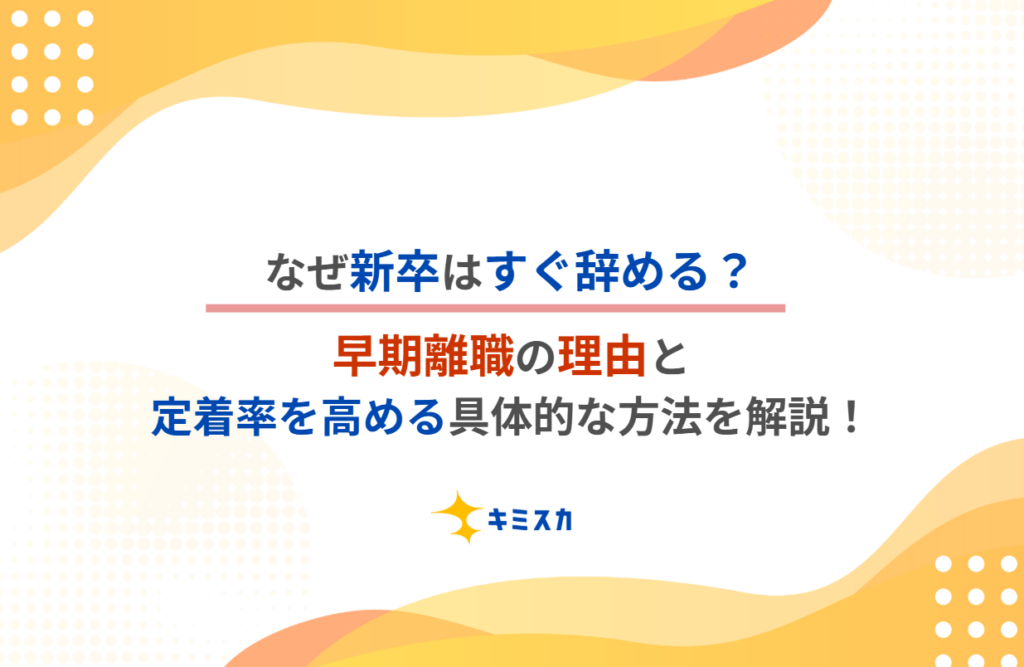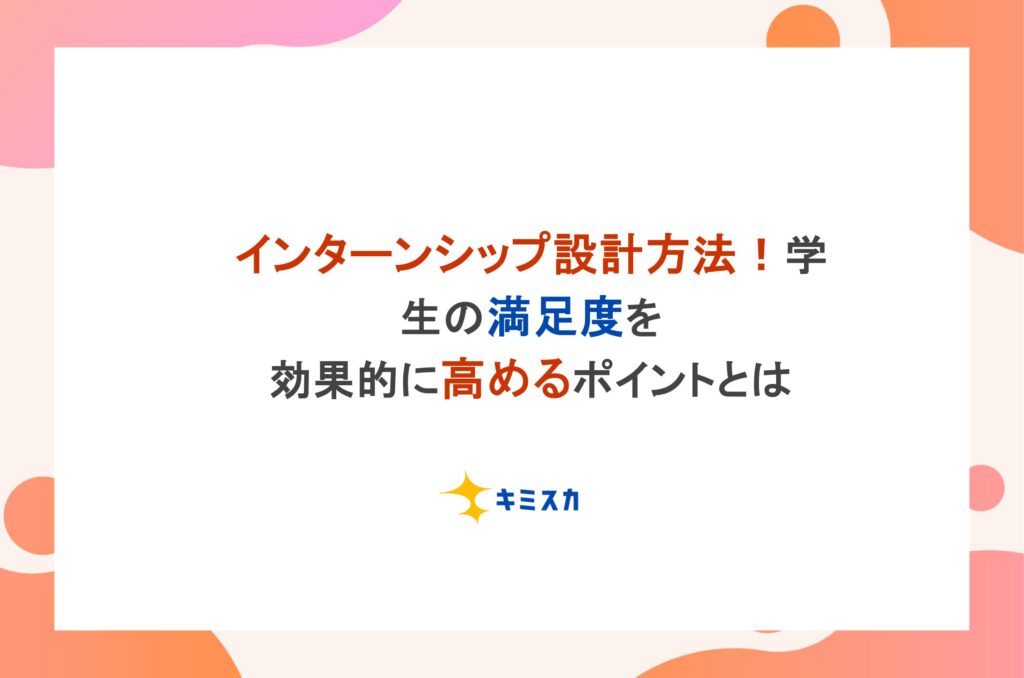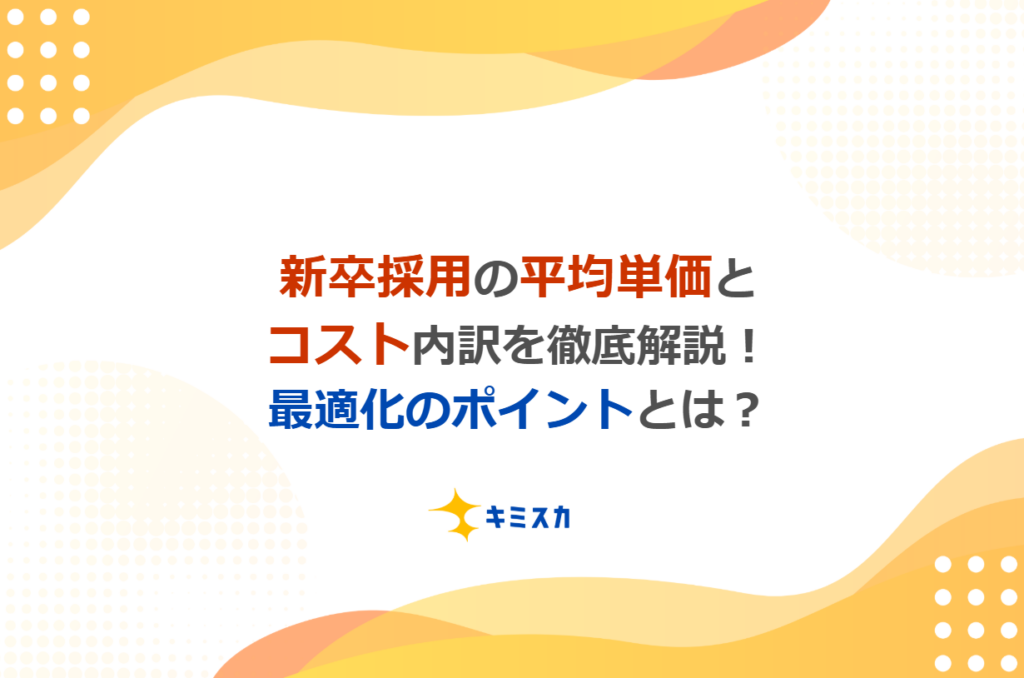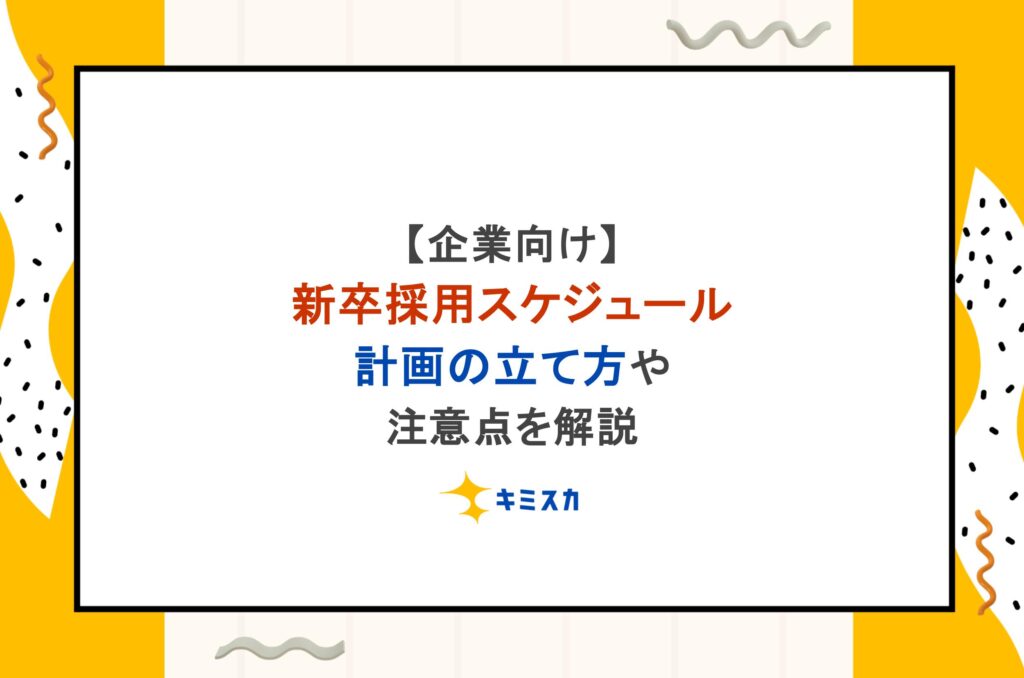
新卒採用は企業の未来を左右する重要な活動ですが、採用スケジュールを適切に立てるのは容易なことではありません。なぜなら、新卒の採用スケジュールは、ターゲットとなる学生の行動や政府が策定した指針を考慮したうえで立てる必要があるためです。
この記事では、新卒採用のスケジュールについて詳しく説明します。効果的な採用計画の立て方や注意点についても触れていきますので、新卒採用の成功を目指す企業はぜひ参考にしてみてください。
新卒の採用スケジュール
新卒採用のスケジュールを立てるときは、政府が定めた指針を理解しておく必要があります。まずは、新卒採用の基本的なスケジュールについて見ていきましょう。
新卒の採用開始はいつから?
新卒の採用スケジュールは、政府主導の取り決めがひとつの基準になります。内閣官房のホームページでは、2025年度卒業・修了予定者を対象とした採用スケジュールを以下のように定めています。
| 項目 | 日程 | 2025年卒の場合 |
| 広報活動開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 | 2023年3月11日以降 |
| 採用選考活動開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 | 2024年6月1日以降 |
| 正式な内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 | 2024年10月1日以降 |
なお、それぞれの日程で可能となる採用活動の具体例は次のとおりです。
| 広報活動開始以降 | 採用情報の公開プレエントリーの受付会社説明会の実施エントリーシートの受付 |
| 採用選考活動開始以降 | 採用試験面接 |
| 内定日以降 | 内定通知内定者フォロー |
ただし、上記のルールはあくまで「指針」であり、強制力があるわけではありません。政府から配慮を要請されてはいますが、就活解禁前に内々定を獲得している学生も多いのが実情です。
実際の採用活動は指針通りに進まないことが多いので、業界の動向や自社のリソースも考慮に入れて、「自社に適したスケジュール」を立てることが大切です。
新卒の採用はいつまで?
新卒採用の終了時期については、明確な規定はありません。多くの企業は4年生の夏ごろまでに採用活動を終えますが、なかには内定者が入社する直前の3月まで採用を続ける企業もあります。
ただし、入社直前の時期まで採用活動を長期化させることはおすすめできません。優秀な学生は早い段階で内定を獲得する傾向にあるので、採用活動が遅くなるほど、希望する人材の確保が難しくなる可能性があるためです。
また内定通知後は、内定者フォローに力を入れる必要があります。内定者との関係性を深め、入社までモチベーションを維持できるようにサポートすることで、内定辞退を防ぐ取り組みが不可欠です。
2025年の採用スケジュールは前倒しになる可能性が高い
経団連と産学協議会は、2025年度以降に条件を満たすインターンシップに参加した学生の情報について、採用選考時に利用することを認めました。これにより、インターンシップが実質的な採用活動の場となる可能性が高まっています。
企業にとっては、より早い段階から優秀な学生を見出し、採用につなげるチャンスが生まれます。一方で、学生側も早期からキャリアを意識し、企業研究を深めるよい機会になるでしょう。
この変更により、実質的な就活解禁は大幅に前倒しになることが予想されます。特に、人気企業や競争の激しい業界では、より早期から採用活動を始める動きが出てくるでしょう。各企業はこのような動向を考慮したうえで、自社の採用戦略を見直す必要があります。
新卒採用スケジュール早見表
新卒の採用スケジュールは、大きく3つのパターンに分けることが可能です。ここでは、各パターンの詳しいスケジュールについて確認していきましょう。
標準的なスケジュールの場合
| 企業の行動 | 時期 | 学生の行動 |
| ・前年の採用活動の振り返り | 2年生冬 | ・情報収集 |
| ・母集団形成・夏インターンの準備、選考 | 3年生4~6月 | ・自己分析・企業や業界研究・夏インターンへのエントリー |
| ・夏インターンの実施・秋冬インターンの準備、選考 | 3年生7~9月 | ・夏インターンへの参加・秋冬インターンへのエントリー |
| ・秋冬インターンの実施・本選考開始 | 3年生10~12月 | ・秋冬インターンへの参加・本エントリー |
| ・本選考・内定通知 | 3年生1~3月 | ・エントリーシートや面接による選考・内定承諾、辞退 |
| ・つなぎ止め施策・内定者に向けたインターン | 4年生4月以降 | ・内定者イベントへの参加・入社の最終判断 |
標準的なスケジュールの場合、3年生の春ごろに母集団形成をスタートします。就活生に向けた情報発信はもちろんのこと、企業説明会の開始やSNSを使ったPRなど、さまざまな手法で自社の認知拡大を目指します。
夏ごろからインターンシップを開始し、秋冬のインターンシップの時期に本選考を始める企業も少なくありません。早ければ、大学3年生の冬ごろには内定通知を出し始めます。
このタイプの選考スケジュールを採用するのは、大企業やブランド力が高い人気企業、旧帝大以上の学生を採用したい企業などです。優秀な学生をいち早く確保したい場合は、このスケジュールがおすすめです。
早期スケジュールの場合
| 企業の行動 | 時期 | 学生の行動 |
| ・前年の採用活動の振り返り | 2年生秋 | ・情報収集 |
| ・母集団形成・春インターンの準備、選考 | 2年生冬 | ・自己分析・企業や業界研究・春インターンへのエントリー |
| ・春インターンの実施・夏インターンの準備、選考 | 3年生4~6月 | ・春インターンへの参加・夏インターンへのエントリー |
| ・夏インターンの実施・本選考開始 | 3年生7~9月 | ・夏インターンへの参加・本エントリー |
| ・本選考・内定通知 | 3年生10~12月 | ・エントリーシートや面接による選考・内定承諾、辞退 |
| ・つなぎ止め施策・内定者に向けたインターン | 3年生1~3月以降 | ・内定者イベントへの参加・入社の最終判断 |
早期スケジュールの場合は、大学2年生の冬くらいから母集団形成を始めます。また、大学3年生の4月以降に春インターンを行う点も特徴的です。
このパターンでは、大学3年生の12月には内定出しが行われ、1月には充足し始めることが多い傾向にあります。早い段階で採用活動が終わる点はメリットでもありますが、内定者フォローの期間が長くなる点に注意が必要です。
早期に選考をスタートする傾向にある企業として、ベンチャー企業や大手金融、外資系企業、総合商社などが挙げられます。特に優秀な学生を採用したい企業や、超人気企業に比べるとブランド力がやや劣る企業に向いています。
晩期スケジュールの場合
| 企業の行動 | 時期 | 学生の行動 |
| ・前年の採用活動の振り返り | 3年生7~9月 | ・情報収集 |
| ・母集団形成・冬インターンの準備、選考 | 3年生10~12月 | ・自己分析・企業や業界研究・冬インターンへのエントリー |
| ・冬インターンの実施・本選考開始 | 3年生1~3月 | ・冬インターンへの参加・本エントリー |
| ・本選考・内定通知・つなぎ止め施策・内定者に向けたインターン | 4年生春以降 | ・エントリーシートや面接による選考・内定承諾、辞退・内定者イベントへの参加・入社の最終判断 |
晩期スケジュールの場合は、大学3年生の秋から母集団形成を始めることが一般的です。開催するインターンシップは冬のみで、同時進行で本選考や内定出しも行わなければいけません。
大学3年生の12月以降、一気に企業負担が大きくなるスケジュールなので、しっかりと計画を立てて採用活動を進めることが大切です。
このスケジュールで採用活動を行うのは、主にトップクラスのブランド力を持つ企業や採用人数が少ない企業です。ゆっくり採用活動を開始しても学生が集まる、超人気企業が該当します。
企業は新卒採用の準備をいつから始めるべき?
新卒採用を成功させるには、十分な準備期間を設けることが大切です。ここでは、新卒採用の準備から内定までの流れについて、5つのステップを確認していきましょう。
【新卒採用スケジュール】1. 採用の準備
採用の準備とは、以下のようなものを指します。
- 昨年の採用活動の振り返り
- 採用人数や具体的な採用スケジュールの策定
- 担当者の振り分け
- 担当者の教育
- 予算の確保 など
採用活動の準備には3か月程度の期間を要することが一般的ですが、採用人数や採用方法によってはさらに時間がかかることもあります。これまでの採用活動を振り返り、自社に適した準備期間を設けましょう。
【新卒採用スケジュール】2. 母集団形成
母集団形成とは、自社に興味を持ってくれる学生を増やし、質の高い応募者を確保する取り組みです。
一般的には、大学3年生の春ごろから本格的に開始します。ただし、春インターンシップを開催する場合は、2年生の冬ごろから準備を始めることもあります。
母集団形成を行う方法の一例は、次のとおりです。
- 会社説明会の開催
- 就活ナビサイトへの掲載
- SNSやメディアを通じた情報発信
- OB・OG訪問の実施
- 合同説明会への出展
大切なのは、単に学生の数を集めるだけではなく、自社と相性のよい良質な母集団を形成することです。母集団形成の手法やコツについては、こちらの記事をご覧ください。
【新卒採用スケジュール】3. インターンシップ
インターンシップは、学生に実際の業務を体験してもらうことで、より深く企業を理解してもらうチャンスです。同時に、企業側も学生の適性を見極める絶好の機会となります。
一般的なインターンシップの実施時期は次のとおりです。
- 春インターン:3年生の4~6月
- 夏インターン:3年生の7~9月
- 冬インターン:3年生の10~12月
- 冬インターン:3年生の1~2月
インターンシップを実施するときは、3か月以上前から準備を行い、3か月前時点ではエントリーを開始するスケジュールが理想的です。また、2025年卒からはインターンシップの参加情報を採用選考に活用できるようになるため、より戦略的な実施が求められます。
インターンシップについてはこちらの記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
【新卒採用スケジュール】4. 選考開始
選考の開始は、政府からの要請では「卒業・修了年度の6月1日以降」だと定められています。
しかし実際は、早い企業では3年生の夏ごろから選考が開始されます。特に、25卒からはインターンから採用まで直結させられるようになるので、選考開始が早期化することは間違いないでしょう。
早めに選考を行うときは、公平性と透明性を確保することが重要です。また、学生の学業に支障をきたさないよう配慮することも忘れてはいけません。
【新卒採用スケジュール】5. 内定
政府の要請では、「大学4年の10月1日」以降に内定出しを行うことが求められています。しかし、実際には大学3年生の冬ごろから内々定を出している企業も少なくありません。
早めに内定を出すことには、優秀な人材を確保できるというメリットがありますが、学生の就職活動の機会を奪ってしまうというデメリットもあります。企業の採用戦略と社会的責任のバランスを考慮しながら、適切な時期に内定を出すことが大切です。
なお、内定辞退対策についてはこちらの資料で解説しています。あわせてご覧ください。
新卒採用スケジュールを立てる手順
新卒採用スケジュールを立てるときの手順は、以下のとおりです。
- ターゲットを明確にする
- 採用KGIを設定する
- 採用KPIを設定する
- KPIから実行すべきタスクを逆算する
- タスクごとの担当者を決める
- 実行スケジュールを決める
まずはどのような学生を採用したいのか、いつまでに何人採用したいのかを明確にします。そのうえで、「説明会に○○人参加してもらう」「一次面接に○○人来てもらう」などのKPIを設定しましょう。
採用活動の対象となるターゲットや目的が明確になったら、そこから実施すべき施策を明らかにしていきます。この際「誰が何をするのか」など、具体的な担当者まで決めておくとスムーズです。
最後に、全体的な採用スケジュールの策定を行いましょう。本記事で紹介した「新卒採用スケジュール早見表」を参考にすると、大まかなスケジュール感を把握しやすくなります。
採用計画を立てるときは、「採用計画表」を作成することがおすすめです。詳しい作り方は、こちらの記事でご確認ください。
新卒採用スケジュールを立てるときの注意点
新卒の採用スケジュールを立てるときは、以下の注意点を意識する必要があります。
- 就活の早期化について理解しておく
- 各年度の就活動向を確認しておく
- リソースや予算に応じてスケジュールを立てる
どのようなことなのか、詳しく見ていきましょう。
就活の早期化について理解しておく
政府が示すルールでは解禁日が細かく定められていますが、実際には前倒しで採用活動をスタートする企業がほとんどです。
就活ルールには法的な拘束力や罰則がないので、「競合よりも早く優秀な人材を確保したい」という企業の都合が優先されてしまうのは仕方のないことかもしれません。さらに、長期インターンの広がりや就活のオンライン化により、早期化傾向は今後も継続すると予想されます。
「就活が早期化することが良い・悪い」と一概にいうことはできません。しかし企業としては、学生の学業に支障をきたすような採用スケジュールを立てることは避けるべきです。早期化傾向にあることを理解しつつ、ターゲットと自社に適した採用スケジュールを検討することが大切です。
各年度の就活動向を確認しておく
就活ルールは年々変化しており、学生の就活動向も毎年のように変わっています。そのため、「今年度はどうなのか」を正確に把握することが重要です。
例えば、2025年卒からはインターンシップの参加情報を採用選考に活用できるようになりました。また、オンライン選考が一般化するなど、採用を取り巻く環境は常に変化しています。
これらの動向をふまえて、自社の採用スケジュールや選考方法を適切に調整することが求められます。就職情報会社のレポートや、他社の採用担当者との情報交換などを通じて、最新の動向をキャッチアップしておきましょう。
リソースや予算に応じてスケジュールを立てる
採用活動は、企業にとって大きな投資です。やみくもに早期から採用活動を開始してもリソースや予算を無駄にしてしまうだけなので、計画的に行うことが大切です。
もちろん、早期から採用活動を開始すれば、自社に適した学生に出会えるチャンスは増えます。しかし、そのぶん多くの手間や費用がかかります。途中でリソースが足りなくなれば、学生一人ひとりと十分にコミュニケーションを取れなくなり、かえって採用の質が低下してしまうかもしれません。
まずは自社のリソースや予算を正確に把握して、それに見合った採用スケジュールを立てましょう。場合によっては、採用活動の一部をアウトソーシングしたりツールを導入したりして、効率化を図ることも検討してみてください。
新卒採用を成功させるスケジュールのポイント
新卒採用を成功させるスケジュールを立てるには、以下のポイントを意識することがおすすめです。
- ターゲット層の動きを理解しておく
- 早期から情報発信を開始する
- 前年度の採用スケジュールを振り返っておく
- 内定後のフォローにも力を入れる
- ダイレクトリクルーティングサービスを活用する
各項目の詳細を説明します。
ターゲット層の動きを理解しておく
自社に適した人材を確保するには、ターゲットとする学生層の動きを十分に理解しておく必要があります。
例えば、優秀な学生を獲得したい場合は早期に採用活動を始める必要があります。体育会系の学生をターゲットにする場合は、部活を引退するタイミングでアプローチするとよいでしょう。
このように、ターゲットによって就活をスタートする時期は異なります。採用したい学生の特性や行動パターンを分析して、それに適したスケジュールを組みましょう。
早期から情報発信を開始する
近年は、競合他社と差別化を図り、自社に入社したいと思ってもらうためのブランディング戦略が重要となっています。ブランディングには早期からの情報発信が大切なので、可能な範囲で取り組んでおきましょう。
情報発信の手法としては、次のようなものが有効です。
- 自社サイトやオウンドメディアの情報を充実させる
- SNSを活用する
- 早期インターンシップを開催する
- 大学でセミナーを開催する
企業・商材の魅力発信や、ターゲットとのコミュニケーションを通してエンゲージメントを高めておくと、学生にプラスの印象を抱いてもらえます。一貫性のある情報発信を行うことで、入社後のミスマッチを防ぎやすくなるというメリットもあります。
前年度の採用スケジュールを振り返っておく
前年度の採用スケジュールを振り返り、プロセスに改善の余地がないか確認しておくことも忘れてはいけません。
- 目標とする人数や質の人材を採用できたか
- 説明会やインターンシップなど、各施策がどの程度成果につながったか
- 各施策のタイミングは適切だったか
- 人的・金銭的リソースは適切に配分されていたか
- 競合他社の採用活動と比較して、自社の強みや弱みは何だったか
上記のような分析を行い、反省点やよかった点を今年度の採用スケジュールに反映させましょう。実際のデータをもとに改善を繰り返すことで、よりよい採用戦略にブラッシュアップしやすくなります。
内定後のフォローにも力を入れる
採用スケジュールの早期化だけを意識してしまうと、内定者のフォローがおろそかになり、内定辞退につながるため注意が必要です。意欲を維持させるために、内定者と定期的にコミュニケーションを取りましょう。
内定者フォローの具体的な取り組みとしては、次のようなものが挙げられます。
- 定期的な連絡
- 内定者向けイベントの開催
- 入社前研修の実施
- 情報提供
- メンター制度
このような活動を通じて内定者の不安を解消し、入社への期待感を高めていきましょう。同時に、内定者の状況を把握することで、入社後のミスマッチを防ぐ効果も期待できます。
ダイレクトリクルーティングサービスを活用する
就活の早期化による企業の負担増加を回避しつつ優秀な人材を採用するには、「ダイレクトリクルーティングサービス」の活用がおすすめです。
ダイレクトリクルーティングとは、企業がターゲットへ直接アプローチする「攻め」の採用活動です。近年注目されている「スカウトサービス」が、ダイレクトリクルーティングサービスに該当します。
一般的な就活ナビサイトでは大企業に埋もれやすいため、アプローチできる学生が限られてしまいます。しかし、ダイレクトリクルーティングサービスなら、早期に登録している意欲の高い学生に自社をアピールできるので、ターゲット人材を獲得しやすくなるのです。
ダイレクトリクルーティングサービスについて知りたい方は、ぜひこちらの資料をご活用ください。
新卒採用を成功させるならキミスカをご活用ください!
新卒の採用スケジュールは、自社のリソースやターゲットに応じて立てることが大切です。
2025年以降も、新卒採用スケジュールは早期化することが予想されます。優秀な学生を採用したい企業は、早めに情報発信やインターンシップの実施などを開始するとよいかもしれません。
リソースを抑えつつ新卒採用を成功させたい場合は、新卒向けのダイレクトリクルーティングサービス「キミスカ」をご活用ください。キミスカでは就活解禁前から学生へ積極的にアプローチできるので、早い段階での母集団形成や採用管理に役立ちます。
キミスカのサービス内容については、こちらの資料で詳しく紹介しています。採用スケジュールに課題を感じている企業は、ぜひお気軽にご相談ください。