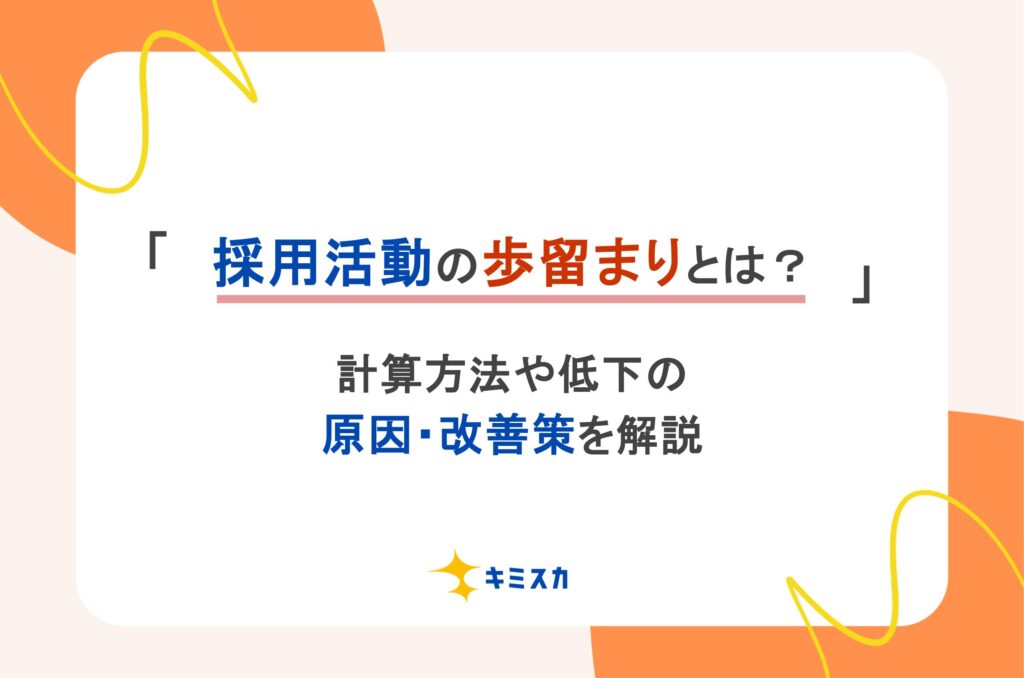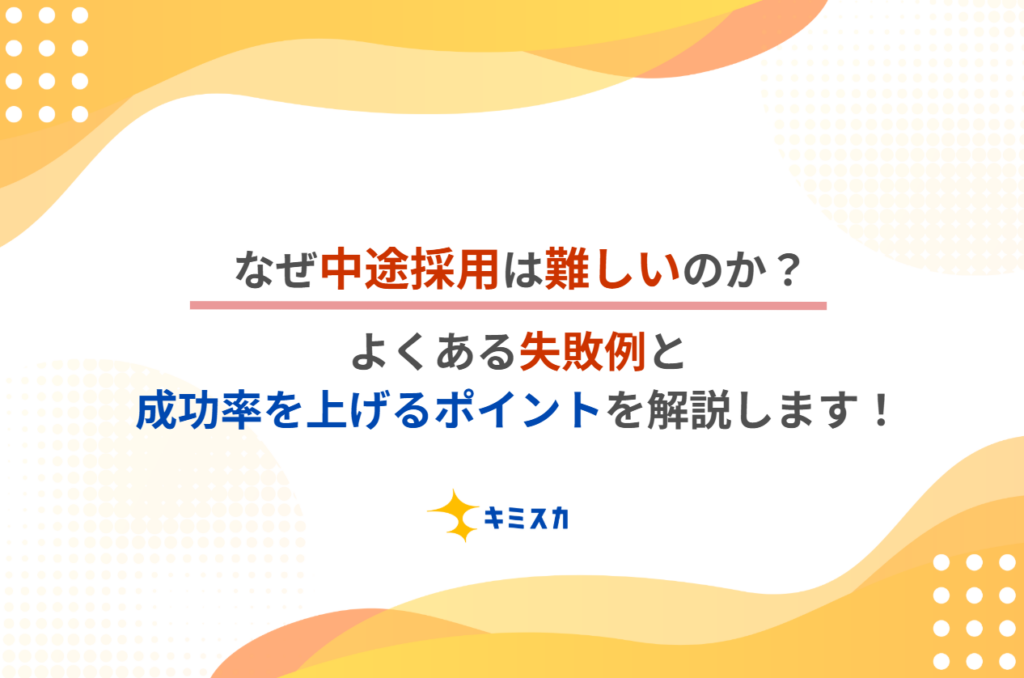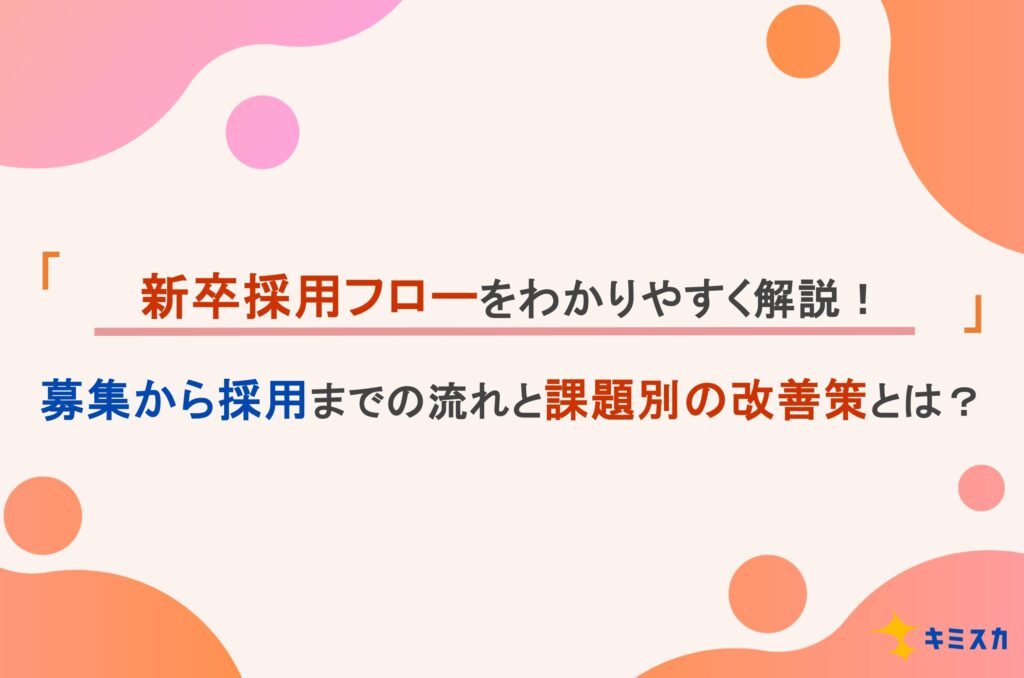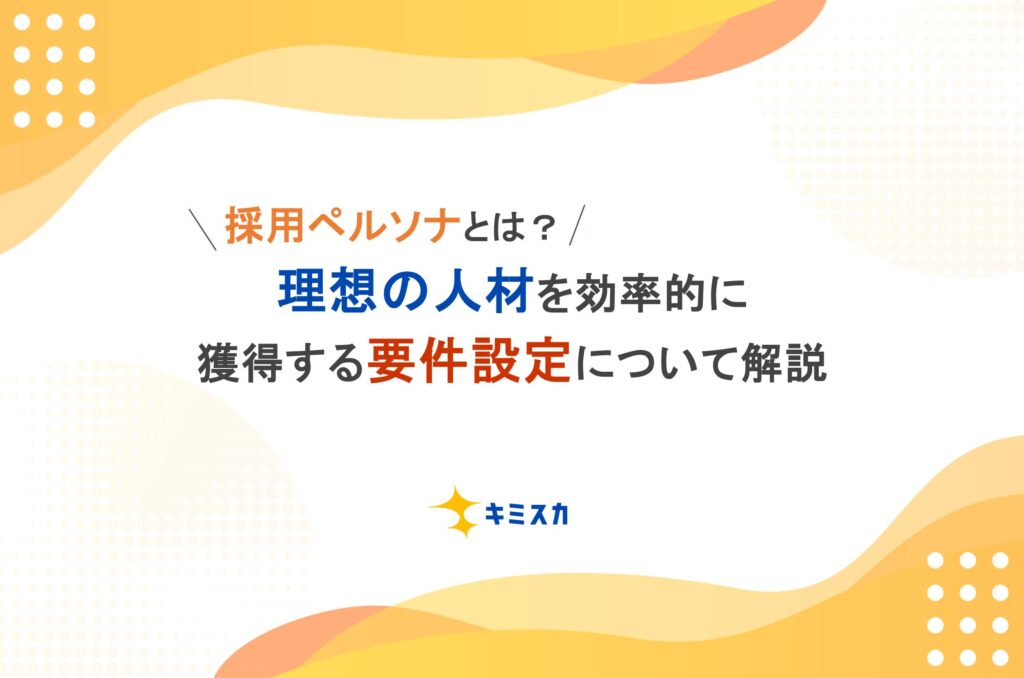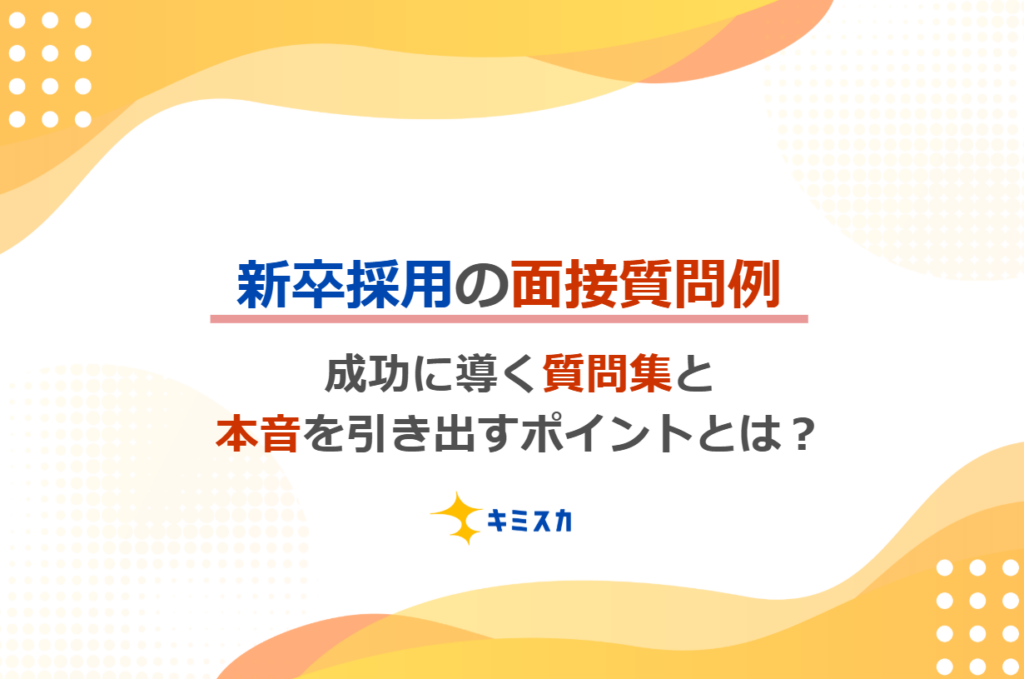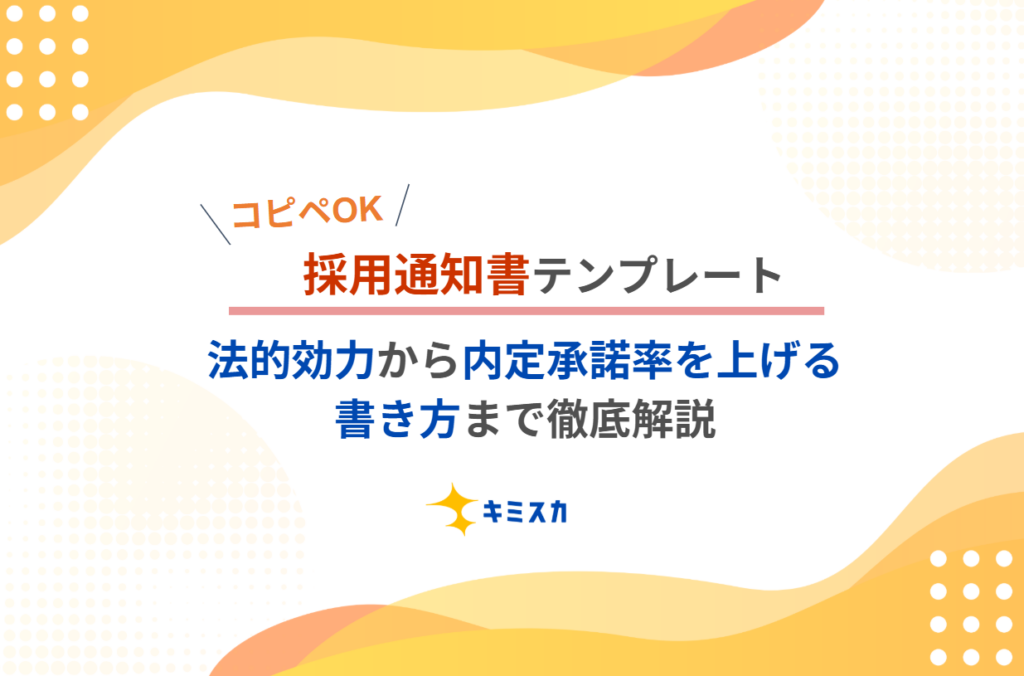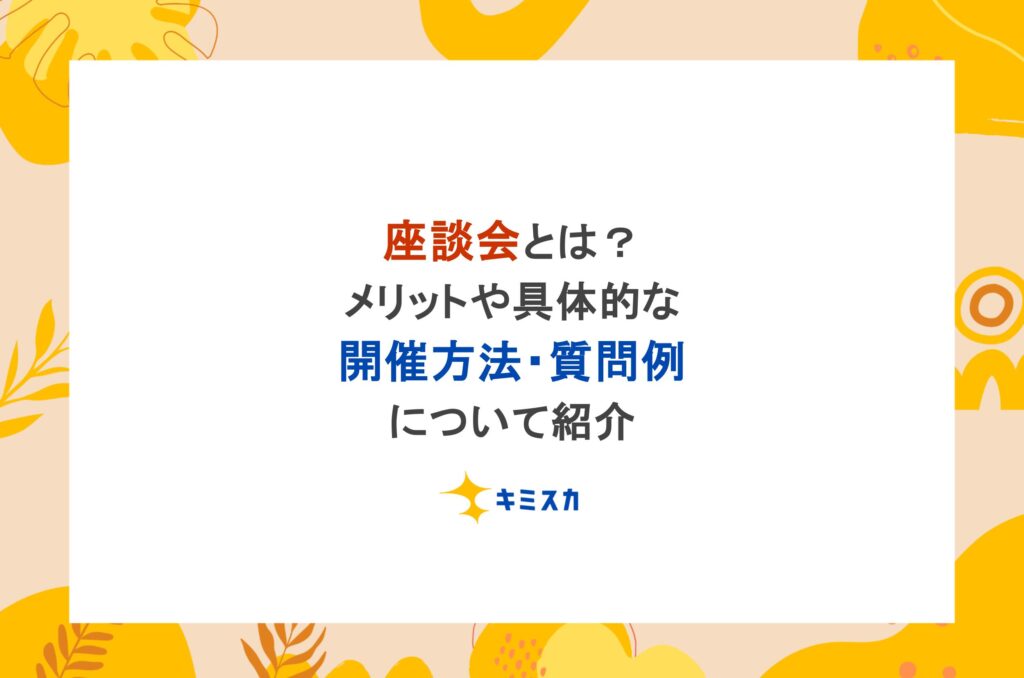
座談会は、企業と学生の相互理解を深める場所として有効な手法の1つです。企業側は学生との接点を深めることができ、学生側は不安を解消することができるため、双方にメリットがあるからです。
とはいえ「そもそも座談会の開催方法が分からない」「学生が何を求めているかが分からない」という不安もあるのではないでしょうか?今回は、座談会のメリットや開催方法、具体的な質問例について解説していきます。今後の開催に向けた改善の一助になりましたら幸いです!
座談会とは?
座談会とは、企業と学生がリラックスした雰囲気で会話をする場のことを指します。
基本的には少人数のグループに分かれて実施するため、学生側は説明会や選考で聞けなかった質問を解消できたり、企業側は学生の内面をより深く知ることができます。
企業が座談会で得られるメリット
座談会は企業と学生の相互理解を深める場ですが、それぞれどんなメリットが得られるのでしょうか。
以下、企業側が座談会で得られるメリットについて3つご紹介します。
学生との接点を増やせる
座談会では学生との接点を増やせるため、選考中の学生や内定出し後の学生との信頼関係を築けるというメリットがあります。複数企業の選考を並行して進めているケースが多いため、学生との接点を増やすことで自社の存在感を上げることができるためです。
選考中の学生であれば、複数の選考に進んでいて優先度が上がりきっていないケースが考えられます。そのため、選考中に座談会を実施することで、学生との接点を増やして自社の魅力を訴求できます。内定後であれば、座談会を通じて会社への理解を深めてもらい、辞退率を下げることにもつながります。
辞退率を下げられる
企業と学生の相互理解が深まることで、選考に進む辞退率や、内定辞退率を下げることができます。選考中であれば、座談会で現場社員から直接フィードバックやアドバイスを受ける機会を提供したり、内定出し後であれば、内定者同士の交流の場を設け、仲間意識を醸成させることができます。
これによって、「自分のことをしっかり見てもらえている」という気持ちが伝わり、企業への安心や信頼が高まります。結果的に企業に対する好感度が上がり、結果的に辞退率を下げるメリットにつながります。
社内の一体感が生まれる
現場社員が座談会に参加することで、会社の一体感が増すというメリットもあります。学生からの質問に回答したり会社のビジョンを語ることで「自分自身も初心に返って頑張ろう」という気持ちが芽生えるためです。
選考中は人事担当者とのやり取りがメインかと思いますが、実際に働く現場社員でなければ伝わらない自社の魅力もあるはずです。また、業務内容の質問があった際に、現場社員から回答した方が説得力が増して、学生へ訴求しやすいこともあります。人事部だけではなく、さまざまな部署を横断して採用活動を進めていく必要があることから「会社全体で採用に取り組む」という意志を持つことが重要です。
そうすることで、社員のモチベーションアップにもつながり、会社全体で一体感が感じられるはずです。
学生が座談会で得られるメリット
では、学生が座談会で得られるメリットはどんなものがあるのでしょうか。
学生視点でのメリットも確認しておくことで、学生が求める内容に寄り添ったコンテンツになります。満足度の高い内容にするために、座談会の要素に盛り込んでみてください。
他学生と情報交換ができる
他学生と情報交換ができることは、多くの学生がメリットに感じるポイントになります。距離の近い友人同士でもクローズになりがちな就活状況などを共有し合ったり、他学生の質問を聞くことで新たな発見が得られるからです。
キミスカ利用学生に聞いたアンケート調査によると「就活に対する不安はありますか?」という質問に対して「とても不安・やや不安」と回答した学生は約8割という結果になりました。
「Z世代就活生」のキャリアや働き方に対する考え方調査~今の学生が企業やキャリアに求める安定性とは~
さらに、何に対して不安を感じているか?という質問では「志望している企業から内定をもらえるか」が最も多い回答となりました。
上記データから、学生の不安を少しでも解消するために、座談会で学生同士が自由に交流してもらう時間を作ると良いかもしれません。自社への魅力付けはもちろんですが、就活の不安をざっくばらんに共有し合う時間や、チーム別で就活の悩み相談会の時間を作ってあげることで、座談会の満足度は上がりやすくなるでしょう。
座談会の開催型式とは?
座談会は大きく分けて3つの開催形式があります。
相互理解を深める場、という位置づけに変わりはないですが、それぞれの特徴を見ていきましょう。
テーブル形式
テーブル形式とは、学生数名と社員1~2名で1つのテーブルを囲み、会話を進めていくスタイルのことを指します。一定時間を経過したらローテーションしていくことで、多くの学生と接点を持てることがメリットです。
例えば、社員1~2名に対して学生5~6名のグループを5つ作り、20分くらいを目安にローテーションをすると、2時間弱で一通り回すことが可能です。ただし、一定時間という制約があるため、話が盛り上がった際に延長が難しかったり、交流時間が足りないという懸念はあるかと思います。その場合は、座談会終了後に個別で時間を取ってあげるのも良いでしょう。
パーティー形式
パーティー形式とは、立食パーティーのように立ちながら学生と交流をするスタイルを指します。飲食しながらリラックスした雰囲気で進められるため、スムーズに場が温まることが期待できます。
テーブル形式のようにグループや時間の制約がないため、話したい話題のところへ自由に足を運ぶことができます。その一方で、自分から積極的に話しかけにいくのが苦手、という学生を上手く巻き込むのが難しいかもしれません。その場合は、年が近い若手社員から積極的に会話の輪に引き込むなど、企業側で細やかの気配りをしていきましょう。
オンライン形式
名前の通り、Zoomなどのオンラインで開催する形式です。場所を問わず開催できるため、地方在住や留学中の学生でも参加ができる点は大きなメリットです。
一方で、通信トラブルなど想定外のことが起こる可能性もあります。オンライン面接に慣れている世代かと思いますが、念のためネットワーク環境の確認は事前にしておきましょう。不安な場合は、会社に来てもらってZoomを繋ぐなど、ハイブリッド型になりますが臨機応変な対応も検討してみてください。
座談会の基本的な進め方
座談会のタイムスケジュールについて、基本的な流れをご紹介します。
座談会全体は2~3時間を想定し、タイムスケジュールと内容を決めていきましょう。下記は一例ですが、終了後は自由に交流できる時間と場所を確保しておくと安心です。
- 初めの挨拶や今日の流れ説明、社員紹介など:15分
- 1グループ20分×5チーム:100分(席移動や延長を想定:20分)
- 終わりの挨拶と今後の流れ案内:10分
- 終了後、追加で質問があれば自由に交流できる時間と場所を確保:30~60分
人事から挨拶と社員紹介
座談会全体の司会は人事担当者になるので、簡単な挨拶とアイスブレイクを兼ねて参加社員の紹介から始めましょう。お互い初対面で緊張している人もいるため、最初は人事担当者がリードして全体を進めることで会話がしやすくなるからです。
座談会の趣旨を軽く説明した後、参加社員を1人ずつ紹介していきます。この時、1枚自己紹介スライドを作成して投影すると、認知してもらいやすく、社員の雰囲気も伝わりやすくなるのでおすすめです。
グループに分かれ、社員から話し始める
最初の挨拶が終わったら、少人数のグループに分かれ、現場社員がサブ司会となって場をリードしていきましょう。学生からの質問に対して丁寧に回答していくのはもちろんですが、なかなか最初から質問が出てこない可能性もあります。その場合、まずは普段どんなことをやっているのか、1日の仕事の流れから話を広げてあげると良いでしょう。そこから気になる質問が派生していき、今まで気になっていたが聞けなかった質問などが出てきやすくなります。
多くの社員とコミュニケーションを取ってもらうために、あらかじめ席の移動時間は決めておきましょう。もし追加で聞きたいことがあれば、座談会終了後に別途時間を確保しておくことをおすすめします。座談会の満足度向上にもつながります。
今後の流れと応援メッセージを伝える
座談会終了後は、今後の案内と応援メッセージを伝えましょう。選考中であれば今後の選考案内を伝え、内定出し後であれば入社までに準備しておくべきことを伝えます。その後で、参加の御礼と今後の応援メッセージを伝え、学生に安心感を持ってもらうことが大切です。
加えて、座談会で意欲が上がり「もう少し社員の人と話したい」と感じる学生がいた場合を想定して、座談会終了後もざっくばらんに会話できる交流時間と場所を確保しておくと良いでしょう。ここは任意参加で「まだ聞きたいことがある場合は、社員はまだここにいるので聞いてくださいね」とアナウンスすると、学生も安心して判断することができます。
座談会を実施する際のポイント
座談会の進め方を決めたら、抑えておくべきポイントを理解して具体的なアクションに落としていきましょう。満足度の高い座談会にするために重要なポイントとなるため、1つずつ解説していきます。
参加社員の選定
「座談会に参加する参加社員の印象=会社の印象」となるため、ふさわしい人選を考えることが大切です。事前にどんな社員と話してみたいか、学生にヒアリングしておくのも良いでしょう。
例えば、人見知りをせず会話の組み立てが上手い社員や、仕事に対して前向きな姿勢で取り組み、成果を出している社員は特に最適です。ハイパフォーマーに多い特徴かと思いますが、ロールモデルとして「こんな人のようになりたい」とイメージを持ってもらいやすいからです。
他には、直近半年以内に中途入社した社員に参加してもらうこともおすすめです。なぜ転職しようと思ったのか、何が決め手で入社を決めたのか、情報が最新のため説得力が増す可能性があるからです。入社したばかりで不安だった気持ちと、学生が社会人を目前に不安を感じる気持ちが理解し合えることもあるので、学生目線で寄り添った対応が期待できます。
座談会を成功させるためには、現場社員の協力が不可欠です。一緒に働く仲間を採用するために、部署を横断して上手く連携できるよう働きかけましょう。
話しやすい雰囲気作りと事前準備
座談会は相互理解の場なので、話しやすいリラックスした雰囲気作りが大切です。序盤は学生同士も初対面で緊張していることが多いためです。
例えば、前年度多くもらっていた質問があれば、よくある質問集としてまとめておくのも良いでしょう。「昨年はこんな質問が多かったです」と参考例があることで、スムーズに解決できたり、そこから派生した会話が生まれます。また、事前に聞きたいことをアンケートフォームのような形で集めておけば、漏れなく疑問に回答することもできます。
とはいえ「現場社員の工数がかかり、準備に多くの時間はかけられない‥」という不安もあるのではないでしょうか。ですが、座談会はあくまで学生との会話がメインなので、スライドに話したいトピックを箇条書きでまとめておくだけでも十分です。学生に「座談会のために忙しい時間を使って準備をしてくれた」と感じてもらうことができ、志望度が上がる可能性も高まります。
そのため、事前準備の大切さにもつながりますが、話しやすいリラックスした雰囲気作りは現場社員にも意識して行動してもらいましょう。
時間配分に気を配る
参加したすべての学生が発言できるように、時間配分に気を配ることが大切です。話が盛り上がるのは良いことですが、一部の学生のみに発言が偏ってしまうと、満足度も比例して偏ってしまうためです。
テーブル形式やオンライン形式では、質問が一巡するようにまずは1人1つずつ回答していき、ローテーションのタイミングも「この時間になったら席を移動させましょう」とスケジュールを決めておくと良いでしょう。
とはいえ、話が盛り上がったりすると、時間配分を忘れて話してしまうこともあると思います。その場合、全体の司会役である人事から定期的にアナウンスを入れると良いでしょう。終了5分前、1分前と刻んでアナウンスを入れることで、逆算して会話を組み立ててもらいやすいです。
学生からの質問例
座談会で学生からどんな質問がくるのか、ある程度イメージしておいた方が当日スムーズに話が進みます。ここでは、座談会でよく聞かれる学生からの質問についてカテゴリ別に4つ紹介します。
仕事内容について
選考中や求人サイトでは分からない、日常業務や具体的な仕事内容について聞かれる傾向があります。現場社員だからこそ伝えられるリアルな情報について、良い面・大変な面どちらも知っておきたいと思う学生が多いためです。
- 1日の業務の流れを教えてください。
- 仕事のやりがいはなんですか?
- 今まで失敗したことや、大変だったことはありますか?
これらについて実体験を基に簡潔に伝えることで、入社後働くイメージがしやすくなります。
職場環境について
職場環境や人間関係が良いかどうかは、特に気にしている学生が多い傾向にあります。就活で最も大切にしたいことは「人間関係が良好な職場で働けるか」というデータにもあるように、職場環境は非常に重要な判断軸となるからです。
就職する上で大切にしたいこと調査 1位は「職場の人間関係」2位は「ワークライフバランス」
- チームの雰囲気は良好ですか?
- どのような人が活躍していますか?
- 御社の良いところ・改善したいところはありますか?
どんな雰囲気で仕事を進めているのか、リアルな情報を伝えることで会社の雰囲気が伝わりやすくなります。
福利厚生・給与について
福利厚生や給与面についても気になる学生は多い傾向にあります。選考中聞いたらタブーな質問なのではないか、と不安に感じて聞けない学生が多いためです。
- 給与は入社してからどのくらい上がりましたか?
- 成果を出したら昇給しやすいですか?
- 福利厚生はどのようなものがありますか?
具体的な給与については答えにくいかと思うので、評価基準や会社として大切にしていることを伝えるのも良いでしょう。
キャリア形成について
入社後のキャリア形成についても関心が高い話題です。自分がやりたいことが実現できるか、数年後のキャリアステップはどのように進んでいくのかを知ることで、入社後のイメージがしやすくなるからです。
- 研修やキャリア支援の制度はありますか?
- 入社してから他職種への異動はありましたか?
- 一緒に働くならどんな人と働きたいですか?
自分がやりたいと手を挙げたら、応援してくれる環境なのかどうかを知りたいという意図から、上記質問も想定されます。同じ職種でキャリアアップをして成果を出したり、キャリアチェンジをして仕事の幅を広げた社員の事例があれば、実体験を基に話すと良いでしょう。
まとめ
今回は座談会を実施するメリットや、具体的な開催方法・質問例についてご紹介しました。
座談会を実施することで「学生との接点を増やせる」「辞退率を下げられる」「社内の一体感が生まれる」というメリットがあるため、採用成功に向けて重要なプロセスの1つです。
現場社員と連携しながら、自社にマッチする座談会を検討してみてください!