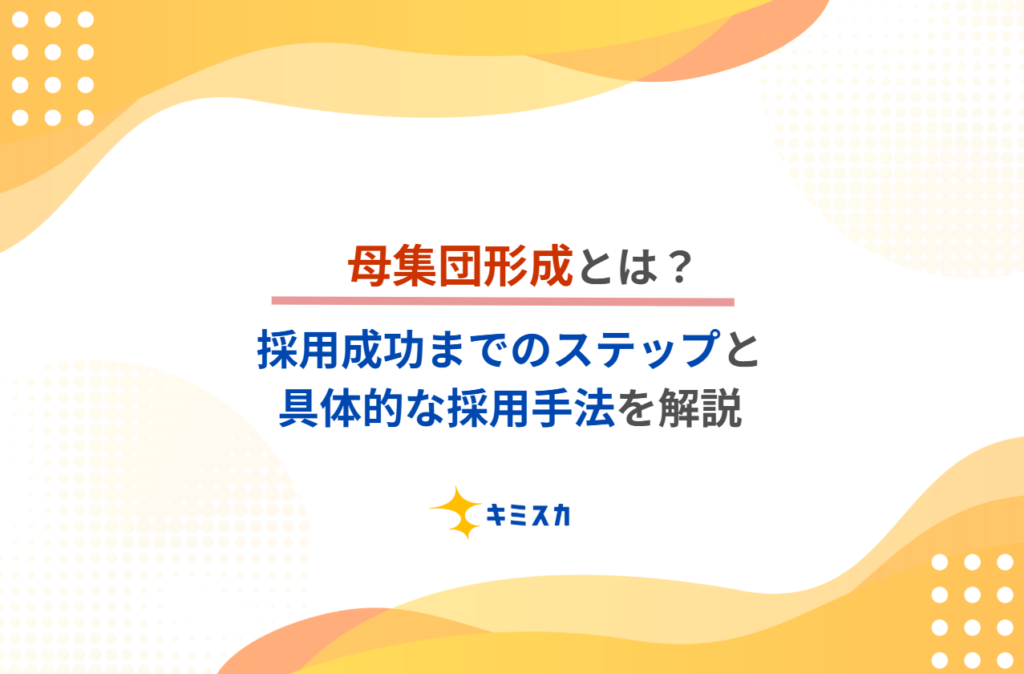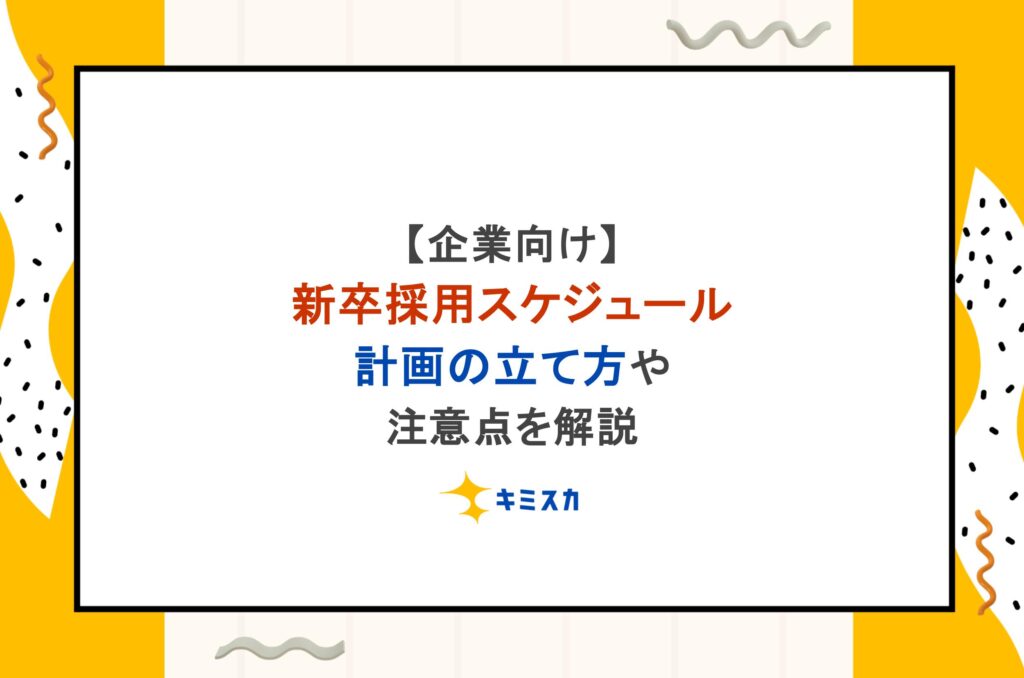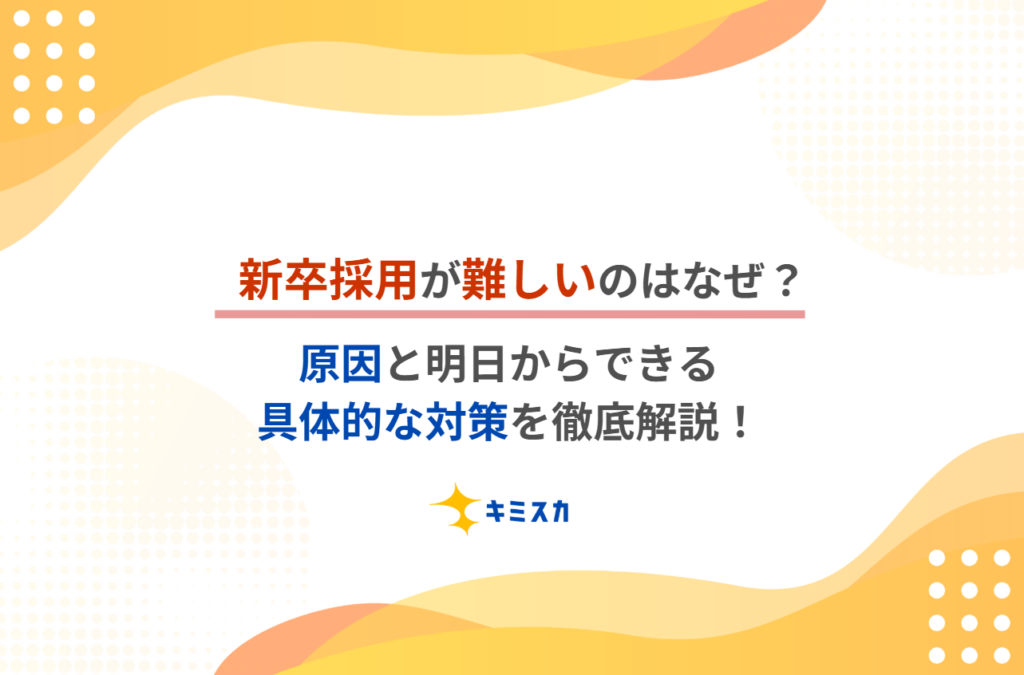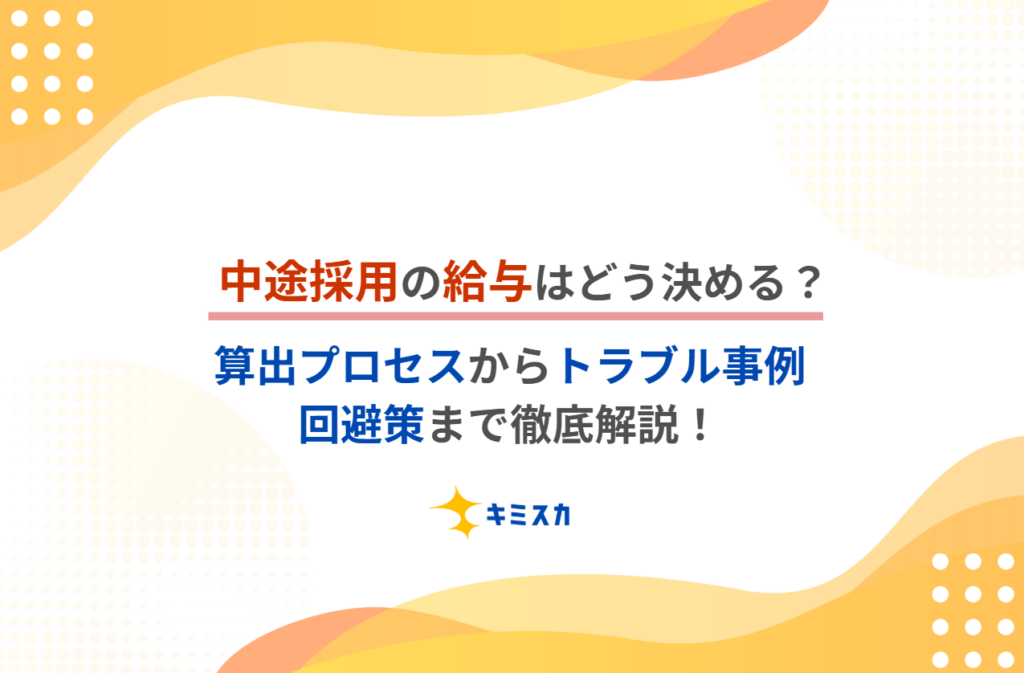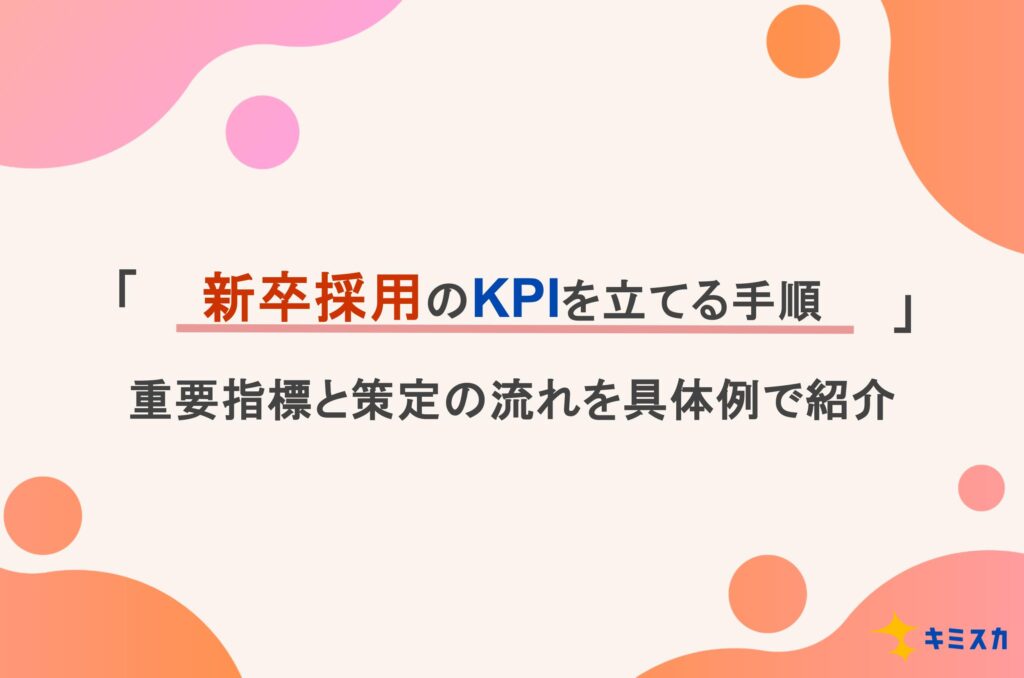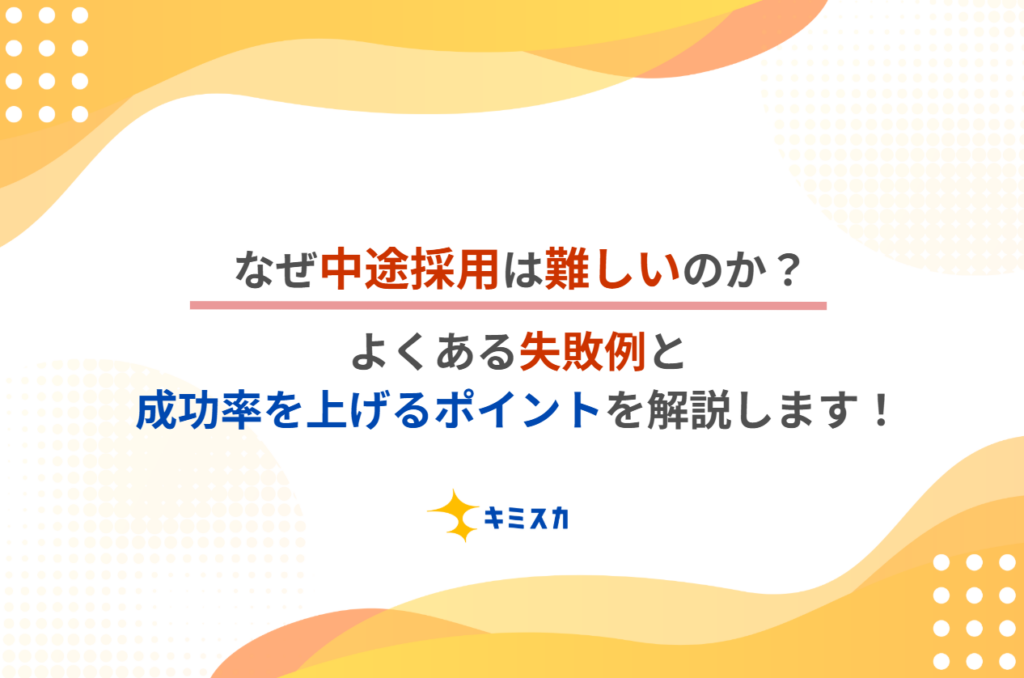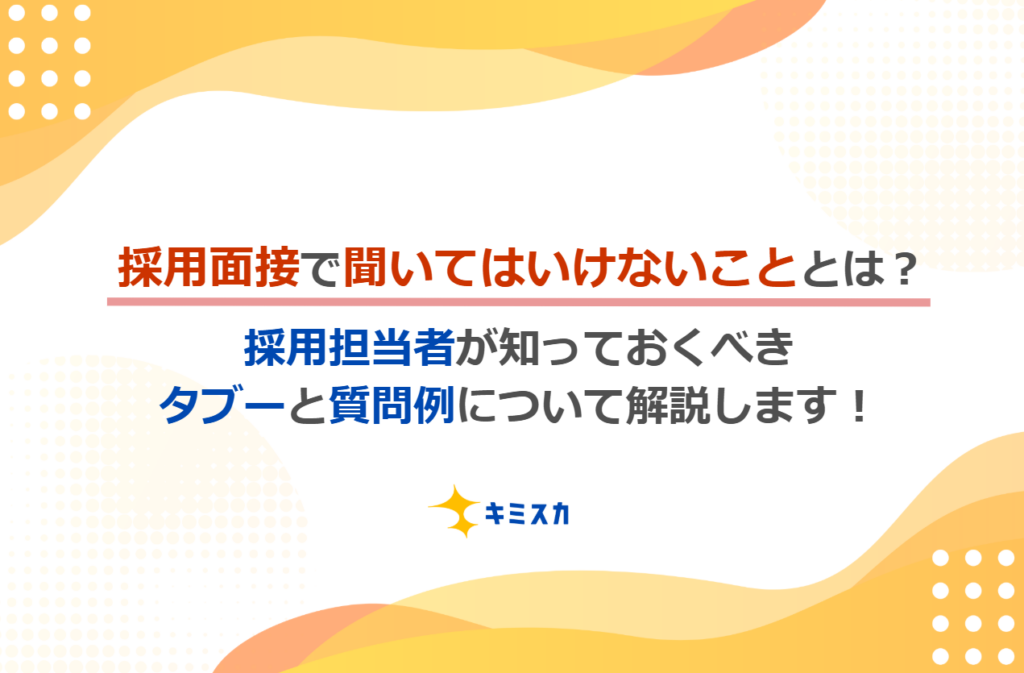
採用は、企業の未来を担う人材を獲得するための重要なプロセスです。面接はその中でも、応募者の能力や適性、人となりを見極める上で欠かせない機会となります。
しかし、応募者の情報を得るために、どのような質問をしても良いというわけではありません。法律や倫理上の観点から、面接で「聞いてはいけないこと」、つまりタブーとされる質問が存在します。
本記事では、新卒採用の面接官が知っておくべき基本的な考え方から、厚生労働省が定めるタブー、具体的なNG質問例、そして適切な質問例までを網羅的に解説します。
面接官に求められる基本的な考え方
採用面接において、面接官は単に質問をするだけでなく、応募者を公平かつ客観的に評価する役割を担っています。そのため、以下のような基本的な考え方を常に持つことが求められます。
- 公平性と客観性: 全ての応募者に対して平等な機会を提供し、個人的な感情や先入観に左右されない客観的な評価を行う必要があります。
- 能力と適性の評価: 応募者のスキル、知識、経験、潜在能力、そして企業の求める人物像や職務への適性を的確に見極めることが重要です。
- 個人を尊重する姿勢: 応募者は一人の人間として尊重されるべきであり、威圧的な態度や差別的な言動は厳に慎む必要があります。
- 企業の代表としての自覚: 面接官は企業の顔であり、応募者は面接官の印象を通じて企業イメージを形成します。誠実かつプロフェッショナルな対応が求められます。
- 法律と倫理の遵守: 採用活動に関する法律や倫理規範を理解し、遵守することが不可欠です。
厚生労働省が定める2つのタブー
日本の採用選考においては、厚生労働省が「公正な採用選考の基本」として、特に以下の2つの視点からタブーとなる質問を提示しています。
本人に責任のない事項
これは、応募者自身の努力や能力とは関係なく、個人の属性によって左右される可能性のある事柄に関する質問です。具体的には、以下のような項目が該当します。
- 家族に関すること: 家族構成、家族の職業、学歴、収入など
- 住居に関すること: 持ち家か賃貸か、間取り、家族構成など
- 生活環境・生い立ちに関すること: 家庭環境、育った場所、経済状況など
- 本籍地・出生地に関すること: 出身地による差別を助長する可能性があるため
これらの質問は、応募者の能力や適性を評価する上で直接的な関連性が低く、不当な差別につながる可能性があるため、原則として禁止されています。
本来自由であるべき事項
これは、応募者の思想や信条、個人的な自由に関わる事柄に関する質問です。具体的には、以下のような項目が該当します。
- 思想・信条に関すること: 政治的信条、宗教、尊敬する人物など
- 支持政党に関すること: 特定の政党への支持の有無や理由
- 労働組合・社会運動に関すること: 加入の有無や活動経験
- 購読新聞・雑誌・書籍に関すること: 個人の思想傾向を探る可能性があるため
これらの質問は、個人の自由な意思や権利を侵害する可能性があり、採用選考の公平性を損なうため、原則として禁止されています。
面接官が聞いてはいけない質問とは?
厚生労働省の指針を踏まえ、面接官が具体的に聞いてはいけない質問をさらに詳しく見ていきましょう。
家族構成に関する質問
これらの質問は、応募者の能力や適性とは無関係であり、家庭環境による差別につながる可能性があります。
- 「ご家族は何人ですか?」
- 「ご両親のお仕事は何をされていますか?」
- 「兄弟姉妹はいらっしゃいますか?」
- 「ご家族と同居されていますか?」
住居・生活環境に関する質問
これらの質問も、応募者の経済状況や家庭環境を探るものであり、採用選考の判断材料としては不適切です。通勤時間については、配属先の可能性を考慮して確認する必要がある場合もありますが、本人の希望や通勤手段を確認するに留めるべきです。
- 「一人暮らしですか、実家暮らしですか?」
- 「家賃はいくらですか?」
- 「通勤時間はどのくらいですか?」
- 「どのような家に住んでいますか?」
思想・信条・宗教に関する質問
これらの質問は、応募者の思想や信条の自由を侵害する可能性があり、採用選考の判断に用いることは許されません。
- 「何か信仰している宗教はありますか?」
- 「尊敬する人物は誰ですか?」
- 「支持している政党はありますか?」
- 「学生時代に何か社会運動に参加していましたか?」
健康状態に関する質問(業務遂行に直接関係のない場合)
健康状態に関する質問は、業務遂行に支障があるかどうかを確認するために必要な場合もありますが、必要以上に詳細な情報を聞いたり、業務と直接関係のない病歴などを尋ねることはタブーです。
- 「過去に大きな病気をしたことはありますか?」
- 「健康状態は良好ですか?」
- 「体力には自信がありますか?」
結婚・出産に関する質問
これらの質問は、女性に対する差別的な意図があるとみなされる可能性が高く、男女雇用機会均等法に抵触する恐れがあります。
- 「結婚の予定はありますか?」
- 「お子さんはいますか?」
- 「出産後も仕事を続けたいですか?」
容姿・身長・体重に関する質問(業務遂行に直接関係のない場合)
容姿や体格に関する質問は、職種によっては必要な場合もありますが(例:モデル、スポーツ選手など)、一般事務職や技術職など、業務遂行に直接関係のない場合はタブーとなります。
- 「身長は何センチですか?」
- 「体重は何キロですか?」
- 「何かスポーツはされていますか?」
年齢に関する質問(年齢制限が認められる場合を除く)
原則として、年齢を理由とした差別は禁止されています。ただし、定年制度や労働基準法などの例外規定により、年齢制限が認められる職種もあります。
- 「年齢はおいくつですか?」
その他の差別につながる可能性のある質問
下記以外にも、応募者の属性に基づいて、不当な差別につながる可能性のある質問は避けるべきです。
- 特定の地域出身者であることを前提とした質問
- 特定の学校の出身者であることを前提とした質問
- 特定のアルバイト経験を前提とした質問
面接で聞いても問題ない質問
一方で、応募者の能力や適性、仕事への意欲などを適切に評価するために、面接で聞いても問題ない質問は数多く存在します。
職務遂行能力に関する質問
これまでの経験や強み・弱みなどを質問することで、入社後の活躍がイメージできます。そのため、下記質問は面接の中で深堀りする必要があります。
- 「これまでの経験で最も成果を上げたことは何ですか?その際、どのような役割を果たしましたか?」
- 「あなたの強みと弱みは何ですか?それらは仕事にどのように活かせますか?」
- 「学生時代に最も力を入れたことは何ですか?そこから何を学びましたか?」
- 「プログラミングスキルについて、具体的にどのような経験がありますか?」
仕事への意欲・熱意に関する質問
自社に興味を持ったきっかけや入社意欲を確認することで、志望度の高さを見ることができます。また、入社後のミスマッチ防止にもつながります。
- 「なぜこの業界・企業を選んだのですか?」
- 「当社のどのような点に魅力を感じていますか?」
- 「入社後、どのような仕事に挑戦したいですか?」
- 「キャリアプランについて、どのように考えていますか?」
自己PR・個性に関する質問
自己分析結果や他者評価を知ることで、その人のキャラクターがイメージしやすくなります。特に、困難な状況をどのように乗り越えたかなど、ストレス耐性や対応力も併せて確認すると良いでしょう。
- 「あなた自身をアピールしてください。」
- 「周りの人からはどのような人だと言われることが多いですか?」
- 「ストレスを感じた時、どのように解消しますか?」
- 「困難な状況にどのように立ち向かいますか?」
企業文化への適応性に関する質問
企業文化、会社の雰囲気に合っているかどうか確認しましょう。ミスマッチが確実に防げる質問は存在しませんが、企業理念への理解度・共感度や、チームでどのような立ち回りをしてきたかを質問することで、企業文化への適応性がイメージしやすくなります。
- 「チームで働くことは好きですか?どのような役割を果たすことが多いですか?」
- 「当社の企業理念について、どのように考えていますか?」
- 「変化の多い環境で働くことに抵抗はありますか?」
タブー質問をしないために面接官ができること
面接官が意図せずタブー質問をしてしまうことを防ぐために、以下の対策を講じることが重要です。
これらの対策を通じて、面接官は安心して応募者の能力や適性を見極めるための質問に集中できるようになります。
採用基準の明確化
採用基準を明確にし、評価項目と質問内容が連動しているかを確認することが大切です。
採用基準については、こちらの記事『「採用基準」の重要性とは?具体的な設定方法とメリットを解説!』をご覧ください!
面接官研修の実施
定期的に面接官向けの研修を実施し、タブー質問に関する知識やNG事例を共有することで、意識向上を図りましょう。また、タブー質問に関する最新の情報や注意喚起など、採用担当者間で共有する仕組み作りも重要です。
ヒヤリハット事例として共有することは、これから起こりうる大きな事故を未然に防ぐ効果もあります。
ヒヤリハットとは、業務中に「ヒヤリとした」「ハッとした」など危険な事態が発生したものの、幸い大きな事故には至らなかった事象のことです。
参考:ヒヤリハットとは?事例や報告書の書き方、重大事故を防ぐコツを解説
質問項目の事前準備と確認
面接前に質問内容をリストアップし、不適切な質問が含まれていないか複数人で確認する体制を整えましょう。
振り返りと改善スピードを上げるために、過去の面接記録を分析し、問題のある質問や不適切な発言がないか定期的にチェックすることも重要です。
面接時に意識するべきポイント
タブー質問をしないことに加えて、面接官は以下のような点にも意識を向けることで、より効果的で公正な面接を実施することができます。
話しやすい雰囲気作り
質問をするだけでなく、応募者の回答を真剣に聞き、内容を深く理解することが重要です。緊張している応募者もいるため、笑顔で接するなど、リラックスして話せる雰囲気づくりを心がけましょう。
深掘り質問をする
応募者の回答に対して、「具体的には?」「その時の状況は?」など、さらに詳しく尋ねることで、表面的な情報だけでなく、より深い情報を得ることができます。
また、「はい」「いいえ」で答えられるクローズドな質問だけでなく、「どのように」「なぜ」といったオープンな質問を積極的に取り入れることで、応募者の思考力や表現力を引き出すことができます。
採用基準に基づいて評価する
事前に設定した採用基準に照らし合わせながら、応募者の回答を客観的に評価することが重要です。
また、チーム内で振り返りができるように、面接での応募者の発言や印象などを記録に残すことで、後で評価を比較検討する際に役立ちます。
聞いてはいけない質問をしたときの企業への影響
採用面接でタブー質問をしてしまった場合、企業には以下のような悪い影響が生じる可能性があります。
法律違反のリスク
男女雇用機会均等法や雇用対策法などに抵触する可能性があり、訴訟や行政指導を受けるリスクがあります。これにより、企業は罰金や行政からの指導を受け、最悪の場合、訴訟に発展するリスクも発生します。
法的対応には多大な時間と費用がかかり、企業経営に大きな負担となります。悪気なく質問してしまった場合でも対応しなければならないため、未然に防ぐための仕組みを確立しておくことが重要です。
企業イメージの低下
不適切な面接対応は、企業の倫理観や人権意識が低いと判断される要因になります。
SNSや口コミで情報が瞬時に拡散され、企業の評判は大きく傷つき、ブランドイメージが著しく低下します。これは将来の採用活動だけでなく、顧客や取引先からの信頼失墜にも繋がりかねません。
採用コストとプロセスの非効率化
タブー質問によるトラブルが発生した場合、採用選考をやり直す必要が生じる可能性があります。
面接時に不快な思いをした応募者は、たとえ内定を得ても、その企業への入社をためらう可能性が高まります。内定辞退が増えると、追加の募集活動、選考実施にかかる時間、費用、労力など、多大なコストの無駄を意味します。結果として採用活動全体が非効率になり、目標人数達成が困難になります。
まとめ
採用面接は、企業と応募者双方にとって重要な機会です。面接官は、法律や倫理規範を遵守し、応募者の人権を尊重しながら、適切な質問を通じて自社に必要な人材を見極める必要があります。
本記事で解説した「面接で聞いてはいけないこと」をしっかりと理解し、タブー質問を避けることは、公正な採用選考を行う上で不可欠です。適切な質問を通じて、応募者の能力と可能性を見極め、企業の成長に貢献できる人材を採用しましょう。