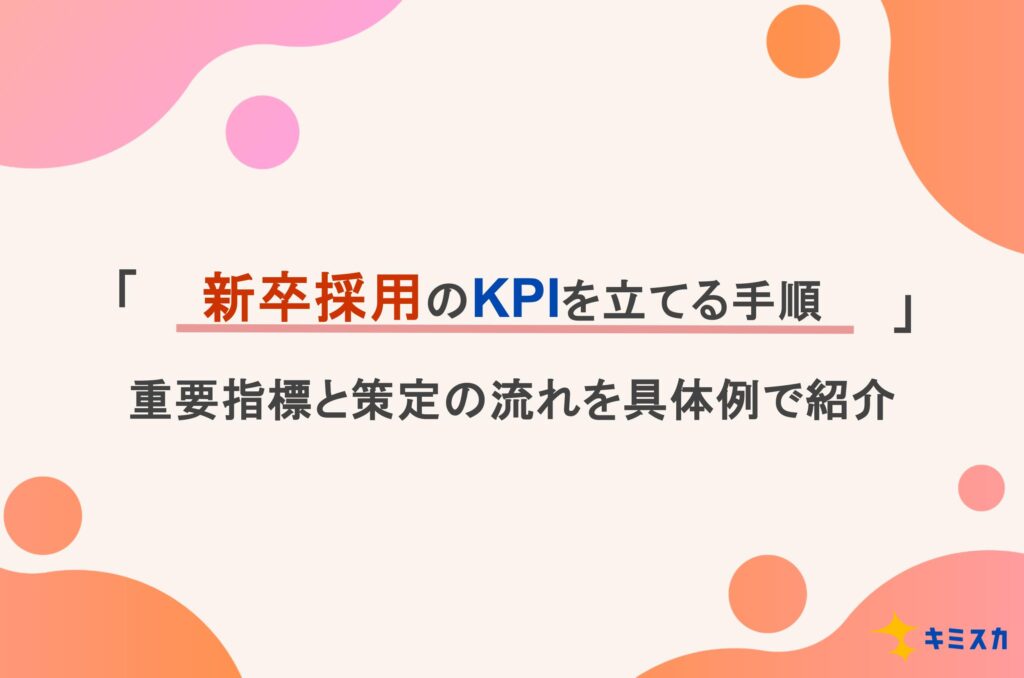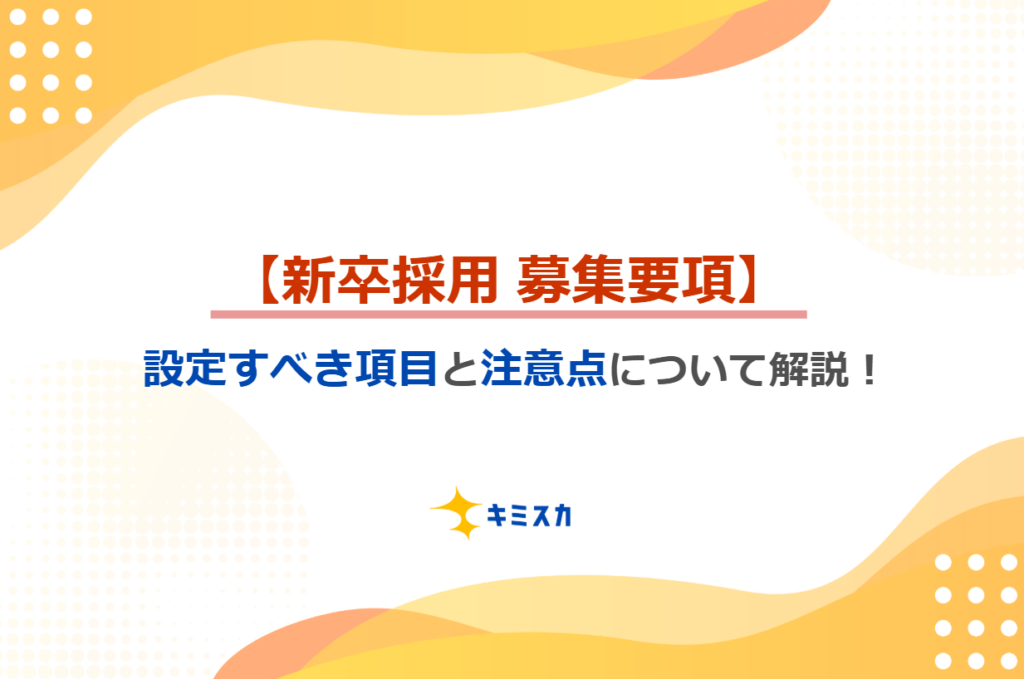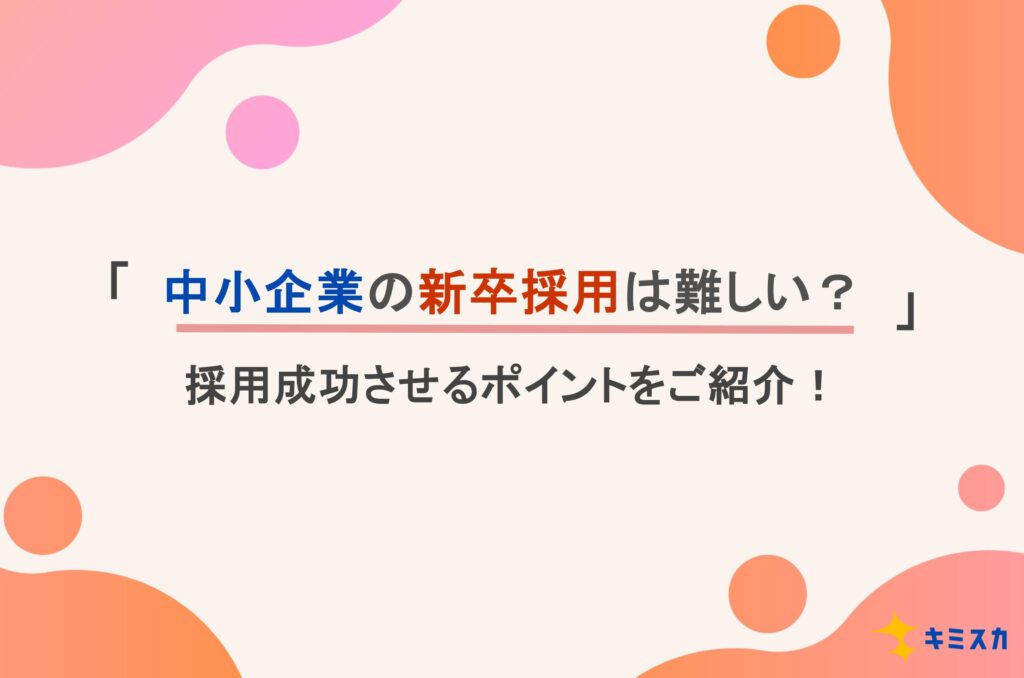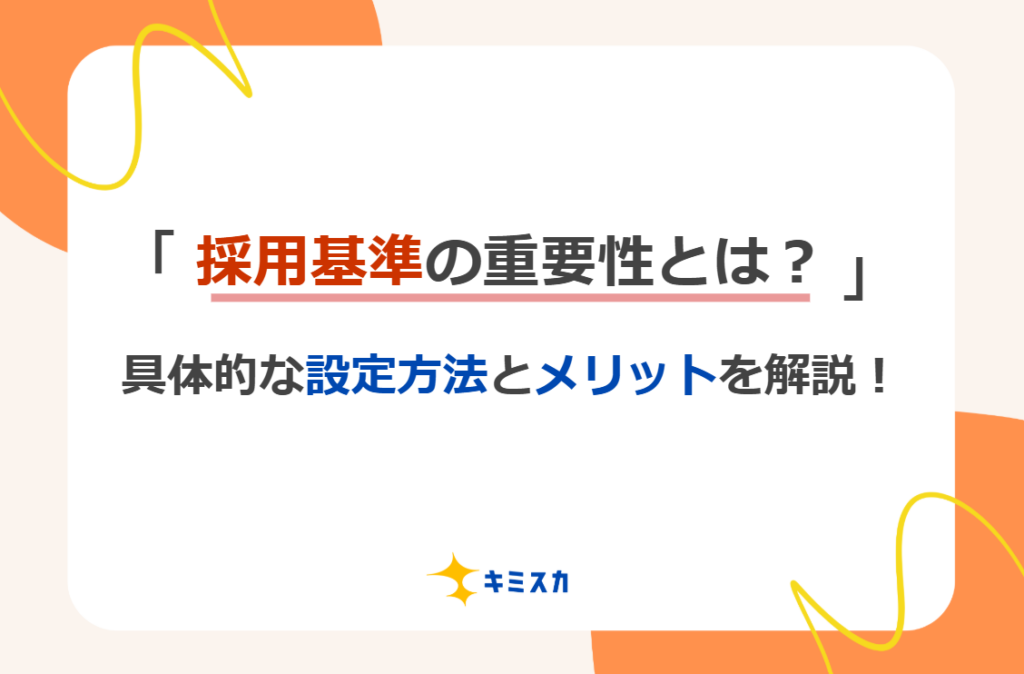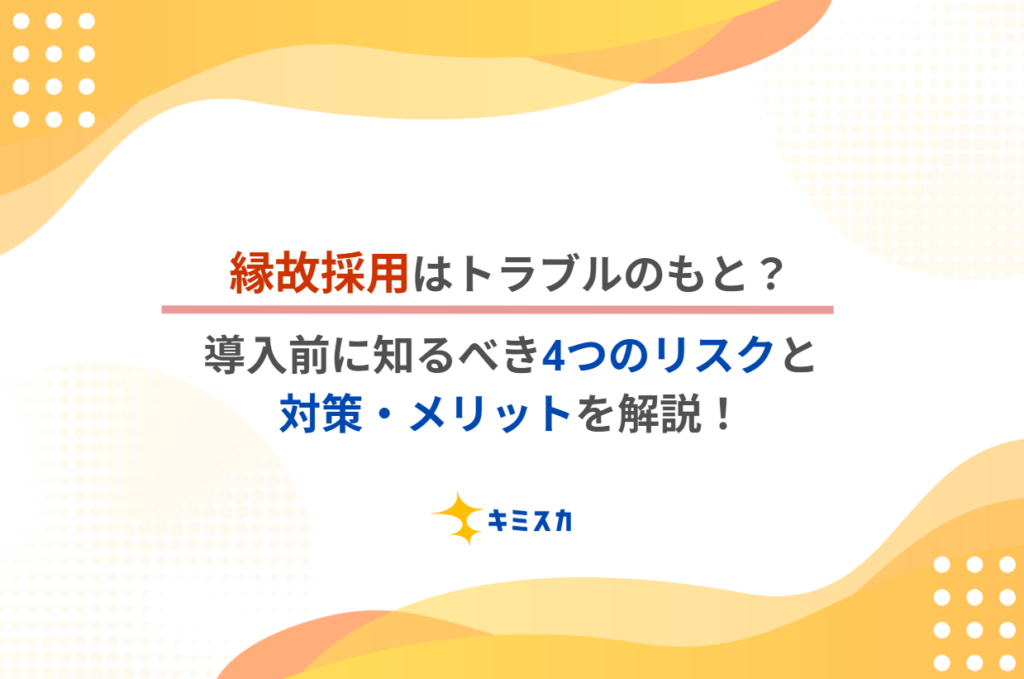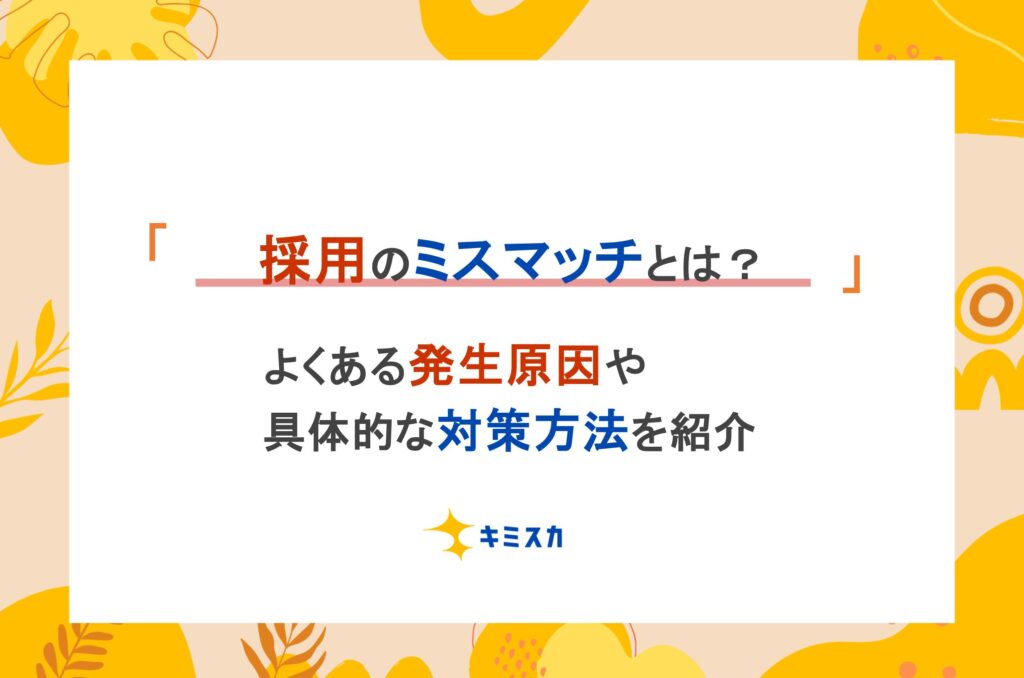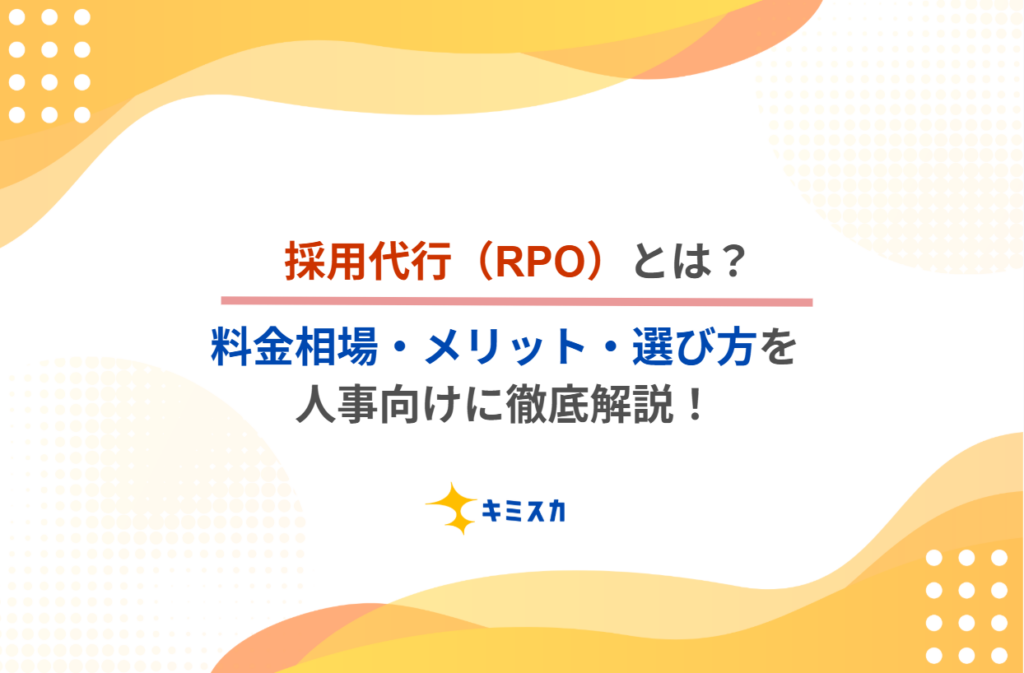
「候補者への連絡や面接の日程調整に時間がかかり、本当に注力すべき面接や採用戦略の立案に集中できない…」
「採用ノウハウが社内になく、毎年手探り状態で採用活動を行っている…」
企業の成長に不可欠な採用活動ですが、特に他の業務と兼任されている人事担当者様にとっては、悩みも多いのではないでしょうか。
この記事では、そうした悩みを解決する手段の一つである「採用代行(RPO)」について、その基本的な定義から、具体的な業務内容、料金相場、そして失敗しないサービスの選び方まで、網羅的に解説します。
採用代行(RPO)とは?人材紹介との違い
採用活動の外部委託を検討する際、まず「採用代行」のサービス内容を正しく理解しておくことが重要です。
ここでは、採用代行の基本的な定義と、関連サービスとの違いを解説します。
採用代行(RPO)の基本的な定義
採用代行とは、RPO(Recruitment Process Outsourcing)とも呼ばれ、企業がおこなう採用活動に関する業務の一部、または全てを外部の専門企業が代行するサービスを指します。採用計画の立案といった上流工程から、母集団形成、選考、内定者フォローに至るまで、企業のニーズに合わせて依頼する業務範囲を柔軟にカスタマイズできるのが特徴です。採用の「プロセス」そのものをアウトソースし、採用業務の効率化や質の向上を目指すためのパートナーと言えるでしょう。
人材紹介との根本的な違い
採用代行と人材紹介の最も大きな違いは、その「役割」と「課金体系」にあります。人材紹介は、企業が求める要件に合致した「人材を紹介」し、採用が成功した場合に年収の数十パーセントを成果報酬として支払うモデルです。一方、採用代行は採用業務の「プロセスを代行」するサービスであり、採用の成功・不成功にかかわらず、委託した業務量や期間に応じて費用が発生します。人材紹介が「人材の獲得」をゴールとするのに対し、採用代行は「採用プロセスの最適化」をゴールとしています。
人材派遣との違い
人材派遣は、派遣会社が雇用する労働者を、企業の指揮命令下で業務に従事させるサービスです。企業と労働者の間には直接の雇用契約はありません。一方、採用代行は、企業の採用業務そのものを代行するサービスであり、最終的に企業が直接雇用する正社員や契約社員の採用をサポートします。人材派遣が「一時的な労働力の確保」を目的とするのに対し、採用代行は「自社の社員となる人材の採用」を目的としており、その役割は全く異なります。
採用代行に依頼できる業務内容一覧
採用代行サービスの大きな魅力は、その柔軟性にあります。自社の採用課題やリソース状況に応じて、必要な業務だけを切り出して依頼することが可能です。ここでは、採用活動のフェーズごとに、具体的にどのような業務を委託できるのかを詳しく解説します。
【フェーズ1】採用計画の策定
採用活動の成功は、綿密な採用計画から始まります。しかし、日々の業務に追われる中で、戦略立案に十分な時間を割けないケースも多いのではないでしょうか。採用代行に依頼することで、市場の動向や競合の状況を分析し、企業の事業計画に基づいた最適な採用ターゲット(ペルソナ)の設定、採用人数の計画、採用手法の選定、年間のスケジューリングといった、採用活動の根幹をなす戦略立案をサポートしてくれます。客観的なプロの視点を取り入れることで、より実効性の高い採用計画を策定できます。
ペルソナ設定については『採用ペルソナとは?理想の人材を効率的に獲得する要件設定について解説』で詳しく解説しておりますので、まずは自社で整理しておきたい、とお考えでしたらぜひご覧ください。
【フェーズ2】母集団形成
ターゲットとなる候補者からの応募をいかにして集めるか、という母集団形成は、採用活動における重要なステップです。採用代行では、求人媒体の選定・出稿・管理はもちろん、ダイレクトリクルーティングにおける候補者の検索・リストアップ・スカウトメールの文面作成・送信といった、工数のかかる業務を委託できます。また、会社説明会の企画・運営・当日の司会進行まで任せることも可能です。これにより、多角的なアプローチで効率的に質の高い母集団形成を支援してくれます。
【フェーズ3】選考・候補者対応
選考フェーズは、候補者とのコミュニケーションが最も密になる段階であり、企業の印象を大きく左右します。採用代行では、応募書類の受付管理・書類選考、面接日程の調整・連絡、Web面接のセッティング、合否連絡といった、煩雑ながらも迅速かつ丁寧な対応が求められる業務を幅広くカバーします。これにより、採用担当者は面接や候補者の見極めといったコア業務に集中でき、選考プロセス全体の質を高めることが可能になります。
【フェーズ4】内定・入社フォロー
内定を出した後も、入社承諾を得て、無事に入社してもらうまで気は抜けません。特に売り手市場においては、内定辞退を防ぐためのきめ細やかなフォローが不可欠です。採用代行では、内定者への定期的な連絡、内定者懇親会の企画・運営、入社手続きの案内といった内定者フォロー業務を委託できます。内定者との継続的なコミュニケーションを通じて、入社への意欲を高め、内定ブルーによる辞退リスクを低減させる重要な役割を担います。
採用代行の料金形態と費用相場
採用代行の導入を検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。料金体系は提供会社やサービス内容によって様々です。自社の採用計画や予算に合わせて最適なプランを選ぶためには、まず料金形態の種類とそれぞれの特徴、そして費用相場を理解しておくことが重要です。
1. 月額固定型
月額固定型は、依頼する業務内容と量に応じて、毎月一定の料金を支払う形態です。採用人数にかかわらず費用は変動しないため、予算管理がしやすいのが大きなメリットです。継続的に一定量の採用業務が発生する場合や、採用計画の策定から母集団形成、選考サポートまで、広範囲の業務を長期間にわたって依頼したい場合に適しています。
費用相場は、依頼する業務範囲によって大きく異なりますが、月額20万円~70万円程度が一般的です。例えば、面接の日程調整や応募者対応といった事務業務が中心であれば20~30万円、スカウト配信や書類選考といった専門的な業務も加わると50万円以上になるケースが多く見られます。
2. 成果報酬型
成果報酬型は、採用が成功した場合にのみ費用が発生する形態です。主に、採用決定や入社といった成果に対して、1名あたり数十万円、あるいは理論年収の数十パーセントといった形で料金が設定されています。初期費用がかからないため、導入のハードルが低いのが特徴です。
しかし、採用人数が多くなると、結果的に月額固定型よりもコストが割高になる可能性があります。採用人数が少ない場合や、特定のポジションをピンポイントで採用したい場合に有効な選択肢です。費用相場は、1名採用あたり30万円~100万円以上と、対象とする職種や役職の難易度によって幅があります。
3. 複合型(月額固定+成果報酬)
複合型は、月額固定型と成果報酬型を組み合わせた料金形態です。毎月、業務委託の基本料金として低めの月額費用を支払い、さらに採用成功者が出た場合に成果報酬を追加で支払うモデルです。月額固定型よりもランニングコストを抑えつつ、成果報酬型よりも1名あたりの採用単価を低く設定できる場合があります。提供会社にとっては、最低限の収益を確保しながら、採用成功へのインセンティブも働くため、質の高いサービスが期待できるという側面もあります。双方のメリットを享受できる、バランスの取れた料金形態と言えるでしょう。
業務別の費用相場一覧
採用代行は、業務単位で依頼することも可能です。ここでは、特定の業務のみを依頼した場合の一般的な費用相場をご紹介します。予算が限られている中小企業にとっては、自社のボトルネックとなっている業務だけをピンポイントで依頼するのも賢い活用法です。
- 求人票作成・出稿代行:1求人あたり3万円~10万円
- スカウトメール配信代行:月額10万円~30万円(配信数による)
- 書類選考代行:1名あたり500円~2,000円
- 面接日程調整代行:月額5万円~20万円(対応件数による)
- 会社説明会代行:1回あたり10万円~30万円(企画・運営含む)
これらの費用はあくまで目安であり、依頼する業務の難易度や量、求める品質によって変動します。必ず複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することが重要です。
少子高齢化の影響を受け、限られた予算の中で自社にマッチする学生と多く出会うのは年々難易度が上がっています。新卒採用全体にかかるコストについては、こちらの記事『新卒採用のコストを解説!単価相場や費用の削減方法についても紹介』で詳しく解説しておりますので、合わせてご覧ください。
採用代行を利用する5つのメリット
採用代行を導入することで、企業は様々なメリットを受けられます。
ここでは、採用代行がもたらす5つの主要なメリットについて解説します。
1. 採用担当者がコア業務に集中できる
最大のメリットは、採用担当者がノンコア業務から解放され、本来注力すべきコア業務に集中できることです。面接日程の調整、応募者への事務連絡、スカウト候補のリストアップといった定型的な業務を委託することで、創出された時間を採用戦略の立案・見直し、面接による候補者の見極め、魅力づけといった、企業の未来を左右する重要な業務に充てられるからです。これにより、採用担当者の専門性を最大限に活かすことができます。
2. 採用のプロの知見を活用できる
採用代行会社は、多種多様な業界・企業の採用を支援してきた実績を持つ「採用のプロフェッショナル」です。そのため、自社だけでは得られない最新の採用市場の動向、効果的な母集団形成の手法、候補者の心をつかむコミュニケーション術といった専門的な知見やノウハウを活用できます。特に採用ノウハウが社内に不足している企業にとっては、強力な外部パートナーとして、採用活動全体のレベルを引き上げてくれる存在となるでしょう。
3. 採用活動の質とスピードが向上する
採用業務に精通した専門スタッフが、迅速かつ丁寧に応募者対応を行うことで、候補者の満足度(CX:候補者体験)が向上します。メールの返信が早い、面接日程の調整がスムーズといった一つひとつの体験が、企業の印象を良くし、選考辞退や内定辞退の防止に繋がります。また、煩雑な業務を効率的に処理することで、採用プロセス全体がスピードアップし、競合他社に先んじて優秀な人材を確保できる可能性が高まります。
4. 採用コストを最適化できる
一見、外部への委託費用がかかるためコスト増に思えますが、総合的に見ると採用コストの最適化に繋がるケースも少なくありません。例えば、採用担当者を新たに1名雇用する場合、給与や社会保険料、福利厚生費などを含めると年間で数百万円のコストがかかります。採用代行であれば、必要な時期に必要な業務だけを依頼できるため、人件費を固定費化せずに済みます。また、プロの知見によって採用効率が上がることで、結果的に一人当たりの採用単価が下がる効果も期待できます。
5. 採用担当者の負担を軽減できる
採用活動は時期によって業務量が大きく変動し、特に繁忙期には担当者に極端な負荷がかかりがちです。採用代行を活用すれば、業務の繁忙期・閑散期に合わせて外部リソースを柔軟に活用できるため、担当者の残業時間を削減し、心身の負担を軽減できます。これにより、担当者のエンゲージメントを維持し、離職を防ぐ効果も見込めます。兼務人事が多い中小企業にとっては、特に大きなメリットと言えるでしょう。
採用代行を利用する3つのデメリット
採用代行は多くのメリットがある一方で、導入にあたっては注意すべきデメリットも存在します。
ここでは、採用代行の主な3つのデメリットを解説します。
1. 採用ノウハウが社内に蓄積しにくい
採用業務の多くを外部に委託するため、採用に関する知見やノウハウが自社内に蓄積しにくいというデメリットがあります。特に、採用活動の全プロセスを「丸投げ」してしまうと、将来的に自社で採用活動を行おうとした際に、一からノウハウを構築しなければならない状況に陥る可能性があります。これを防ぐには、代行会社と密に連携し、定例会などを通じて採用市場の動向や効果のあった施策、改善点などの情報を積極的に共有してもらう姿勢が重要です。
2. 委託先との情報共有に手間がかかる
採用代行会社が自社の採用担当としてスムーズに業務を遂行するには、企業の理念や文化、求める人物像、選考基準などを深く理解してもらう必要があります。そのため、導入初期には、委託先との間で綿密な情報共有や認識合わせを行うための時間と手間が発生します。また、運用開始後も、選考状況や候補者の情報をリアルタイムで共有するための連携体制を構築しなければ、かえって業務が非効率になる恐れもあるため注意が必要です。
3. ミスマッチや応募者満足度が低下する恐れ
委託先の担当者が、自社の魅力や社風を十分に理解しないまま候補者とコミュニケーションを取ってしまうと、候補者に誤った情報や印象を与え、入社後のミスマッチに繋がるリスクがあります。また、画一的な対応や機械的な連絡に終始してしまうと、候補者体験(CX)を損ない、企業のブランドイメージを低下させる恐れも否定できません。
そのため、代行会社がいかに「自社の一員」として熱意を持って候補者に対応してくれるかを見極めることが重要になります。前述の通り、採用成功に向けた伴走してもらえるよう、コミュニケーションを丁寧に取り続けることがポイントです。
失敗しない採用代行会社の選び方5ステップ
採用代行サービスの効果は、どの会社をパートナーとして選ぶかに大きく左右されます。料金の安さや知名度だけで選んでしまうと、期待した成果が得られないばかりか、かえって業務負担が増えることにもなりかねません。ここでは、自社に最適な採用代行会社を選ぶための5つのステップを解説します。
1. 導入目的と依頼範囲を明確にする
まず最初に、「なぜ採用代行を導入するのか」「どの業務を任せたいのか」を社内で明確に定義することが最も重要です。「ノンコア業務を削減してコア業務に集中したい」「専門家の知見を借りて採用戦略を改善したい」「とにかく人手が足りないので即戦力が欲しい」など、目的によって選ぶべきパートナーは異なります。目的が明確になれば、依頼すべき業務範囲もおのずと定まり、代行会社に的確な要望を伝えることができます。この軸がブレていると、導入後のミスマッチの最大の原因となります。
2. 自社の採用課題に合った実績があるか確認する
採用代行会社には、それぞれ得意な領域があります。新卒採用に強い会社、ITエンジニアなど専門職採用に強みを持つ会社、アルバイト・パート採用が得意な会社など様々です。自社が募集したい職種や業界での採用支援実績が豊富かどうかを必ず確認しましょう。過去の具体的な支援事例や、どのような課題をどう解決したのかを詳しくヒアリングすることで、自社の採用を成功に導いてくれるかの判断材料になります。公式サイトの実績ページを確認するだけでなく、商談の場で直接質問することが重要です。
3. 担当者との相性や連携体制を見極める
採用代行は、最終的には「人」が提供するサービスです。実際に自社の採用を担当してくれる担当者のスキルや経験、そして何よりも「相性」が、プロジェクトの成否を大きく左右します。提案時の営業担当者と、運用開始後の実務担当者が異なるケースも多いため、可能であれば契約前に実務担当者と面談させてもらいましょう。自社の理念やビジョンに共感し、同じ熱量で採用活動に取り組んでくれるか、コミュニケーションは円滑か、といった点を見極めることが大切です。
4. 対応可能な業務範囲と柔軟性を確認する
自社が依頼したい業務に、漏れなく対応可能かどうかを確認します。また、将来的に依頼範囲を拡大・縮小する可能性も考慮し、柔軟に対応してくれるかどうかも重要なポイントです。例えば、「最初はスカウト配信業務だけを依頼し、成果が出たら面接調整もお願いしたい」といった段階的な依頼が可能か、といった点です。パッケージプランだけでなく、自社のニーズに合わせて業務内容を細かくカスタマイズできる会社であれば、より費用対効果の高い活用が期待できます。
5. 情報セキュリティ体制を確認する
採用活動では、応募者の氏名や連絡先、経歴といった多くの個人情報を取り扱います。万が一、情報漏洩が発生すれば、企業の社会的信用は大きく損なわれます。そのため、委託先の情報セキュリティ体制は必ず確認しなければならない最重要項目の一つです。例えば、プライバシーマーク(Pマーク)やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証を取得しているかは、信頼性を判断する上での一つの基準となります。データの管理方法やアクセス権限の設定など、具体的なセキュリティ対策についてもしっかりと確認しておきましょう。
【目的別】おすすめの採用代行(RPO)サービス
採用代行サービスは数多く存在し、それぞれに特徴や強みがあります。自社の課題や目的に合わないサービスを選んでしまうと、期待した効果は得られません。ここでは、企業のニーズに合わせて選べるよう、代表的な採用代行サービスを「大手・総合型」「専門特化型」「中小・ベンチャー向け」の3つのカテゴリに分けてご紹介します。
総合力で選ぶ!大手・実績豊富な採用代行サービス
まずは、幅広い業種・職種に対応可能で、豊富な実績とノウハウを持つ大手サービスです。採用活動全体を包括的にサポートしてほしい、安定した運用を任せたいという企業におすすめです。
1. ネオキャリア

ネオキャリアは、業界トップクラスの実績を誇り、新卒・中途・アルバイト・パートまで、あらゆる採用領域に対応できる総合力が魅力です。全国に拠点を持ち、長年培ってきた豊富なノウハウを基に、企業の採用課題に対して多角的なソリューションを提供します。採用業務全般を安心して任せたい場合に最適なパートナーとなるでしょう。
2. パーソルキャリア(doda RPOサービス)

転職サービス「doda」で知られるパーソルキャリアが提供するRPOサービスです。人材紹介事業で培った膨大なデータと知見を活かし、採用戦略の立案から実行までを一気通貫で支援します。特に中途採用領域に強みを持ち、質の高い採用活動を実現したい企業に適しています。
3. マンパワーグループ

マンパワーグループは世界的な総合人材サービス企業であり、グローバル水準のノウハウと大規模な採用プロジェクトにも対応できる体制が強みです。採用プロセス全体の設計・最適化から、一部業務の切り出しまで、企業のニーズに柔軟に対応。外資系企業や、全国規模での大量採用などを検討している場合に頼りになる存在です。
特定領域に強み!専門特化型の採用代行サービス
特定の職種や業界に特化し、高い専門性を持つサービスです。
ITエンジニアや医療系専門職など、採用難易度の高い職種の採用を成功させたい場合に大きな力を発揮します。
4. レバレジーズ
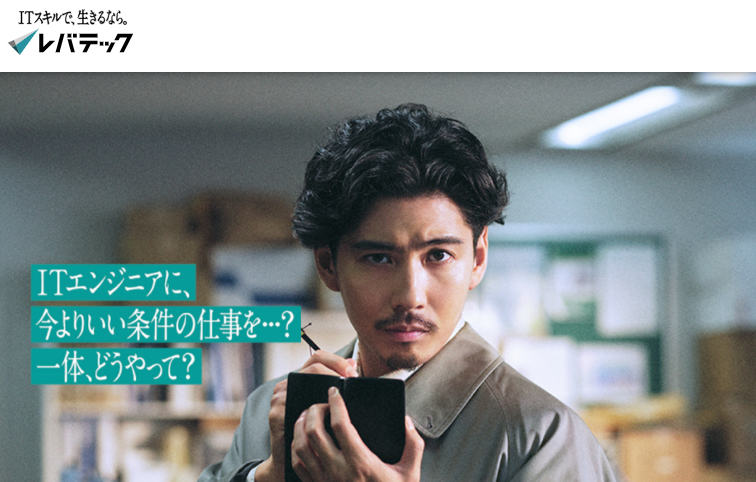
IT・医療・介護といった専門領域に特化した人材サービスを展開しており、各分野の採用市場を深く理解しているのが特徴です。「レバテック」などで知られるITエンジニアの採用支援には特に定評があり、専門知識を持つコンサルタントが、採用要件の定義から候補者の動機づけまでを強力にサポートします。
5. ツナグ・ソリューションズ

アルバイト・パート採用の領域において、国内トップクラスの実績を持つコンサルティング会社が提供するRPOです。飲食・小売・サービス業など、多店舗展開を行う企業の大量採用や、採用率・定着率の改善を得意としています。応募者の対応から面接設定まで、現場の負担を大幅に軽減します。
コストと柔軟性で選ぶ!中小・ベンチャー向け採用代行サービス
オンラインを主体とし、必要な業務を必要な分だけ柔軟に依頼できるサービスです。
コストを抑えながら、採用のボトルネックを解消したい中小・ベンチャー企業に最適です。
6. CASTER BIZ recruiting(株式会社キャスター)

完全オンラインで採用アシスタント業務を依頼できるサービスです。月額制で、スカウトメールの送信、日程調整、応募者対応など、工数のかかるノンコア業務を幅広くカバーします。1ヶ月単位での契約が可能で、採用の繁閑に合わせて柔軟に活用できるため、特に兼務人事の方におすすめです。
7. HELP YOU(株式会社ニット)

採用業務に限らず、人事、経理、営業サポート、Webサイト運用まで、様々なバックオフィス業務をオンラインで支援するサービスです。チーム体制でのサポートが特徴で、多岐にわたる業務を兼任している担当者が、採用業務と合わせて他の業務もアウトソースしたい場合に非常に有効です。
8. corner(株式会社コーナー)
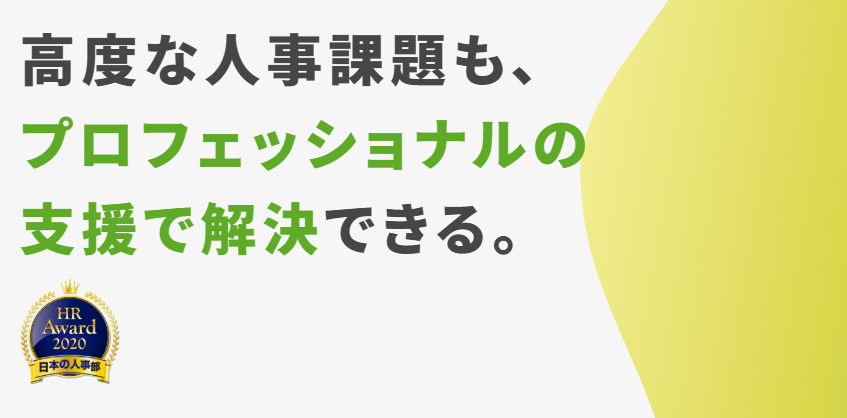
人事・採用領域のフリーランスや複業のプロフェッショナルと企業をマッチングするプラットフォームです。採用戦略の策定や制度設計といった上流工程から、スカウト代行などの実務まで、企業の課題に合わせて必要なスキルを持つプロに直接依頼できます。特定の期間だけ専門家の力を借りたい場合に適しています。
9. HeaR株式会社
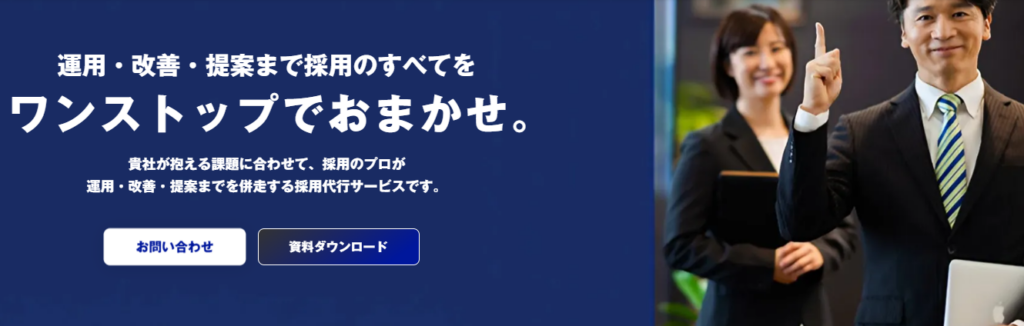
スタートアップ・ベンチャー企業向けの採用支援に特化しています。特に、ダイレクトリクルーティングの運用代行や、採用広報の強化、CX(候補者体験)の向上といった、現代の採用トレンドに沿った支援を得意としています。企業のカルチャーに合った人材の採用を目指す場合に心強いパートナーです。
【企業規模別】採用代行のおすすめ活用法
採用代行サービスは、企業の規模やフェーズによって最適な活用方法が異なります。自社の状況に合わせて戦略的に活用することで、費用対効果を最大化できます。ここでは、特に中小・ベンチャー企業と中堅・大手企業に分けて、おすすめの活用法をご紹介します。
中小・ベンチャー企業の場合
採用担当者が他業務と兼任していることが多い中小・ベンチャー企業では、リソース不足が深刻な課題です。そのため、まずは自社の採用プロセスの中で、最も時間がかかっている、あるいは最も苦手としている業務を特定し、そこだけをピンポイントで委託するのがおすすめです。
例えば、「スカウトメールの配信」や「面接日程の調整」といったノンコア業務を切り出すことで、担当者は候補者との対話や口説きといったコア業務に集中できます。限られた予算の中で、最大限の効果を発揮するための賢い活用法と言えるでしょう。
中堅・大手企業の場合
ある程度の採用体制が整っている中堅・大手企業では、採用人数の増加に伴う業務量の増大や、採用チャネルの多様化による管理の煩雑さが課題となりがちです。この場合、特定の部門(例:新卒採用部門)や特定の業務プロセス(例:応募から一次面接まで)をまるごとアウトソースすることで、業務の標準化と効率化を図る活用法が有効です。また、専門職採用など、特定の領域に特化した知見を持つ代行会社のノウハウを活用し、自社の採用力をさらに強化するという戦略的な使い方も考えられます。
まとめ
本記事では、採用代行(RPO)の基本的な定義から、業務内容、料金相場、メリット・デメリット、そして失敗しない選び方まで、網羅的に解説してきました。
採用代行は、単に人手不足を補うためのサービスではありません。採用のプロフェッショナルの知見を借り、採用担当者がノンコア業務から解放されることで、企業の採用活動そのものを戦略的に進化させるための強力なパートナーとなり得ます。特に、リソースが限られる中で多様な業務をこなす中小企業の人事担当者様にとっては、自社の課題を解決し、採用成功をぐっと引き寄せるための有効な選択肢の一つです。
最後に、新卒採用でお困りごとがありましたら「キミスカ」にぜひご相談ください。効率的にターゲット学生に絞った母集団を形成し、採用成功に向けて伴走させていただきます。
※お問い合わせはこちら、のボタンを入れたい