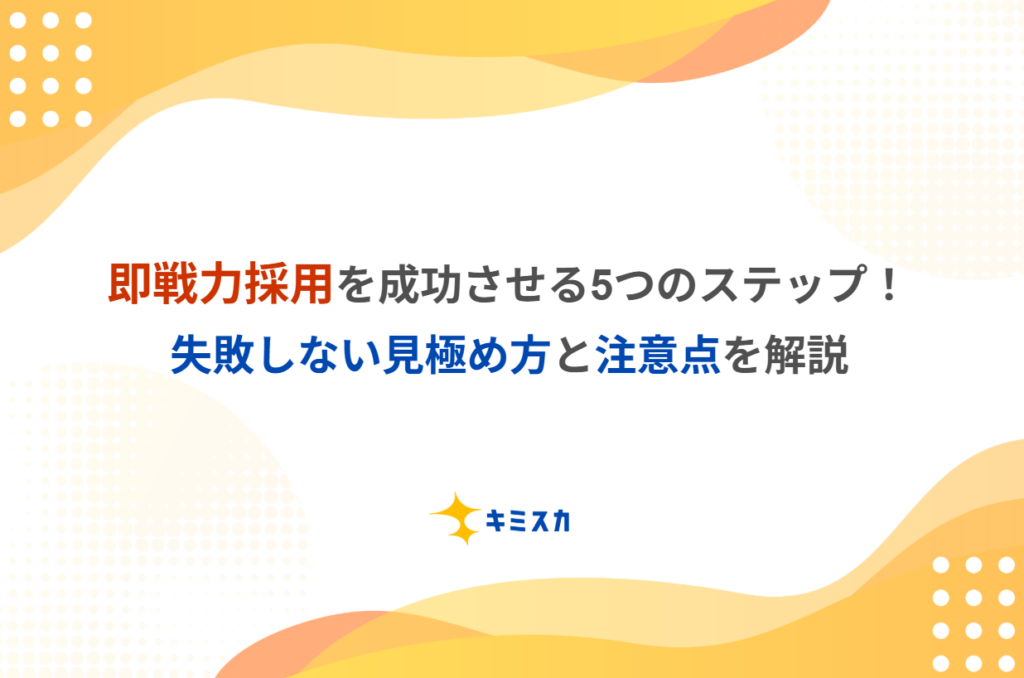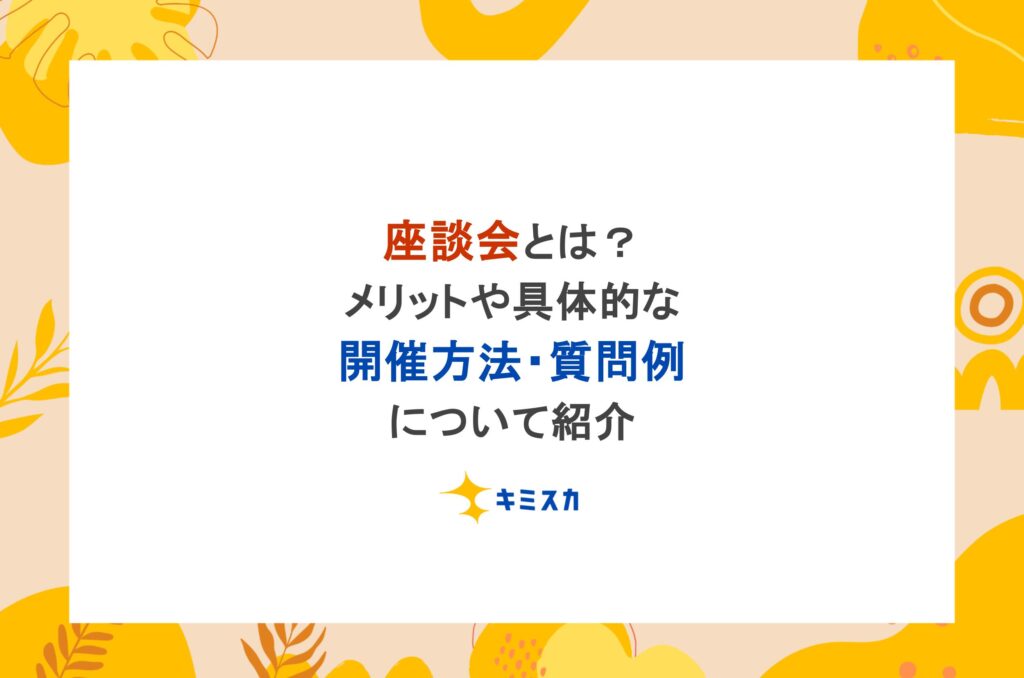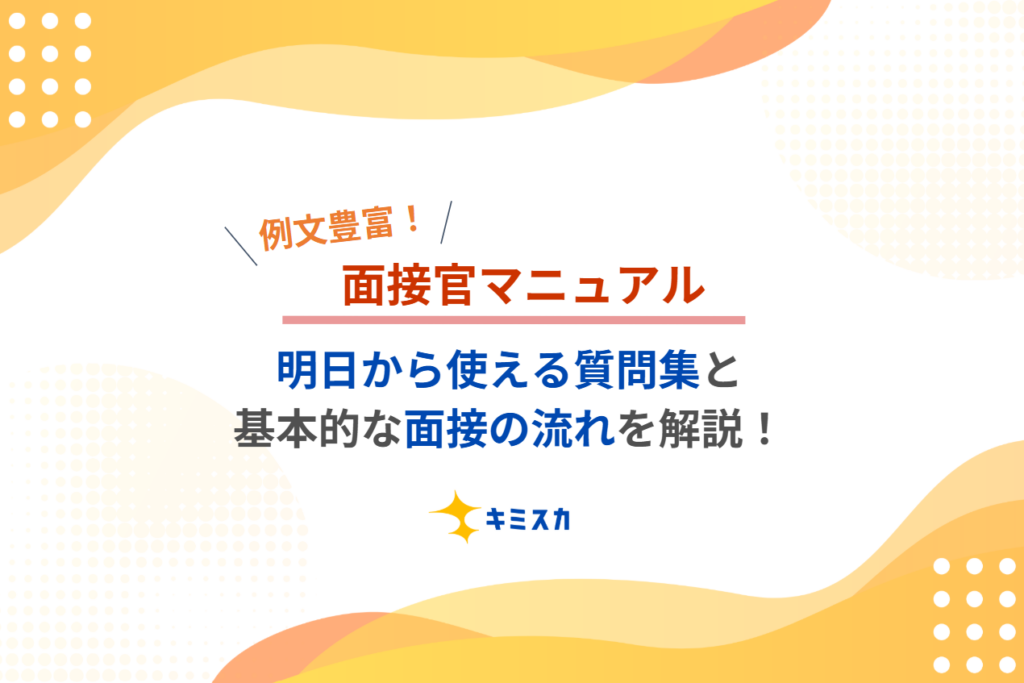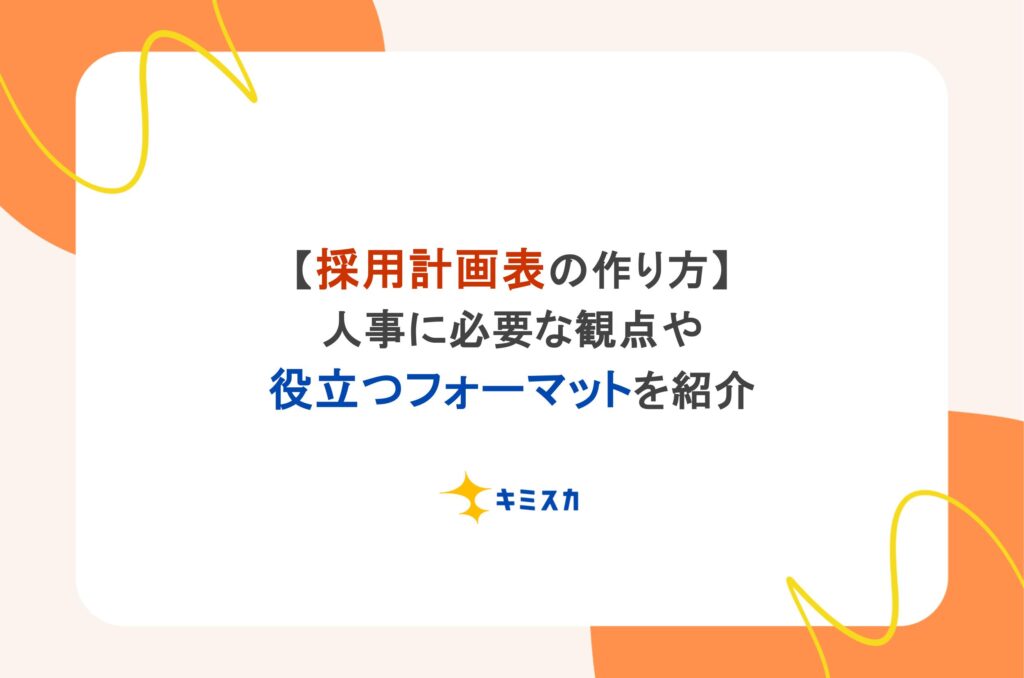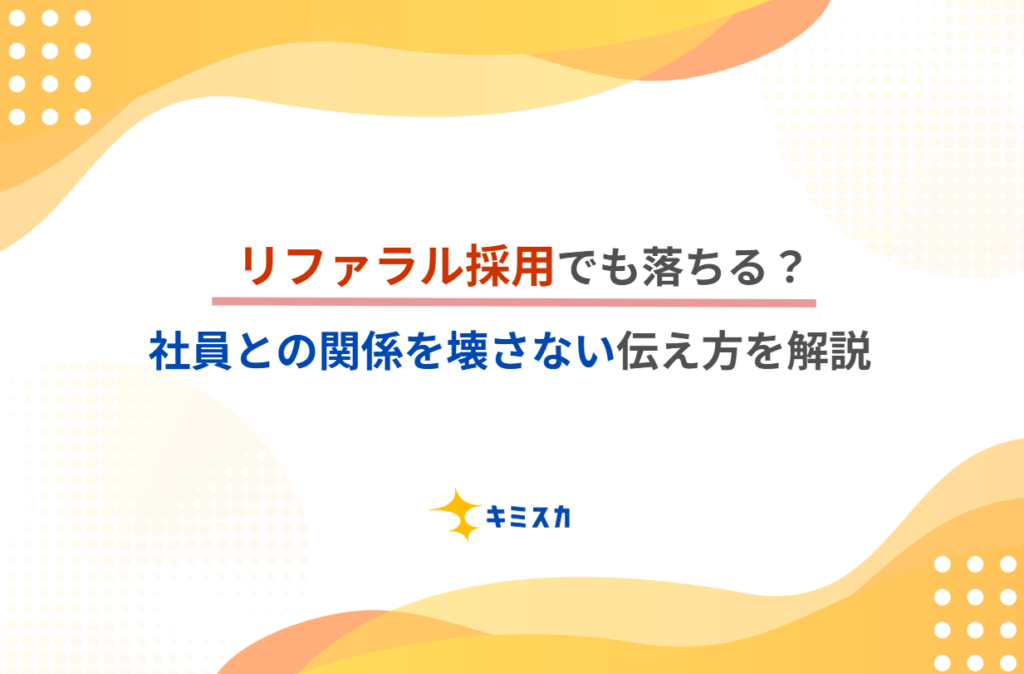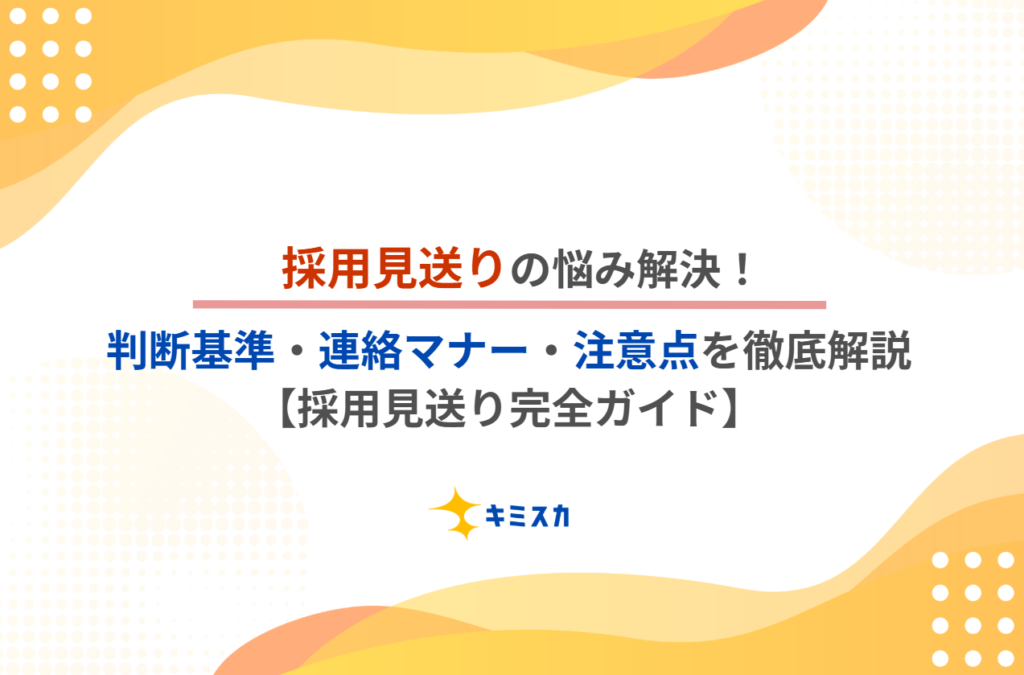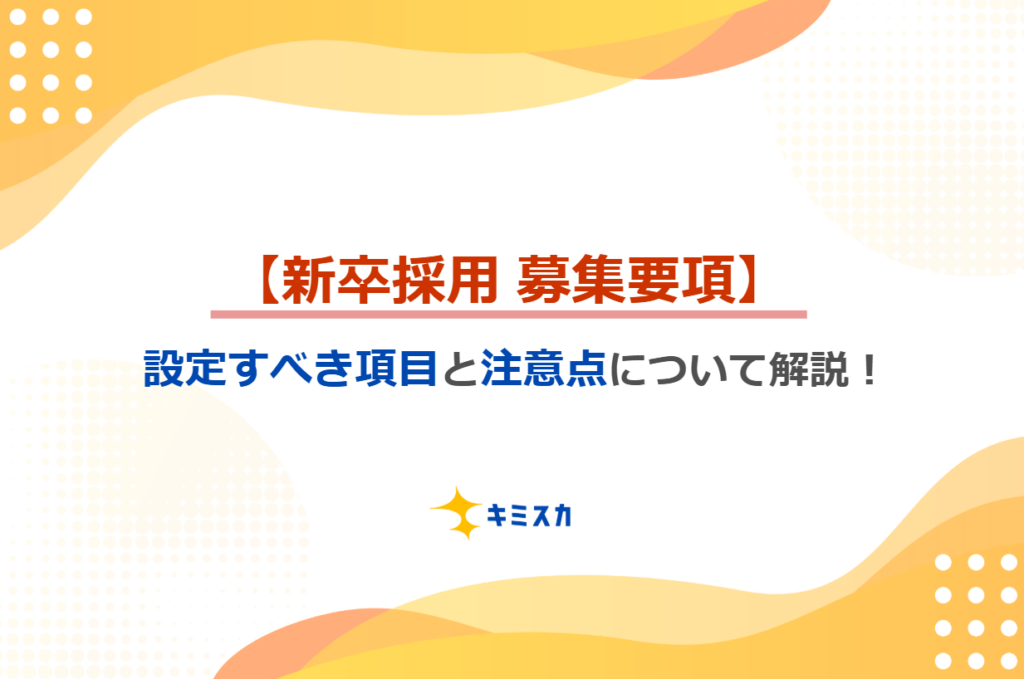
新卒採用において、募集要項は企業が求める人材像を明確にし、就活生に自社の魅力を効果的に伝えるための最初の接点となります。そのため、魅力的な募集要項を作成することは、優秀な人材を惹きつけ、採用活動を成功に導くための重要な第一歩と言えます。
本記事では、新卒採用における募集要項の基本から、必ず記載すべき項目、陥りやすい間違い、そして応募者数を増やすためのポイントまでを詳しく解説します。
新卒採用の募集要項とは?
新卒採用における募集要項とは、企業が新卒者に向けて「どのような人材を求めているのか、どのような条件で採用を行うのかを具体的に示すもの」です。
これは、就活生が自分に合った企業や職種を選ぶための重要な判断材料となります。詳細な情報を提供することで、企業は求める人物像に近い学生からの応募を増やし、ミスマッチを防ぐことができます。
必ず記載すべき項目と記載ポイント
効果的な募集要項を作成するために、以下の項目は必ず記載するようにしましょう。
募集職種
単に職種名を書くだけでなく、具体的な業務内容をイメージできるように記載しましょう。
「〇〇職(営業)」のように、職種名と具体的な業務内容を併記したり、「顧客への課題解決型営業」「新規顧客開拓」など、業務内容のキーワードを入れると、応募者は自分に合った職種かどうか判断しやすくなります。また、配属予定の部署やチーム、キャリアパスの例などを加えると、入社後のイメージが湧きやすくなります。
応募資格
応募できる学生の条件を記載します。学部・学科を限定する場合は、その理由を明確にしましょう。
不必要に限定してしまうと、応募者の機会を狭める可能性があります。「〇〇学部・学科卒以上」とするだけでなく、「〇〇の知識や関心がある方」といった表現も加えることで、より幅広い層にアピールできます。卒業見込み年度は正確に記載し、既卒者も応募可能かどうかを明記することも重要です。
必要なスキルや資格は、必須のものと歓迎するものに分けて記載すると、応募者は自身の状況に合わせて判断しやすくなります。
例:「必須スキル:基本的なPCスキル(Word, Excel, PowerPoint)」
「歓迎スキル:TOEIC〇〇点以上、プログラミング経験」
募集人数
採用予定人数は具体的な数字を記載することで、就活生は応募の目安を立てやすくなります。
「若干名」とする場合は、ある程度の人数感を補足説明すると良いでしょう。例えば、「〇名程度」といった表現や、「事業拡大に伴う増員」といった背景を伝えることで、応募意欲を高める効果も期待できます。
勤務地
複数の勤務地がある場合は、全て具体的に記載しましょう。
「〇〇本社(東京都〇〇区)、全国の事業所」のように、可能性のある勤務地を網羅的に示すことが大切です。将来的な転勤の可能性についても触れておくと、入社後のミスマッチを防ぐことができます。
給与・待遇
初任給、昇給、賞与、諸手当、福利厚生など、待遇に関する情報を具体的に記載します。
初任給は、基本給だけでなく、諸手当を含めた総支給額を示すことが望ましいです。昇給や賞与の制度についても、可能な範囲で具体的に説明しましょう。福利厚生は、社会保険、有給休暇、育児休業制度、住宅手当、社員食堂など、充実した内容を具体的に記載することで、企業としての魅力を高めることができます。
勤務時間
始業時間、終業時間、休憩時間など、基本的な勤務時間を記載します。
定時勤務の場合は、始業時間と終業時間を明確に記載します。フレックスタイム制や裁量労働制を採用している場合は、その制度の概要やコアタイムの有無などを詳しく説明しましょう。残業の有無や平均残業時間などを記載することも、応募者にとって重要な情報となります。
選考プロセス
応募から内定までの流れを具体的に記載します。
応募から内定までの各ステップを明確に示し、それぞれのステップで何が行われるのか(例:書類選考→エントリーシートの内容に基づき選考、筆記試験→一般常識・能力検査、一次面接→人事担当者による個別面接)を具体的に説明しましょう。各ステップの所要期間の目安を示すと、応募者はスケジュールを立てやすくなります。
応募方法
応募に必要な書類(履歴書、エントリーシート、成績証明書、卒業見込証明書など)を全てリストアップし、それぞれの提出方法と提出期限を明確に記載します。
オンラインでの応募方法については、具体的な手順や推奨するファイル形式などを詳しく説明しましょう。
応募締切
応募を受け付ける最終日時を明確に記載します。
「〇月〇日(〇)〇時必着」のように、期日と時間を具体的に示すことが重要です。締切間近になって慌てる応募者が出ないよう、余裕を持った締切日を設定することも考慮しましょう。
採用スケジュール
インターンシップ、説明会、書類選考、筆記試験、面接などの日程が決まっている場合は、可能な範囲で記載します。
現時点での予定だけでなく、今後のスケジュールについても随時更新していく姿勢を示すことが大切です。
問い合わせ先
募集要項に関する質問を受け付ける窓口の連絡先(電話番号、メールアドレスなど)を記載します。
電話での問い合わせ時間や、メールでの返信にかかる時間などの目安を示すと、応募者は安心して問い合わせをすることができます。
企業情報
企業の基本情報(会社名、所在地、設立年月日、代表者名、事業内容など)を改めて記載することで、就活生の理解を深めます。就活生の親が見る可能性もあるため、企業への信頼度を上げるためにも詳細に記載しましょう。
求める人物像
どのような人と働きたいか、マッチング精度を上げるためにも具体的に記載しましょう。
抽象的な表現だけでなく、「主体的に行動できる方」「チームワークを大切にできる方」「新しいことに挑戦する意欲のある方」など、具体的なキーワードを用いて、どのような能力や意欲を持った人材を求めているのかを明確に伝えましょう。企業の理念やビジョンに共感できる人材を求めている場合は、その点も強調するのがおすすめです。
必須ではないが推奨される項目
募集要項に必ず記載しなければならない項目に加えて、以下の情報を積極的に盛り込むことで、企業の魅力をより効果的に伝え、優秀な人材の獲得に繋げることができます。
研修制度
入社時研修(ビジネスマナー、企業理念、業界知識など)、OJT研修、階層別研修、専門スキル研修、資格取得支援制度、メンター制度などを具体的に記載します。
研修の期間、内容、特徴などを具体的に説明することで、どのようなスキルを習得できるのか、どのように成長できるのかをイメージさせることが重要です。「入社後3ヶ月間はOJT研修として先輩社員が丁寧に指導します」といった具体的な情報を加えることで、安心感を与えることができます。
キャリアパス
入社後の具体的なキャリアステップ(例:一般社員→主任→係長→課長)、ジョブローテーション制度、社内公募制度などを記載します。
数年後にどのようなキャリアを描ける可能性があるのかを示すことで、長期的な視点を持った優秀な人材にアピールできます。「〇年後にはリーダーとしてチームを牽引する」「将来的には海外事業に携わるチャンスも」といった具体的なキャリアパスの例を提示すると、応募者のモチベーション向上に繋がります。
職場の雰囲気、社員の声など
実際に働く環境や社員のリアルな声は、就活生にとって企業選びの重要な判断材料となります。
文字情報だけでなく、写真や動画などを活用して、職場の雰囲気を具体的に伝えることが効果的です。例えば、若手社員のインタビュー記事を作成し、入社の決め手や1日の業務内容についてオープンに開示することで、理解度と親近感が増します。
「よくある間違い」とは?
募集要項を作成する際に、採用担当者が陥りやすい間違いがいくつか存在します。
これらの間違いを避けることで、より効果的な募集要項を作成することができます。
曖昧な表現が多い
募集職種の業務内容や応募資格などが曖昧に書かれていると、就活生は自分に合っているかどうか判断できず、応募をためらってしまう可能性があります。開示できる範囲で構いませんので、具体的な表現を心がけましょう。
また、給与や福利厚生などの基本的な情報しか記載されておらず、企業の文化や働く環境、成長機会などが伝わらない募集要項は、就活生の興味を引くことができません。写真や動画などを活用して、企業の魅力を積極的にアピールしましょう。
条件が厳しすぎる
高すぎる語学力や専門知識を必須条件としてしまうと、応募者の間口を狭めてしまい、優秀な人材を逃してしまう可能性があります。
就活生はまだ就業経験がないため、将来の活躍可能性に投資することも考慮する必要があります。そのため、ポテンシャル採用の視点も持ち、必須条件と歓迎条件を明確に区別しましょう。
情報が古い
前年度の情報をそのまま流用している場合、最新の情報と異なる可能性があります。募集要項は毎年見直し、最新の情報に更新するようにしましょう。
過去採用実績や、社員インタビュー記事・社内行事などのコンテンツは毎年更新することで、会社のイメージや働く社員の雰囲気が正しく伝わりやすくなります。
専門用語を多用する
業界特有の専門用語を多用すると、新卒の就活生には理解できない場合があります。分かりやすい言葉で説明することを心がけましょう。
加えて、誤字脱字が多い募集要項は、企業の信頼性を損ねる可能性があります。公開前に必ず複数人で確認することも忘れないようにしてください。
募集要項は「間口を広く」がおすすめ
新卒採用において、募集要項は間口を広く作成することをおすすめします。その理由は以下の通りです。
多様な人材の確保
応募資格や必須条件を厳しく設定しすぎると、特定のスキルや経験を持つ学生しか応募できなくなり、多様な視点や発想を持つ人材を確保する機会を失ってしまいます。現時点でのスキルや経験だけでなく、将来的な成長の可能性(ポテンシャル)も視野に入れるべきです。
一方で、企業の求める人物像やコアとなる能力は、明確に伝えることも重要です。間口を広げすぎると、ミスマッチに繋がりかねないためです。量と質のバランスが難しいですが、ここでは「採用基準」を設定しておくことがポイントです。
採用基準の重要性や具体的な設定方法については、こちらの記事『「採用基準」の重要性とは?具体的な設定方法とメリットを解説!』をご覧ください!
企業イメージの向上
幅広い学生に門戸を開いている企業は、社会貢献意識が高く、多様性を尊重する企業として好印象を持たれる傾向があります。もちろん、職種によっては一定の知識やスキルが必要となる場合もありますが、その場合でも、必須条件は必要最低限に留め、ポテンシャルを重視した条件設定を検討することをおすすめします。
例えば、「〇〇の知識がある方歓迎」といった歓迎条件として記載することで、間口を広げながらも求める人物像に合致する人材からの応募を促すことができます。
まとめ
新卒採用における募集要項は、企業の採用活動の成否を左右する重要な指標です。
就活生は複数の企業の募集要項を比較検討しています。そのため、競合他社の募集要項を参考にしながら、自社の強みや魅力を際立たせるような工夫を凝らすことが重要です。
本記事では、必ず記載すべき項目から、よくある間違い、そして間口を広くすることの重要性について解説しました。魅力的な募集要項を作成し、ターゲット学生との出会いを広げる一助になれば幸いです。