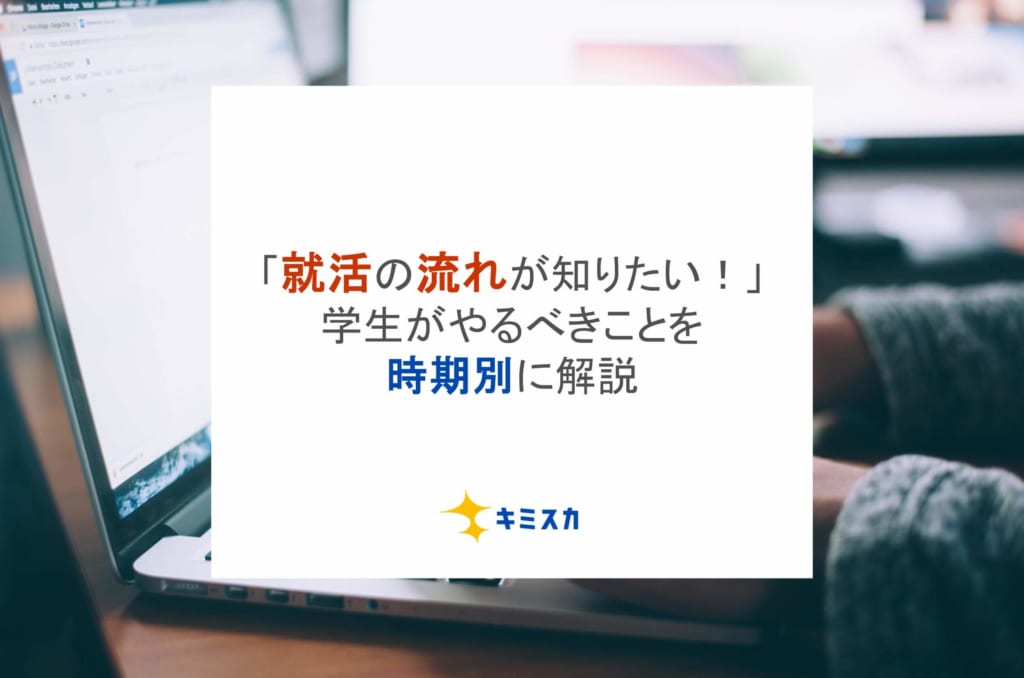
大学生のほとんどが未経験の状態で始めることになる就活。やるべきことはある程度わかっているものの、全体像を掴みきれていない方は少なくないでしょう。
そこで、今回は就活の流れについて解説します。また、就活を進めるうえで欠かせない作業をはじめ、書類選考や面接などの対策を時期別に紹介します。効率よく就活を進めるためにも、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。
就活の流れを把握することが内定への近道
就活ではやるべきことが数多くあります。自己分析や企業研究といった作業をはじめ、ES(エントリーシート)や面接などの選考対策も必要になるので、準備不足にならないためにも全体像を把握しておくことが重要です。
就活の流れを理解しておけば、就活に対する漠然とした不安がなくなり、作業や対策を計画的に進められます。また、十分に準備ができていれば、自分らしさや入社意欲の高さを選考で伝えられ、内定獲得の可能性も高まるでしょう。
就活の流れを時期別に紹介
就活の選考が始まる時期はいくつかパターンがあり、経団連に加盟しているかどうか、外資系企業かどうかなどによって異なる可能性があります。
以下にそれぞれの選考時期をまとめましたが、自分の志望する企業については個別に確認しておきましょう。
<経団連に加盟している企業>
| 大学3年7月~ | 夏期インターンシップ |
| 大学4年3月~ | エントリー、企業説明会、ES |
| 大学4年6月~ | 選考(適性検査・筆記試験、面接)、内々定 |
| 大学4年10月~ | 内定出し |
<経団連に非加盟の企業>
| 大学3年7月~ | 夏期インターンシップ |
| 大学3年10月~ | 秋期インターンシップ、早期エントリー・選考・内定出し |
| 大学3年1月~ | 冬期インターンシップ |
| 大学3年3月~ | 一般エントリー・選考 |
| 大学4年6月~ | 適性検査・筆記試験、面接、内々定 |
| 大学4年10月~ | 内定出し |
<外資系企業>
| 大学3年7月~ | 夏期インターンシップ |
| 大学3年10月~ | 選考・内定出し |
なお、本記事では“経団連に加盟している企業”のスケジュールに沿って就活の流れをまとめています。就活の計画を立てるときは、自分が志望する企業の選考スケジュールに置き換えて準備を進めましょう。
【就活の流れ1】自己分析は3年の6月~
自己分析は遅くとも大学3年の6月から始めておきましょう。自己分析とは、自己理解を深めるための作業のことを指しており、以下のことが明確になります。
強み・弱み
長所・短所
価値観
就活の軸
これらがわかることで、ES(エントリーシート)や面接で伝えるアピールポイントが明確になります。また、就活の軸がわかることで、自分に合った企業を見つけやすくなるため、企業選びのときにも役立つでしょう。
自己分析の具体的なやり方については、以下の記事を参考にしてみてください。
【就活の流れ2】業界・企業研究は3年の6月~
自己分析とあわせて、業界・企業研究も6月ごろから始めましょう。
業界研究は志望する業界を決めるために、メーカーや商社といった業界について調べることです。そして、企業研究は興味のある企業について深く理解するために、競合他社との違いや業務内容といった幅広い視点から企業の特質を明らかにすることです。
就活が始まってから業界・企業研究をすると、時間に余裕がないまま就活や選考を進めることになるため、早めに着手しておきましょう。
まずは志望する業界を絞ることが効果的なので、以下の記事を参考に業界研究を進めてみてください。
【就活の流れ3】インターンシップ参加は大学3年の夏・冬
インターンシップは大学3年の夏か冬に1度は参加しておきましょう。関心のある企業のインターンシップに参加することで、企業研究などで抱いたイメージとギャップがあるかどうか確かめられます。
また、自分の適性を把握したり企業研究を深められたりするほか、場合によっては内定に直結する可能性もあります。
インターンのプログラム内容や形式、実施期間、メリットなどについては以下の記事をチェックしてみてください。
【就活の流れ4】ES・履歴書の提出は3年の3月~
経団連に加盟している企業では、大学3年の3月から選考が本格的にスタートします。ESの設問は企業によって異なる場合がありますが、基本的には「自己PR」や「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」などが主です。
自己分析で自分の特徴を把握し、企業研究を通じて志望企業に合わせたアピールが可能となるため、ESを作成する前に必ず済ませておきましょう。
なお、魅力的なESを作成するためのポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。
【就活の流れ5】適性検査・筆記試験の対策は3年の冬~
大学3年の冬は、ES対策とあわせて適性検査や筆記試験などの対策も進めておきましょう。
試験の種類はいくつかあり、SPIや玉手箱などの適性検査を実施する企業もあれば、企業独自の試験を課すところもあります。例えば、SPIは中学~高校レベルの問題が出題されますが、何の対策もしていないと高得点を狙うことは難しいでしょう。
対策としては問題集や過去問を何度も解いて出題傾向に慣れ、解法を理解しておくことが大切です。また、試験では1問ごとに制限時間が設けられていることもあるため、時間内に解く練習も欠かせません。
適性検査の種類や具体的な対策方法について知りたい方は、以下の記事を確認しておきましょう。
【就活の流れ6】企業説明会への参加・エントリーは3年の3月~
大学3年の3月1日から、企業説明会への参加やエントリーが可能となります。就活サイトや企業の採用ページからプレエントリーをし、会社説明会に参加して志望企業の情報を集めましょう。
プレエントリーの時点ではまだ選考は始まっていませんが、説明会の案内や選考スケジュールに関する連絡が届くため、興味のある企業は欠かさずプレエントリーをしておきましょう。
【就活の流れ7】面接対策は3年の3月~
経団連加盟企業の場合、面接は大学4年の6月から始まります。選考解禁されると、企業説明会に参加したりESの作成・提出をしたりと忙しくなるため、遅くとも大学3年の3月から面接対策をしておきましょう。
面接では自己PRや志望動機といった質問を投げかけられるほか、就活生の話し方や入退室のマナーなども見られているため、十分に対策しておく必要があります。
面接対策の方法については、以下の記事を参考にしてみてください。
【就活の流れ8】内定獲得は4年の6月~
大学4年の6月ごろになると、徐々に内々定が出始めます。ミスマッチの企業の内定承諾をしてしまうと、入社後に早期退職してしまう可能性もあるため、内定をもらったとしても十分に検討することが大切です。
就活をいつから始め、いつ終えるのかは人によって異なるため、自分が納得できるまで就活を進めることを意識しましょう。
ただ、夏までに内定をもらえていない場合は注意が必要です。大学4年の秋まで続ける学生も少なくありませんが、“無い内定”が続いている場合は以下の記事を参考に対策しておきましょう。
就活の流れを効率よく進めるためのコツ

続いては、就活を効率よく進めるために押さえておきたいコツを紹介します。ゴールから逆算して計画を立てたり、物事の優先順位をつけて取り組んだりと、事前に考えておくことでスムーズに就活を進められます。
【就活の流れ効率化のコツ1】逆算して計画を立てる
就活の準備から選考まで効率的に進めるためにも、まずは計画を立てましょう。選考解禁となる大学3年の3月1日に合わせるのか、それよりも早い外資系企業の選考に合わせるのかで就活を始める時期が異なります。
周りに流されて就活を始めると、手遅れや準備不足になる可能性が高いため、自分だけの就活のゴールや期限を決め、そこから逆算してスケジュールを立てましょう。
【就活の流れ効率化のコツ2】やることの優先順位をつける
就活をスムーズに進めるためにも、計画を立てる際に物事の優先順位をつけておきましょう。例えば、就活に関することであれば、自己分析や企業研究といった作業のほか、ESや適性検査、面接などの選考対策が必要です。しかし、就活生は卒業単位の取得も必須で、人によってはゼミやサークル活動などで忙しくしている人もいるでしょう。
就活の進め方や開始時期は人それぞれ異なり、選考対策にかける時間は本人の得意・不得意によって大きく変わります。そのため、自分の“やるべきこと”や“やりたいこと”を明確にしたうえで、就活に必要な準備・期間をすり合わせ、優先順位をつけて取り組みましょう。
以下の記事では最低限必要なことや学年別にやるべきことをまとめているので、メリハリをつけて行動したい人は参考にしてみてください。
【就活の流れ効率化のコツ3】キャリアセンターを頼る
大学生のなかには初めて聞く人もいるかもしれませんが、キャリアセンターとは大学で就職支援や進路支援業務を行っている専門部署のことです。就職ガイダンスや業界別のセミナーなどを開いたり、模擬面接や個別の就活相談を受け付けたりしており、就活生にとっては非常に頼りになる存在といえます。
就活が本格的に始まる時期になると、キャリアセンターのスタッフも忙しくなるため、できるだけ時間に余裕を持って相談しに行くのがおすすめです。
就活の流れでつまずきがちなポイントと対策
ここまで就活の基本的な流れや効率よく進めるためのポイントを紹介してきましたが、つまずきやすいポイントもあるため事前に把握しておきましょう。
ここからは特に注意が必要な自己分析、ES、面接の3つを詳しく解説します。
【就活の流れでつまずきやすいポイント1】自己分析
自己分析は就活で必須の作業ですが、例年多くの学生が失敗しています。自分史やモチベーショングラフなど、自己分析のやり方はさまざまですが、あらかじめ目的を設定しておかないと、中途半端な分析になりかねません。また、あまり時間をかけずに自己分析をすると、事故理解が浅い状態で選考に望むことになってしまいます。
このほか、人によっては短所ばかりが目についてしまったり、経験の深掘りができていなかったりするために、自己分析が思うように進まないケースも少なくありません。
自己分析でつまずいてしまった人や、自己分析が心配な方はキミスカの自己分析ツールを試してみてください。簡単な質問に答えていくだけで強み・弱みや価値観などがわかり、自分に合った適職診断も行ってくれます。
自己分析ツールの詳細については、以下をご確認ください。
【就活の流れでつまずきやすいポイント2】ES
学生のなかには、選考の序盤で提出するESがなかなか通過しない人もいます。企業によっては学歴フィルターでふるいにかけている場合もありますが、記載する内容や伝え方のコツを意識しておかないと、あなたの魅力はなかなか伝わりません。
ESで重要なのは、企業の求める人物像に合致する自分の強みをアピールすることです。また、結論・理由・具体例・結論の順に伝えるフレームワークを使うことで、相手は書かれてある内容を理解しやすくなります。
ESでつまずいてしまう人は、以下の記事を参考に基本的な書き方のポイントを把握しておきましょう。
【就活の流れでつまずきやすいポイント3】面接
志望企業の社員や役員と直接話す面接に対して、苦手意識を持っている人は少なくありません。面接で落とされる原因はいくつかありますが、主な理由として以下に挙げたものが考えられます。
選考基準が高いため
ミスマッチの企業を受けているため
面接対策が足りていないから
入室から退室までのマナーがなっていないため
面接では企業と学生がマッチするかどうかを確かめるために質疑応答を繰り返すのが基本ですが、入退室のマナーや言葉遣い、身だしなみの清潔感も評価されています。
いずれも事前に対策しておかないと、マイナスの印象を持たれるかもしれません。受け答えがうまくできるか心配な方は、以下の記事を参考に想定質問で面接の練習をしておきましょう。
就活の流れを押さえて効率よく準備・対策を進めよう!
就活を効率よく進めるためには、全体の流れを把握しておくことが重要です。もちろん就活を始める時期は人によって異なりますが、選考解禁の3月1日に合わせる場合は大学3年の6月から準備を進めておきましょう。
自己分析やES、面接は多くの就活生がつまずきやすいポイントなので、ぜひ本記事で紹介した内容を参考に自分だけの就活に動き出してみてください。

