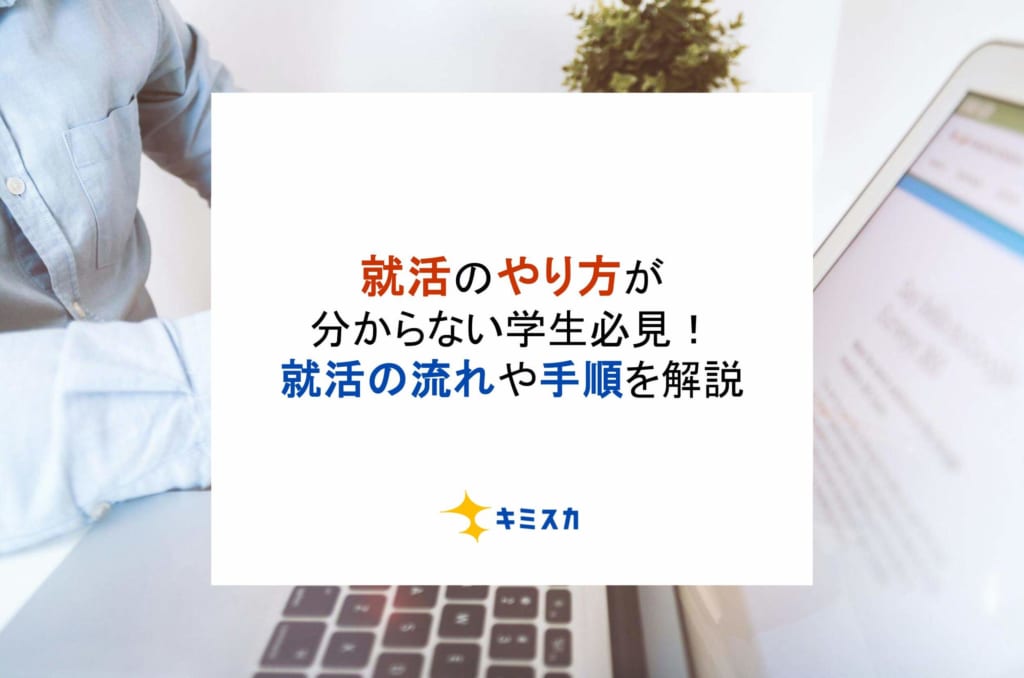
就活を始めようと考えている学生のなかには、「就活のやり方が分からない」「選考対策の手順を知りたい」という人もいるでしょう。また、いつから就活に取り組むべきか悩んでいる学生もいるかもしれません。周りが動き出して焦るけど、自分だけ遅れてる気がして不安…。でも大丈夫。就活にはちゃんと「やり方」があります。
そこで本記事では、就活の大まかな流れと就活のやり方を解説します。解説を参考に、就活ライフをスタートさせましょう。
就活の大まかな流れを確認しよう
就活のエントリーは、大学3年の3月から始まります。しかし、企業のなかには前倒しでエントリーを受け付けているところもあり、3月より前にエントリーを済ませている学生も少なくありません。
また、選考は大学4年の6月頃から行われる場合が多く、面接に関しては一次面接から最終面接まで段階を踏んで実施される場合もあります。
就活イベントの大まかな流れ
以下の表をご覧ください。
| 時期 | 就活スケジュール概要 |
|---|---|
| 大学3年8~9月 | 夏インターンシップ |
| 大学3年10月 | 秋インターンシップ/外資系企業の選考開始 |
| 大学3年11月 | 秋インターンシップ/大手マスコミの選考開始 |
| 大学3年12~2月 | 冬インターンシップ/経団連非加盟企業の選考開始 |
| 大学3年3月 | 就活解禁/説明会/ES提出 |
| 大学4年4~5月 | 説明会/ES提出 |
| 大学4年6月 | 経団連加盟企業の選考開始 |
| 大学4年7~9月 | 面接の本格化/内定者決定 |
さらに詳しい就活スケジュールを知りたい学生は、ぜひこちらの記事をチェックしてください!
まずは何から?就活のやり方を順序別に解説

就活が本格化すると、やることや考えることが山積みになります。そこで、ここからは就活が本格的に始まるまでにやっておきたい作業のやり方をまとめました。
1. 自己分析
就活の第一歩は、自分自身を理解することです。企業選び、エントリーシート、面接、これらすべては自分がどんな人間か、どんな価値観を持っているか、この答えが土台になります。
自分の人生の「目的」と「手段」を知るために必要な作業が自己分析です。文字通り自己を分析することで、自分の長所や短所、適性などを見つけ出します。すると、面接で自分を説明しやするなるだけでなく、企業とのミスマッチを防ぐことができます。
自己分析のざっくりとした流れは、
- 過去の出来事を振り返り、書き出す
- この時に何を感じていた/考えていたかを書き出す
- いくつかの経験から、そこに一貫性がないか探る
- 自分の価値観を分析する
- 将来的にやりたいこと・興味関心の方向性を推測する
自己分析のやり方は複数ありますが、幼少期から現在までを振り返ってグラフに記入する「モチベーショングラフ」や、これまでの経験を年表のようにまとめる「自分史」などが有名です。
自己分析のやり方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
2. 業界研究
業界研究とは、業界ごとの業務内容や将来性などを把握する作業です。まずはどんな業界があるのかを調べて、業界ごとの関係性を把握していきましょう。
-
業界ごとのビジネスモデルや社会的役割を知る
例えば「メーカーはモノづくり」「商社は流通のハブ」「金融はお金を支える」など、大まかな特徴を理解しましょう。 -
成長性や将来性をチェック
業界研究は東洋経済新報社の『業界地図』や、マイナビ出版編集部の『業界&職種研究ガイド』など、書籍を活用するやり方が一般的です。
業界研究のやり方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
3. 企業研究
業界研究を済ませた後は、企業研究を始めましょう。企業研究とは、企業の基本情報や競合他社との違いを調べる作業です。
-
企業理念・ビジョン
自分の価値観と合っているか確認。理念が自分に刺さる企業は、長く働きやすいです。 -
働き方・福利厚生
-
社風やその企業らしさ
- 事業の強み・弱み
企業研究は企業の公式サイトや就職情報サイトをチェックしたり、東洋経済新報社の『就職四季報』を活用したりして行います。また、会社説明会やインターンシップに参加することで企業理解を深める方法もおすすめです。オンラインで開催される説明会も多いので、まずは参加してみましょう。
企業研究のやり方を調べている学生は、こちらの記事もご覧ください。
4. OB・OG訪問
企業のHPや口コミでは分からない「リアルな働き方」や「社風の空気感」を知るには、実際にその会社で働く人の話を聞くのが一番です。
OB・OG訪問とは、志望企業で実際に働いている社員を訪問し、企業について質問する機会を指します。OB・OG訪問は大学等の先輩に依頼、大学のキャリアセンターを通じて紹介してもらうことが可能です。また、最近は企業と学生を結びつけるサービスがいくつかあるため、利用してみてはいかがでしょうか。
OB・OG訪問は会社説明会や合同説明会では聞きにくいことまで質問できる貴重な機会なので、積極的に依頼しましょう。なお、OB・OG訪問の際はあらかじめ質問リストを作成しておき、終わった後はお礼の言葉や学んだことを記載したお礼メールを送信するのがおすすめです。
5. エントリーシートの作成
企業の選考でまず最初に見られるのが、エントリーシート(ES)です。ESでは、学生時代に力を入れていた活動(ガクチカ)、あなたの強み弱み、志望動機、キャリアプランなどが聞かれます。これらの設問には、それぞれ見られているポイントが異なるため、きちんと準備するべきです。
-
結論から書く(PREP法)
Point(結論)→ Reason(理由)→ Episode(具体例)→ Point(まとめ) の順番で書くと、話の流れが理解されやすい -
数字や成果を入れる
例:「売上を30%伸ばした」「○人のチームをまとめた」など、定量的に伝えると説得力が増します。
こうしたコツや、各設問ごとの回答のポイントは、案外学生目線では分からないものです。ぜひ、他の記事も参考にしてみましょう。
6. 適性検査(webテスト)の準備
企業によっては、選考の一環としてWEBテストを導入しているところもあります。WEBテストとは学生の能力や人柄を知るためのテストのことで、足切りとして活用する企業も少なくありません。
WEBテストは「能力検査」と「性格検査」に分かれており、問題の傾向や回答のスピード感に慣れるためにも、初見での受検は避けるべきです。
WEBテストの種類や受検方法について、詳しくはこちらをご確認ください。
7. 面接対策
面接は入室から退室にいたるまで、守るべきマナーがあります。また、頻出質問や面接直前の準備など、覚えることが山積みです。まずは入退室のマナーを覚えて、頻出質問の回答を用意するなど、できることから始めましょう。
面接当日までに模擬面接を繰り返し行うことも大切です。家族や友人、キャリアセンターの職員に面接官役を依頼し、人前で話すことに慣れておくことで本番の過度な緊張を防げます。
面接マナーや頻出質問に関しては、こちらの記事もチェックしてみてください。
就活に向けて、準備すべき「物」とは何か
就活を円滑に進めていくためには、今後選考などで必要な「物」をあらかじめ購入しておくことが大切です。
ビジネスアイテム
-
リクルートスーツ(黒・紺・グレー系)
-
白シャツ(替え用含めて数枚)
-
黒の革靴(男性)/黒のパンプス(女性)
-
ビジネスバッグ(A4サイズ対応・自立型)
これらはすぐに購入するのではなく、採寸等を含め、きちんと選ぶ必要があります。なぜなら、身だしなみに気を付けることで、信頼感を醸成することができるからです。
それぞれのアイテムには、気を付けるべき点やあると良い機能があります。事前にネットで調べてから店に訪ねてみてはいかがでしょう。
面接に必須な書類・小物
面接を成功させるために、実際の面接時に用いるもの、あるいは事前の準備で必要な小物は数多くあります。
- 提出書類
- スマートフォン
- ESや履歴書のコピー
- 筆記用具
- 身分証
- 財布
- ハンカチ・ティッシュ
これらは、新たに購入する必要がないものも多いですね。だからといって、忘れ物だけは絶対に避けましょう。
あると役立つ衛生グッズ
面接にはベストな状態で臨みたいものです。しかし、雨風といった天候、長時間の移動によって身だしなみが崩れてしまうことは多々あります。こうしたピンチに、以下のアイテムは役立つことでしょう。
-
鏡(コンパクトミラー)
-
櫛・ヘアブラシ
-
制汗シート/汗ふきシート
-
リップクリーム
-
ハンドクリーム
-
マスク(予備もあると◎)
-
絆創膏(靴ずれ対策)
-
ヘアゴム/ヘアピン(女性)
-
予備のストッキング(女性)
-
歯ブラシセット(長時間外出時)
オンライン面接を成功させるためのアイテム
オンライン面接では、通信環境やカメラの状態によって、相手に与える印象が大きく変わってしまいます。例えば、相手の声が途切れてしまう場合、もう一度聞き直す必要があります。こうした一つ一つのロスが、相手に不快感を与えてしまう恐れがあります。
-
Web面接用のPC(カメラ・マイク確認)
-
Zoom/Teamsなどのアプリをインストール
-
ネット環境
知っておくべきマナー

学生生活とは大きく異なり、社会人の方と直接やりとりをする機会が沢山あります。学生気分で社会人の方々とコミュニケーションをとってしまうと、気づかぬうちに信頼関係にヒビが入ることも。
正しい敬語
敬語は、就活中のあらゆる場面で求められる基本的なスキルです。丁寧語・尊敬語・謙譲語の違いを意識しながら、正しく使えるようにしましょう。
例えば、常体では「言う」。これを自分が言う時には「申し上げる」(謙譲語)、目上の方が言う時には「おっしゃる」(尊敬語)と表現します。
就活序盤では不自然な敬語になってしまうことも。前もって敬語を勉強しておくことで、ライバルに差をつけましょう。
メールのマナー
企業とのやり取りで最も多いのがメールです。面接の日程調整を含め、書き方ひとつで印象が変わるので、基本ルールは必ず押さえておきましょう。
● 件名
「面接日程のご連絡(○○大学・氏名)」
→ 件名だけで要件が伝わるように。
● 実際の構成(基本フォーマット)
-
宛名(〇〇株式会社 人事部 ○○様)
-
挨拶と自己紹介(○○大学の○○と申します)
-
本文(ご連絡いただきありがとうございます、等)
-
結び(何卒よろしくお願い申し上げます)
-
署名(氏名・大学名・連絡先など)
電話のマナー
面接日の調整や当日の連絡などで、電話対応が必要になる場面もあります。短く、要点をまとめて話すことが大切です。
- まず自分の名前と所属を名乗る(例:○○大学の○○と申します)
- 終業時間に電話を掛けない
- 挨拶とお礼は欠かさない。
具体的なやり取りやフォーマットは以下の記事を参考にしてみてください。
インターンシップって何?
インターンシップとは、学生が企業で実際の業務を体験できる制度のことです。就職活動が本格化する前に、働く現場を知ることができる貴重なチャンスです。もともとは職業体験に近いものでしたが、今では就活の一部と考えられるほど、重要な位置づけになっています。
大学3年の5〜6月には夏季インターンの申し込み、10~1月には冬季インターンの申し込みが始まります。
インターンシップには誰でも参加できる?
インターンシップにはエントリーすれば誰でも参加できるパターンと、選考を通過しなければ参加できないパターンがあります。インターンシップの選考は書類選考から筆記試験、面接まで一通り行われる場合も多く、選考対策が必要です。
インターンの種類と期間
インターンにはいくつかの種類があります。
| 種類 | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1dayインターン | 会社説明や簡単な仕事体験 | 半日〜1日 |
| 短期インターン | グループワーク・実務体験など | 2日〜1週間程度 |
| 長期インターン | 実際の業務に継続的に関わる(有給ありも) | 1ヶ月〜半年以上 |
インターンに参加するメリット
インターンに参加する最大のメリットは、業界や職種への理解が深まることです。実際に企業の業務を体験することで、「自分に合っているか」「やりがいを感じられそうか」を具体的にイメージできます。
また、現場の雰囲気や社員の人柄に直接触れることで、企業選びの判断材料にもなります。さらに、インターンでの経験はエントリーシートや面接でのエピソードとして活用でき、説得力のある自己PRにつながります。
企業によっては、インターン参加者に早期選考の案内が来たり、評価が本選考に反映されるケースもあるため、内定に一歩近づくチャンスにもなります。就活に向けた経験値を高めたい人にとって、インターンは大きな意味を持つステップです。
インターンシップの参加方法について、詳しくはこちらの記事をご確認ください。
就活のやり方に関するよくある失敗
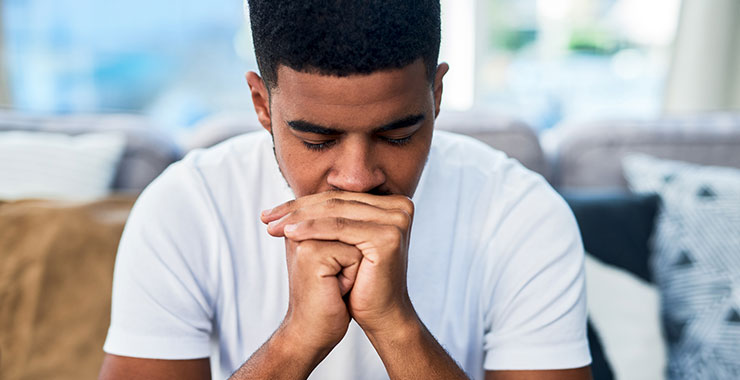
最後に、面接のやり方に関する失敗談を見ていきましょう。就活を経験した先輩たちは、どのような失敗をしてきたのでしょうか。
自己分析が不十分
自己分析は就活の第一歩ともいわれており、自己分析が不十分だと就活の軸がブレたり、自己PRや志望動機に説得力が出なかったりと、就活に良い効果をもたらしません。業界研究や企業研究、選考対策などに取り組む前に、まずは自己分析を行うことが重要です。
就活解禁日までに間に合わない
まだ大丈夫だと油断していると、すぐに大学3年の3月がきてしまいます。そこから就活準備を始めることも可能ですが、余裕をもって準備や対策を講じるためにも早めの準備を心がけましょう。
就職活動成功へのカギ ~心がけ~
これまで就活のやり方について解説してきました。実は長期戦になる就職活動において、マインドセットやメンタル面が非常に重要です。ここでは、就活を前向きに進めるために大切な「心がけ」を紹介します。
少しでも前に進み続ける
就活中は思うようにいかないこともたくさんあります。エントリーしても返信がこなかったり、面接で落ちたり…。そんなときでも、立ち止まらず、小さな一歩を積み重ねることが大切です。
「今日は自己PRを書いてみる」「説明会に1社だけ参加してみる」──それだけでも前進です。
完璧を目指しすぎると、「うまくいかなかったらどうしよう」と手が止まってしまいます。結果よりも、“動いたこと自体”をまず自分で認めてあげましょう。自分を責めるのではなく、コツコツ積み重ねる姿勢が、最後には大きな成果につながっていきます。
他人と比べすぎない
SNSや友人の会話で、「もう内定出た」「◯◯社に決まった」という話を耳にすると、焦る気持ちは誰にでもあります。ですが、就職活動のタイミングやスピードは人それぞれ。焦って無理にペースを上げても、自分に合わない会社に飛び込んでしまう可能性もあります。
就活は早く決まる人が偉いわけではありません。自分にとってのベストタイミングは今じゃないだけと、気持ちを切り替えることが大切です。
就活のやり方を把握して理想の就活を実現しよう!
就活のやり方は、作業や対策の種類によって異なります。就活スケジュールとあわせて一通り把握したら、手順に沿って就活準備を始めましょう。
就活のやり方を調べている学生におすすめしたいのは、逆求人型のスカウトサービス『キミスカ』への登録です。キミスカに登録すれば企業からスカウトが来るだけでなく、自己分析ツールをはじめとする便利な機能を無料で利用できます。就活の手助けになることは間違いないので、この機会に登録しておきましょう。

