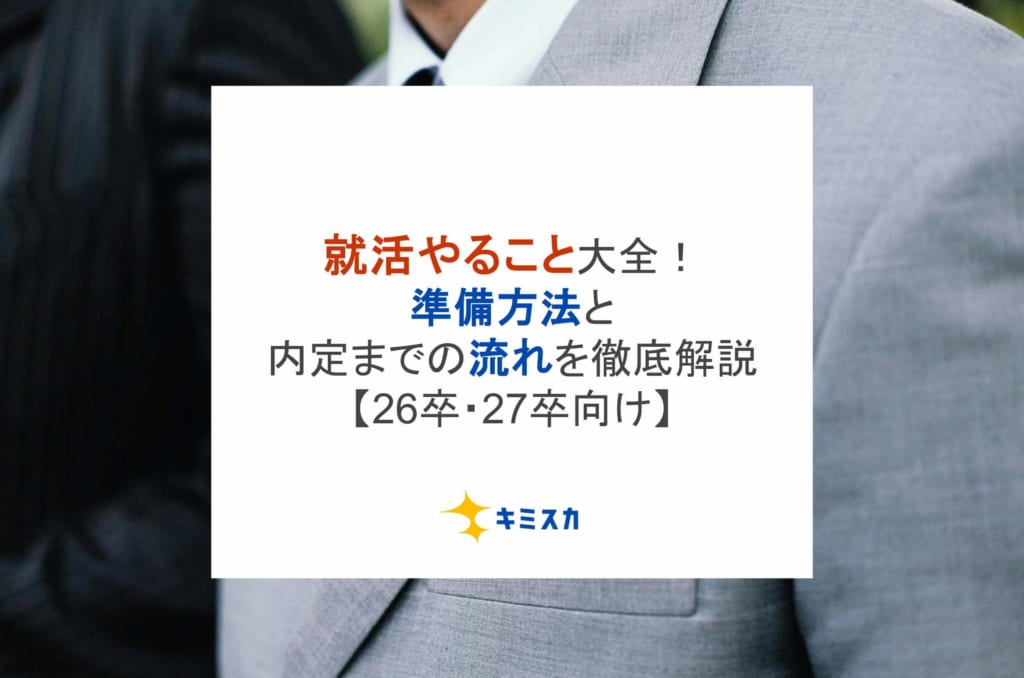
「就職活動って、何から手をつければいいんだろう?」「やるべきことが多すぎて、どうしよう…」そんな不安を抱えていませんか?就職活動は、多くの学生にとって初めての経験であり、戸惑うのは当然のことです。
この記事では、そんな就活生の皆さんのために、内定獲得までに「いつ・何をすべきか」を完全網羅したロードマップを提示します。大学1・2年生向けの準備から、3・4年生の本格的な進め方、さらには文系・理系の違いまで徹底解説しています。
大学1・2年生が就活に向けてやるべきこと
就活はまだ先の話と思っている1・2年生も多いかもしれません。しかし、この時期の過ごし方が、後の就職活動に大きな差を生みます。
本格的な選考が始まる前に、将来の自分を助ける土台作りを始めましょう。ここでは、低学年のうちから意識しておきたい4つのポイントを解説します。少しずつでも行動することで、余裕を持って就活のスタートラインに立つことができます。
1. 自己分析の基礎を固める
本格的な自己分析は3年生からで十分ですが、1・2年生のうちか基礎固めをしておくことをおすすめします。難しく考える必要はありません。「自分は何が好きか」「何をしている時に楽しいと感じるか」「どんなことにやりがいを感じるか」など、日常生活の中で自分の感情が動く瞬間をメモしておきましょう。
こうした日々の記録が、3年生になってから「自分の強み」や「価値観」を発見し、説得力のある自己PRを作るための重要なヒントになります。
2. 様々な経験を積んでガクチカを作る
就活で必ず問われる学生時代に力を入れたこと、いわゆるガクチカ。これは、学業やサークル・アルバイト・ボランティアなど、どんな経験でも構いません。
大切なのは、目標を立てて主体的に行動し、その経験から何を学んだかです。企業は華やかな結果よりも、あなたの考え方や行動のプロセスを知りたがっています。少しでも興味があることには積極的に挑戦し、自分だけのストーリーを作っておきましょう。
3. 早期インターンシップやイベントに参加する
最近では、大学1・2年生を対象とした短期のインターンシップやキャリアイベントが増えています。これらに参加する一番のメリットは、働くことの具体的なイメージを掴めることです。社会人と話す機会を持つだけでも、視野が大きく広がるでしょう。
選考に直接関係することは少ないですが、業界や企業への理解を深める絶好の機会なので、ぜひ参加してみてください。
4. 社会や企業への興味を広げる
いきなり「業界研究するぞ」と意気込む必要はありませんが、普段から社会の動きにアンテナを張る習慣をつけておくと後々役立ちます。
例えば、自分がよく使うアプリやサービスが、どの企業によって提供されているのか調べてみるのも良いでしょう。ニュースを見て世の中で何が流行っているのか、どんな新しい技術が生まれているのかを知ることも大切です。こうした小さな興味の積み重ねが、将来入りたい業界や企業を見つけるきっかけになります。
大学3・4年生が就活でやること【全体像】

いよいよ就活が本格化する大学3・4年生。ここからは、内定獲得までの大まかな流れを4つのステップで解説します。就職活動は長期戦であり、全体像を把握しておくことで、今自分がどの段階にいるのかを客観的に理解できます。
まずは就職活動の流れを頭に入れて、計画的に進める準備をしてみましょう。
| 時期 | やること |
| 大学3年4月~ 就活準備期間 | 自己分析 |
| 大学3年6月~ インターンシップ期間 | サマーインターンシップ参加 |
| 大学3年9月~ インターンシップ期間 | ウィンターインターンシップ参加 |
| 大学3年1月~ | ESの作成 |
| 大学3年3月~ 本選考期間 | 就活解禁、説明会参加 |
| 大学4年6月~ 内定・入社準備期間 | 選考開始・内定 |
【ステップ1】就活準備期間(大学3年4月〜)
本格的な就活のスタートダッシュを決めるための重要な準備期間です。この時期の行動が、後のインターンシップや本選考の結果に直結します。
まずは「自己分析」で自分の強みや価値観を言語化し、「業界・企業研究」で世の中にどんな仕事があるのかを知ることから始めましょう。ここで「就活の軸」を仮でも良いので設定できると、その後の行動に一貫性が生まれます。
【ステップ2】 インターンシップ期間(大学3年6月〜)
夏から冬にかけては、インターンシップの選考と参加がメインになります。特にサマーインターンシップは多くの企業が開催するため、参加することで企業理解を深めたり早期選考につながったりする可能性があります。
エントリーシート(ES)の作成やWebテスト、面接といった本選考さながらのプロセスを経験できる貴重な機会です。インターンシップの選考に落ちても落ち込む必要は全くありません。本選考に向けた絶好の練習と捉えましょう。
【ステップ3】 本選考期間(大学3年3月〜)
大学3年の3月からは企業が選考情報を解禁し、本選考が一斉にスタートします。多くの企業説明会への参加やESの提出、Webテストの受験、複数回の面接など、非常に多忙な時期となるでしょう。
ここまでに培ってきた自己分析や企業研究の成果を発揮する場です。スケジュール管理を徹底し、万全の体調で臨めるように準備しておくことが大切になります。多くの企業を同時に受けることになるため、どの企業の選考がどこまで進んでいるかやスケジュール管理を徹底しておきましょう。
【ステップ4】 内定・入社準備期間(大学4年6月〜)
大学4年の6月以降、多くの学生が内々定を獲得し始めます。複数の内々定を獲得した場合は、これまで定めてきた就活の軸に立ち返り自分にとって最適な一社を慎重に選びましょう。
この時期は内定式に参加したり残りの大学生活を謳歌したりと、入社までの準備期間となります。卒業に必要な単位を取得することも忘れてはいけません。
また、内定が出た後も企業によっては課題が出されたり懇親会が開かれたりすることがあるので、油断せずに対応しましょう。
【時期別】大学3・4年生の就活やることロードマップ
就活の全体像を掴んだら、次は具体的な時期ごとに何をすべきかを見ていきましょう。カレンダーに落とし込んで考えることで、より計画的に行動できるようになります。
周りの学生の動きも活発になるため、焦りを感じるかもしれませんが、自分のペースで着実にタスクをこなしていくことが重要です。ここでは、一般的な就活スケジュールに沿った「やること」を解説します。
大学3年生:春(4月〜6月)
この時期は、本格的な就活に向けた準備運動の期間です。まずは、就活情報サイトに登録し、様々な企業の情報を集められる状態にしておきましょう。そして、自己分析と業界・企業研究をスタートさせます。
サマーインターンシップの情報も公開され始めるので、興味のある企業の選考スケジュールをチェックしES作成の準備を始めることが大切です。この段階で、自己PRやガクチカの骨子を作っておくと、後のES作成が格段に楽になります。
大学3年生:夏(7月〜9月)
夏休みは、サマーインターンシップに参加する絶好の機会です。実際に仕事を体験することで、その企業や業界への理解が深まります。インターンシップに参加するためには、ESや面接などの選考を突破する必要があるため、本選考に向けた実践的な練習にもなるでしょう。
並行して、筆記試験やWebテストの対策も少しずつ進めておくことをおすすめします。学業との両立がしやすい夏休みを有効活用できるかどうかが、就活の成否を分けるポイントの一つです。
大学3年生:秋(10月〜12月)
秋から冬にかけては、オータム・ウィンターインターンシップが開催されます。夏に参加できなかった人も、ここがチャンスです。また、この時期のインターンシップは、より実践的で、早期選考に直結するケースも増えてきます。
夏に得た経験を元に、自己分析や企業研究をさらに深め、OB・OG訪問を始めるのも良いでしょう。現場で働く社員の生の声を聞くことは、企業HPだけでは得られない貴重な情報となります。
大学3年生:冬(1月〜3月)
本選考を目前に控え、就活が最も忙しくなる時期です。多くの企業が企業説明会を開始し、エントリー受付も本格化します。これまでに準備してきたESをブラッシュアップし、様々な企業に提出しましょう。
面接練習も本格的に始める必要があります。大学のキャリアセンターや就活エージェントなどを活用し、模擬面接を重ねておくと安心です。3月の情報解禁と同時にスムーズにスタートダッシュが切れるよう、万全の準備を整えておきましょう。
大学4年生:春以降(4月〜)
いよいよ本選考の真っ只中。ES提出やWebテスト受験に追われながら、各地で面接やグループディスカッションに臨むことになります。
スケジュール管理はもちろん、体調管理も非常に重要です。面接で不合格が続くと精神的に辛くなるかもしれませんが、それはあなた自身が否定されたわけではありません。「単にその企業と縁がなかっただけ」と気持ちを切り替え、次の選考に集中することが大切です。そして、内々定を獲得したら、慎重に承諾先を決めましょう。
就活で必ずやることリスト10選【タスク別】

就職活動には様々なタスクがありますが、ここでは具体的な就活対策として「必ずやるべきこと」を10個に絞って解説します。これらは、内定を獲得するために避けては通れない重要な項目です。
一つひとつのタスクの意味を理解し、丁寧に取り組むことが、納得のいく就活につながります。何から手をつければ良いか分からない人は、まずはこのリストの上から順番に取り組んでみることをおすすめします。
1. 自己分析で自分を知る
自己分析は、全ての就活の土台となる最も重要な作業です。自分の長所短所・価値観・やりたいことなどを深く掘り下げることで、自分に合った企業を見つける「就活の軸」が定まります。
また、面接で「自己PR」や「長所」を語る際の説得力にも直結します。自分史やモチベーショングラフを作成したり、信頼できる友人に他己分析を頼んだりする方法が有効です。企業は「自社で長く活躍してくれる人材か」を見ているため、自分を偽らず、ありのままの自分を理解することが大切です。
自己分析のやり方や自分のタイプを知りたいと思った方は、こちらの記事をチェックしてみましょう。適性検査の受け方や結果の分析方法まで詳しく解説しています。
2. 業界・企業・職種研究で社会を知る
自己分析で自分を知ったら、次は「社会」を知る番です。世の中にはどんな業界や企業、職種があるのかを幅広く研究しましょう。業界地図や四季報を読んだり、企業のウェブサイトや採用ページを読み込んだりするのが基本です。
この研究を通して、自分の興味や強みが活かせる場所を探していきます。視野が狭いままだと、自分に合う企業を見逃してしまう可能性があります。最初は興味がない業界でも、調べてみると思わぬ発見があるかもしれません。
業界研究のやり方については、こちらの記事でさらに詳しく解説していますので合わせて確認してみてください。
3. 就活の軸を明確にする
自己分析と企業研究を進めると「自分はどんな環境で、何を大切にして働きたいか」という就活の軸が見えてきます。例えば「人々の生活を豊かにしたい」「若いうちから裁量権を持って働きたい」「安定した環境で長く勤めたい」など、人によって様々です。
この軸が明確であればあるほど企業選びで迷うことがなくなり、面接での志望動機にも一貫性が生まれます。就活の軸は、企業を選ぶ際の自分だけの譲れない条件であり、就活の道標となるものです。
4. 就活サイトに登録する
就活を始めるにあたり、就活情報サイトへの登録は必須です。リクナビやマイナビといった大手サイトには、多くの企業情報やインターンシップ、企業説明会の情報が集約されています。まずは2〜3つのサイトに登録し、様々な情報を得られるようにしておきましょう。
他にも、特定の業界に特化したサイトや企業からスカウトが届く逆求人型のサイトなどもあります。複数のサイトを併用し、自分に合ったものを見つけて効率的に情報収集を進めるのがおすすめです。
キミスカでは、ES免除や役員面談付きの特別なスカウトが届くゴールドスカウトがあります。スカウトが3種類分かれているため特別なスカウトに気づきやすく、企業との相性も一目で分かります。
あなたの適性検査の結果からもスカウトが届くのでマッチ度の高い企業と出会えるのもメリットです。下のリンクから簡単に登録できますので、大学3年生・4年生はぜひ登録してみてください。
5. インターンシップに参加する
インターンシップは、企業の仕事を実際に体験できる貴重な機会です。仕事内容や社風を実際に見て感じることで、その企業が自分に合っているかどうかを判断する材料になります。
また、企業側にとっても学生の能力や人柄を知る良い機会と捉えられており、参加が早期選考につながるケースも少なくありません。選考に有利になるという側面だけでなく自分のキャリアを考える上で非常に有益な経験となるため、積極的に挑戦しましょう。
インターンシップに参加したいと考えている方は、こちらの記事も見てみてください。
6. OB・OG訪問をする
OB・OG訪問とは、自分の大学の卒業生で興味のある企業で働いている先輩を訪ね、話を聞くことです。ウェブサイトや説明会では得られない、現場のリアルな情報を知ることができます。
仕事のやりがいや大変なこと、職場の雰囲気など、気になることを直接質問してみましょう。人脈の作り方としては、大学のキャリアセンターに相談したり、OB・OG訪問専用のアプリを使ったりする方法があります。実際に働く社員から得られる生の情報は、企業選びや志望動機作成において非常に強力な武器となります。
OBOG訪問について詳しく知りたい方はこちらの記事も合わせて確認してみましょう。
7. エントリーシート(ES)対策
ESは、企業への応募における最初の関門です。ここで問われるのは主に「自己PR」「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」「志望動機」の3つです。
自己分析や企業研究で深めた内容を元に、あなたという人間がどんな人物で、なぜこの会社で働きたいのかを分かりやすく伝える必要があります。誤字脱字はもちろん、質問の意図を正確に汲み取り、結論から簡潔に書く「PREP法」を意識することが重要です。
「エントリーシートって何?」「ESの書き方が知りたい」という方は、こちらの記事でさらに詳しく解説していますので合わせてチェックしてみてください。
8. 筆記試験・Webテスト対策
多くの企業が、ESと同時あるいはES通過後に筆記試験やWebテストを実施します。代表的なものに「SPI」や「玉手箱」があり、言語能力や計算能力、論理的思考力などが問われます。
これらは対策をすれば必ずスコアが上がるものなので、早めに準備を始めることが大切です。市販の問題集を1冊買い、繰り返し解いて問題形式に慣れておきましょう。せっかく魅力的なESを書いても、テストで基準点に満たなければ面接に進めないため、決して侮ってはいけません。
WEBテストについてはこちらの記事で詳しく解説しています。「WEBテストって何だろう?」「どんなテストなの?」と思った方はぜひ確認してみてください。
9. 面接・グループディスカッション対策
面接は、あなたの人柄や熱意を企業に直接伝える最終関門です。ESに書いた内容、特に自己PRやガクチカについて深い質問をされることが多いため、自分の言葉でしっかりと語れるように準備しておく必要があります。
グループディスカッション(GD)では、論理性や協調性が見られています。どちらも慣れが重要なので、大学のキャリアセンターや友人同士で模擬練習を重ねましょう。自信を持ってハキハキと話すこと、そして何より正直に自分を伝える姿勢が、面接官に好印象を与えます。
グループディスカッションについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
10. 就活に必要なモノを準備する
就活にはスーツやカバン証明写真など、事前に準備しておくべきモノがいくつかあります。特にスーツや写真は、説明会や面接が本格化する前に揃えておくと安心です。直前になって慌てないよう、リストアップして計画的に準備を進めましょう。
特に重要な2つのアイテムについて解説します。
リクルートスーツやカバン
リクルートスーツは、就活の戦闘服とも言えるアイテムです。色は黒や濃紺の無地が基本で、清潔感が最も重要になります。自分の体に合ったサイズのものを、2着ほど持っておくと着回しに便利でしょう。
カバンはA4サイズの書類が折らずに入る、黒色の自立するタイプがおすすめです。靴も黒の革靴を用意し、常に綺麗に磨いておきましょう。身だしなみは、あなたの第一印象を決定づける重要な要素。細かい部分まで気を配ることが社会人としてのマナーです。
証明写真
ESや履歴書に貼る証明写真は、あなたの第一印象を左右する大切な要素です。
スピード写真ではなく、写真館でプロに撮影してもらうことを強くおすすめします。プロは表情や姿勢を的確にアドバイスしてくれますし、仕上がりの綺麗さが全く違います。髪型や服装を整え、清潔感のある明るい表情で撮影に臨みましょう。
一度撮影すれば焼き増しができるので、3年生の秋頃までには撮影を済ませておくと、後のES提出がスムーズに進みます。
理系学生と文系学生の就職活動の違いとは
就活の基本的な流れは同じですが、理系と文系ではいくつかの違いがあります。自分がどちらのタイプに当てはまるのかを理解し、それぞれの特徴に合わせた対策をすることが重要です。
ここでは、理系学生と文系学生の就職活動における主な特徴を解説します。自分の専門性や強みをどう活かすか、戦略を立てる上での参考にしてください。
理系学生の就活の特徴
理系学生の就活は、専門知識や研究内容が直接評価につながる「専門職採用」が多いのが特徴です。そのため、自身の研究内容を分かりやすく説明できる能力が求められます。
また、指導教官や研究室と企業のつながりによる「推薦応募」という制度があり、これを利用すると一般応募より有利に選考が進むことがあります。
一方で、研究活動が忙しく、就活に割ける時間が限られることが多いので、効率的なスケジュール管理がより一層重要になります。
文系学生の就活の特徴
文系学生の就活は、特定の専門性よりもコミュニケーション能力や課題解決能力といったポテンシャルが重視される「総合職採用」が中心です。そのため、業界や職種の選択肢が非常に幅広いのが特徴と言えるでしょう。
ガクチカや自己PRを通じて、自分の人間性や強みをいかに魅力的に伝えるかが鍵となります。選択肢が多い分、なぜその業界・企業なのかという点を、自己分析と結びつけて明確に語れるように準備しておく必要があります。
ライバルと差がつく!就活を効率的に進める4つのコツ

やることが多く、長期戦になりがちな就職活動。ここでは、就職活動を効率的に進めるための、ワンランク上の就活対策を4つご紹介します。
これらのコツを意識するだけで、他の就活生よりも一歩リードできるはずです。精神的な余裕を保ちながら、納得のいく結果を目指しましょう。
1. スケジュールを可視化して管理する
就活中は、複数の企業のES締切や面接日程が同時進行で進みます。これらのスケジュールを頭の中だけで管理するのは非常に危険です。Googleカレンダーや手帳アプリなどを活用し、全ての予定を一元管理しましょう。
締切日だけでなく、「〇日までにESの推敲を終える」といった自分だけのタスクも書き込むのがおすすめです。スケジュールを可視化することでダブルブッキングや締切忘れを防ぎ、計画的に行動できるようになります。
2. 大学のキャリアセンターなどを積極的に活用する
一人で就活を進めるのには限界があります。大学のキャリアセンターや新卒応援ハローワーク、就活エージェントなど、就活生をサポートしてくれる場所はたくさんあります。
これらのサービスは、ESの添削や模擬面接、個別相談など、無料で利用できるものがほとんどです。客観的なアドバイスをもらうことで、自分では気づけなかった改善点が見つかるでしょう。
3. 完璧主義にならず、まずは行動してみる
「もっと完璧な自己分析ができてから…」「完璧なESが書けるまで…」と考えていると、いつまで経っても行動に移せません。就活に100%の正解はありません。最初は60%の完成度でも良いので、まずはESを提出してみる、企業説明会に参加してみる、といった行動を起こすことが大切です。
行動する中で新たな発見や改善点が見つかり、徐々に質が高まっていきます。完璧を目指すあまり行動できないのが一番の機会損失。まずは「やってみる」精神を大切にしましょう。
4. 学業や私生活とのバランスを意識する
就活に集中するあまり、大学の授業をおろそかにして卒業できなくなっては本末転倒です。また、息抜きの時間も非常に重要。友人とおしゃべりしたり、趣味に没頭したりする時間を作ることで、心に余裕が生まれます。
就職活動は長期戦だからこそ、意識的にリフレッシュする時間を作り、心身ともに健康な状態で臨むことが、良い結果につながります。頑張りすぎるあまり、心や体を壊してしまっては元も子もないのでオンとオフの切り替えを大切にしてください。
就活の「やること」に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、就活生からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。多くの人が同じような疑問や不安を抱えています。記事の本文では触れきれなかった細かいポイントについて解説するので、あなたの悩みを解決するヒントがきっと見つかるはずです。
Q. 結局、就活は何から始めるのが正解ですか?
多くの就活生が悩むこの質問ですが、結論から言うと「自己分析」から始めるのが最もおすすめです。なぜなら、自分自身のことを理解していなければ、どんな企業が自分に合うのか判断できないからです。
自己理解を深めて初めて、意味のある業界・企業研究ができます。まずは自己分析をする時間を作るところからスタートしましょう。
Q. やることが多すぎて、終わりが見えません…
その気持ち、よく分かります。就職活動はやらなければいけないことが多く、圧倒されてしまいますよね。
そんな時は、やらなければいけないことを一度紙に書き出してみてください。そして、優先順位をつけて、今日やるべきこと・今週中にやるべきことと細かく分解してみましょう。一度に全てをやろうとせず、目の前の小さなタスクを一つずつクリアしていくことが、結果的にゴールへの一番の近道になります。
Q. 就活に有利な資格はありますか?
「この資格があればどんな職種にも絶対に有利」という万能な資格は、残念ながらありません。しかし、TOEICや簿記、ITパスポートなどは、業界を問わず評価されやすい傾向にあります。
しかし、企業は資格を持っているか否かだけでなく「なぜその資格を取ろうと思ったのか」という目的意識や学習意欲も知りたいと思っています。そのため、面接前には資格取得の目的を自分の言葉で語れるようにしておくことが大切です。
Q. IR情報は読んだほうがいいですか?
必須ではありませんが、特に志望度の高い企業であれば読むことを強くおすすめします。IR情報とは、企業の経営状況や将来の戦略をまとめた資料のことです。IRは上場している企業しか出していないので、注意してください。
IRに書かれている全てを理解する必要はなく、中期経営計画や事業の強みが書かれた部分に目を通すだけでも、企業の方向性を知ることができます。
面接でIR情報から得た視点を交えて話せば、他の就活生と差がつく深い企業理解と高い入社意欲をアピールできるでしょう。
Q. 企業のSNSは見てもいいですか?いいねやコメントはしてもいいですか?
企業のSNSは、社風や社員の雰囲気を知る上で非常に有益なので、ぜひ見ることをおすすめします。
また、いいね(高評価)やコメントは慎重に行うべきです。不用意な発言でマイナスの印象を与えてしまうリスクがあります。あなたのアカウントを企業に見られてしまう可能性もあるため、いいねやコメントなどのアクションは控えておくのがベストです。
もしもコメントをする場合は、就活用のアカウントを作成してから企業の迷惑にならない常識的な内容を書きましょう。
やるべきことを把握して自信をもって就活を進めよう!
今回は、就職活動でやるべきことを学年別・時期別・タスク別に網羅して解説しました。やることが多くて圧倒されそうになるかもしれませんが、この記事を読んだことで、内定までに何をすべきか、その道筋が明確になったのではないでしょうか。
就職活動は、不安や焦りを感じることも多いですが、正しい手順で計画的に進めれば、必ず乗り越えることができます。
何から始めるか迷ったら、まずは「自己分析」で自分自身と向き合うことから始めてみてください。そして、一人で抱え込まず、大学のキャリアセンターや周りの人を積極的に頼りましょう。
就職活動は、自分自身の未来を切り拓くための大切な第一歩です。完璧を目指さず、あなた自身のペースで、今日できることから着実に進めていきましょう。

