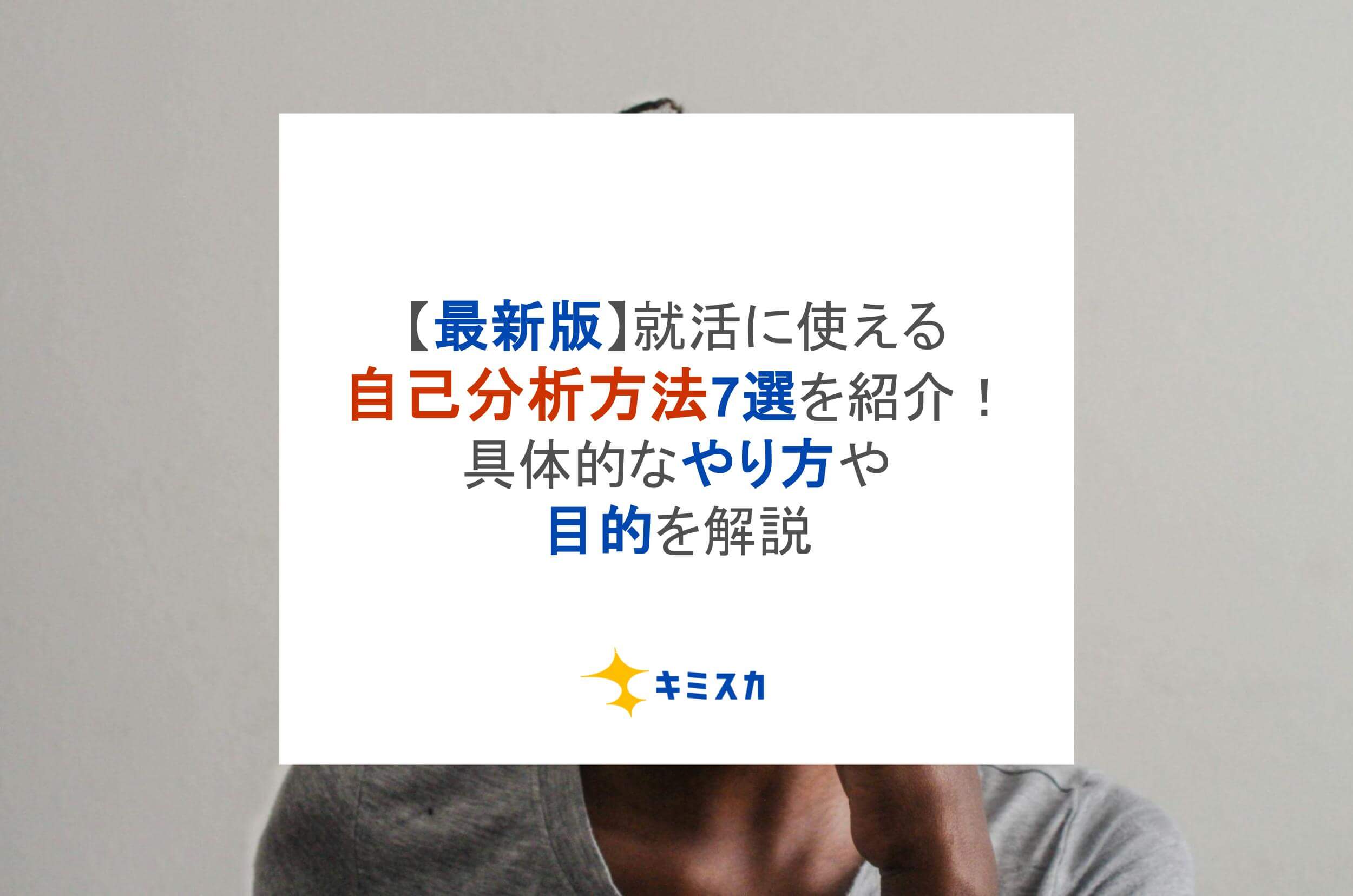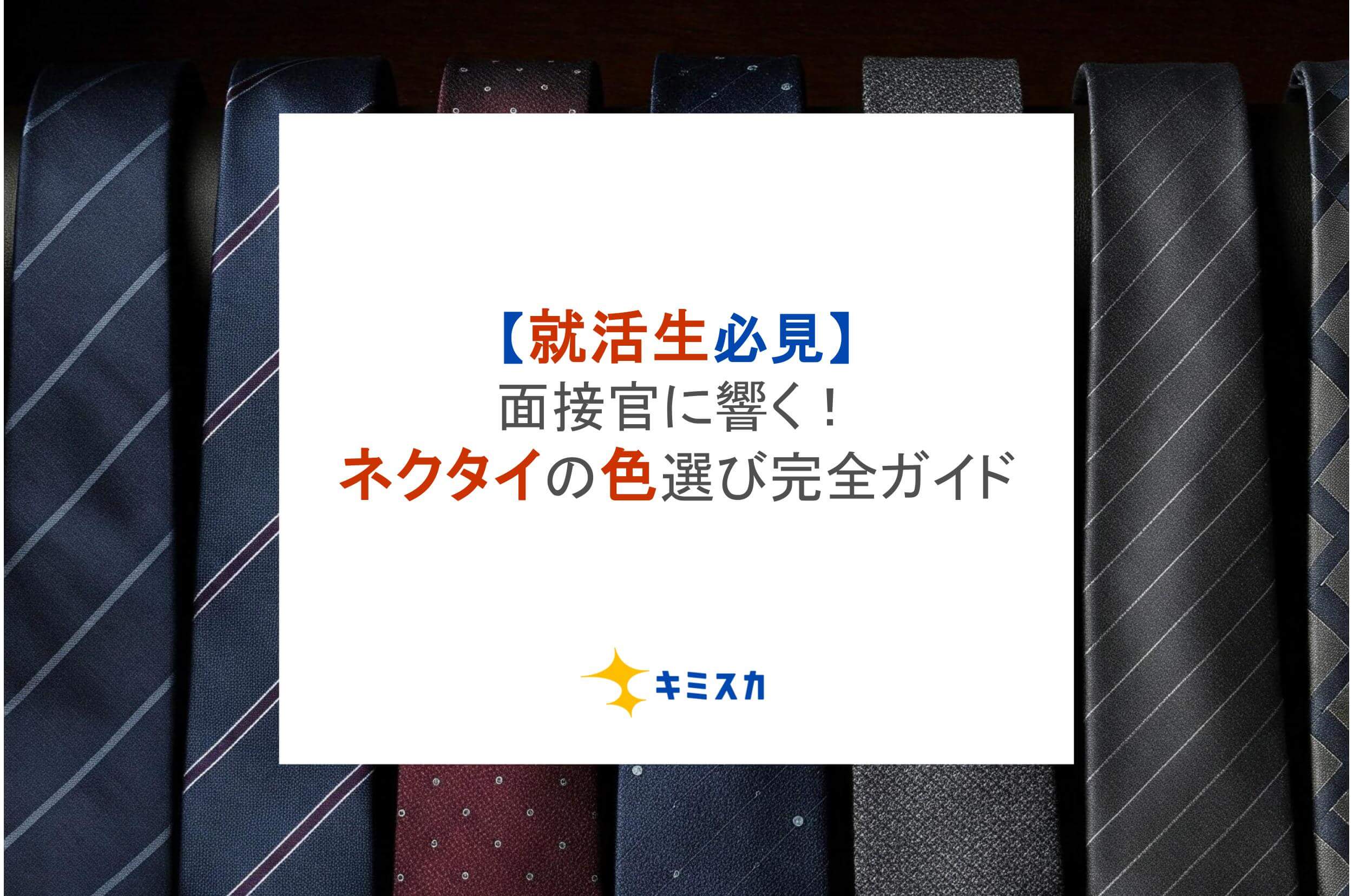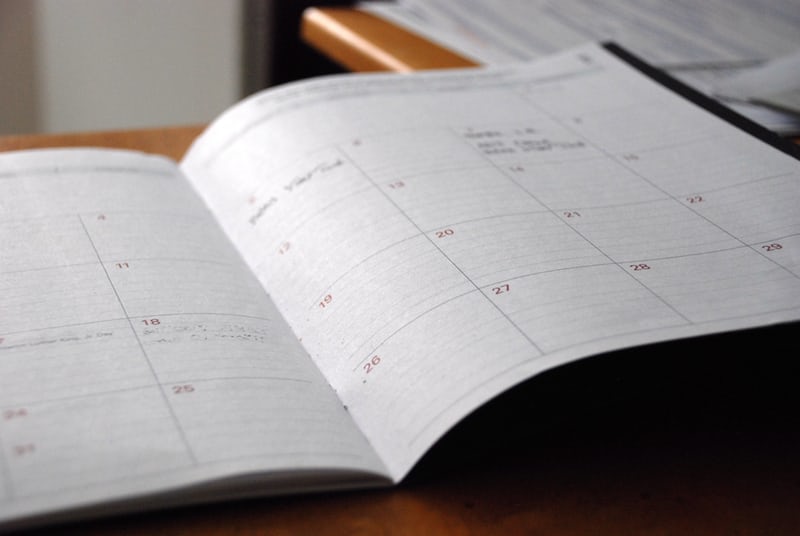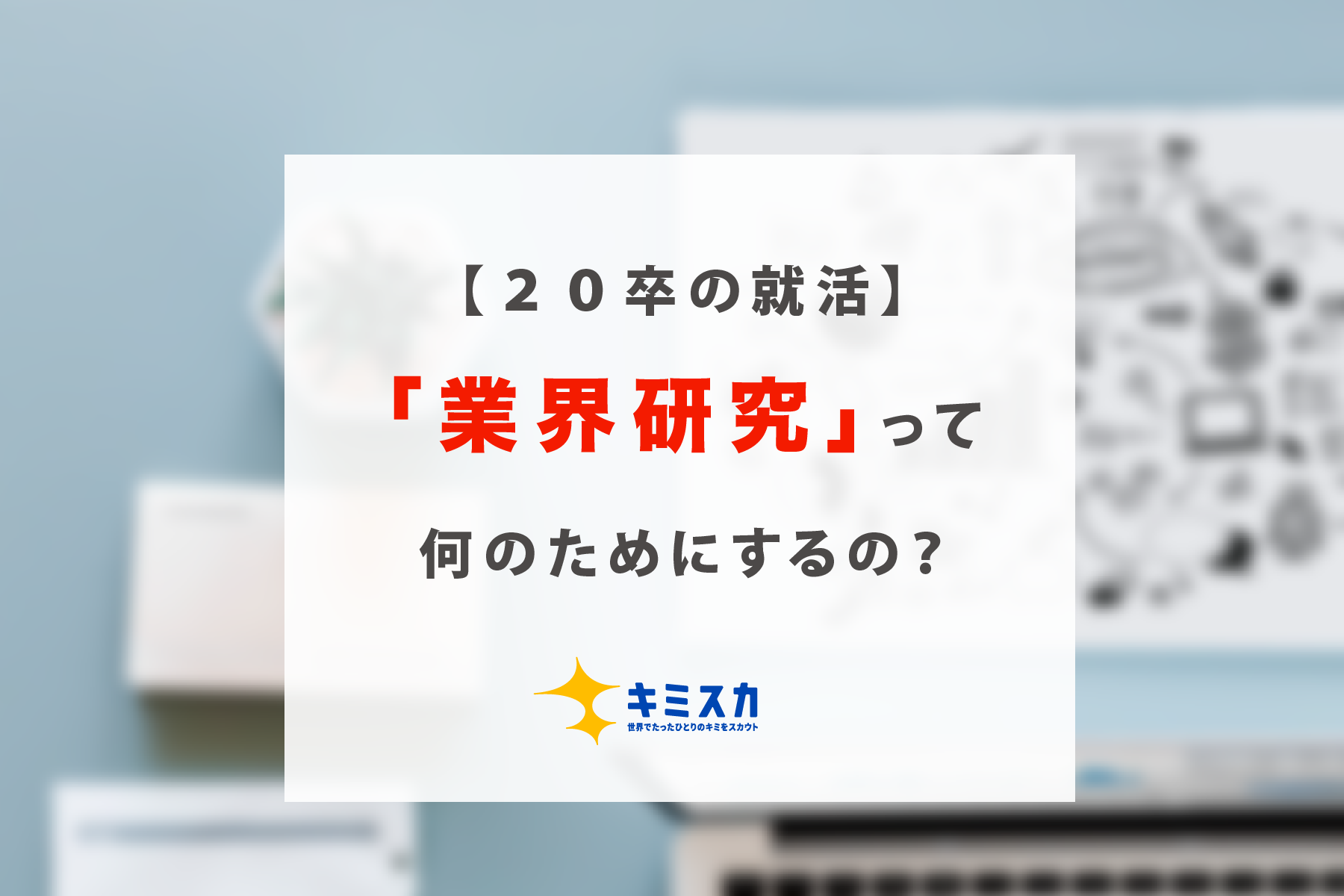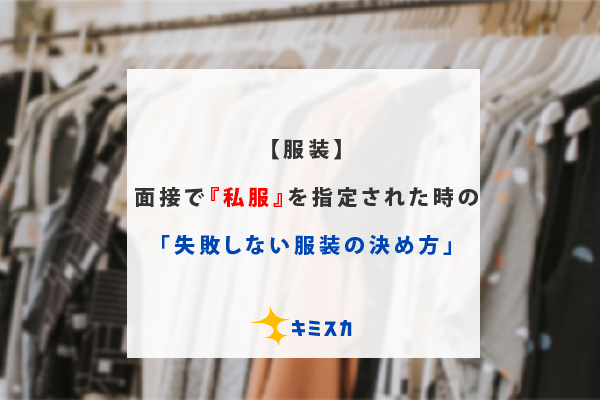就活のグループワーク、初めてだと不安ですよね。どんなことをするのか、どうすれば評価されるのか分からない方も多いでしょう。実際、グループワークの対策不足で本来の力を発揮できないケースも少なくありません。
この記事では、グループワークの基本から具体的な流れ、評価ポイント、役割別の攻略法、苦手対策まで網羅的に解説します。最後まで読んで一緒に選考突破を目指しましょう。
就活のグループワークとは?
就職活動を進める中で、「グループワーク」という選考形式に出会うことがあります。初めて聞く方にとっては、何をするのか、どう対策すれば良いのか、不安に感じるかもしれません。この章では、グループワークの基本的な定義や目的、そしてよく似た「グループディスカッション」との違いについて、就活を始めたばかりの方にも分かりやすく解説していきます。まずはここを読んで、グループワークの全体像を掴みましょう。
1. グループワークの定義と目的
グループワーク(GW)とは、複数の就活生がグループとなり、企業から与えられた特定の課題やテーマについて共同で作業や議論を行い、制限時間内に結論や成果物をまとめ、発表する形式の選考です。
企業はこの選考を通して、皆さんの思考力やコミュニケーション能力、チームで協力して目標を達成する力など、個人の能力だけでは測れない「集団の中での働きぶり」を見ています。
2. グループディスカッションとの違いは?
グループワークと似た選考に「グループディスカッション(GD)」があります。グループディスカッションは、主にテーマに対する「議論のプロセス」や「結論の質」が評価されます。
一方、グループワークは議論に加えて、実際に手を動かして資料を作成したり、模型を作ったりといった「具体的な成果物(アウトプット)」を完成させることが求められる場合が多いのが特徴です。そのため、議論だけでなく、作業の進め方やメンバーとの協力体制も評価の対象となります。
3. 企業が就活でグループワーク選考を実施する理由
企業がグループワーク選考を取り入れる主な理由は、書類選考や面接だけでは見極めにくい、学生の潜在的な能力や実際の仕事に近い状況での行動特性を知りたいからです。
チームで課題に取り組む中で、論理的に考える力、周りの意見を聞きながら自分の意見を伝える力、異なる考えを持つ人々と協力して目標に向かう力などがどのように発揮されるかを見ています。入社後に他の社員と協力して仕事を進められる人材かを見極める目的があります。
就活グループワーク選考の一般的な流れと進め方

グループワーク選考は、事前準備から始まり、当日の議論、発表、そして終了後の振り返りまで、一連の流れがあります。それぞれの段階で意識すべきポイントを押さえておくことで、当日落ち着いて臨むことができます。
ここでは、一般的なグループワーク選考の流れをステップごとに解説し、それぞれの段階でどのように行動すれば良いか、具体的な進め方のコツを紹介します。この流れを頭に入れておきましょう。
1. 選考前の事前準備で差をつける
グループワークに臨むにあたり、事前の準備は非常に重要です。まず、選考を受ける企業の事業内容や企業理念を理解しておきましょう。どのような人材を求めているかを知ることで、議論の方向性や自分のアピールポイントが見えてきます。
また、時事問題や業界の動向など、テーマになりそうな情報を日頃から収集しておくことも有効です。準備をしっかり行うことで、当日どんなテーマが出ても焦らず、自信を持って議論に参加できるようになります。
2. 開始直後の動き方:自己紹介と役割分担
グループワークが始まったら、まずメンバー同士で簡単な自己紹介をしましょう。時間は限られているので、簡潔に行うことが大切です。
「〇〇大学の△△です。人の意見を聴き、それをまとめることが得意です。本日は皆さんと協力して、時間内に良い成果を出せるよう頑張ります。よろしくお願いします。」のように、名前と大学名に加えて、自分の得意なことや意気込みを一言添えると、人となりが伝わりやすくなります。
その後、必要であれば議論を効率的に進めるために、司会、書記、タイムキーパーといった役割を決めると良いでしょう。
3. 時間配分を意識した議論の進め方
グループワークは制限時間が設けられています。効率的に議論を進め、時間内に結論を出すためには、開始時に時間配分を決めることが重要です。例えば、60分のグループワークなら、「最初の5分で役割と時間配分決め、10分でテーマの定義確認、20分でアイデア出しと議論、15分で結論まとめと資料作成、最後の10分で発表準備」のように、大まかなスケジュールを立てます。
議論が白熱すると時間を忘れがちですが、タイムキーパーを中心に時間を確認し、計画通りに進める意識を持ちましょう。
4. 成果物の作成と効果的なまとめ方
グループワークでは、議論した内容を模造紙やホワイトボード、あるいはパワーポイントなどにまとめて成果物として発表することが多いです。限られた時間の中で、分かりやすく、見やすい成果物を作成する必要があります。議論で出た重要なポイントや結論、その根拠などを整理し、図や箇条書きなどを活用して視覚的に訴える工夫をしましょう。誰が見ても議論の流れと結論が理解できるように、情報を整理し構造化することが大切です。
5. 伝わる発表(プレゼンテーション)のコツ
グループでまとめた成果を発表する際には、分かりやすく伝える工夫が必要です。まず、「私たちのグループの結論は〇〇です」のように、結論から先に述べましょう。
次に、「その理由は3点あります。第一に~、第二に~、第三に~です」というように、結論に至った根拠や理由を具体的に説明します。
最後に、「以上の理由から、私たちは〇〇という結論に至りました」と再度結論を述べて締めると、内容が伝わりやすくなります。
自信を持って、はっきりとした声で、聞き手が理解しやすいように話すことを心がけましょう。時間内に収まるように、事前に発表の練習をしておくことも重要です。
6. 評価を左右する質疑応答への対応
発表後には、社員の方や他のグループから質問されることがあります。質疑応答も評価の対象となるため、落ち着いて誠実に対応することが重要です。
質問された内容がよく分からなかった場合は、「申し訳ありません、もう一度質問をお願いできますでしょうか」と正直に聞き返しましょう。
答える際は、「ご質問ありがとうございます。〇〇という点については、私たちのグループでは~のように考えました」と、まず質問に感謝を示し、グループとしての見解を述べることが基本です。個人的な意見を求められた場合を除き、独断で答えるのは避けましょう。
7. 選考終了後の振り返りで次に活かす
グループワーク選考が終わったら、それで終わりではありません。今回の経験を次に活かすために、必ず振り返りを行いましょう。
議論の進め方、自分の発言内容、他のメンバーの良かった点、グループとしての成果など、具体的に思い出してみます。特に、「もっとこうすれば良かった」と感じる点があれば、それは次回の改善点となります。成功体験だけでなく、反省点もしっかりと分析することで、着実に成長に繋げることができます。選考の結果に関わらず、振り返りは必ず行いましょう。
就活グループワークの種類と頻出テーマ例を知っておこう
グループワークで出されるテーマは多岐にわたりますが、ある程度の傾向はあります。事前にどのような種類のテーマがあるかを知っておけば、本番で戸惑うことなく対応できるでしょう。ここでは、就活のグループワークでよく見られる代表的なテーマの種類を、具体的な例とともに紹介します。自分がどのタイプのテーマが得意か、あるいは苦手かを知るきっかけにもなります。
1. ビジネス課題型:企業の課題解決策を考える
企業の実際の事業に関連する課題がテーマとして出されるタイプです。「〇〇(商品名)の売上を半年で2倍にするための施策を考えてください」「当社の新規事業として、〇〇業界に参入すべきか検討してください」といった具体的な問いが出されます。
このタイプでは、単なる思いつきではなく、現状分析に基づいた実現可能なアイデアや、具体的なアクションプランを論理的に示すことが求められます。企業研究で得た知識も活かせるでしょう。
2. 社会問題解決型:社会的なテーマを議論する
「少子高齢化対策として有効な政策は?」「若者の〇〇離れを食い止めるには?」など、現代社会が抱える問題の解決策を探るテーマです。答えが一つではないため、多様な視点から問題を捉え、自由な発想で議論を深めていくことが求められます。
メンバーそれぞれの価値観や知識を組み合わせ、多角的な視点から現状を分析し、実現可能性も考慮した上で、説得力のある解決策を導き出すことが重要になります。
3. 資料読み取り選択型:情報から最適解を選ぶ
複数の資料(グラフ、文章、データなど)が提示され、それらを読み解いた上で、「新店舗を出すならA市とB市どちらが良いか」「3つの選択肢のうち、最も優先すべき施策はどれか」といった問いに対して、グループとしての最適解を選択し、その理由を説明するタイプです。
情報を正確に読み取り、分析する力、そして選択の根拠を論理的に説明する力が試されます。られた時間で効率的に情報を処理する能力も必要です。
4. 作業型・ゲーム型:協力して目標達成を目指す
「配布されたカードの情報だけを頼りに地図を作成してください」「限られた材料で最も高いタワーを作ってください」など、メンバーと協力して具体的な作業を進め、成果物を完成させるタイプです。
このタイプでは、最終的な成果物の質だけでなく、目標達成に向けてメンバーとどのようにコミュニケーションを取り、協力し合って作業を進めるかというプロセスが重視されます。予期せぬ問題への対応力も見られています。
企業はどこを見ている?就活グループワークの評価ポイント

グループワーク選考において、企業の人事は皆さんのどのような点に注目しているのでしょうか。評価ポイントを事前に理解しておくことで、どのような行動を心がければ良いかの指針になります。ここでは、企業がグループワークを通じて見極めようとしている代表的な能力や資質について解説します。これらのポイントを意識して、選考に臨むようにしましょう。
1. 積極性:議論への参加意欲
まず見られているのは、議論に積極的に参加しようとする意欲、すなわち積極性や主体性です。他のメンバーの発言をただ聞いているだけでなく、自ら意見を述べたり、質問をしたり、議論を前に進めようとしたりする姿勢が評価されます。
ただし、自己主張が強すぎたり、他の人の発言を遮ってまで話そうとしたりするのは逆効果になる可能性があるので注意が必要です。周囲とのバランスを見ながら、貢献する意識を持ちましょう。
2. 論理的思考力:筋道を立てて考える力
与えられたテーマや課題に対して、筋道を立てて考え、その内容を分かりやすく説明できるかどうかも重要な評価ポイントです。なぜその結論に至ったのか、どのような根拠に基づいているのかを論理的に説明する力が求められます。
感情論や思いつきではなく、データや事実に基づいて意見を構築し、説得力のある説明を心がけることが大切です。複雑な情報を整理し、構造化する能力も含まれます。
3. コミュニケーション能力:聴く力と伝える力
グループワークは、他者との共同作業です。そのため、コミュニケーション能力は非常に重視されます。
自分の意見を分かりやすく伝える発信力はもちろんのこと、他のメンバーの意見を注意深く聴き、理解しようとする傾聴力も同じくらい重要です。異なる意見が出た場合でも、相手の意図を正確に汲み取り、建設的な議論を進める力が評価されます。
4. 協調性:チームで協力する姿勢
グループワークでは、個人の能力だけでなく、チーム全体として成果を出すことが求められます。そのため、他のメンバーと協力し、目標達成に向けて貢献しようとする協調性が不可欠です。
自分の意見を主張するだけでなく、時には意見を譲ったり、他のメンバーをサポートしたりするなど、チーム全体のことを考えて行動できるかが評価のポイントになります。グループの雰囲気を良くするような働きかけも大切です。
5. リーダーシップ・フォロワーシップ:状況に応じた貢献
チームをまとめ、議論を牽引するリーダーシップも評価されますが、全員がリーダーである必要はありません。リーダーを支え、議論を活性化させるために貢献するフォロワーシップも同様に重要です。グループの状況や他のメンバーの動きを見ながら、自分が今どのような役割を果たすべきかを判断し、チームに貢献する柔軟性が評価されます。縁の下の力持ち的な存在も、企業はしっかりと見ています。
就活グループワークを攻略!役割別の立ち回りとコツ
グループワークを円滑に進め、チームとしての成果を最大化するためには、メンバーそれぞれが役割を意識して動くことが有効です。必ずしも役割を決めなければならないわけではありませんが、自分の得意なことや特性に合わせて立ち回ることで、よりチームに貢献しやすくなります。ここでは、代表的な役割とその立ち回りのコツを紹介します。自分に合った役割を見つけてみましょう。
1. 司会(ファシリテーター):議論を円滑に進める
司会は、議論の進行役です。メンバー全員から意見を引き出し、話が脱線しないように軌道修正し、時間内に結論が出るように議論を導きます。重要なのは、メンバー全員が平等に発言できるような雰囲気を作り、意見が対立した際には中立的な立場で話を整理することです。自分の意見を押し付けるのではなく、あくまで議論を円滑に進めるためのサポート役に徹することが求められます。リーダーシップを発揮したい人に向いています。
2. 書記:議論を整理し可視化する
書記は、議論の内容や決定事項を記録し、メンバー全員が見えるようにまとめる役割です。ホワイトボードや模造紙、あるいはパソコンを使って、議論の要点や流れ、出たアイデアなどを分かりやすく整理します。単にメモを取るだけでなく、記録した内容を元に、「今までの議論をまとめると~ですね」「論点がずれていませんか?」などと発言し、議論の整理や深化に貢献できると高く評価されます。情報を整理するのが得意な人に向いています。
3. タイムキーパー:時間管理で議論を効率化する
タイムキーパーは、グループワークの制限時間を管理し、議論がスケジュール通りに進むように促す役割です。最初に決めた時間配分に基づき、「アイデア出しはあと5分です」「そろそろ結論をまとめる時間です」などと、適切なタイミングで声かけをします。
ただし、時間管理に集中しすぎて議論に参加しないのはNGです。時間を意識しつつ、自分自身の意見もしっかりと述べ、議論に貢献することが大切です。計画性のある人に向いています。
4. アイデアマン・サポート役:多角的に貢献する
特定の役割に就かなくても、議論を活性化させるために貢献する方法はたくさんあります。例えば、積極的に新しいアイデアを出して議論の幅を広げるアイデアマンになったり、他のメンバーの発言を要約したり、分かりにくい点を質問したりするサポート役になったりするのも良いでしょう。発言が少ないメンバーに話を振ったり、資料作成を手伝ったりするなど、チーム全体を見て足りない部分を補う動きも高く評価されます。
【要注意】就活グループワークのNG行動と失敗しないための注意点

グループワークで評価されるポイントがある一方で、評価を下げてしまう可能性のあるNG行動も存在します。自分では良かれと思って取った行動が、実はマイナス評価に繋がってしまうこともあります。ここでは、グループワークで避けるべき代表的なNG行動と、失敗しないための注意点について解説します。事前に知っておくことで、無用な失敗を防ぎましょう。
1. これだけは避けたい!評価を下げるNG行動リスト
グループワークでは、以下のような行動はマイナス評価に繋がりやすいので注意しましょう。
・人の意見を頭ごなしに否定する、批判ばかりする
・全く発言しない、議論に参加しようとしない
・自分の意見ばかり主張し、他の人の話を聞かない
・時間を守らない、時間管理の意識がない
・他のメンバーを見下すような態度をとる
・スマートフォンをいじるなど、マナー違反な行動
これらの行動は、協調性やコミュニケーション能力がないと判断される原因になります。
2. 時間切れは致命的!タイムマネジメントの重要性
グループワークは制限時間内に結論や成果物を出すことが求められます。どんなに良い議論をしていても、時間内にまとめきれなければ評価は大きく下がってしまいます。
「時間切れで結論が出ませんでした」となるのは絶対に避けなければなりません。タイムキーパー任せにするのではなく、メンバー全員が常に時間を意識し、効率的に議論を進めることが重要です。残り時間を考慮して、議論を収束させる意識を持ちましょう。
3. 困ったメンバーへの対処法(クラッシャー対策)
グループの中には、残念ながら議論を妨げるような行動を取る人(いわゆるクラッシャー)がいる可能性もあります。例えば、否定ばかりする人、話が長い人、全く協力しない人などです。このようなメンバーがいても、感情的にならず冷静に対処することが大切です。
まずは相手の意見を一度受け止めた上で、「〇〇さんの意見も分かりますが、△△という視点もありますね」のように、建設的な方向に話を向けましょう。感情的な対立は避けるべきです。
オンライン就活グループワーク特有の注意点と対策
近年、オンライン形式でグループワークを実施する企業が増えています。オンラインには、対面とは異なる特有の難しさや注意点があります。事前にオンラインならではのポイントを理解し、対策しておくことで、スムーズに参加し、自分の力を発揮することができます。ここでは、オンライングループワークで気をつけるべき点と、その対策について解説します。
1. 事前準備:通信環境とツールの確認は必須
オンライン選考で最も重要なのが、安定したインターネット接続環境です。途中で接続が切れたり、音声や映像が途切れたりすると、議論に参加できず、評価にも影響しかねません。
必ず事前に接続テストを行い、Wi-Fi環境が不安定な場合は有線LAN接続なども検討しましょう。また、企業から指定されたツール(Zoom、Teamsなど)の基本的な使い方(マイクのオンオフ、画面共有、チャットなど)も事前に確認しておくことが不可欠です。
2. オンラインでの円滑な議論の進め方のコツ
オンラインでは、相手の表情や場の空気が読み取りにくいため、対面以上に丁寧なコミュニケーションを心がける必要があります。
発言する際は、まず「〇〇(名前)ですが、発言よろしいでしょうか」と断りを入れるとスムーズです。また、相手が話している時は、カメラを見てうなずいたり、相槌を打ったりするなど、意識的に反応を示すと「聞いている」ことが伝わります。発言が重ならないように注意することも大切です。
3. 画面越しでも伝わる自己アピール方法
オンラインでは非言語情報が伝わりにくいため、意識的にアピールする必要があります。カメラ映りを意識し、明るい場所で、背景にも気を配りましょう。
話すときは、普段より少し大きめの声で、はきはきと話すことを心がけると良いでしょう。Zoomなどのリアクション機能を効果的に使ったり、チャットで議論の要点や参考情報を共有したりすることも、貢献意欲を示すアピールになります。積極的にツールを活用しましょう。
就活グループワークが苦手な人向けの対策・克服法
「人前で話すのが苦手」「初対面の人と協力するのが不安」など、グループワークに苦手意識を持っている人も少なくないでしょう。しかし、苦手だからといって諦める必要はありません。自分の苦手な点を理解し、適切な対策を取れば、誰でもグループワークを乗り越えることができます。
ここでは、グループワークが苦手な人向けの具体的な対策や克服法を紹介します。
1. まずは自分の苦手なポイントを分析しよう
「グループワークが苦手」と漠然と感じている場合、まずは具体的に何が苦手なのかを自己分析してみましょう。
「意見を思いつくのが苦手」「自分の意見を言うのが怖い」「議論をまとめるのが苦手」「時間管理ができない」など、苦手なポイントは人それぞれです。自分の弱点を具体的に把握することで、どのような対策を取れば良いか、どのような役割なら貢献しやすいかが見えてきます。まずは自分を知ることから始めましょう。
2. 発言だけが全てじゃない!参加姿勢を示す方法
グループワークで評価されるのは、目立つ発言だけではありません。積極的に議論に参加しようとする姿勢そのものが評価されます。もし意見を言うのが苦手でも、他の人の意見に熱心に耳を傾け、うなずいたり相槌を打ったりする、分からないことを質問する、書記のメモを手伝う、時間を気にする声かけをするなど、できることはたくさんあります。どんな形でも良いので、チームに貢献しようという意欲を示すことが大切です。
3. 自分に合った役割を見つけて貢献する意識を持つ
無理に苦手な役割をやる必要はありません。自分の得意なことや、比較的抵抗なくできる役割を見つけて、そこでチームに貢献することを目指しましょう。
例えば、話すのが苦手でも人の話を聴くのが得意なら書記や、時間を守るのが得意ならタイムキーパーが向いているかもしれません。自分の強みを活かせる役割を見つけ、責任を持ってその役割を果たすことで、自信にも繋がり、チーム全体の成果にも貢献できます。
就活グループワークの練習で自信をつける

グループワークは、ぶっつけ本番で臨むよりも、事前に練習を重ねておくことで、格段にスムーズに進められるようになります。練習を通じて、議論の流れや時間配分、他のメンバーとの協力の仕方などを体験的に学ぶことができます。ここでは、グループワークに自信を持って臨むための、効果的な練習方法をいくつか紹介します。ぜひ試してみてください。
1. 大学のキャリアセンターや就活イベントを活用する
多くの大学のキャリアセンターでは、グループワーク対策講座や模擬選考会などを実施しています。また、就職情報会社などが主催するイベントでも、グループワークを体験できる機会があります。こうした場では、他の就活生と一緒に実践的な練習ができ、職員や企業の採用担当者からフィードバックをもらえることもあります。積極的に活用して、本番の雰囲気に慣れておきましょう。
2. 友人や仲間と模擬グループワークを実施する
気の合う友人や就職活動中の仲間を集めて、模擬グループワークを行うのも効果的な練習方法です。実際の選考のようにテーマと時間を設定し、役割分担をして議論を進めてみましょう。練習後には、お互いの良かった点や改善点を指摘し合うことで、客観的な視点からの気づきを得られます。リラックスした雰囲気の中で、気軽に試行錯誤できるのがメリットです。回数を重ねることで、議論の進め方のコツが掴めてきます。
3. 就活サイトや動画で情報収集と比較を行う
実際にグループワークに参加する前に、就活情報サイトの記事を読んだり、動画サイトで模擬グループワークの様子を見たりすることも有効な準備になります。他の就活生がどのように議論を進めているか、どのような点が高く評価されているかなどを知ることで、具体的なイメージを持つことができます。成功例だけでなく、失敗例からも学ぶことは多いので、様々な情報源からインプットを行いましょう。
就活グループワークについてのよくある質問(Q&A)
ここまでグループワークについて様々な角度から解説してきましたが、まだ細かい疑問や不安が残っているかもしれません。ここでは、就活生の皆さんからよく寄せられるグループワークに関する質問とその回答をQ&A形式でまとめました。これを読めば、さらに安心してグループワーク選考に臨めるはずです。ぜひ参考にしてください。
Q1. 服装はスーツ?私服?持ち物は?
服装は、企業から特に指定がない限りリクルートスーツを着用するのが基本です。私服可や私服推奨の場合でも、オフィスカジュアルを意識した清潔感のある服装を心がけましょう。
持ち物は、筆記用具(複数色あると便利)、ノート、腕時計は必須です。オンラインの場合は、服装の指示に従いつつ、上半身が映ることを意識しましょう。メモを取るための筆記用具は手元に用意しておくと安心です。
Q2. 全く発言できないと落ちる?
発言回数だけが評価の全てではありませんが、全く発言せず、議論に参加する意欲が見られない場合は、残念ながら低評価に繋がる可能性が高いです。意見を言うのが難しくても、質問する、相槌を打つ、メモを取って共有するなど、何らかの形で貢献しようとする姿勢を示すことが重要です。まずは「聞いている」ことを態度で示し、短い発言からでもチャレンジしてみましょう。
Q3. 役割は必ず決めなければいけない?
必ずしも役割を決める必要はありません。メンバー全員がそれぞれの役割を意識しながら、自然な形で議論を進められるのであれば問題ありません。しかし、特に初対面のメンバーで効率的に議論を進めたい場合は、最初に司会、書記、タイムキーパーなどの役割を決めておくと、スムーズに進みやすいことが多いです。役割を決めるかどうかは、グループの雰囲気やテーマに応じて判断しましょう。
Q4. メンバーと意見が対立したらどうすればいい?
グループワークでは、意見が対立することも当然あります。大切なのは、感情的にならず、建設的に議論を進めることです。
相手の意見を否定するのではなく、「〇〇さんの意見も一理ありますね。一方で、△△という考え方もできませんか?」のように、相手の意見を受け止めつつ、別の視点や折衷案を提案する姿勢が重要です。共通のゴールを目指していることを忘れず、協力して最善策を探しましょう。
Q5. 良いアイデアが思いつかない時はどうする?
議論中、なかなか良いアイデアが思いつかないこともあるでしょう。そんな時は、焦る必要はありません。無理に奇抜なアイデアを出そうとするよりも、他のメンバーが出した意見に対して、「〇〇さんの意見、良いですね。具体的にはどういうことですか?」と質問して深掘りしたり、「△△さんのアイデアに、□□を加えるのはどうでしょう?」と意見に乗ってみたりするのも立派な貢献です。まずは議論の流れに乗ることを意識しましょう。
まとめ:自信を持って就活グループワークに臨もう
今回は、就活のグループワークについて、基本的な知識から具体的な対策、苦手克服法まで幅広く解説しました。グループワークは、多くの就活生が不安を感じる選考ですが、事前にしっかりと準備をし、評価されるポイントや注意点を理解しておけば、決して怖いものではありません。大切なのは、完璧を目指すことではなく、自分にできる方法でチームに貢献しようとする姿勢です。この記事で学んだことを活かし、自信を持ってグループワークに臨んでくださいね。