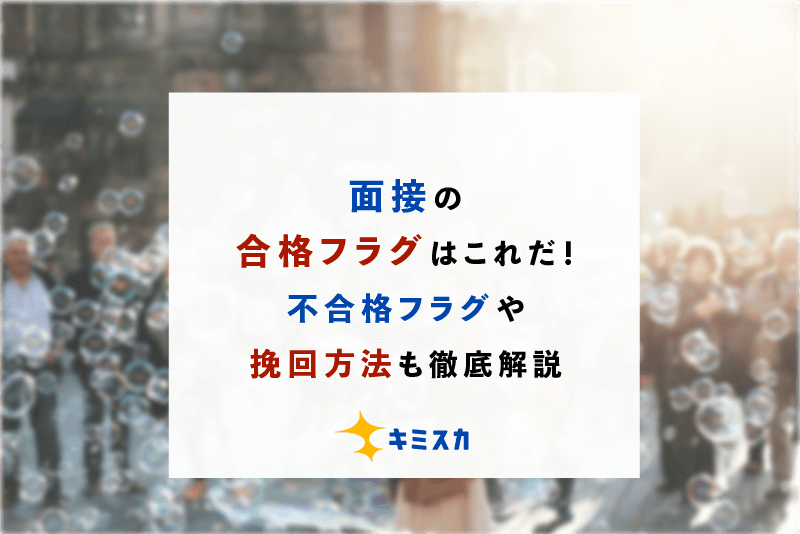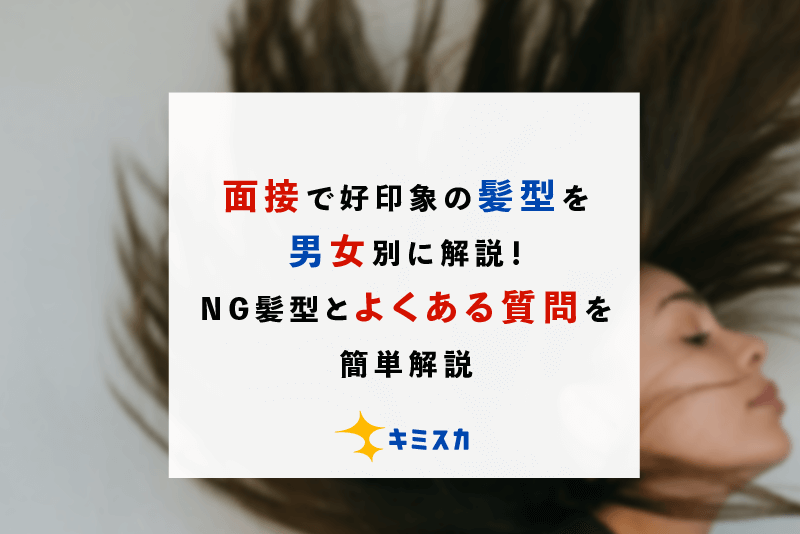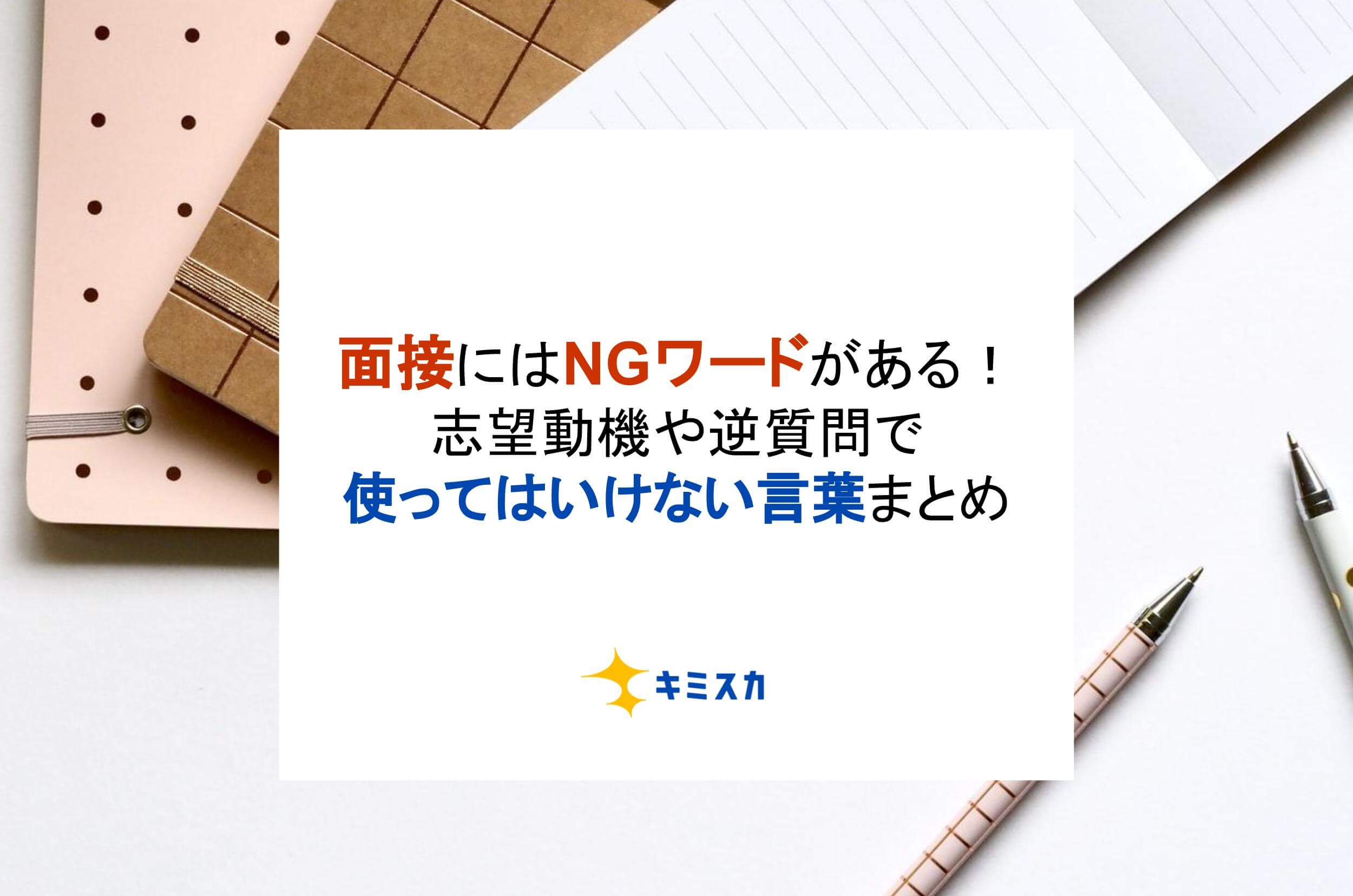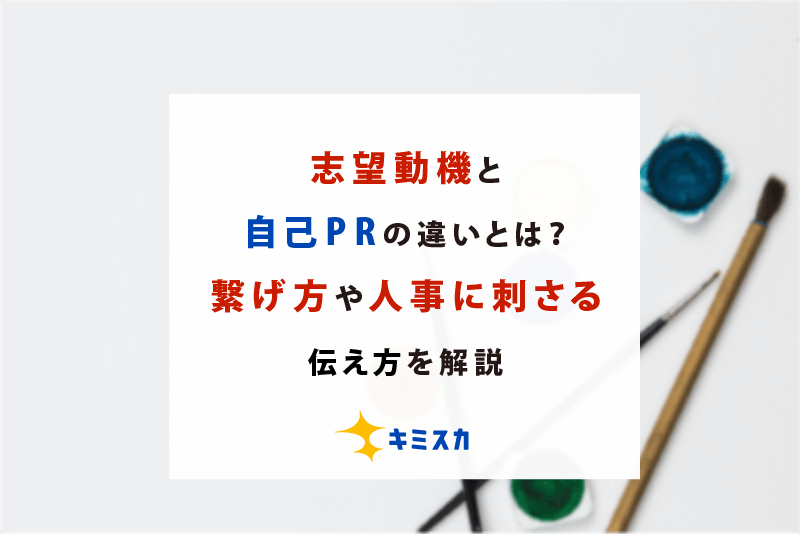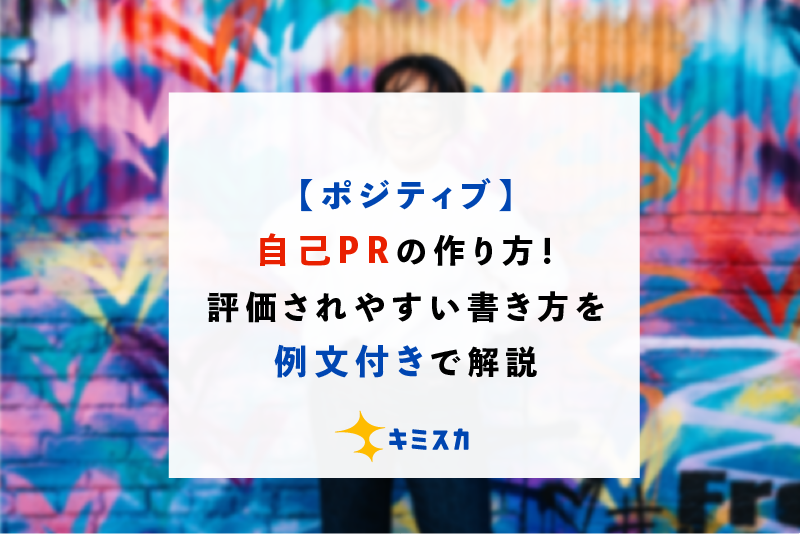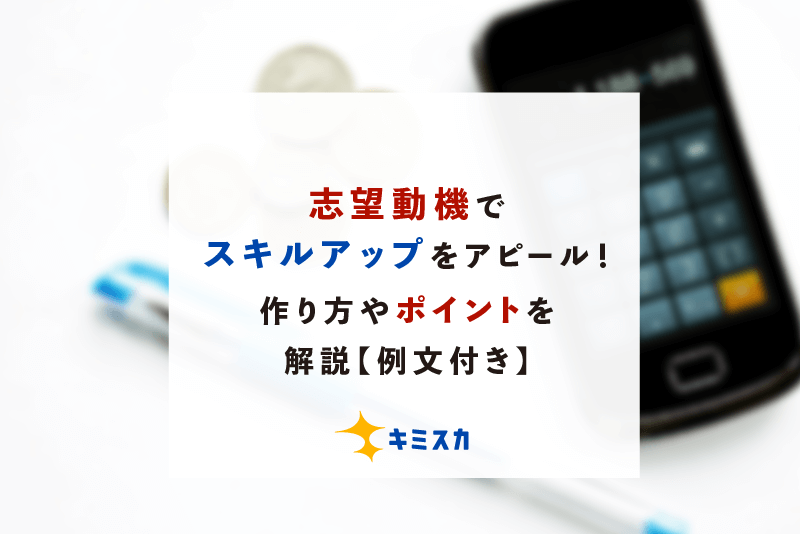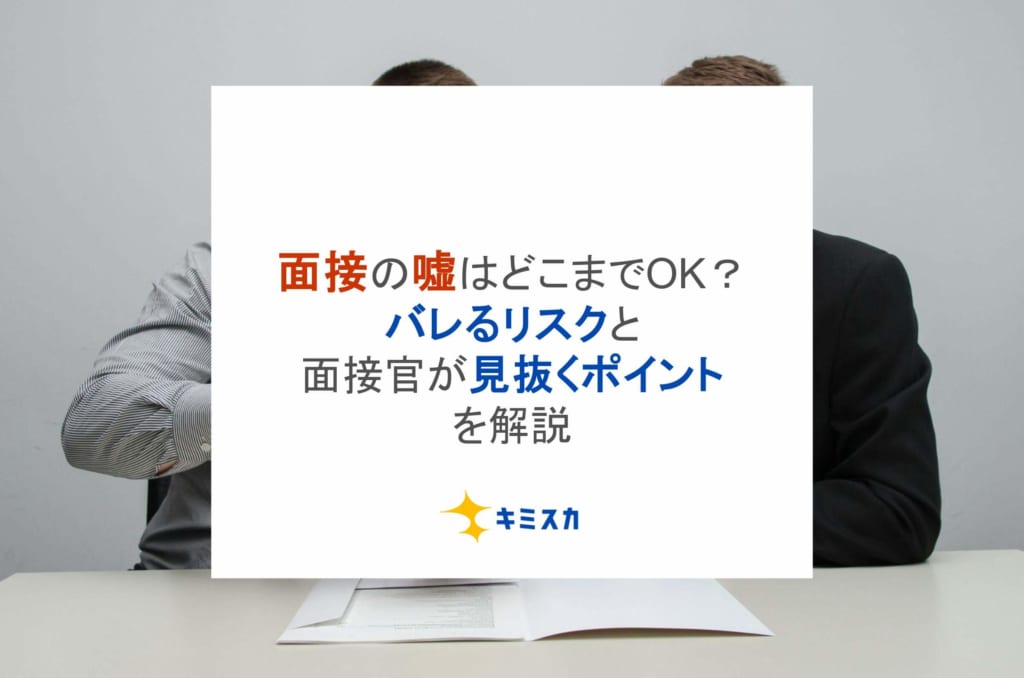
「面接で少しでも自分を良く見せたいけど、嘘をついたらバレるのかな…」「正直に話すと評価されないかもしれない…」就職活動を進める中で、面接での発言に悩む学生は少なくありません。特に、周りの話を聞いて「もしかして、自分も話を盛った方がいいの?」と不安になることもあるでしょう。
この記事を読むことで、就活の面接での「嘘」に関する疑問や不安が解消され、自信を持って面接に臨むためのコツが分かります。
面接での嘘は高確率でバレる!その理由とは?
「少しくらいならバレないだろう」と軽い気持ちで嘘をつこうと考えていませんか?実は、面接官は多くの学生と面談を重ねているため、話の些細な矛盾点や不自然な様子から嘘を見抜くことがあります。
ここでは、なぜ面接で嘘がバレてしまうのか、その具体的な理由を分かりやすく解説していきます。
1. 話の矛盾点や不自然さ
一度嘘をつくと、その嘘を隠すために別の嘘を重ねる必要が出てくることがあります。その結果、話全体で辻褄が合わなくなったり、面接官からの深掘り質問に対してしどろもどろになってしまうケースは少なくありません。
面接官は、あなたが話す内容の一貫性も評価ポイントとして見ているので嘘をつくとすぐにバレてしまいます。
2. 表情や態度、声のトーンの変化
人は嘘をつく際、無意識のうちに表情がこわばったり、視線が不自然に動いたり、声のトーンが変わったりすることがあります。
面接官は、あなたが話す言葉の内容だけでなく、そうした言葉以外のサインも注意深く観察しています。そのため、不自然な振る舞いから「何かおかしいな」と違和感を覚えることがあるのです。
3. ESや適性検査との食い違い
事前に提出したエントリーシート(ES)の記述内容や筆記試験の一環で受けた適性検査の結果と、面接でのあなたの発言内容が大きく異なっている場合、どちらかの情報が事実と異なるのではないかと疑念を持たれる可能性があります。
企業はあなたに関する情報や面接での発言を照らし合わせて、あなたの人物像を掴もうとしているのです。
4. 具体的なエピソードの欠如
例えば、自己PRで大きな成果を上げた経験や珍しい体験について語ったとしても、具体的な状況や経験を説明できないと「嘘をついているのではないか」と疑われてしまいます。
その経験を通じて何を学び、どのように成長できたのかなど、自分の経験を一貫して説明できない場合、信憑性の低い話と判断されやすくなります。
面接で嘘をつくリスクとは?

面接の場で軽い気持ちでついてしまった嘘が、万が一発覚してしまった場合、一体どのような事態を招くのでしょうか。その嘘が、あなたの就職活動や将来に深刻な影響を及ぼす可能性も否定できません。
ここでは、嘘がバレた場合に起こりうる、特に重大なリスクについて具体的に説明します。
1. 内定取り消しの可能性
最も深刻なリスクとして挙げられるのが、内定の取り消しです。
特に、学歴や過去の職務経歴、あるいは業務に必要な資格といった重要な情報に関して嘘をついていたことが発覚した場合、企業からの信用を著しく損ねる行為と見なされ、内定が取り消されるケースが実際にあります。これは、入社後に発覚した場合でも同様です。
2. 企業から信用してもらえなくなる
たとえ内定取り消しという最悪の事態には至らなかったとしても、面接で嘘をついたという事実によって企業からの信頼されなくなる可能性があります。
ビジネスの世界において信頼関係は重要であり、一度失ってしまった信頼を回復するのは難しいものです。
3. 入社後のミスマッチに繋がる
もし、偽ったスキルや経験を採用担当者が評価して採用が決まった場合、入社後に実際の業務レベルについていけず、結果的にあなたが苦労することになるかもしれません。
スキル不足で業務についていけない精神的な負担だけでなく、採用した企業側にとってもデメリットに繋がります。双方にとって不幸な結果を招いてしまうので、面接では嘘をつかないようにしましょう。
就活生がつきがちな嘘とバレやすいポイント
就職活動中の学生が、面接で少しでも自分を有利に見せようとして「つい嘘をついてしまう」という行動にはいくつかの典型的なパターンが存在します。
ここでは、ついてしまいがちな嘘の例となぜ面接官に見抜かれるのかを具体的なポイントを交えて解説します。
スキルや資格の誇張・偽装
例えば、「TOEICのスコアを実際よりも少し高く申告する」や「実際には扱えないプログラミング言語を『業務レベルで扱える』と言う」などがこれにあたります。
資格については、企業から証明書の提出を求められた際に簡単に事実と異なることが発覚しますし、スキルについては実際の業務や研修で試される場面で露見してしまいます。
学生時代の経験(ガクチカ)の捏造や大幅な誇張
「実際にはリーダー経験がないにも関わらず、サークルのリーダーだったと語る」や「実際には小さな成果だったものを、大幅に誇張して話す」といったケースです。
この種の嘘は、面接官からの「その時、一番困難だったことは何ですか?」「具体的にどのような行動を取りましたか?」といった深堀の質問に答えられず、話の辻褄が合わなくなるために嘘であると気づかれることが多いです。
他社の選考状況に関する嘘
「実は、既に他社様からいくつか内定をいただいておりまして…」と、選考を有利に進めようとして嘘をつく就活生もいます。しかし、具体的な企業名や現在の選考フェーズについて尋ねられた際に、曖昧な回答しかできなかったり、しどろもどろになったりすると、不審に思われる原因となります。
場合によっては、企業間で情報交換が行われる可能性もゼロではないことを心に留めておきましょう。
「嘘」と「話を盛る」の境界線はどこ?
「面接で嘘をつくのは良くないと分かっていても、自分の経験を多少良く見せる『話を盛る』くらいなら許されるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
結論から言うと、嘘と話を盛るの境界線は「事実かどうか」です。嘘は事実無根の話であり、話を盛る行為は事実に色を足すことをいいます。具体的な例を用いて説明します。
事実でないことを事実のように話すことをいいます。ないものをあるように話す(0を1にすること)
例:経験していないことを経験したと話す、取得していない資格を取得済みだと話す、TOEICで560点だったが800点と話す
事実に基づいて少しだけ大げさに、あるいはより魅力的に話すことをいいます。あるものを良く見せる(1を1.5にすること)
例:1年のうち数日さぼってしまう日があったが「毎日練習した」と言う、「誰にも負けない○○なところです」とより印象的な言葉で話す
事実を捻じ曲げない範囲での表現工夫はOK
あなたが実際に経験した事実や、達成した成果そのものを偽るのではなく、その伝え方や言葉の選び方を工夫することは「盛る」範囲内と考えて良いでしょう。
例えば、同じ成果を伝えるにしても、よりポジティブで魅力的な言葉を選んだり、相手に分かりやすく、かつ印象的に伝わるように話の構成を工夫したりすることなどが挙げられます。
面接でついてはいけないNGな嘘

面接では自分を少しでも良く見せたいという気持ちが働くかもしれませんが、なかには「NGな嘘」が存在します。これらは発覚した場合に内定取り消しはもちろん、あなたの社会的な信用や将来のキャリアにまで深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。
具体的には、学歴や職歴といった経歴の詐称や資格やスキルに関する嘘がNGな嘘・誇張にあたります。
例えば、「アルバイト先の売上を前年比3倍に貢献した(実際は1.2倍だった)」とか、「SNSのフォロワー数を1ヶ月で1000人増やした(実際は100人だった)」など、具体的な数値や客観的な実績を偽ることも「嘘」と判断されるので注意しましょう。
このような嘘は、後々発覚した場合のリスクが非常に高く信用を大きく損なう原因となります。
なぜ面接で嘘をつきたくなってしまうのか?
面接で嘘をつくことは避けるべきだと頭では理解していても「少しでも自分を良く見せたい」「他の就活生に負けたくない」といった気持ちから、嘘をついてしまうことは誰にでも起こりえるものです。
ここでは、就活生が面接で嘘をつきたくなってしまう背景にある、主な心理的要因について解説します。
1. 自分に自信がない
「自分には他の人に誇れるような特別な経験なんてない」「他の優秀な就活生と比べて、自分は見劣りするのではないか」といった自己肯定感の低さや自信のなさが、実際よりも自分を大きく、有能に見せようとして嘘をついてしまう大きな原因となります。
ありのままの自分では評価されないのではないか、という不安が背景にある場合が多いです。
2. 周囲からのプレッシャー
友人たちが次々と内定を獲得していく状況や家族からの期待、大学関係者からの言葉にプレッシャーを感じて焦ってしまうこともあるでしょう。「何としても選考を突破したい」という強い焦りを生み、結果として嘘をついてでも内定を得たいという気持ちに繋がることがあります。
3. 企業に評価されたいという強い願望
「この企業にどうしても入りたい」「この会社で働きたい」という入社への熱意が強すぎるあまり、その企業が求める理想の人物像に自分を無理に当てはめようとして、結果的に事実とは異なるアピールをしてしまうことがあります。
純粋な入社意欲や企業への憧れが、かえって自分を偽るという形で裏目に出てしまうパターンです。
面接で嘘をつかずに自分を魅力的に伝える方法とは

面接で嘘をつかなくても、あなたの持っている魅力や将来の可能性を面接官にしっかりと伝える方法はあります。
最も大切なのは、自分自身の魅力を理解し、それを効果的に採用担当者に伝えることです。さらに詳しくアピール方法について具体的なコツをご紹介します。
1. 自己分析で自分の強みを理解する
何よりもまず、あなた自身について深く理解を深めることが全ての始まりです。これまでの学生生活やアルバイト、サークル活動などの経験を丁寧に振り返り、どんな時に喜びややりがいを感じ、どのような困難に直面し、それをどう乗り越え、そこから何を学んだのかを具体的に整理してみましょう。
何でもないような経験の中にも、あなたの個性や強みが隠れているはずです。
自己分析が思うように進まなかったり、まだ手を付けられていなかったりする方はキミスカの適性検査を受けてみましょう。質問に答えていくだけで、あなたの強みや適性だけでなく性格の特徴や適職診断もわかります。詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。
2. 等身大の経験を具体的に語る
誰もが目を見張るような華々しい成果や、特別なリーダー経験などがなくても全く問題ありません。あなたが真剣に取り組み努力したプロセスや成長できた点を具体的に自分の言葉で語ることが重要です。
面接官は、結果の大小よりもあなたの物事への取り組み方や思考プロセス、ポテンシャルを知りたいと思っています。
3. ポジティブな言葉選びと伝え方を意識する
同じ内容を伝えるにしても、言葉の選び方や話の展開次第で相手に与える印象は大きく変わります。例えば、過去の失敗談やネガティブに捉えられがちな経験も、そこから何を学び取り、その学びを次にどう活かそうと考えているのかを前向きな姿勢で語ることで、あなたの成長力や課題解決能力を効果的にアピールすることができます。
4. 企業研究を深めて自分との共通点を伝える
応募する企業の理念やビジョン、事業内容、そしてどのような人材を求めているのかを事前にしっかりと研究し、深く理解することが不可欠です。その上で、あなたの価値観や経験が応募企業のどんなところと合致するのかを具体的に説明しましょう。
企業への深い理解と共感を示すことで、あなたの志望度の高さを正直に説得力を持ってアピールできます。
正直に話すことで得られるメリットとは?

面接において正直に自分のことを話すのは、単に嘘がバレるリスクを避けるという消極的な意味だけではありません。むしろ、正直であることによって短期的な選考の突破以上のメリットがあります。
1. 企業とのミスマッチを防げる
ありのままの自分を企業に評価してもらうことで、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを効果的に減らすことができます。
自分に本当に合った社風や仕事内容の企業で働くことは、あなたが充実した社会人生活を送り、長期的な視点でキャリアを築いていく上で、大きなプラスになります。
2. 誠実な人柄が評価される
企業が採用選考で重視しているのは、応募者の能力やスキルだけではありません。その人の持つ人柄や誠実さや信頼できる人物かどうかといった点も大切なポイントです。
真摯な態度で面接に臨むあなたの姿勢は面接担当者に好印象を与え、結果として信頼感に繋がるでしょう。
3. 自分らしくいられる安心感
もし面接で嘘をついてしまうと、その嘘がいつかバレてしまうのではないかという不安を内定後も抱え続けることになりかねません。
面接で正直に自分をアピールすることで、そのような精神的なプレッシャーや後ろめたさを感じる必要もなくなります。選考にも堂々と挑めますし、入社した後も気持ちよくスタートをきれます。
面接で嘘をついてしまった時はどうすればいい?
選考を受けた後に「面接の緊張で、とっさに事実と違うことを言ってしまった…」と悩んでいる方もいるかもしれません。
確かに、一度ついてしまった嘘の事実を変えることは難しいでしょう。同じミスを繰り返さないための対処法を解説していきます。後ろめたさや後悔の念を感じることもあると思いますが。前向きに就職活動を進めていきましょう。
同じ嘘を繰り返さない
一度ついてしまった嘘を隠蔽するために、さらに別の嘘を重ねるようなことは避けなければなりません。
そうした行為は、状況をさらに悪化させるだけでなく、あなた自身を精神的にますます苦しめることになります。大切なのは、犯してしまった過ちを素直に認める勇気を持つことです。
なぜ嘘をついたのかを自己分析する
面接で嘘をついてしまったという事実の裏には、何かしらの不安やプレッシャー、あるいは自己肯定感の低さといった、あなた自身の心理的な要因が隠れているはずです。
その根本的な原因を冷静に分析して、今後の就職活動や自分自身の成長に活かしていくことも重要です。同じ過ちを繰り返さないための貴重な学びとしましょう。
「面接の嘘」についてのよくある質問(Q&A)
ここでは、「面接での嘘」というテーマに関して、多くの就活生が抱きがちな疑問とその回答をQ&A形式で分かりやすくまとめました。これらの情報を参考にすることで、面接に対する漠然とした不安を少しでも和らげ、より自信を持って選考に臨むための一助となれば幸いです。
Q1. 面接官はどのくらい嘘を見抜けますか?
一概に「この程度」と言うのは難しいですが、日々多くの学生と接している経験豊富な面接官は、話の矛盾や行動で嘘を見抜く能力に長けています。
「このくらいバレないだろう」と考えず、ありのままのあなたをアピールしましょう。
Q2. 少し話を盛るのもNGですか?
事実そのものを捻じ曲げたり全くの虚偽を述べたりするのでなければ問題ない場合もあります。自分の強みや経験をより魅力的にアピールするために、表現方法を工夫する「話を盛る」こと自体は、一概にNGとは言えません。
しかし、実績や経験の数値を偽るなどの行為は明確な「嘘」と見なされるので注意しましょう。
Q3. 嘘をついて内定を得ても、入社後にバレることはありますか?
残念ながら入社後に嘘がバレることもあり得ます。例えば、面接で「使いこなせる」と偽ったスキルが、実際の業務を行う中で一人で使いこなせていなかった場合や入社後の提出書類で後から発覚する可能性もあります。
入社後であっても、発覚した嘘の内容が悪質であったり業務に支障をきたしたりする場合には、懲戒解雇などの厳しい処分に繋がる可能性もあることを理解しておきましょう。
あなたらしい魅力を効果的に面接官にアピールしよう
面接において嘘をつくことは、短期的な視点で見ればもしかしたら有利に働くように見えるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば発覚した際のリスクは大きく、あなた自身の信頼を損なう行為に他なりません。
最も大切なのは、自分自身を偽るのではなく、ありのままの自分を深く理解し自分らしい強みを面接官に伝えることです。この記事で解説してきたポイントを参考に、自信を持って面接に臨んでください。