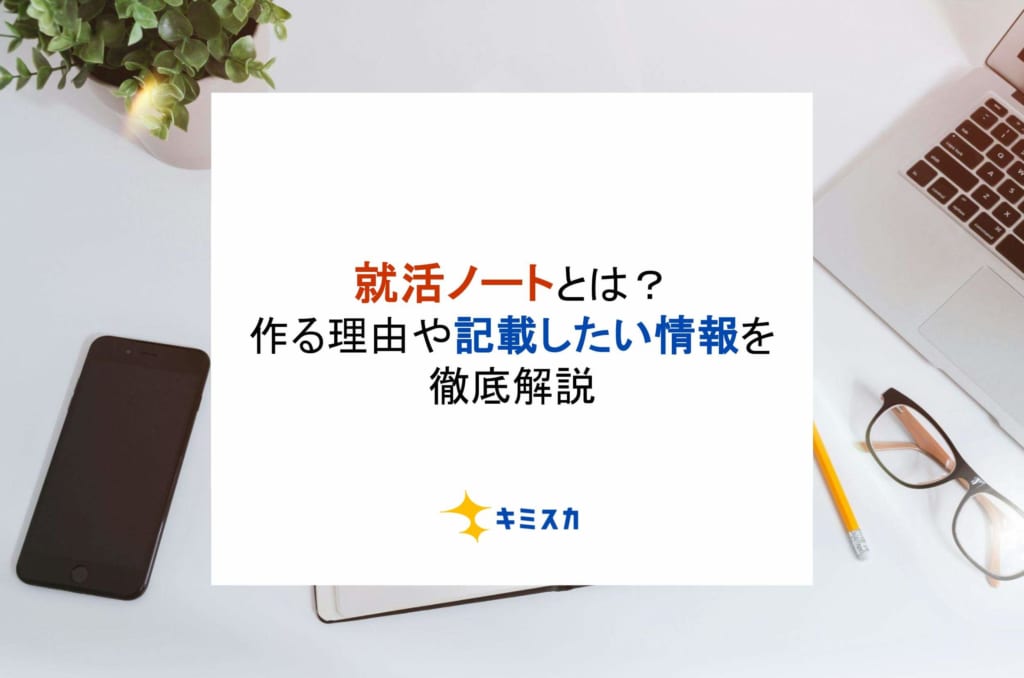
就活初心者に苦戦している人は「何から始めればいいのかわからない」「やることが多すぎる」といった悩みを抱えがちです。こうした学生に共通している問題は、情報が整理できていないという点です。そのため、頭だけで考えるのではなく、ノートなどで一度文字に起こしてみるのは非常に有効でしょう。
就活ノートとは、自己分析の結果や業界・企業研究で調べたこと、就活スケジュールなどをまとめたノートのことです。これは自分の考えや経験を深めるためのツールとして活用できます。また、就活ノートは就活に役立つだけでなく、モチベーションの維持にもつながります。
そこで本記事では、就活ノートの作り方や使い方、注意点などを詳しくまとめました。まだ就活ノートを作っていない就活生は、ぜひ参考にしてみてください。
就活ノートとは?
改めて、就活ノートとは何か解説しますね。
就活は多くの情報を扱う必要があります。エントリーする企業の特徴や選考の進捗状況、面接のフィードバックなどを把握しておかないと、次のステップで適切な準備ができません。しかし、頭の中だけで整理するのは難しく、記憶に頼ると情報を忘れてしまうこともあります。そんなときに役立つのが就活ノートです。
就活ノートには、自己分析、企業分析、面接のスケジュールや反省を書きましょう。そうすることで、一つ一つの活動を効率よく進めることができるため、良い結果が得られること間違いありません!
もちろん、綺麗にまとめられるのが理想ではありますが、まずノートに書いてみることが大切です。学生の皆さんが就活ノートを書き始められるよう、丁寧に書き方や注意点を解説しますね。
就活ノートを作るべき理由
就活ノートとは、就活に関する情報をまとめたノートのことです。就活生のなかには、先輩や教授から「就活ノートを作ったほうがいい」と言われた経験のある人もいるのではないでしょうか。
そこで、ここからは就活ノートを作るべき主な理由を3つ紹介します。
1. 自己分析を深められる
就活ノートは自己分析に活用でき、ノートを見返すたびに自己理解を深めることができます。自分の長所や短所、これまでの経験、自己分析ツールで得た結果などを一通りまとめてみることで、自身の新たな一面を発見できる場合も少なくありません。
2. 業界・企業の情報を整理できる
さまざまな業界・企業の情報を収集していると、企業理念や事業内容などの情報が混ざってしまい、頭の整理が追いつかなくなる場合があります。そこで活用したいのが就活ノートです。
就活ノートを用いて業界・企業の情報を整理しておけば、業界・企業理解が深まるだけでなく、競合他社との比較もしやすくなるでしょう。
3. 過去の面接の振り返りに役立つ
就活ノートに面接の内容や社員の雰囲気、感想などを書き残しておけば、過去の面接を振り返りやすくなります。どこが評価されたのか、何が伝わらなかったのかなど、合否の理由や原因を振り返ることで、次の面接をより有意義なものにできるでしょう。
就活ノートに記載すべき情報3つ

就活情報の整理に役立つ就活ノートですが、具体的に何を書けばいいのでしょうか。ここでは、就活ノートに記載すべき3つの情報を紹介します。
ただし、これはあくまでも最低限の情報であり、ほかにもまとめたいことがあれば追加して構いません。ちなみに、会社説明会や座談会ではメモ代わりとして活用するのもおすすめです。
1. 自己分析や自分の価値観
就活ノートに記載すべき情報の一つ目は、自己分析の結果です。自分の長所・短所や価値観をまとめておけば、自己PRや志望動機の作成時に役立ちます。
就活を進めるうえで、自分自身の強みや価値観を明確にすることが重要です。以下のような情報をノートにまとめることで、自己分析が深まり、面接時の受け答えもスムーズになります。
- 自分の長所・短所
- 学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)
- 過去の経験や成功・失敗体験
- 志望動機の根拠
- キャリアの軸(自分が仕事で大切にしたいこと)
上記の項目を記載する目には、自己分析が不可欠です。自己分析のやり方はさまざまですが、自己理解を深める方法としておすすめしたいのが「自分史」「モチベーショングラフ」です。自分史とモチベーショングラフの作り方は、以下の記事を参考にしてみてください。
2. 業界・企業研究で得た情報
続いて、業界・企業研究で得た情報をまとめましょう。就活ノートにまとめておけば、「せっかく調べた業界・企業の情報を忘れてしまった」「情報が多すぎて頭が混乱してしまう」といった状況を避けられます。企業ごとの違いや特徴を整理することで、志望企業選びの判断材料や面接でのアピールにつなげることが可能になります。
- 業界の特徴やトレンド
- 各企業の事業内容・理念
- 財務状況や成長性
- 社訓やカルチャー
- 競合企業との違い
- 企業説明会やOB・OG訪問で得た情報
- 労働条件(労働時間、給料、勤務地、年間休暇)
これらの情報をまとめるには、どこから情報を取ってくるかが非常に重要です。以下の記事を参考に、業界・企業研究のやり方やポイントを押さえましょう。
3. 面接のスケジュールと活動記録
就活ノートに就活スケジュールや活動記録をまとめておくと、就活中に起こりがちな日程の勘違いやダブルブッキングを防止できます。面接の日程はもちろん、会社説明会やOB・OG訪問、インターンのエントリー時期など、就活に関する予定をまとめて把握できるようにしておきましょう。
また、活動記録をつけることでモチベーション管理をするだけでなく、面接の振り返りができます。企業が異なれど、面接で見られているポイントは企業ごとに大きく異なるわけではありません。なぜ落ちてしまったのか改善点を探すこと、通過した理由から自分の強みを探すことを意識しましょう。
- 企業説明会の日程
- インターンシップ日程・内容
- エントリーシート提出日・締切
- 面接日程と結果
- 面接の会場
- 面接で聞かれた質問と自分の回答
- 面接での手応えや改善点
- 他の応募者との違いを感じたポイント
就活ノートの上手なまとめ方

就活ノートはただ情報を詰め込めばいいものではありません。作成後、見直したときに分かりやすいまとめ方を心がける必要があります。
あえて余白を作る
就活ノートを作る際は、余白を大切にすることが重要です。情報をびっしり書き込むのではなく、あえて余白を残しておくことで見やすくなります。
また、後で関連した情報を追加しやすくなります。例えば、企業の情報をまとめたページに余白があれば、会社説明会や面接で得た情報をメモしたり、訂正したりすることが可能です。
事実だけでなく感想も書く
就活ノートを作るとなると、どうしても得た情報や結果をまとめることに専念しがちです。しかし、就活ノートには事実だけでなく感想も書いておくことをおすすめします。
なぜなら業界・企業研究をして思ったことやインターンに参加して感じたこと、自分の考えなどを記しておくことで、就活の軸がぶれていないかどうかを確認できるからです。また、自分の本心と向き合うこともできるので、たとえ短くても感想を記しておきましょう。
イベント直後に書く
面接やインターンが終わったら、すぐに就活ノートをまとめるのがおすすめです。イベント直後だからこそ書けることもあるので、疲れたからと後回しにするのは避けましょう。
とくにおすすめしたい方法は、イベントに就活ノートを持参し、帰りの電車やバスの中などで簡単にでもメモを残しておくことです。新鮮な情報を記しておけば、後で見返したときにその光景や場面を思い出せるでしょう。
就活ノートの選び方や役立つ道具は?
就活ノートに決まりはないので、好きなノートやペンを選んでも問題ありません。とはいえ、面接会場や企業に持参する場合は見られることを想定して、無地のシンプルなノートとペンを選んでおく必要があります。
以下に就活ノートに使えるノートや筆記用具、役立つ道具をまとめたので、就活ノート作成時の参考にしてみてください。
ノート(持ち歩く場合はA5サイズがおすすめ)
ルーズリーフ
手帳
市販の就活ノート
スマホやタブレット
付箋
蛍光ペン
スケジュール管理アプリ
どのタイプのノートが良い?

ノートといってもどのサイズのノートがいいのかは迷いますよね。
それぞれノートのタイプによって強みがあります。4つの種類についてそれぞれ解説しますので、自分の使い方や拘りに合ったノートを選択しましょう。
手帳
手帳の良さはずばり持ち運びやすいこと。「就活ノートを説明会に持って行って直接書き進めたい」、書き進めていくと「面接の直前に確認したい」と思うことが必ずあります。
また、スケジュール帳が付随しているため、面接やイベントの日程調整に最適です。面接の日程を勘違いしたという声が毎年、就活生から届きますが、日程調整のミスは本当にもったいないです。そのため、カレンダーがついている手帳はこのミスを減らす施策として有効でしょう。
ルーズリーフ
ルーズリーフの強みであり、唯一無二の特徴はページを並び替えられることです。自分のノートをより美しくまとめたいと考える就活生にとって、カスタマイズ性の高いルーズリーフは魅力的でしょう。
例えば、6月に会社説明会、10月に同じ会社の社員座談会に参加したとします。同じ会社であればなるべく近いページでまとめたいなと思うが、何せ4か月も前の出来事なので、ページは残念ながら離れてしまいます。しかし、ルーズリーフであればこうした状況において大いに活躍することでしょう。
市販の一般的なノート
最も使い慣れたノートが最強だ。こう考える就活生も少なくありません。なぜ、あのノートが最も一般的で、最も学校で使われてきたのでしょうか?それは、サイズ、書き心地、購入のしやすさ、これらの総合点が最も高いからです。
強い拘りが無いのであれば、最も無難な選択と言えるかもしれません。
スマホやパソコン上のアプリ
紙媒体でノートをとるのではなく、アプリ上でノートをとるという選択肢もあります。クラウドで保存することができるため、スマホさえ持ち歩いていれば、いつどこでもノートにアクセスすることができます。
アプリを使いこなすには慣れが必要ですが、ポテンシャルは非常に高く、スケジュールアプリとの連携やノートの「ワード検索」など、アプリにしかできない機能は魅力的ですね。
ただ、社員さんの目の前でメモをとる際には注意が必要です。スマホでメモを取る行為は失礼であるという印象を与えかねません。時と場合を考えて、使うようにしましょう。
就活ノートはいつから作り始めるべき?
就活ノートの書き方や重要性は皆さんに分かってもらえたかと思います。では、いつから就活ノートは書き始めると良いのでしょうか?
結論:大学三年生の6月頃から書くべし
就活スケジュールにおいて、もっとも忙しくなるシーズンの一つが「サマーインターン」の選考中です。サマーインターンは夏休みに開催されるため、その選考は夏休みの一か月前、つまり6-7月に集中します。面接前には、自己分析や業界分析を完璧ではなくても、一通りやっておきたいです。そのため、6月を目安に就活ノートを書き始めると良いでしょう。
ただ、就活ノートを書く際に「遅すぎる」なんてことはありません。「面接で中々うまくいかないなー」、「就活出遅れちゃったなー。」そんな学生の皆さんはいち早く、就活ノートを書き始めましょう!
就活ノートの注意点
最後に、就活ノートを作成する際の注意点をご紹介します。就活ノートを作る前に、一通り目を通しておきましょう。

綺麗にまとめることを過度に意識しない
就活ノートの目的は、あくまでも就活情報の整理や振り返りにあります。見やすさや分かりやすさは必須ですが、必要以上に綺麗にまとめることを意識するのはおすすめできません。
綺麗にまとめることに意識が向いてしまうと、ノートの作成に時間がかかるだけでなく、情報の追加や修正がしにくくなります。
ノートを数冊に分けない
就活ノートを数冊に分けると、情報を探すだけで多くの時間を無駄にしてしまいます。また、持ち運びも大変になるので、できるだけ1冊にまとめることを心がけましょう。
最初からページ数が多くなることが予想される場合は、ルーズリーフを活用するのがおすすめです。ルーズリーフならページの入れ替えも可能なので、志望度の高さ順に並べ替えることもできます。
すぐに止めてしまう
就活ノートは記載すべき情報が多いため、途中でしんどくなって止めてしまう就活生も少なくありません。しかし、就活ノート作りは継続することに意味があり、すぐに止めてしまうのはもったいないことです。
就活ノートは誰に提出するわけでもないので、過度に綺麗にまとめる必要はありません。情報をひとつずつ追加し、あなただけの就活ノート作りに励みましょう。
自分だけの就活ノートを活用しよう
就活ノートに自己分析の結果や業界・企業研究で得た情報、就活スケジュールなどをまとめておけば、ES(エントリーシート)対策や面接対策に活用できます。また、これまでの就活を振り返りやすくなるので、就活に対するモチベーションの維持にも役立つでしょう。
就活ノートの使い方はさまざまですが、ESを書く前や面接前に見直すことで質問への回答をまとめやすくなり、自分の気持ちを再確認できます。この記事を参考に自分だけの就活ノートを作り、就活に活用してみてください。

