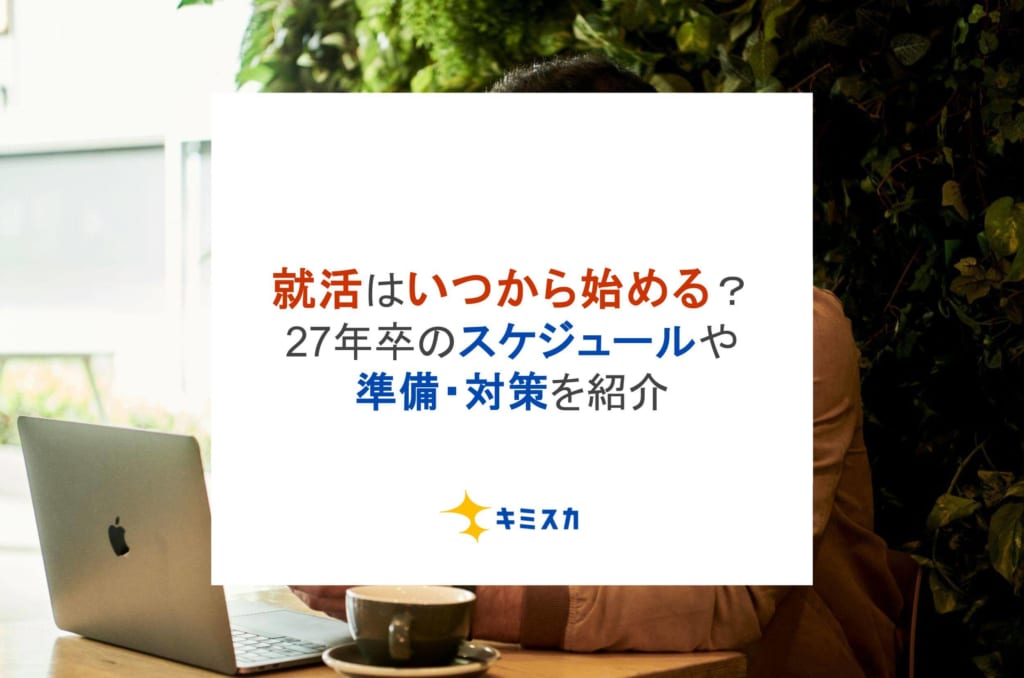
講義をはじめ、ゼミやサークル、アルバイトなど、大学では“やりたいこと”や“やるべきこと”が数多くあるかもしれません。ただ、将来のことを考えたときに「就活はいつから始めるのがいいんだろう」と疑問に思う学生は少なくないでしょう。
そこで、本記事では準備をいつから始めるべきなのかについて解説します。27卒のスケジュールもまとめているので、就活を控えている学生はぜひ参考にしてみてください。
就活はいつから始めるの?
結論からお伝えすると、就活を始める時期は早ければ早いほど良いです。就活が本格的に開始するのは、多くの企業で選考が解禁される大学3年の3月ごろなので、「4年生になる前に始めればいいか」と考えている人もいるでしょう。
しかし、近年は“就活の早期化”と言われており、選考解禁よりも早く選考を行う企業も少なくありません。そのため、志望する業界・企業が決まっている場合や、焦って就活を進めたくない場合は早めに準備しておくのがおすすめです。
また、就活を早めに始めておくことで、時間に余裕を持って志望企業の研究を深められたり、SPIや面接などの選考対策ができたりします。人によってはインターンシップで経験を積み、早期に内定を獲得できるケースもあるため、できるだけ早く就活を始めましょう。
【27卒】就活はいつから始まる?
27卒の就活は、26卒と同様のスケジュールで進みます。経団連に加盟している企業の採用スケジュールは、大学4年の6月以降に選考開始、10月以降に内定出しとなっています。
ただ、経団連に加盟しているのは大企業がほとんどです。エントリーの受付や選考などの詳細な時期は、企業ごとによって異なることも珍しくありません。
外資系企業やベンチャー企業などでは大学3年のうちに内定を出すこともあり、大学3年3月に就活を始めた場合は、すでに選考が終了している可能性もあるので注意が必要です。
就活を始める目安は3パターンある
就活をいつから始めるべきなのか迷っている学生は、企業の選考開始時期を把握しておきましょう。以下の表にまとめたように、大きく3パターンに分けられます。
<経団連に加盟している企業>
| 大学3年7月~ | 夏期インターンシップ |
| 大学3年3月~ | エントリー、企業説明会、ES |
| 大学4年6月~ | 選考(適性検査・筆記試験、面接)、内々定 |
| 大学4年10月~ | 内定出し |
<経団連に非加盟の企業>
| 大学3年7月~ | 夏期インターンシップ |
| 大学3年10月~ | 秋期インターンシップ、早期エントリー・選考・内定出し |
| 大学3年1月~ | 冬期インターンシップ |
| 大学3年3月~ | 一般エントリー・選考 |
| 大学4年6月~ | 適性検査・筆記試験、面接、内々定 |
| 大学4年10月~ | 内定出し |
<外資系企業>
| 大学3年7月~ | 夏期インターンシップ |
| 大学3年10月~ | 選考・内定出し |
“経団連に加盟している企業”の選考を受ける場合は、大学4年に上がる前から就活が始まります。
一方で、“経団連非加盟の企業”や“外資系企業”は、大学3年の秋ごろに内定を出すこともあるため、志望企業の選択肢が一番多い時期に合わせるのであれば、大学3年の4月ごろから就活を始めるのが無難です。
いつから何を始めると就活に間に合う?
就活の準備をする時期は人それぞれ違うため、「この時期から始めれば良い」という明確な答えはありません。しかし、自分に合った就活開始時期を考える場合は、ゴールから逆算するのがおすすめです。
ここでは、就活が本格的に始まる大学3年の3月までに行っておきたい準備を紹介します。大学3年の2月から準備を進めると、やることが多すぎて間に合わない可能性もあるため、大学1・2年のうちから少しずつ進めましょう。
なお、選考開始の時期は企業ごとに異なるため、気になる企業や志望企業が決まっている場合は、早めにスケジュールを確認しておくことが大切です。
【就活が始まる前の準備1】自己分析
自己分析は、就活を進めるうえで必ずやっておきたい作業の一つです。自己分析とは、自身の強み・弱みをはじめ、長所・短所や価値観を分析することをさしており、自分がどんな人間なのかを深く理解することにつながります。
また、ES(エントリーシート)や面接で伝えるアピールポイントが明確になるだけでなく、自身の就活の軸が明確になるためにミスマッチのリスクを減らせるのもポイントです。
【就活が始まる前の準備2】業界・企業研究
続いて、自分に合う企業を見つけるためにも業界研究と企業研究は、必ず行っておきましょう。業界研究とは、自分がどの業界に興味があるのかを知るために、幅広い業界についてリサーチすること。そして、企業研究とは特定の企業の基本情報をはじめ、他社との違いやその企業ならではの特徴を調査・整理することです。
また、業界・企業研究の内容や自己分析の結果をベースに、職種研究を進めるのもおすすめです。職種研究とは職種別に業務内容や必要なスキル・知識を調べる作業のこと。自分がどのような働き方をしたいのかを具体的にイメージしやすくなるため、あわせて行っておきましょう。
業界研究のやり方については、以下の記事で詳しく紹介しています。
【就活が始まる前の準備4】インターンシップ参加
興味のある志望企業を絞れてきたら、自分のなかにある企業イメージを確かめるために、インターンシップに参加してみるのもおすすめです。インターンシップは大学3年から参加できるものもありますが、大学1・2年生でも参加できる場合があるため、気になる方は早めに調べておきましょう。
また、参加できるインターンシップがなかったとしても、仕事体験や社員との交流を図れる「オープン・カンパニー」が開催されている場合もあるため、積極的に参加して自分の適性やマッチ度を確認してみてください。
インターンシップについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみましょう。
【就活が始まる前の準備】OB・OG訪問
就活の情報を集める方法の一つに、OB・OG訪問が挙げられます。先輩のリアルな話しを聞くことで、エントリーを考えている企業への志望度が高まったり、ミスマッチに気づけたりすることもあるため、できるだけ具体的な話しを聞きましょう。
OB・OG訪問は知り合いの先輩に相談しても良いですが、大学のキャリアセンターを通じて紹介してもらうことも可能です。会社説明会や合同説明会などでは聞きづらいことも気軽に聞けるため、企業研究を深めることにも役立つでしょう。
【就活が始まる前の準備】将来的に必要なスキル・資格の取得
志望する業界・企業がある程度明確になっている場合は、将来的に必要なスキルを習得したり、資格を取得したりしておくのもおすすめです。
例えば、金融や不動産業界に興味がある場合はファイナンシャルプランナーの資格を取得し、業務に英語力が求められる企業を志望しているなら海外留学で英語力を磨いてみるのも一つの手です。
スキルや資格を得るにはある程度の時間がかかるため、時間に余裕のある大学1・2年生のうちから進めておきましょう。
【就活が始まる前の準備】何かに全力で打ち込む
就活の準備として、何かに全力で打ち込むことも重要です。なぜなら、就活では「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を聞かれることが多くあるためです。企業はガクチカを通じて、学生がどんな課題に直面してどのように解決したのか、そこから何を学んだのかを確かめています。
就活が始まってからでは、自分が取り組んだことや詳細な内容を忘れてしまっている場合もあるため、全力で打ち込んだことに関する記録を残しておくと良いでしょう。テーマはゼミやアルバイト、サークル活動などが主ですが、詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。
【就活が始まる前の準備】就活・逆求人サイトに登録
就活サイトや逆求人サイトなど、実際に就活で活用するサイトに登録しておくのもおすすめです。操作や情報の見方に慣れることができるほか、企業の情報を集めたり選考の流れなどを確認したりできます。
また、近年注目を集める逆求人サイト「キミスカ」は、大学2年の2月1日から登録が可能です。あなたに興味を持った企業からスカウトの連絡が届くため、自分らしく就活を進めたい人にはぴったりのサービスといえるでしょう。
またキミスカ登録者限定のイベントも多数開催しているため、就活に役立つ情報を得ることも可能です。興味がある人は、下記リンクより詳細を確認してみてください。
就活の選考対策はいつから始めればいい?
新卒採用の選考では、基本的に以下の3つが行われます。
書類選考(ES・履歴書)
適性検査・筆記試験
面接(一次~最終まで複数回)
人によって得意・不得意がありますが、遅くとも選考を受ける1ヶ月前から準備しておきましょう。ただ、選考対策をしてみて初めて自分の不得意なことに気づく場合もあるため、大学2年生ごろには一通りやってみるのもおすすめです。
以下の記事では選考別の対策方法を解説しているので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
「就活をいつから始めるか」はあなた次第!計画的に準備を進めよう
就活の準備を早めに始めたからといって、必ず内定を獲得できるとは限りません。また、大学生の本分は学業であり、学生によってはサークルや部活動などに力を入れている人もいるでしょう。
本記事で紹介した内容は、あくまでも就活を始める際に参考となる時期の目安です。ぜひあなたのやりたいこと・やるべきことのバランスをとって、自分だけの就活スケジュールを立てておきましょう。

