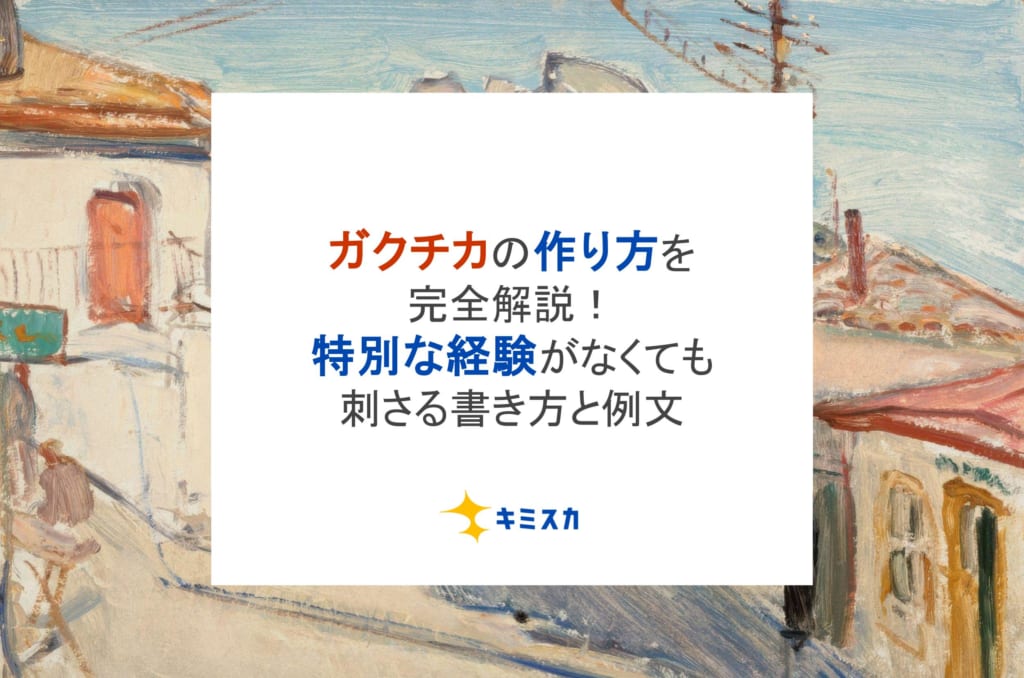
就職活動で避けては通れない「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」。いざ準備を始めようとしても、「アピールできるような経験がない」「どうすれば企業に響くのか分からない」と、手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ガクチカの本質から企業が見るポイント、ネタ探しのコツ、論理的な作り方、そして経験別の例文までを網羅的に解説します。特別な経験がなくても大丈夫。あなただけの魅力が伝わるガクチカを完成させ、自信を持って選考に臨みましょう。
ガクチカとは?企業が「学生時代に力を入れたこと」を知りたい理由
就職活動を始めると必ず耳にする「ガクチカ」。これは「学生時代に力を入れたこと」の略称です。企業はなぜ、あなたのガクチカを知りたいのでしょうか。その理由を理解することが、効果的なガクチカ作成の第一歩です。
ガクチカの基本的な定義
ガクチカとは、あなたが学生時代に主体的に目標を設定し、その達成に向けて努力・工夫した経験のことです。学業、サークル、アルバイト、ボランティアなど、どのような活動でも構いません。
重要なのは、その経験を通じて何を考え、どのように行動し、何を学び、どのように成長したのかを具体的に示すことです。単なる活動報告ではない点を意識しましょう。
企業がガクチカで見ている5つのポイント
企業はガクチカというエピソードを通じて、あなたの様々な側面を評価しようとしています。主に以下の5つのポイントが注目されています。これらを意識することで、企業に響くガクチカを作成できるでしょう。
1. 主体性・行動力
企業は、指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ、目標を設定し、その達成に向けて行動できる人材を求めています。あなたがどのような動機でその活動を始め、困難な状況下でどのように自ら考え、行動を起こしたのかを見ています。
誰かに言われたからではなく、自分の意志で動いた経験は高く評価される傾向にあります。現状維持ではなく、変化を起こそうとした経験を探してみましょう。
2. 目標達成に向けた思考・プロセス
設定した目標に対して、どのような計画を立て、どのような戦略や工夫を用いて取り組んだのか、その思考プロセスを企業は重視します。
単に「頑張った」のではなく、目標達成のために何を考え、どのような手段を選び、なぜその手段を選んだのかを論理的に説明できることが重要です。PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)を意識した経験があれば、有力なアピールポイントになります。
3. 課題発見・解決能力
活動を進める中で、どのような壁にぶつかり、それをどのように分析し、乗り越えるためにどのような策を講じたのか。企業は、あなたが困難な状況に直面した際に、冷静に課題を発見し、粘り強く解決に向けて取り組めるかを見ています。
どのような小さな課題でも構いません。課題の本質を見抜き、具体的な解決策を実行した経験は、あなたの問題解決能力を示す良い証拠となります。
4. 周囲との関わり方・協調性
多くの仕事は一人では完結せず、チームで協力して進める必要があります。企業は、あなたが目標達成の過程で、周囲の人々とどのように関わり、協力体制を築き、時にはリーダーシップを発揮したのかを知りたいと考えています。
異なる意見を持つ人々とどのように合意形成を図ったか、チーム全体の成果にどう貢献したかといった点は、あなたのコミュニケーション能力や協調性を判断する上で重要な指標となります。
5. 学びと成長(再現性)
企業が最も知りたいのは、その経験を通じてあなたが何を学び、どのように成長したのか、そしてその学びを入社後にどのように活かせるのか(再現性)です。
経験から得た気づきや教訓を自分自身の言葉で語り、それが仕事でどのように役立つのかを具体的に示すことが重要です。経験を通じて得た「あなただけの学び」こそが、将来の活躍を期待させる鍵となります。
ガクチカと自己PRの違いを理解しよう
ガクチカと自己PRは混同されがちですが、目的が異なります。自己PRは、あなたの「強み」そのものをアピールするものです。一方、ガクチカは「強みが発揮された具体的なエピソード」を通じて、あなたの行動特性や人柄を伝えるものです。ガクチカは自己PRの根拠となるエピソードであり、両者を連携させることで説得力が増します。
例えば、自己PRで「私の強みは課題解決能力です」と述べ、ガクチカでその能力を発揮した具体的な経験を語るといった形です。
ガクチカがないと悩む人用【ネタの見つけ方完全ガイド】
「自分には話せるようなすごい経験がない…」そう悩んでいる就活生は少なくありません。しかし、心配は無用です。ガクチカは自慢話大会ではありません。
企業はあなたの経験の大小ではなく、その経験に対するあなたの向き合い方を知りたいのです。ここでは、平凡だと思える経験からもガクチカのネタを見つける方法を紹介します。

「すごい経験」は必要ない!企業が見たいのは結果よりプロセス
全国大会優勝や、学生起業、長期海外ボランティアといった華々しい経験は、必須ではありません。むしろ、企業が重視するのは、あなたが目標に対してどのように考え、工夫し、行動したかという「プロセス」です。
ありふれた経験であっても、あなた自身の主体的な取り組みや学びが具体的に語られていれば、それは十分に魅力的なガクチカになります。結果が成功でも失敗でも、そこから何を学んだかが重要です。
まずは学生時代の経験を洗い出してみよう
どのような経験でもガクチカのヒントになり得ます。まずは固定観念を捨てて、大学入学以降の経験をできるだけ多く書き出してみましょう。どんな些細なことでも構いません。記憶を辿り、具体的な行動や感情を思い出すことが大切です。
1. 学業・ゼミ・研究
特定の授業で高評価を得るために工夫したこと、苦手科目を克服した経験、ゼミでのディスカッションや共同研究、卒業論文の作成などは立派なガクチカになります。
特に、難解な課題に対してどのように情報を収集し、分析し、結論を導き出したか、あるいはチームでの研究でどのような役割を果たしたかといったプロセスを具体的に振り返ってみましょう。目標設定、計画立案、実行、評価といった一連の流れを語りやすいテーマです。
2. アルバイト
多くの学生が経験するアルバイトも、ガクチカの宝庫です。単に仕事をこなすだけでなく、売上向上や業務効率化のために自分で考えて行動したこと、後輩の指導で工夫したこと、お客様からのクレームに誠実に対応した経験などはありませんか。
与えられた業務の中で、どのように付加価値を生み出そうとしたか、どのような課題意識を持って取り組んだかを掘り下げてみましょう。責任感やホスピタリティ、課題解決能力などをアピールしやすいでしょう。
3. サークル・部活動
役職経験や大会実績がなくても問題ありません。練習方法を改善したこと、新入部員を増やすために企画したこと、メンバー間の意見対立を調整したこと、イベント運営で苦労したことなど、チーム目標達成のために貢献した経験を振り返りましょう。
目標達成意欲、リーダーシップ、協調性、粘り強さなどをアピールできます。特に、目標と現状のギャップを埋めるためにどのような工夫をしたかがポイントになります。
4. インターンシップ・ボランティア
実際のビジネス現場に近いインターンシップや、社会貢献活動であるボランティアは、ガクチカとして非常にアピールしやすい経験です。どのような目的意識を持って参加し、そこでどのような役割を担い、どのような成果を出したのか、あるいは社会課題に対してどのように向き合ったのかを具体的に述べましょう。
仕事への理解度や主体性、社会貢献意識を示すことができます。社員の方との関わりや、組織の中で動いた経験は貴重な財産です。
5. 資格取得・趣味・個人的な取り組み
特定の資格取得に向けて計画的に勉強した経験、趣味を通じて何かを極めた経験、あるいはブログ運営やプログラミング学習といった個人的な取り組みも、目標設定能力や継続力、探求心を示すガクチカになり得ます。
なぜそれに取り組んだのか、どのような目標を立て、どのように努力したのか、そして何を得たのかを明確に説明できれば、十分にアピール可能です。主体性や自己管理能力を示す良い機会となるでしょう。
経験からガクチカの「原石」を見つける3つの視点
洗い出した経験の中から、特にガクチカとして深掘りできそうな「原石」を見つけるためには、以下の3つの視点から経験を振り返ってみることが有効です。
これらの視点で考えると、平凡だと思っていた経験にも、アピールできる価値があることに気づくはずです。
1. 最も熱中したこと・時間をかけたこと
あなたが最も夢中になって取り組んだことは何でしょうか。寝食を忘れるほど没頭したこと、気づいたら膨大な時間を費やしていたことはありませんか。
熱中できたということは、そこにあなたの強い動機や興味関心があった証拠です。なぜそれに熱中したのか、その過程で何を考え、感じたのかを掘り下げると、あなたの価値観や情熱を伝えるガクチカが見つかります。
2. 課題や困難に直面し、乗り越えたこと
順風満帆な経験よりも、むしろ課題や困難に直面し、それを乗り越えるために試行錯誤した経験の方が、あなたの強みや学びを雄弁に物語ることがあります。
どのような壁にぶつかり、その時どのように感じ、どのように考えて行動し、最終的にどう乗り越えたのか(あるいは乗り越えられなかったとしても、何を学んだのか)を整理してみましょう。課題解決能力やストレス耐性、粘り強さを示すことができます。
3. 目標を設定し、工夫して取り組んだこと
何か具体的な目標を設定し、その達成に向けて自分なりに工夫や努力をした経験はありませんか。その目標は、大きなものでなくても構いません。
「〇〇をできるようになる」「〇〇の売上を△%上げる」「〇〇大会で□位以内に入る」など、どんな目標でも良いのです。重要なのは、目標達成のためにどのような計画を立て、どのような工夫をし、周囲をどう巻き込んだか、そのプロセスです。計画性や実行力、主体性をアピールできます。
【基本】ガクチカの作り方フレームワーク(STARメソッド)
ガクチカのネタが見つかったら、次はそれを効果的に伝えるための構成を考えましょう。ここでは、多くの企業で評価されやすい論理的なフレームワーク「STARメソッド」を紹介します。このフレームワークに沿って情報を整理することで、あなたの経験が具体的かつ分かりやすく伝わります。
1. S (Situation):状況設定
まず、あなたがどのような状況に置かれていたのかを簡潔に説明します。所属していた組織(サークル、ゼミ、アルバイト先など)の規模や特徴、当時のあなたの役割や立場、そしてその組織がどのような状況にあったのか(例:目標、課題など)を具体的に述べます。
採用担当者がエピソードの背景をスムーズに理解できるよう、必要な情報を過不足なく伝えることが重要です。5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識すると良いでしょう。
2. T (Task):課題・目標
次に、その状況下であなたが担っていた具体的な課題や、設定した目標について説明します。組織全体としての課題・目標でも良いですし、あなた個人としての課題・目標でも構いません。
なぜそれが課題だと感じたのか、なぜその目標を設定したのか、その背景にある考えも併せて述べると良いでしょう。課題や目標は、できるだけ具体的で、可能であれば数値化できると、その後の行動や結果のインパクトが伝わりやすくなります。
3. A (Action):具体的な行動
設定した課題や目標に対して、あなたが「具体的に」「どのように」行動したのかを詳しく説明します。ここがガクチカの最も重要な部分です。
他のメンバーとどのように協力したのか、どのような工夫や試行錯誤をしたのか、なぜその行動を選んだのか、その根底にあるあなたの考えを明確に示しましょう。受け身の行動ではなく、あなた自身の主体的な意志に基づいた行動を具体的に記述することが、高く評価されるポイントです。
4. R (Result):結果と学び
最後に行動の結果、どのような成果が得られたのかを述べます。可能であれば、定量的な成果(例:売上が〇%向上した、〇人の参加者を集めたなど)を示すと説得力が増します。しかし、結果が必ずしも成功である必要はありません。
たとえ目標未達でも、その経験から何を学び、どのような気づきを得て、どのように成長できたのかを具体的に語ることが重要です。そして、その学びを入社後にどのように活かしていきたいのかを示すことで、企業への貢献意欲をアピールできます。
【実践】ガクチカ作成5ステップ
STARメソッドを理解したら、次はいよいよガクチカを文章化していく実践ステップです。以下の5つのステップに沿って進めることで、論理的で魅力的なガクチカを効率的に作成できます。
一つ一つのステップを着実に踏むことが、採用担当者の心に響くガクチカ作成への近道です。焦らず、じっくりと取り組みましょう。

1. 経験の洗い出しとネタ選定
まずは「ガクチカがないと悩む君へ」で紹介した方法で、学生時代の経験を可能な限り洗い出します。そして、その中から、企業の求める人物像や、あなたがアピールしたい強みと最も合致する「これだ!」と思えるネタを一つ、あるいはいくつか選びます。
この段階で、STARメソッドのS(状況)とT(課題・目標)を明確にしておくと、後のステップが進めやすくなります。
2. フレームワークに沿って情報を整理
選んだネタについて、STARメソッド(状況・課題・行動・結果)の各要素に当てはまる情報を具体的に書き出していきます。この段階では、文章にする必要はありません。
箇条書きで構わないので、できるだけ詳細に、具体的な事実や数値を思い出して書き留めましょう。特にA(行動)の部分は、なぜその行動をしたのかという理由も含めて、詳しく書き出すことが重要です。
3. 企業の求める人物像を意識して肉付け
整理した情報をもとに、志望する企業がどのような人材を求めているのかを意識しながら、ストーリーに肉付けしていきます。例えば、協調性を重視する企業であれば、チームでの協力体制を強調するなど、アピールするポイントを調整します。
ただし、嘘をつくのは厳禁です。あくまで、あなたの経験のどの側面を強調するか、という視点で考えましょう。
4. PREP法で伝わりやすい構成にする
文章全体の構成は、結論から述べるPREP法(Point:結論 → Reason:理由 → Example:具体例 → Point:結論の再強調)を意識すると、非常に伝わりやすくなります。
まずガクチカの要点(Point)を述べ、STARメソッドで整理した内容を理由(Reason)や具体例(Example)として展開し、最後に学びや貢献意欲(Point)で締めくくる流れです。これにより、話の要点が明確になり、論理的な印象を与えられます。
5. 具体的な言葉で磨き上げる(推敲)
文章が完成したら、必ず推敲を行います。誤字脱字、文法的な誤りがないかはもちろん、「頑張った」「努力した」といった抽象的な言葉を避け、具体的な行動や成果が伝わる言葉を選びましょう。専門用語や略語は避け、誰にでも分かる平易な表現を心がけます。
声に出して読み、リズムや長さを確認することも有効です。友人やキャリアセンターの職員など、第三者に読んでもらい、客観的な意見をもらうことで、さらに質の高いガクチカに磨き上げることができます。
ガクチカをさらに魅力的にする5つのコツ
基本的なガクチカが作成できたら、次は他の就活生と差をつけ、採用担当者の印象に強く残るための工夫を加えましょう。
以下の5つのコツを意識することで、あなたのガクチカはさらに魅力的になります。これらのコツは、あなたの経験をより輝かせ、入社後の活躍を具体的にイメージさせるためのスパイスです。
1. 具体的な数字や固有名詞を入れる
「売上を上げるために頑張った」ではなく、「前年比10%の売上向上を目指し、〇〇という新商品を提案した」のように、具体的な数字や固有名詞を盛り込むことで、話にリアリティと説得力が生まれます。組織の人数、期間、目標値、成果などを具体的に示すことで、あなたの取り組みの規模感や達成度合いが、採用担当者により正確に伝わります。
2. あなた自身の考えや工夫を明確にする
単なる事実の羅列ではなく、その状況であなたが「何を考え」「なぜそう判断し」「どのような工夫をしたのか」という思考プロセスを明確に示しましょう。あなたならではの視点や創意工夫が伝わることで、あなたの個性や問題解決能力を効果的にアピールできます。「自分だったらどうするか」という視点が重要です。
3. 「学び」を言語化し、入社後の再現性を示す
経験を通じて何を得たのか、その「学び」を自分の言葉で明確に言語化することが重要です。そして、その学びが一時的なものではなく、今後も活かせる汎用的なものであること、特に入社後にその企業でどのように活かせるのか(再現性)を示すことで、企業はあなたを採用するメリットを具体的に感じることができます。
4. 企業が求める力と結びつける
企業研究を通じて把握した、その企業が求める人物像や重視する能力(例:リーダーシップ、協調性、挑戦意欲など)と、あなたのガクチカでアピールする強みが一致するように意識しましょう。あなたの経験が、その企業で活躍するために必要な資質を備えていることの証明となるようにストーリーを構築することがポイントです。
5. 結論ファーストで簡潔に話す(書く)
特に面接では、まず結論(何を成し遂げたのか、何をアピールしたいのか)から話し始めることが重要です。ESにおいても、書き出しで要点を明確にすることで、採用担当者は内容を把握しやすくなります。限られた時間や文字数の中で最も伝えたいことを効果的に伝えるためには、結論ファーストと簡潔さが不可欠です。
【経験別】ガクチカ例文集
ここからは、具体的なガクチカの例文を経験別に紹介します。これらの例文は、あくまで書き方や構成の参考です。あなたの経験や個性を活かし、オリジナルのガクチカを作成するためのヒントとして活用してください。例文を参考にしつつも、あなた自身の言葉で、あなただけのストーリーを語ることが最も重要です。
1. アルバイト経験をアピールする例文
私が学生時代に最も力を入れたことは、〇〇(例:カフェ)でのアルバイトにおいて、お客様のリピート率を向上させるための提案と実践です。
当初、当店は新規顧客は多いものの、再来店に繋がらないという課題がありました。私は、お客様が心地よく過ごせる空間作りと、記憶に残る接客が重要だと考え、二つの施策を実行しました。一つ目は、お客様の顔と名前、好みを覚える努力をし、次回来店時にパーソナライズされた声かけを行うことです。二つ目は、スタッフ間で顧客情報を共有する簡単なノートを作成し、チーム全体で温かい接客を実践することです。
その結果、半年後には担当エリアのリピート率が〇%向上し、お客様から名指しで感謝の言葉をいただく機会も増えました。この経験から、相手の立場に立って考え行動することの重要性と、チームで目標を共有し実行する力を学びました。貴社でもこの顧客視点と実行力を活かし、〇〇(貢献内容)に貢献したいと考えております。
2. サークル活動をアピールする例文
私が学生時代に力を入れたことは、所属する〇〇サークル(例:軽音楽部)において、新入部員の定着率向上に取り組んだことです。
私のサークルでは、毎年多くの新入部員が入るものの、夏休み前には半数近くが辞めてしまうという課題がありました。私は、その原因が新入部員の孤立感や練習への参加しにくさにあると考え、新入部員向けの交流イベントの企画と、初心者向けの練習メニューの導入を提案・実行しました。特に、上級生がマンツーマンでサポートする制度を設けたことで、新入部員は気軽に質問できるようになり、練習への意欲も高まりました。
その結果、その年の新入部員の定着率は過去最高の〇%を達成し、サークル全体の活性化にも繋がりました。この経験を通じて、課題の本質を見抜き、周囲を巻き込みながら具体的な解決策を実行する力、そして後輩を育成する喜びを学びました。貴社においても、持ち前の課題解決能力と協調性を活かし、チームの目標達成に貢献したいです。
3. ゼミ・学業をアピールする例文
私が学生時代に最も注力したのは、〇〇教授のゼミにおける「△△(研究テーマ)」に関する共同研究です。
当初、私たちのチームは意見の対立が多く、研究が停滞していました。私は、その原因がメンバー間のコミュニケーション不足と役割分担の曖事故にあると考え、まず定期的なミーティングの開催と議事録の共有を徹底しました。さらに、各メンバーの得意分野や興味関心をヒアリングし、それぞれの強みが最大限に活かせるような役割分担を再提案しました。私自身は、△△(具体的な担当役割と行動)に責任を持ち、他のメンバーとの連携を密に行いました。
その結果、チームの一体感が高まり、研究は加速。最終的には学会発表で〇〇賞を受賞するという成果を収めることができました。この経験から、多様な意見を調整し、チーム全体の力を引き出す調整力と、目標達成に向けた計画実行力を身につけました。貴社の〇〇(職種)においても、この力を活かして貢献できると確信しております。
4. インターンシップ経験をアピールする例文
私が学生時代に力を入れたことは、貴社(あるいは同業他社)の〇〇部門における長期インターンシップです。
そこでは、△△(具体的な業務内容)を担当させていただきました。当初は業界知識も浅く、戸惑うことも多かったのですが、私は「誰よりも早く成長し、具体的な成果で貢献する」という目標を立て、三つの行動を徹底しました。第一に、毎日業務日誌をつけ、疑問点や学びを言語化し、翌日には必ず先輩社員に質問・相談すること。第二に、関連書籍や業界ニュースを読み込み、基礎知識と最新動向をインプットし続けること。第三に、指示された業務だけでなく、自分なりに「もっとこうすれば良くなるのでは」という改善提案を積極的に行うことです。
その結果、〇ヶ月後には△△(具体的な成果)を達成し、社員の方からも高い評価をいただくことができました。この経験を通じて、未知の領域にも臆せず飛び込み、主体的に学び行動する力と、ビジネスの現場で成果を出すことの厳しさ・面白さを学びました。この経験を活かし、一日も早く貴社の戦力となりたいです。
ガクチカ作成の注意点とNG例
ガクチカを作成する際には、いくつかの注意点があります。せっかくの経験も、伝え方を間違えるとマイナスの印象を与えかねません。
ここでは、陥りやすいNG例とその対策について解説します。これらのポイントを押さえて、誠実かつ効果的なガクチカを目指しましょう。

絶対にNG!嘘や過度な誇張
自分を良く見せたいという気持ちから、事実と異なることを話したり、実績を過度に誇張したりすることは絶対に避けましょう。嘘は面接での深掘り質問や、入社後の経歴確認などで露呈する可能性が高いです。
信頼を失うリスクは非常に大きく、たとえ内定を得ても後々苦しむことになります。等身大のあなたを、誠実に伝えることが何よりも大切です。
具体性に欠ける抽象的な表現
「コミュニケーション能力を発揮した」「リーダーシップを発揮した」「困難を乗り越えた」といった抽象的な表現だけでは、採用担当者には何も伝わりません。
どのような状況で、具体的にどのような行動を取り、その結果どうなったのかを詳しく説明することが重要です。STARメソッドなどを活用し、具体的なエピソードで裏付けのないアピールは避けましょう。
結果だけをアピールする内容
「〇〇大会で優勝した」「売上を〇%上げた」といった結果だけを強調しても、企業はあなたがどのようにその結果を出したのかを知ることができません。
企業が見たいのは、その結果に至るまでのあなたの思考や行動、つまり「プロセス」です。結果に至るまでの課題、工夫、努力、そして学びを具体的に語ることが、あなたの本当の価値を示すことに繋がります。
企業が求める力とズレている
いくら素晴らしい経験でも、その企業が求めている人物像や能力と大きくかけ離れたアピールをしてしまうと、評価されにくい場合があります。
例えば、協調性を重視する企業に対して、個人での成果ばかりを強調しても響きません。事前に企業研究をしっかり行い、その企業がどのような人材を求めているのかを理解した上で、アピールする経験や側面を選ぶことが重要です。
ガクチカに関するよくある質問(Q&A)
ここでは、ガクチカに関して就活生の皆さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。志望動機作成で迷ったときや、疑問点がある場合の参考にしてください。細かい疑問点を解消しておくことで、自信を持ってガクチカを語れるようになります。
Q1. ガクチカは何個くらい用意すれば良い?
必ずしも複数用意する必要はありませんが、できれば異なる強みや側面をアピールできるガクチカを2~3個用意しておくと、様々な企業のニーズや面接の状況に対応しやすくなります。
例えば、「リーダーシップを発揮した経験」と「地道な努力を続けた経験」のように、異なるタイプの経験があると、あなたの多面的な魅力を伝えることができます。まずは一番自信のある「鉄板ネタ」をしっかり作り込むことから始めましょう。
Q2. 複数のガクチカを企業によって使い分けるべき?
はい、企業が求める人物像や職種に合わせて、最も効果的だと思われるガクチカを選んでアピールすることは非常に有効な戦略です。
例えば、チームワークを重視する企業にはサークル活動での協調性を、挑戦意欲を求める企業には新しいことに取り組んだ経験を話すなど、相手に合わせてアピールポイントを調整しましょう。そのためにも、事前に企業研究をしっかり行い、各企業の特色を理解しておくことが重要になります。
Q3. 留学経験や資格勉強もガクチカになる?
もちろんなります。留学経験であれば、異文化の中でどのような困難に直面し、それをどう乗り越え、何を学んだのかを具体的に語ることで、適応能力やグローバルな視点をアピールできます。
資格勉強であれば、目標設定能力、計画性、継続的な努力といった強みを示すことができます。重要なのは、経験の種類ではなく、その経験を通じてあなたがどのように考え、行動し、成長したのかを具体的に示せるかどうかです。
Q4. 「ガクチカを盛る」のはどこまでOK?
前述の通り、事実を捻じ曲げる「嘘」は絶対にNGです。しかし、事実をより魅力的に伝えるための「表現の工夫」は許容範囲であり、むしろ推奨されます。
例えば、曖昧な表現を具体的な言葉に変えたり、数字を用いて成果を分かりやすく示したり、自分の行動の意図や学びを明確に言語化したりすることです。「盛る」というのは、0を1にすることではなく、1を1.5に見せるための表現技術だと考えましょう。事実に基づいていることが大前提です。
あなただけのガクチカを完成させて自信を持って就活に挑もう
この記事では、ガクチカの基本的な考え方から、ネタの見つけ方、具体的な作り方、そして魅力的に伝えるコツまでを詳しく解説してきました。
ガクチカは、あなたの個性やポテンシャルを企業に伝えるための絶好の機会です。「すごい経験がない」と諦めずに、あなた自身の経験と真摯に向き合い、自信を持って語れるガクチカを作成してください。

