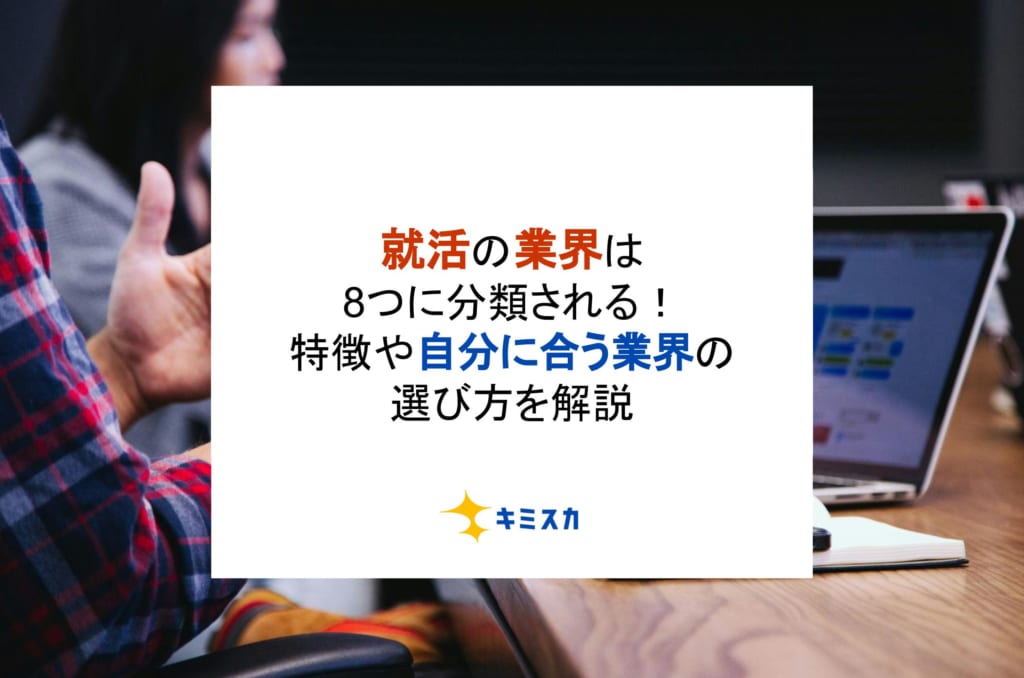
就活を始めるなら、まずどのような業界があるのか把握することが大切です。業界によって仕事内容や雰囲気が大きく異なるので、入社後のミスマッチを防止するためにも業界ごとの特徴を理解おきましょう。
そこで本記事では、就活の業界を大きく8つに分類して紹介します。業界選びのポイントや注意点もまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
就活生は業界の把握から始めよう
そもそも業界とは、産業・商業別に企業を分類したものです。世の中にはさまざまな企業があり、そのどれもがなんらかの業界に属しています。
就活における「業界」と「業種」の違い
業界と混同されがちな言葉に業種があります。業種とは事業の分野を指し、業界を細分化したものです。
例えば、金融といえば業界のことで、その中から銀行を取り出すと業種となります。総務省の公式サイトを見れば、業界が大分類で、業種が中分類にあたると理解できるでしょう。
就活の業界は大きく8つに分類される
業界を細かく分けると30種類以上ありますが、就活では以下の8つに大別して考えるのが一般的です。
メーカー
商社
小売
金融
サービス
ソフトウェア・通信
マスコミ
官公庁・公社・団体
ここからは、それぞれの業界を詳しく見ていきましょう。
1. メーカー
メーカーとはモノづくりをする業界を指し、製造業とも呼ばれます。一口にメーカー業界といっても、製品を企画・開発し、製造・販売するため、マーケティングや営業など職種は多岐にわたります。また、取り扱う製品も自動車・鉄鋼・食品・アパレルなど幅広い分野があり、BtoB(企業向け)とBtoC(消費者向け)に分けられます。
例えば、自動車メーカーはトヨタやホンダ、食品メーカーは明治やキリンなどが代表的です。メーカー企業に対して、古い印象を持たれる方もいらっしゃるかと思いますが、研究開発が盛んで、技術革新が求められているのが特徴です。
ものづくりに関心がある人や、新しい技術を追求するのが好きな人に向いている業界だと言えるでしょう。
2. 商社
商社とは卸売りをする業界のことで、国内外の企業間で商品を売買し、流通を支える業界です。エネルギーや食品、金属など、さまざまな分野の商品やサービスを取り扱う総合商社(三菱商事、伊藤忠商事など)と、特定分野の商品やサービスを取り扱う専門商社(メタルワン、日鉄物産など)に分けられます。
商社はメーカーから仕入れた商品を小売店に販売するなど、企業間取引の仲介役を担うことで手数料を得て収益を上げる仕組みです。商社の仕事は、単なる「モノの仲介」ではなく、新規事業の開発や投資、物流の管理も行い、海外企業との取引も多いため、語学力や交渉力が求められます。
そのため、こうした対人スキルに強みを持っていたり、グローバルな視点を持っていたりする人に向いている業界です。
3. 小売
小売業界とはモノの販売を担う業界で、消費者に直接商品を販売する業界です。スーパーやコンビニ、百貨店などが小売業界に属しています。企業によって販売規模が異なりますが、普段から利用する機会が多いことから身近に感じやすい業界といえるでしょう。代表的な企業では、イオン、セブン&アイ、楽天などが挙げられます。
小売業界の特徴は、消費者のニーズを的確に捉えることが重要である点です。商品を仕入れるバイヤーの役割や、店舗の運営、マーケティング、物流の管理など、幅広い仕事があります。最近では、EC(電子商取引)の拡大やデジタルマーケティングの活用が進んでおり、ITスキルも求められるようになっています。
トレンドの変化に敏感な人や、接客が好きで人と関わるのが得意な人、店舗運営や経営に興味がある人に向いている業界と言えるでしょう。
4. 金融
金融業界とは、お金を動かすことで利益を得ている業界です。金融といえば銀行のイメージが強くありますが、株券売買や企業の買収・合併の仲介などを行う証券や、生命保険や損保保険などを取り扱う保険会社なども金融業界にあたります。それぞれ、三菱UFJ銀行、野村證券、日本生命などが代表企業です。
銀行業務では、個人や企業に融資を行ったり、資産を管理したりする役割があります。証券会社では、株式や債券の取引を仲介し、投資家の資産運用をサポートします。保険会社では、リスクを管理し、万が一の事態に備える商品を提供します。
経済の動向に影響を受けやすく、数字に強い人や、リスク管理能力のある人が活躍しやすい業界です。
5. サービス
サービス業界とは、消費者が求める形のないサービスを提供することで利益を得る業界です。小売業界と混同されがちですが、小売業界がモノの販売を行うのに対し、サービス業界では目に見えないサービスを提供します。サービス業界には飲食、ホテル、教育、コンサルティングなどが含まれ、代表企業としては、マクドナルド、リクルート、星野リゾートなどがあります。
一口にサービス業界といっても、個人にサービスを提供するBtoC、企業にサービスを提供するBtoB、個人にも企業にもサービスを提供するBtoBtoCなど、販売先はさまざまです。
サービス業の特徴は、顧客との接点が多く、対応力やホスピタリティ精神が求められる点です。例えば、コンサルティング業界では、企業の課題を分析し、解決策を提案する仕事が中心になります。一方、飲食業界では、店舗運営や商品開発が重要になります。
人と関わるのが好きな人や、顧客の満足度を高める仕事に興味がある人に向いています。
6. ソフトウェア・通信
ソフトウェア・通信業界とは、情報の伝達や処理などに関するサービス、例えばIT技術を活用したシステム開発やインフラ整備を提供する業界です。スマホアプリやシステムなどを開発するのがソフトウェアで、通信はパソコンの回線業者やプロバイダなどがあたります。代表企業には、NTT、ソフトバンク、富士通などがあります。
ソフトウェア業界では、アプリやシステムの開発を行い、企業の業務効率化や新しいサービスの提供をサポートします。通信業界では、インターネットやモバイル通信のインフラを支える仕事が中心になります。近年は、クラウド技術やAI、DX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されています。
技術に対する知識であったり、常に新しい技術を学び続ける姿勢であったりが求められます。理系の割合が高い業界ではありますが、文系学生が多数派の企業も存在します。
7. マスコミ
マスコミ業界とは、世の中の情報を広める仕事を担う業界です。さまざまなメディアを通して情報を伝える広告、雑誌や単行本などの発行・出版を行う出版社、映像や音声で情報を広めるテレビ業界などがあり、発信する情報は企業によって異なります。代表的な企業には、日本テレビ、講談社、電通などがあります。
マスコミ業界の特徴は、情報収集力や発信力、企画力が求められる点です。新聞社や出版社では記事の執筆や編集が主な業務となり、テレビ業界では番組制作や広告営業の仕事があります。デジタル化が進む中、Webメディアの重要性が増しており、SNSや動画コンテンツを活用したマーケティングも注目されています。
情報発信に興味がある人や、流行に敏感な人、クリエイティブな仕事をしたい人に向いている業界です。
8. 官公庁・公社・団体
官公庁・公社・団体とは、民間ではできない公的な事業を担う業界です。国や地方自治体などが提供するサービスは、官公庁・公社・団体を通して提供されます。官公庁・公社・団体の例を挙げると、市区町村の役場や学校、病院などがあり、名称に国立・県立・市立とついているものはこの業界に属するものです。
官公庁の仕事は、法律や政策の策定、公共サービスの提供、国民生活のサポートなど多岐にわたります。公社や団体では、インフラの管理や地域活性化の事業が中心となります。安定性が高い一方で、社会貢献の意識が求められる業界です。
公共の利益を考え、広い視野を持って働きたい人に向いています。
就活の業界の選び方は大きく三つある

就活の8業界を紹介しましたが、自分に合った業界が分からず悩んでいる就活生もいるでしょう。そこで、ここからは就活の業界の選び方を3つ紹介します。自分に合ったやり方を選び、実践してみましょう。
自分がやりたいことから考える
自分がどんな仕事をしたいかを最初に考え、その仕事がどの業界に存在するかを探る方法です。例えば、人を喜ばせるようなモノを作りたいのならメーカー業界、人を幸せにできるような空間を目に見えない形で提供したいのならサービス業界が考えられます。自分が抱く生み出したい価値を明確にすることで、志望する業界が絞りやすくなります。
自分の強みから考える
自分が得意とすることを活かせる業界を考える方法です。たとえば、数字やデータを扱うのが得意なら金融業界やIT業界が適しているかもしれません。自分の強みが発揮できる業界を選べば、入社難易度が格段に下がるだけでなく、入社後に活躍できる可能性が大幅に上昇します。
自分の強みを理解して、それを最大限に発揮できる業界を選びましょう。
タイプ別適職診断を使う
就活の業界選びを始めるなら、最初の一歩として自己分析を行いましょう。自己分析は自分の人生の「目的」と「手段」を知るために必要な作業であり、自分がやりたい仕事や向いている仕事が明らかになります。
自己分析のやり方は複数ありますが、なかでも簡単に取り組めるのが自己分析ツールの活用です。キミスカは自己分析ツール『適性検査』を提供しており、キミスカへの無料登録を済ませるだけで受験できます。80問に回答すると自分がどのようなタイプの人間なのか知ることができるので、ぜひ活用してみてください。
就活生が気をつけたい業界選びの注意点
就活の業界選びでは、いくつか気をつけたいことがあります。以下に業界選びの注意点を3つ挙げたので、それぞれ確認していきましょう。
業界を絞りすぎない
自己分析の結果、自分には特定の業界が合っていると思い込み、早い段階から業界を絞りすぎるのはおすすめできません。自己分析はあくまでも自分の適性を把握する作業であり、あなたの可能性を奪ったり、狭めたりするものであってはいけないのです。
ある程度業界を絞ることは大切ですが、「自分には向いていないから」「この仕事しかできないから」というように、ネガティブな考えで業界を絞りすぎるのはよくありません。
業界をまたぐ企業がある
業界研究をしていると、複数の業界をまたいでいる企業があることに気付く就活生もいるでしょう。とくにIT系の企業は業界の区別がなくなってきており、いくつかの業界をまたぐ企業が増えています。
業界をまたぐ企業に入社した場合、想像とは違う仕事を任されることがあるので注意が必要です。入社後のミスマッチを防止する意味でも、業界研究を進めた後は企業研究も欠かせません。
悩んだ時は知り合いに相談する
どうしても業界を決められない場合は、知り合いに相談するのも一つの手です。第三者に相談することで、自分に合う業界が見えてくる場合も少なくありません。
家族や友人に相談するのもよいですが、大学のOB・OGやアルバイト先の社員など、あなたについて詳しく知らない身近な社会人に相談してみるのもおすすめです。
業界分析のやり方

業界全体の大まかな概要は掴めたと思います。次に、興味のある一つ一つの業界を詳しく知る必要があります。しかし、何から始めれば良いのか、中々分かりませんよね。そこで、このパートでは誰でもできる業界分析のやり方について解説します。
1. 業界の概要を理解する
業界分析の最初のステップは、各業界の基本的な特徴を理解することです。例えば、業界の市場規模、成長性、競争環境、主要プレイヤーなど、業界全体の傾向を把握することが求められます。これにより、その業界が自分に合うかどうかを判断するための基礎を作ることができます。
この記事を読んでいる皆さんは、このステップは半分クリアしたようなものですね。
具体的な方法としては、
- 業界レポートを活用する:業界団体や調査機関が発行している業界レポートを読んで、市場規模や成長率を把握しましょう。
- 業界ニュースをフォローする:業界の最新の動向やトレンドを知るために、ニュースサイトや業界専門のメディアを定期的にチェックします。
2. 業界の将来性を評価する
業界が今後どのように成長するか、または変化するかを見極めることは非常に重要です。将来性のある業界で働くことで、キャリアの安定性や成長のチャンスを得られる可能性が高くなります。また、将来性が無いと言われているような業界であっても、自分がその業界でどのように振る舞いたいかを伝えるのが、面接やESにおいては非常に重要です。
具体的な方法としては、
- 市場トレンドの予測:業界の専門家やアナリストによる予測を参考にして、業界の将来像を描きます。
- 技術革新や規制の変化をチェックする:新しい技術の進展や規制の変更が業界にどのような影響を与えるかを調べます。たとえば、AIやIoT技術の進化が特定の業界を変える可能性があります。
3. 求人情報やインターンシップを活用して業界を体験する
実際に業界を体験することも、業界分析において非常に効果的な方法です。インターンシップやアルバイト、ボランティアなどを通じて、業界の実情を直接感じることができます。
具体的な方法としては、
- 業界関連のインターンシップに参加する:インターンシップに参加することで、その業界の実際の仕事を体験できます。実際に働いてみることで、業界の文化や働き方を肌で感じることができ、業界分析がより具体的になります。
- 業界セミナーやイベントに参加する:業界関連のセミナーやイベントに参加することで、業界の動向やネットワーキングの機会を得ることができます。
この方法は「就活生だけが」できる貴重な体験です。就活期間を無駄なく、有意義に過ごしましょう。
詳しいやり方は以下の記事を参照してみてください。
8つの業界から就活生に合う業界を見つけよう
就活の業界は8つに大別され、それぞれ特徴が異なります。業界によって仕事内容はもちろん、求められるスキルや社員の雰囲気にも違いがあるので、まずは自己分析をして自分に合う業界を探してみてください。
ただし、早い段階から業界を絞りすぎるのは避けたいところです。自分自身の可能性を奪ってしまうことのないように、複数の業界を見て視野を広げましょう。

