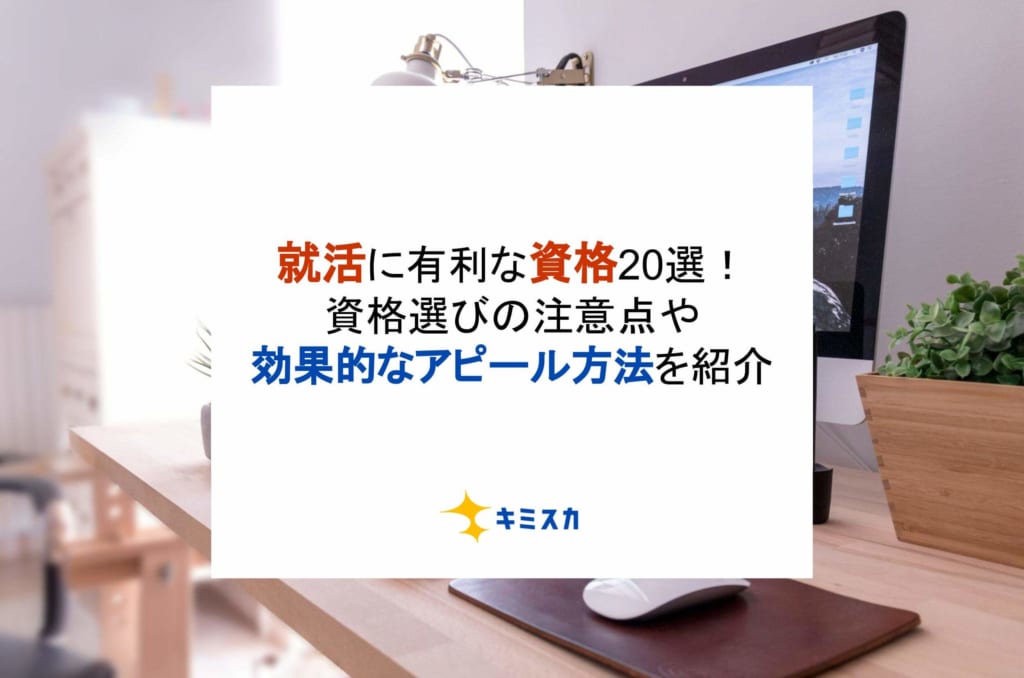
就活では自己PRや志望動機など、自分のことをアピールする機会が多々あります。そこでなんらかの資格を有していることをアピールできれば、就活に有利に働くこともめずらしくありません。
そこで本記事では、就活に有利になる資格をまとめて紹介します。取得する資格選びの注意点や、エントリーシートや面接でアピールする方法も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
就活で資格が必要になることは少ない
結論からいうと、就活で資格を必須とする企業はほとんどありません。そのため資格を有していないからといって、焦る必要はないでしょう。
ただし、一部の業界・企業では資格の取得や免許の所持を求められるケースがあります。例えば、医療関係であれば専門資格を有している学生が有利になり、運輸・輸送関係であれば運転免許が必要です。
そのほかにも、TOEICの点数が企業の定めた基準に満たしていない場合は入社できない場合もあるので、志望企業が決まっているのであれば早い時期から募集要項を確認しておきましょう。
就活で持っていると有利な資格10選【一般編】
就活では資格を有していなくても問題ありませんが、資格があれば自分の能力をアピールできるだけでなく、初任給が変わる場合もあります。就活を少しでも有利に進めたいなら、今のうちに資格を取得しておくのがおすすめです。
この章では、就活で有利になる一般的な資格を10個選出しましたので、ぜひ参考にしてみてください。

普通自動車第一種運転免許
普通自動車第一種運転免許の概要
普通自動車第一種運転免許は、いわゆる「運転免許証」です。この資格があれば、車を運転することができ、営業や外回りの業務を担当する際に非常に役立ちます。
なぜ就活に有利?
多くの企業では営業職や運転を伴う仕事の際に、入社時に運転免許を持っていることを前提にしている場合があります。特に営業職では、外回りや顧客訪問に車を使うことが多く、運転免許の有無は大きなポイントになります。
普通自動車第一種運転免許を持っていると、こんな企業に有利
特に営業職をはじめとする、顧客訪問やフィールドワークが求められる職種では、運転免許が必須となる場合があります。例えば、以下のような業界や企業で有利です
- 営業職(特に外回り営業)
- 物流業界(配送業務や運転手)
- 建設業界(現場での移動が頻繁)
- 不動産業界(物件案内時に車を使うことがある)
運輸・運送業や営業職などは、普通自動車第一種運転免許が必須となりことも多いです。教習所に通う場合は免許取得までに数ヶ月かかるので、早めに準備するのがおすすめです。
普通自動車第一種運転免許の取得に必要な時間
試験は筆記と実技があり、短期間で取得を目指す合宿であれば最短2週間で免許取得が可能です。通いで学業と並行して行う場合、2、3か月ほどになることが多いです。
| 目安 | |
| 勉強時間 | 2~3ヶ月最短で2週間程度) |
| 費用 | 20~30万円前後 |
ITパスポート
ITパスポートの概要
ITパスポートは、IT(情報技術)の基本的な知識を証明する国家資格です。IT業界や技術職に限らず、ビジネス全般で必要とされる基礎的なITスキルを学ぶことができるため、ITを活用するすべての社会人や学生が備えておくべき国家資格です。試験内容には、IT基礎知識、ネットワーク、セキュリティ、システム開発、マネジメントなどが含まれます。
なぜ就活に有利?
今の時代、どんな職種でもPCやIT技術を使用する機会が増えており、ITパスポートを持っていることは、自分のPCスキルやITリテラシーの高さを証明できるという点で非常に有利です。
また、非IT系の職種でも役立つ資格です。例えば、営業職であればITを活用した営業ツールの使用が求められることがありますし、事務職でもデータ処理や資料作成にITスキルが必須となります。この資格を持っていれば、ITに対する理解度を企業にアピールできるため、採用担当者に好印象を与えることができます。
ITパスポート資格を持っていると、こんな企業に有利
ITパスポートを持っていると、特に以下のような業界や職種で有利です。
- IT業界:システムエンジニアやネットワークエンジニア、ITコンサルタントなど、ITスキルが求められる職種では必須の資格です。IT業界の企業では、基本的なIT知識を証明する資格として評価されます。
- 金融業界:最近では、金融業界でもデジタル化が進んでおり、金融システムを扱う場面が増えています。ITパスポートを持っていることで、IT基盤への理解が評価されます。
- 製造業:ITを活用した業務が一般的になった現在、製造業などでも基本的なIT知識が求められています。例えば、業務管理システムや在庫管理ソフトの操作にITスキルが必要となるため、ITパスポートを持っていると有利です。
ITパスポートの取得に必要な時間
資格試験自体の難易度が比較的低く、短期間で取得可能です。なので、就活を始める前に取得しておくと、アピールポイントとして非常に役立ちます。
| 目安 | |
| 勉強時間 | 100〜200時間 |
| 費用 | 7,500円 |
MOS
MOSの概要
MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)とは、マイクロソフト社が主催するMicrosoft Office製品の知識・操作スキルを評価・証明する資格試験です。最近では業界・企業問わずパソコンの知識や技術が求められるので、積極的に取得しておきたい資格の一つといえるでしょう。
MOS資格試験の科目は、「Word」「Excel」「PowerPoint」「Access」「Outlook」の5科目があり、さらに一般レベルと上級レベル(エキスパート)で異なるテストが設けられています。
なぜ就活に有利?
実際、ExcelやPowerPointを利用する機会が多い職種であれば、そのすべての場面において重宝されるわけです。そのため、特定の業界に役立つ専門性というよりも、日常的な業務における安心感を証明することができます。
MOSを持っていると、こんな企業に有利
MOS(Microsoft Office Specialist)はPCスキルを証明する資格で、事務職や営業職、IT系職種など、幅広い業界で活かせる資格です。特に、データ処理や文書作成を多く行う職種では、MOSの資格があると即戦力として期待されることが多いです。資格取得は比較的短期間で可能なので、就活前に取っておくと強い武器になります。
- 事務職や営業職:WordやExcelのスキルは、どんな企業でも必須となります。特にデータ分析や資料作成を行う仕事では、MOSの資格を持っていると、即戦力として認められることが多いです。
- IT業界:IT系の仕事では、Office製品を使ったデータ管理やレポート作成が必須となるため、MOSの資格があると非常に有利です。
MOSの取得に必要な時間
MOSスペシャリストの勉強時間は20~40時間が目安 · MOSエキスパートの勉強時間は50~80時間が目安となっています。ただ、合格率は平均して70%程と言われており、パソコンを日常的に利用している人は、この勉強時間よりも少ない時間で合格を狙うことができるでしょう。
| 目安 | |
| 勉強時間 | 一般レベル:1科目20〜40時間、上級レベル:1科目50〜80時間 |
| 費用 | 1科目1万円前後(学割制度あり) |
秘書検定
秘書検定の概要
秘書検定とは、公益財団法人実務技能検定協会が実施している検定で、社会人が備えておくべき基本的な常識が問われます。具体的な試験内容では、ビジネスマナーや電話対応、文書作成、スケジュール管理、接遇マナーなど、秘書として必要な実務的な能力が求められます。試験は1級、準1級、2級、3級の4つのレベルに分かれており、企業の規模や業種に応じた対応力を高めるために、役立つ資格です。
なぜ就活に有利?
秘書検定を持っていることは、単に秘書職だけでなく、ビジネスマナーがしっかりしていることを示す証拠となります。多くの企業が電話対応や来客対応、社内外の調整役など、ビジネスパーソンとしての基本的なマナーを重視しており、秘書検定はその能力を証明できる資格です。
また、秘書検定は単に知識やスキルを証明するだけでなく、プレッシャー下での対応力や優れたコミュニケーション能力、時間管理能力なども求められるため、どの職種でも役立つ汎用的なスキルを証明することができます。
秘書検定を持っていると、こんな企業に有利
秘書検定は、以下の業界や職種で特に役立ちます。
- 総務・人事:企業のバックオフィスを支える総務や人事職では、秘書検定を持っていると来客対応や電話対応、スケジュール管理がスムーズにできると評価されます。
- 営業職:営業職では、クライアントとのやりとりが多く、マナーや時間管理が重要です。秘書検定を取得しておくことで、接遇や調整役としての能力をアピールでき、商談をスムーズに進めることができます。
- 金融業界:特に企業の上層部との調整や書類の管理を行うことが多いため、秘書検定を持っていると、信頼性や管理能力が高く評価される傾向があります。
秘書検定の取得に必要な時間
| 目安 | |
| 勉強時間 | 30~60時間(2級の場合) |
| 費用 | 5,200円(2級の場合) |

TOEIC
TOEICの概要
TOEICは、英語を使用した国際的なコミュニケーション能力を測定するための試験で、主にビジネス英語に焦点を当てています。試験は、リスニングとリーディングの2つのセクションで構成され、各セクションともに100問の問題があります。スコアは10点から990点の範囲で、各セクションのリスニングとリーディングがそれぞれ495点満点です。TOEICは英語力の証明として広く認知されており、特にグローバル企業や英語を使った業務に携わる企業で重視されています。
外資系企業のなかにはTOEICの点数の基準を設けている企業があり、その点数に満たない場合は選考を受けられません。
合格点こそありませんが、スコアによって受験者の英語能力が評価され、就職活動や昇進、異動などに影響を与えることがあります。
なぜ就活に有利?
TOEICのスコアは、英語力の証明として企業に広く認知されています。特に、国際的なビジネスを展開している企業では、英語を使ったコミュニケーション能力が非常に重要視されます。海外のクライアントとのやり取りや、海外出張、英語でのプレゼンテーションなどが求められる職場では、TOEICのスコアを持っていると非常に有利になります。
また、TOEICは点数をスコアで表すため、自分の英語力の具体的な証拠を示すことができ、採用担当者に分かりやすくアピールできます。企業が求める英語力の基準に応じて、高得点を取得しておくことが有利となり、就職活動の際に他の候補者と差別化を図ることができます。
TOEICを持っていると、こんな企業に有利
TOEICを持っていると、特に以下の業界や職種で有利です。
- グローバル企業:多国籍企業や海外支社がある企業では、TOEICのスコアが高いほど有利になります。英語を用いたコミュニケーションが仕事の一部であるため、業務に直結します。
- 商社・金融業界:海外との取引が多い商社や金融業界では、国際的な取引や海外の市場とやりとりをするため、TOEICのスコアが求められることが多いです。特に国際業務に携わる部署では、高得点が期待されます。
- 観光業や教育業界:外国人の顧客や生徒とのコミュニケーションが求められる観光業や教育業界では、TOEICのスコアが有利に働くことがあります。英語の指導や接客を行う場合にも、高い英語力を証明するためにスコアを活用できます。
スコア別の難易度と業務で求められるスコア
TOEICのスコアは、企業が求める英語力を示す指標となりますが、スコアによって業務で求められる能力も異なります。
- 500〜600点(初心者〜中級者)
このスコア帯は、基本的な英会話や読み書きができるレベルです。英語を日常的に使う業務には難しいかもしれませんが、カスタマーサポートや一般的な事務作業など、簡単な英語が使われる業務では十分に役立ちます。
企業例:一般事務やサポート業務、英語を使う機会が少ない企業。 - 600〜700点(中級者)
このスコア帯では、ビジネスで使う基本的な英語を理解し、簡単な会話やメールのやり取りができるレベルです。英語での簡単な会議や、海外の顧客とのやり取りなども可能になるため、営業職や事務職では十分活用できるスコアです。
企業例:営業職(顧客対応)、カスタマーサポート、国際的なチームとのやり取りがある職種。 - 700〜800点(中級上〜上級者)
このスコア帯は、会話がスムーズにでき、ビジネスでのやり取りにも問題なく対応できるレベルです。英語でのプレゼンテーションや会議に参加し、英語で複雑な議論ができるようになります。
企業例:海外営業、マーケティング、海外進出している企業、IT企業の国際部門など。 -
800〜900点(上級者)
ここまでのスコアを取ると、英語を母国語とする相手との会話や交渉をスムーズに行うことができるレベルになります。英語でのプレゼンテーションや会議も難なくこなし、複雑なビジネス交渉にも対応可能です。国際的なプロジェクトに関わる業務や、海外赴任を視野に入れた業務で非常に強みとなります。
企業例:グローバル企業の経営企画部門、海外取引先との商談が多い営業職、マーケティング部門、IT企業のプロジェクトマネージャーなど。 -
900点以上(上級者〜超上級者)
900点以上を取得することで、英語での高度なビジネス交渉や複雑なプレゼンテーションを完璧にこなせるレベルになります。このスコアは、国際的なリーダーシップや海外進出している企業での幹部候補としても大いにアピールでき、非常に重宝されます。
企業例:グローバル企業の役員、海外営業部門、プロジェクトリーダー、海外法人の管理職など。
TOEICの取得に必要な時間
| 目安 | |
| 勉強時間 | 100〜600時間と、求めるスコアによって大きく異なる |
| 費用 | 7,810円 |
簿記(日商簿記検定)
簿記(日商簿記検定)の概要
簿記とは、日々の取引を帳簿に記入して決算書を作成する作業を指します。簿記(日商簿記検定)は日本商工会議所が実施する資格試験であり、特に日商簿記がよく知られており、1級、2級、3級の3つの級に分かれています。経理や事務などの職種を志望している場合は3級以上を取得するのがおすすめです。
なぜ就活に有利?
簿記は経理・財務・会計などの職種に直結するだけでなく、ビジネス全般に役立つスキルです。
例えば、企業の会計業務を担う経理や財務部門では簿記の知識が必須です。特に簿記2級を持っていると、実務で活かせる知識があると判断され、評価が上がります。こうした財務知識は売上や利益、コスト管理の視点を持たせるため、営業職や企画職でも役立ちます。特に数字を扱う機会の多い職種では「データを分析できる力」として評価されることがあります。
このように汎用性の高い簿記は、実際の業務に直結する知識を学ぶため、企業側も「即戦力として活躍できる可能性が高い」と考えます。
簿記資格を持っていると、こんな企業に有利
- 経理・財務・会計関連の職種:業界を問わず、多くの 企業の資金管理や決算業務を担うため、簿記の知識はほぼ必須です。
- 銀行・証券などの金融業界:企業の財務諸表を分析し、融資や投資の判断をする業務では、簿記の知識が大いに役立ちます。
スコア別の難易度と業務で求められるスコア
-
簿記3級(初級レベル)
業務レベル:事務職や営業職で役立つ基礎知識
企業の基本的な取引の流れや帳簿のつけ方を理解できる。経理以外の職種でも「最低限の会計知識がある」と評価されることでしょう。 -
簿記2級(実務レベル)
業務レベル:中小企業の経理担当・金融業界・営業職・管理部門
仕訳の処理や決算書の作成ができるレベル。中小企業の経理業務なら、簿記2級があれば十分対応可能。金融業界の志望者も持っておくと有利。 -
簿記1級(上級レベル)
業務レベル:大企業の経理・財務部門・公認会計士・税理士の基礎
連結決算や税務計算など、会計の専門知識が必要になります。簿記1級を持っていれば、大企業の経理部門や会計系の専門職を目指せます。
簿記の取得に必要な時間
簿記の学習時間は、目指す級によって大きく変わります。
-
簿記3級:50〜100時間(1〜2ヶ月)
毎日1〜2時間の勉強で2ヶ月ほどで合格可能。独学でも十分対応できますが、試験対策用の問題集を解くのがポイントです。 -
簿記2級:150〜200時間(3〜4ヶ月)
仕訳や財務諸表の作成が必要になります。独学も可能だが、効率よく学ぶなら通信講座やオンラインスクールを活用するのもおすすめ。 -
簿記1級:300〜500時間(6ヶ月〜1年)
難易度が一気に上がり、試験範囲も広いため、独学ではハードルが高い。専門学校やオンライン講座を活用しながら、計画的に学習を進めることが吉でしょう。
| 目安 | |
| 勉強時間 | 150〜200時間(簿記二級の場合) |
| 費用 | 4,720円(2級) |
FP技能検定
FP技能検定の概要
そもそもFPとはファイナンシャルプランナーの略語であり、相談者の目標を叶えるために資金計画を立て、経済的な側面からサポートする専門家です。
FP技能検定(ファイナンシャル・プランニング技能検定)は、お金に関する総合的な知識を証明する国家資格です。税金・保険・年金・投資・不動産・相続など、金融に関する幅広い分野の知識を学ぶことができるため、ファイナンシャルプランナーの資格は金融業界で有利に働くだけでなく、今後の人生における資産運用や家計管理でも生かせるでしょう。
また、簿記と同様、FP技能検定は、3級・2級・1級の3つのレベルに分かれており、それぞれ習得できる知識の深さが異なります。
なぜ就活に有利?
FP技能検定が就活で評価される理由は、金融知識の習得を証明できることと、論理的思考力や数値を扱う能力をアピールできることにあります。
FPの資格を持っていると、こんな企業に有利
FP技能検定は、以下のような業界・職種で有利になります。
- 銀行・証券・保険(金融業界)
資産運用・投資・保険プランの提案に役立ちます。 - 不動産業界(住宅ローン・不動産投資コンサル)
住宅ローン・相続・資産運用に関する知識が活かせます。 - 経理・財務・管理部門(一般企業)
企業のコスト管理や税務業務に貢献できます。
スコア別の難易度と業務で求められるスコア
-
FP3級(基礎レベル)
業務レベル:個人の資産管理・金融リテラシー向上
金融知識の礎となり、自己学習の姿勢をアピールすることができます。 -
FP2級(実務レベル)
業務レベル:金融・不動産・保険業界の営業職、経理・財務部門で活用
実務に活かせるため、金融・不動産業界を志望する人にはおすすめ。FP2級を一つの基準として設けている企業も存在しています。 -
FP1級(専門レベル)
業務レベル:コンサルタント・企業の財務戦略担当向け
取得している新卒は少ないが、持っていると高評価。ただし、経験者向けの資格という側面が強いです。
FP技能検定の取得に必要な時間
FP技能検定の取得に必要な学習時間は以下の通りです。
- FP3級:50〜100時間(1〜2ヶ月)
テキスト学習+過去問演習で独学でも十分合格可能。 - FP2級:150〜300時間(3〜6ヶ月)
3級よりも範囲が広くなるため、スクールや通信講座を活用すると効率的。 - FP1級:300〜500時間(6ヶ月〜1年)
難易度が高いため、独学よりも専門講座の受講が推奨される。
| 目安 | |
| 勉強時間 | 50~100時間(3級の場合) |
| 費用 | 8,000円(3級の場合) |

日経TEST
日経TESTの概要
このテストでは、単なる知識の暗記ではなく、視野の広さ・視座の高さ・視点の鋭さを客観的に測定する試験であり、経済・金融・企業経営に関する理解力や、データをもとに考え抜く力が問われます。そのため、取得しておけばエントリーシートや面接なでビジネスに必要な幅広い知識と汎用スキルをアピールできます。
なぜ就活に有利?
日経TESTが就活で評価される理由は、ビジネスの理解力と論理的思考力を証明できるからです。特に以下の2つのポイントで有利になります。
-
経済・金融の知識を持っている証明になる
日経TESTは、経済の基礎知識から企業戦略・マーケット分析まで幅広く問われます。そのため「日経新聞を読んでいます」と言うだけでなく、スコアという客観的な数値で証明できるのが強みです。
-
思考力や情報収集力のアピールになる
単なる暗記ではなく、データをもとに論理的に考える問題が多いことから、「ビジネスの本質を見抜く力がある」と企業に評価されやすいです。
この資格を持っていると、こんな企業に有利
日経TESTのスコアを持っていると、特に以下の業界・職種で有利になります。
- 金融業界(銀行・証券・保険)
経済への感度や分析力は、業務に直結します。 - コンサルティング業界
市場分析・企業戦略の理解度が求められるため、クライアントの課題解決には経済・ビジネスの知識が不可欠です。 - マスコミ・出版(経済誌・新聞社など)
日経新聞をはじめ、ビジネスニュースを扱う企業では評価されやすいです。
スコア別の難易度と業務で求められるレベル
日経TESTは合否の概念ではなく、1,000点満点のスコアで計られます。
- 500点以下:基礎レベル
経済ニュースに触れたことが少ない人向け。強みと言えるほどのビジネス知識はまだ十分ではない。 - 600点以上:実務基礎レベル
経済・ビジネスの基本的な知識があり、業務に活かせるレベル。 - 700点以上:応用レベル(就活でアピールしやすい)
市場動向を的確に理解し、経済ニュースを深く読み解ける。 - 800点以上:高度レベル(トップレベルの評価)
企業戦略や経済の仕組みを本質的に理解しており、実務で高く評価される。
日経TESTの取得に必要な時間
日経TESTのスコアを上げるためには、経済ニュースの理解と問題演習が必要です。
ただ、日頃からニュースを見る習慣や素養があるかどうかによって、必要な勉強時間が大きく左右されることは念頭に置いておきましょう。
| 目安 | |
| 勉強時間 | 30時間(スコア500を目指す場合) |
| 費用 | 6,600円 |
宅地建物取引士(宅建)
資格の概要
宅建の略称で知られる宅地建物取引士は、不動産取引における専門家を指す国家資格です。年間20万人が受験していますが、合格率は例年15~17%台と低く、ハイレベルな資格であることは間違いありません。
宅地建物取引士の資格は、不動産業界や金融業界で役立ちます。特に、不動産取引には法律や税制、契約の知識が必要であり、宅建士の資格がないとできない独占業務もあります。また、住宅メーカーなどの建築業でも求められる資格の一つです。
なぜ就活に有利?
宅建は、不動産業界を中心に幅広い業界で評価される資格です。不動産に関する業務、例えば不動産担保ローンや不動産投資、土地開発など、すべてにこの宅建は有効に働きます。
また、宅建の勉強を通じて、民法・契約法・税制などの法的知識を身につけられることも評価される要因の一つです。法務や経理などの職種でも「法律に強い人材」として評価される。
その資格を持っていると、こんな企業に有利
-
不動産業界(ディベロッパー・仲介・管理)
ほぼ全ての不動産企業で評価され、入社後には必須資格として扱われる。宅建士の資格を持っていれば、新卒でも即戦力として評価される。 -
金融業界(銀行・証券・保険)
不動産担保ローン、不動産投資ファンドなどに関わる部門で活かせる。 -
建設・ハウスメーカー
土地の売買や不動産開発を行う企業では、宅建の知識が役立つ。
宅建の取得に必要な時間
宅建の勉強時間の目安は、300〜500時間程度とされています。
-
勉強期間
6ヶ月〜1年かけてコツコツ勉強するのが一般的。特に民法の分野が難しく、理解に時間がかかる。予備校・通信講座を活用することで、 3〜6ヶ月の短期集中で合格を目指すことも可能です。 -
合格率は15〜17%程度
→ 例年、20万人以上が受験し、合格者は3万人ほど。しっかり対策しないと合格は難しいが、説明の通り国家資格としての価値は高いです。
| 目安 | |
| 勉強時間 | 300時間〜500時間 |
| 費用 | 8,200円 |
社会保険労務士(社労士)
社会保険労務士の概要
社労士の略称で知られる社会保険労務士は、社会保険や労働関連の法律の専門家を指す国家資格です。主に企業の労務管理をサポートし、給与計算、労働契約書の作成、社会保険手続き、労働問題の解決支援を行います。社会保険労務士は人事総務部門で役立つ資格であり、最終的に独立して事務所を開業する人も少なくありません。
試験は10科目で構成され、それぞれに合格基準点が設けられていることから、ムラのない点数を取る必要があります。
なぜ就活に有利?
| 目安 | |
| 勉強時間 | 700時間 |
| 費用 | 15,000円 |
就活で持っていると有利な資格10選【独占業務編】
特定の資格を持っていなければできない業務を独占業務といい、独占業務を志望する場合は資格取得が必須となります。以下に独占業務の例として10資格挙げたので、確認してみましょう。
- 司法書士
- 公認会計士
- 税理士
- 医師
- 不動産鑑定士
- 行政書士
- 通関士
- 建築士
- 弁護士
- 弁理士
取得する資格を選ぶ時の注意点
ここからは、資格取得を目指す就活生に気をつけてほしいポイントを2つ紹介します。取得資格を選ぶ前に、必ず確認しておきましょう。
目的が就活のためになっていないか
資格は就活で有利に働くことがありますが、就活のために資格を取得するのはおすすめできません。資格はあくまでも就職後やその先の人生を見据えたうえで取得するものであり、就活のエントリーシートや面接でアピールするために取得するのは本末転倒です。
資格を取得する目的や、就活をする理由が分からなくなってしまった学生は、改めて自己分析をしてみてください。
経済的に挑戦可能かどうか
資格の取得には時間だけでなく、お金もかかります。資格紹介の章ではそれぞれの受験費用を紹介しましたが、書籍を購入したり、通信講座を受けたりする場合はより多くの費用が必要です。
とくに中・高レベルの資格取得は独学では難しい場合があるので、必要な費用を把握したうえで取得を検討しましょう。
就活で資格をESや面接でアピールする方法
就活のエントリーシートや面接で資格をアピールする場合は、資格を取得した動機を伝えることでより効果的なアピールとなります。また、資格取得の経験から得られたものや、その資格を入社後どのように活かせるかを示すことも大切です。
資格取得を決意したきっかけを話す
「数ある資格の中から、なぜその資格を取得することを目指したのか?」これはすべての面接官が感じる疑問でしょう。
この時、自分の今までの経験から培った興味であったり、今後やりたいことを実現するための第一歩としてであったりを話すようにしましょう。そうすることで、あなたの価値観やキャリアビジョンが判明し、高い評価を頂けます。
資格取得の過程における困難や工夫を話す
資格の勉強というのは決して生半可なものではありません。そのため取得途中に挫折することも珍しくありません。こうした苦しい時にこそ、あなたらしさが光ります。「こんなつらいことがあったけど、○○を意識して乗り越えることができた。」と話すことで、目標を達成する姿勢をアピールしましょう。
今後、資格をどう活かすかを話す
資格は取得することがゴールではありません。その資格を生かし、どのような目標を達成したいのかが肝心です。自分が成し遂げたいことや企業に貢献できる点を話しましょう。
資格取得した経験をガクチカとして話したい学生は、以下の記事も参考にしてみてください。
なんのために資格を取るのか明確にしておこう
就活で資格が必要になるケースは稀ですが、企業によっては決まった資格や600~700点以上のTOEICの点数が求められることもあります。また、たとえ資格が不要な企業であっても、資格を有していることで就活が有利に進むことも少なくありません。資格の取得を考えている学生は、資格取得の理由を明確にしたうえで資格取得を目指しましょう。
ちなみに、エントリーシートや面接では勉強中の資格をアピールしても構いません。その場合は以下の記事を参考に、「○○を勉強中」と伝えましょう。

