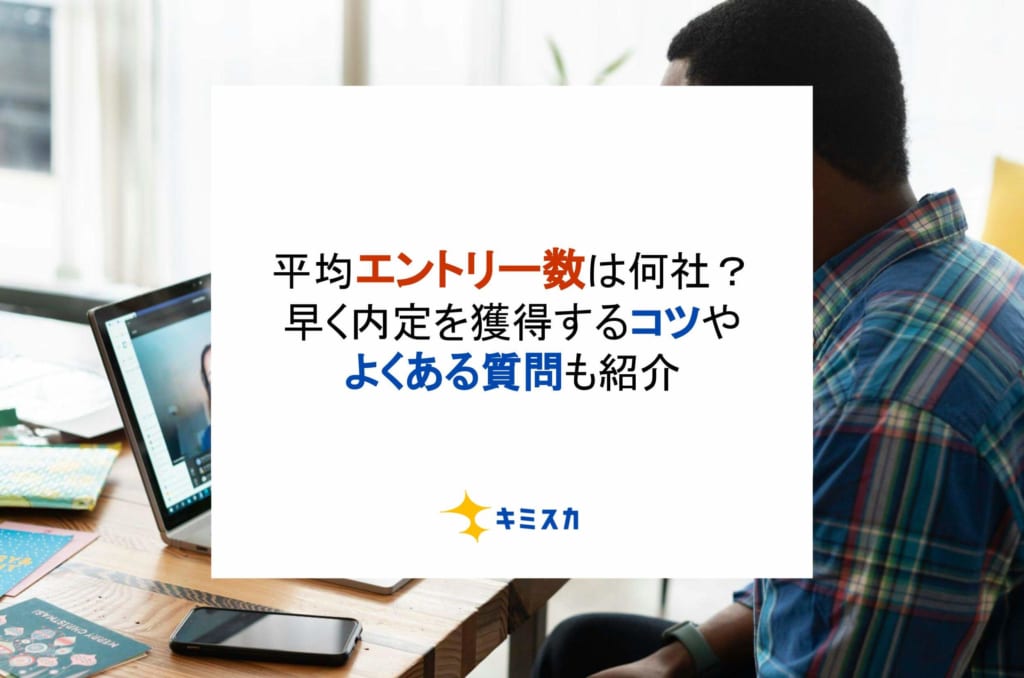
「就活を始めよう!」と思っても、周りから聞こえてくる「エントリー」という言葉の意味がよく分からず、不安に感じていませんか。
「エントリーってなんだろう」「一体いつから、何社くらいエントリーすればいいんだろう…」そんな悩みを抱えている就活生は少なくありません。
この記事を読めば、就活の第一歩であるエントリーの基本から、具体的なやり方、平均社数、注意点まで全てが分かります。エントリーの全体像をしっかり理解して、自信を持って就活をスタートさせましょう!
就活の「エントリー」とは?
就活におけるエントリーとは、簡単に言うと「その企業の選考を受けたいです」という正式な意思表示のことです。
よく似た言葉に「プレエントリー」がありますが、この二つは意味が全く異なります。この違いを理解することが、就活をスムーズに進めるための第一歩です。まずはそれぞれの言葉が持つ意味を正確に把握し、就活のスタートラインに立ちましょう。
プレエントリーとは「興味がある」という意思表示
プレエントリーは、「あなたの企業に少し興味があります」という意思を企業に伝える、意思表示です。
プレエントリーをすると、企業から会社説明会の日程や選考に関する情報が送られてくるようになります。あくまで企業の情報を受け取るための登録なので、プレエントリーをしただけでは選考に進むことはできません。
エントリーとは「選考に参加したい」という意思表示
一方、エントリーは「その企業の選考を受けたいです」という正式な応募手続きを指します。
エントリーを行うと、多くの場合エントリーシート(ES)の提出やWebテストの受験が求められます。企業側も、エントリーした学生を選考希望者として認識し、本格的な選考プロセスへと進んでいきます。プレエントリーが準備運動だとすれば、エントリーは本番の試合への出場登録と考えると良いでしょう。
就活のエントリーはいつから始めるべき?

エントリーをいつ始めるかは、就活全体のスケジュールを左右する非常に重要なポイントです。早すぎても準備不足になりかねませんし、遅すぎるとチャンスを逃してしまう可能性があります。
一般的なエントリー開始時期を把握しつつ、企業ごとの違いも理解しておくことで、計画的に就活を進めることができます。自分の受けたい企業はいつからか、しっかり確認しておきましょう。
一般的なエントリーの開始時期
多くの日系企業が目安としているのが、大学3年生の3月1日です。この日に企業の広報活動が解禁され、多くの就活サイトで一斉にプレエントリーやエントリーの受付が始まります。
そのため、まずは大学3年生の3月を一つの基準として覚えておきましょう。ただし、これはあくまで一般的な目安です。近年は就活の早期化が進んでおり、これより早くから動き出す企業も増えているので注意が必要です。
エントリー時期の業界別例
エントリーの時期は、すべての企業で同じではありません。特に、外資系企業やベンチャー企業は、日系大手企業と比べてかなり早い段階で選考が始まります。
そのため、自分が目指す志望企業のタイプを把握し、それぞれのスケジュールに合わせて早めに情報収集を開始することが、就活を成功させるためのカギとなります。業界や企業ごとの違いを理解しておきましょう。
外資系企業・ベンチャー企業
外資系企業や一部のベンチャー企業では、大学3年生の夏から秋にかけてエントリーが始まるケースが少なくありません。特に、夏休みに開催されるサマーインターンシップが、そのまま早期選考に直結することも多くあります。
これらの企業を志望する場合は他の学生が本格的に動き出す前から、積極的に企業のホームページなどをチェックして機会を逃さないように行動しましょう。
日系大手企業
多くの日系大手企業は、先ほどもお伝えしたように大学3年生の3月以降にエントリーが本格化します。
しかし、この時期から情報収集を始めては手遅れになる可能性もあります。なぜなら、冬に行われるインターンシップなどが、事実上の選考プロセスの一部になっている場合があるからです。「3月からでいいや」と油断せず、秋から冬にかけて企業の動向をしっかりチェックしておきましょう。
就活のエントリー数は平均何社?目安を解説
「エントリーは一体何社くらいすればいいの?」というのは、多くの就活生が抱える共通の悩みです。多すぎても一社ごとの対策が疎かになり、少なすぎても持ち駒がなくなってしまう不安があります。
大切なのは、やみくもに数をこなすのではなく自分に合ったエントリー数を見つけることです。まずは平均的な数値を参考に、自分なりの戦略を考えていきましょう。
文系・理系の平均エントリー数
就職みらい研究所の就職白書2024によると、2024年卒の学生のエントリー社数の平均は、文系で25.0社、理系で18.4社となっています。ただし、これはあくまで平均値です。
業界を広く見ている学生は平均より多くなりますし、早い段階で志望業界を絞っている学生は少なくなる傾向にあります。この平均的な企業数は、自分の立ち位置を考える上での一つの参考にしてください。
エントリー数が多すぎる・少なすぎるデメリット
エントリー数が多すぎると、ESの作成や面接対策が追いつかず、一社一社への準備が不十分になりがちです。
一方で、少なすぎるともし全滅してしまった場合に後からエントリーできる企業が限られてしまうリスクがあります。特に、不採用が続いた時の精神的なダメージは大きく、視野も狭まってしまいがちです。闇雲にエントリー企業を増やすのも、絞りすぎるのも避けるべきでしょう。
自分に合ったエントリー数の見つけ方
自分に合ったエントリー数を見つけるには、質と量のバランスを考えることが大切です。まずは、少しでも興味のある業界や企業をリストアップし、最初は少し広めに20〜30社程度エントリーしてみるのがおすすめです。
就活を進める中で自分の適性や本当にやりたいことが見えてきたら、徐々に本命の企業群に絞っていくという方法がリスクを抑えつつ効率的に進めるコツです。
企業への一般的なエントリー方法

一昔前は就活サイトからのエントリーが主流でしたが、現在はその方法も多様化しています。それぞれの方法にメリットや特徴があるため、それらを理解し、自分に合ったチャネルを複数活用することが、効率的な就活につながります。
主なエントリー方法を4つ紹介します。自分に合ったやり方を見つけてみてください。
1. 大手就活サイトからエントリーする
リクナビやマイナビといった大手就活サイトを利用する方法は、最も一般的と言えます。
多くの企業情報が掲載されており、サイト上でエントリーからスケジュール管理まで一括で行えるのが大きなメリットです。様々な企業を比較検討しながらエントリーを進めたい学生には特におすすめします。
まずはどんな企業があるのかを見てみることから始めてみるのも良いでしょう。
2. 企業の自社ホームページからエントリーする
就活サイトには情報を掲載せず、自社の採用ホームページのみでエントリーを受け付けている企業もあります。特に、専門職の採用や、通年採用を行っている企業に多いケースです。
自社ホームページから直接エントリーすることで、企業研究をしっかり行っているという熱意の証明にも繋がります。志望度の高い企業の場合、必ず自社の採用ページを直接チェックする癖をつけましょう。
3. 企業からスカウトをもらう
キミスカのような逆求人サイトやスカウト型サイトを活用する方法も主流になってきています。
自分のプロフィールや自己PR、ガクチカなど登録しておくと、それを見た企業の人事担当者からスカウトが届く仕組みです。スカウトではインターンシップのお誘いや選考の案内が届きます。そのため、自分では見つけられなかった優良企業と出会える可能性があり、就活の視野を広げる上で非常に有効な手段です。
「自分に合う業界・企業が分からない」「何から動き出せばいいかわからない」という方も企業からスカウトが届く逆求人サイトがおすすめなので、ぜひ登録してみてください。
4. 就活エージェントからの紹介
就活エージェントは、プロのキャリアアドバイザーが面談を通してあなたに合った企業を紹介してくれるサービスです。
一般には公開されていない「非公開求人」を紹介してもらえたり、ESの添削や面接練習といった選考対策をサポートしてもらえたりする点がメリットです。客観的な視点からアドバイスが欲しい人や、一人で就活を進めるのが不安な人におすすめです。
就活のエントリー後の基本的な流れ

エントリーは就活のゴールではなく、あくまでスタート地点に立ったにすぎません。エントリーを済ませた後には、様々な選考ステップが待っています。
この後の全体像をあらかじめ把握しておくことで一つ一つの選考に落ち着いて、かつ計画的に臨むことができます。一般的な選考の流れを理解し、しっかりと準備を進めていきましょう。
1. 会社説明会やセミナーの案内が届く
企業にエントリーすると、マイページなどを通じて会社説明会や各種セミナーの案内が届きます。オンラインで開催されることもあれば、対面の場合もあります。
企業によっては、この説明会への参加が次の選考ステップに進むための必須条件となっていることもあります。案内が届いたら必ず内容を確認し、参加するかどうかを早めに判断して予約しましょう。
2. エントリーシート(ES)を提出する
エントリーと同時あるいは説明会参加後に、エントリーシート(ES)の提出を求められます。これは、自己PRや学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)、志望動機などを記述する応募書類です。
多くの場合、このESの内容で書類選考が行われます。ESは後の面接でも深く掘り下げられるため、時間をかけて丁寧に作成することが非常に重要です。
ESの書き方や各項目の深堀りについては、以下の記事で詳しく解説しているのでチェックしてみてください。
3. Webテストや適性検査を受験する
ESと並行あるいはES提出後に、Webテストや適性検査の受験を求められることも多いです。内容は、言語能力や計算能力を測る「能力検査」と、人柄や価値観を見る「性格検査」で構成されています。
多くの企業が足切りラインを設けているため、参考書でWebテスト対策しておくことが不可欠です。複数の企業で同じ形式のテストが使われることも多く、早めの対策が全体の選考数をこなす上で有利に働きます。
4. 面接・グループディスカッション
書類選考やWebテストを通過すると、いよいよ面接やグループディスカッションといった人物評価のフェーズに進みます。
面接は、個人面接や集団面接など形式は様々で、面接回数も企業によって異なります。ESで書いた内容を基に、あなたの人柄や潜在能力、自社との相性などを見ています。ここでしっかりと自分をアピールできるよう、模擬面接などで練習を重ねておきましょう。
5. 内々定・内定
複数回の面接などの選考をすべて突破すると、企業から「内々定」または「内定」の連絡が来ます。
一般的に、政府が要請する採用選考開始日である6月1日以降に出されるのが「内々定」、正式な内定解禁日である10月1日以降に出される約束が「内定」と呼ばれます。内定を承諾するかどうか、慎重に判断し、指定された期間内に返答しましょう。
就活のエントリーで失敗しないための注意点

エントリーは就活の序盤だからと気を抜いてはいけません。ここで計画性なく動いてしまうと、後々の選考で苦労することになります。
多くの就活生が陥りがちな失敗をあらかじめ知っておき、それを避けるためのポイントを意識するだけで、あなたの就活はぐっと楽になります。ここで紹介する3つの注意点を必ず押さえておきましょう。
1. むやみにエントリー数を増やしすぎない
内定が獲得できるか不安になり手当たり次第にエントリーしてしまう学生がいますが、これは得策ではありません。エントリー数が増えすぎると、企業研究やES作成に十分な時間をかけられず、内容が薄くなってしまいます。
企業側も「とりあえずエントリーしただけだな」と簡単に見抜いてしまいます。「数打てば当たる」という考えは捨て、一社一社にしっかりと向き合う姿勢が内定への近道です。
2. エントリー情報の管理を徹底する
エントリーする企業が増えてくると、「あの企業のIDとパスワードは何だっけ?」「この企業のES締め切りはいつだっけ?」と情報の混乱が起こりやすくなります。
ExcelやGoogleスプレッドシート、就活管理アプリなどを活用し、企業ごとのID・パスワード・選考状況・締切日などを一覧で管理するのもおすすめです。締切日を忘れるといった、単純ですが致命的なミスを防ぐことができます。
3. 企業の採用情報をこまめに確認する
一度エントリーしたからと安心せず、企業のマイページや採用サイトはこまめにチェックする習慣をつけましょう。なぜなら、企業によっては選考スケジュールが変更されたり、追加のセミナー案内が急に告知されたりすることがあるからです。
特に志望度の高い企業の情報は、最低でも2〜3日に1回は確認することで、重要な情報を見逃すリスクを減らすことができます。
就活のエントリーについてのよくある質問(Q&A)
ここでは、就活生から特によく寄せられるエントリーに関する細かい疑問について、Q&A形式でお答えしていきます。
多くの人が同じような点で悩んだり、疑問に思ったりしています。ここで不安や疑問をスッキリ解消して、万全の状態でエントリーに臨みましょう。
Q. エントリーしたのに企業から連絡が来ない場合は?
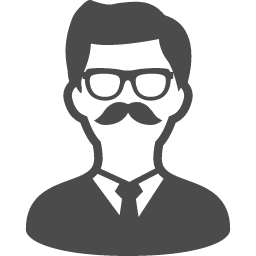 企業
企業 エントリー後に企業から何の連絡もないと不安になりますよね。まずは、登録したメールアドレスの迷惑メールフォルダに振り分けられていないかを確認しましょう。
それでも連絡がない場合は、就活サイトのマイページなどでエントリーが正常に完了しているかを確認します。その上で、企業の採用サイトで当日のスケジュールや詳細が公開されていないかを確認して、それでも不明な点があれば企業に問い合わせてみましょう。
Q. エントリーした後に辞退できる?
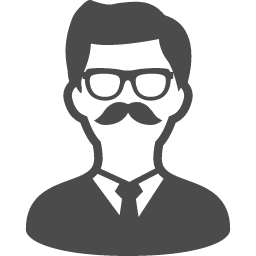
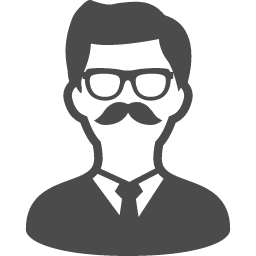
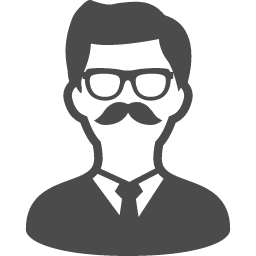
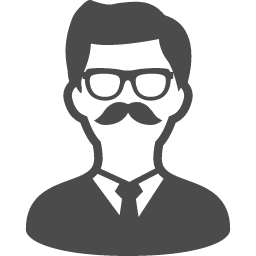
選考途中での辞退は、学生の権利として全く問題ありません。企業側も、学生が複数の企業を同時に受けていることは理解しています。
ただし、最もやってはいけないのが、連絡なしで説明会や面接を欠席する「無断辞退」です。辞退を決めた時点で、できるだけ早く電話やメールで誠意をもって連絡するのが、社会人としての最低限のマナーです。
Q. エントリーを取り消したい場合はどうすればいい?
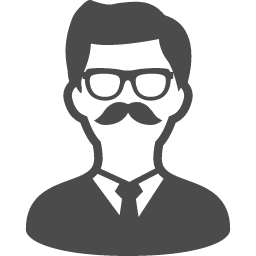
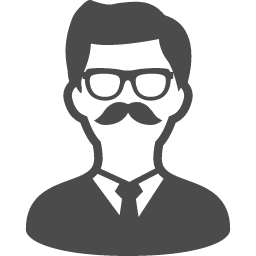
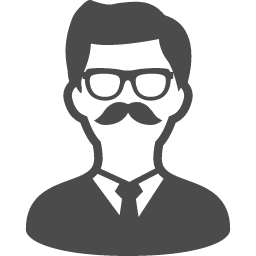
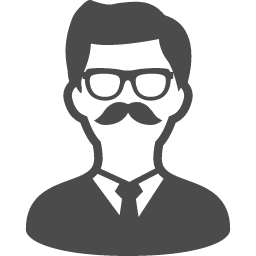
プレエントリー段階などで「やはりこの企業は受けない」と決めた場合、エントリーの取り消しが可能です。
多くの就活サイトでは、マイページから「エントリー済みリスト」のようなページへ進み、自分で取り消し(辞退)の手続きができます。もしサイト上で取り消しができない場合は、企業の採用担当者宛に、大学名と氏名を明記の上、丁重に辞退の旨をメールで連絡しましょう。
就活のエントリー数は質と量のバランスを考えよう
今回は、就活の第一歩である「エントリー」について、プレエントリーとの違いから具体的な方法、注意点まで詳しく解説しました。エントリーは、あなたの就活の可能性を広げるための重要なスタートです。
最初は分からないことだらけで不安に感じるかもしれませんが、一つ一つ意味を理解し、計画的に行動すれば何も怖くありません。この記事を参考に、自信を持ってエントリーに臨み、納得のいく就活に繋げてください。

