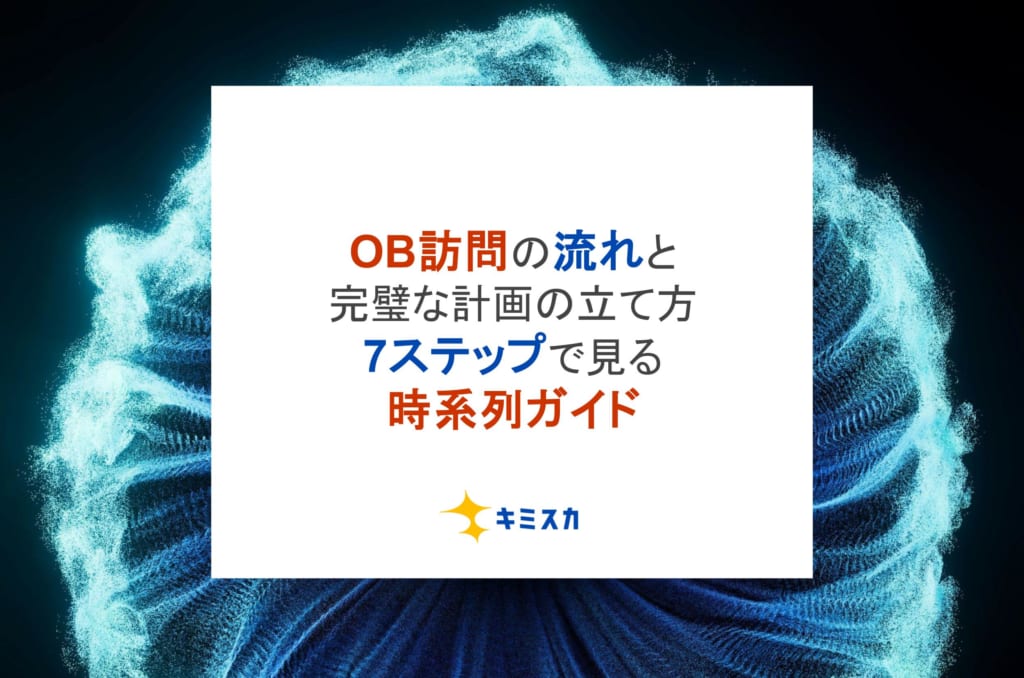
「OB訪問って、何から手をつけて、どの順番で進めればいいの?」「全体の流れが見えないから、計画が立てられなくて不安…」そんな風に悩んでいませんか?OB訪問は、計画的に進めることで、その効果を何倍にも高めることができます。
この記事では、OB訪問の準備から訪問後の振り返りまで、やるべきことの全貌を「7つのステップ」に沿って時系列で詳しく解説します。この記事を読めば、全体の流れが手に取るように分かり、あなたも自信を持って完璧なOB訪問の計画を立てられるようになるはずです。
そもそもOB訪問とは?目的を決めてから始めよう
具体的な流れを見ていく前に最も重要な「目的設定」について解説します。目的が明確であれば、各ステップに意味を持って取り組む事ができ、訪問の質が格段に向上します。
まずはOB訪問でどんな目的が達成できるのかを知り、あなた自身の目的を設定する方法を学びましょう。
OB訪問で達成できる主な3つの目的
OB訪問の目的は人それぞれですが、主に3つのタイプに分けられます。1つ目はWebサイトや説明会では分からない「リアルな情報を得て、企業理解を深める」ことです。
2つ目は社員の働きがいや大変さを聞くことで、「働くイメージを掴み、自己分析に活かす」ことで、3つ目は社会人の先輩のキャリアを聞き、「自分の就活の軸や将来のキャリアプランを明確にする」ことです。これらを参考に自分の目的を考えてみましょう。
自分だけの目的の決め方・設定方法
ではどうやって自分だけの目的を決めれば良いのでしょうか。ポイントは「今の自分の課題は何か?」から逆算して考えることです。
例えば「企業のHPを読んでも、A社とB社の社風の違いが分からない」という課題があるなら、それがそのまま「A社とB社の社風のリアルな違いを知る」という目的になります。訪問後に「〇〇について詳しくなれた!」と自信を持って言える状態をゴールに設定することが、有意義なOB訪問への第一歩です。
【全体像】OB訪問の全7ステップの流れを解説
OB訪問は大きく分けて7つのステップで構成されています。まずは準備から訪問後までの全体像を掴みましょう。
この一連の流れを頭に入れておくだけで、「次に何をすべきか」が明確になり、漠然とした不安が解消されるはずです。これからこの7つのステップを一つずつ詳しく見ていきます。

ステップ1:目的の明確化と自己分析
OB訪問の出発点です。なぜ訪問するのか、何を知りたいのかという目的をはっきりさせます。同時に、自分の興味や価値観を再確認する自己分析も行い、質問の軸を定めます。
ステップ2:訪問したいOB・OGを探す
目的が定まったら、次に話を聞きたい企業のOB・OGを探します。大学のキャリアセンターやゼミの繋がり、OB訪問アプリなど、様々な方法を駆使してアプローチします。
ステップ3:メールでアポイントを依頼する
訪問したい相手が見つかったら、失礼のないように丁寧なメールでアポイント(面会の約束)を依頼します。ここが社会人と接する最初の関門であり、あなたの第一印象が決まります。
ステップ4:企業研究と質問リストの作成
アポイントが取れたら、当日に向けて入念な準備を行います。企業の情報を深く調べ、質の高い質問をリストアップすることで、訪問の価値を最大限に高めます。
ステップ5:OB訪問当日の流れを把握する
いよいよ訪問当日です。受付から挨拶、面談、退室までの一連の流れと、それぞれの場面で求められるマナーをしっかりと頭に入れて、失礼のないように振る舞います。
ステップ6:当日中にお礼メールを送る
訪問が終わったら、その日のうちに必ずお礼のメールを送ります。貴重な時間をもらったことへの感謝を伝え、丁寧な対応を心がけることで、良い印象で締めくくります。
ステップ7:振り返りと情報整理を行う
OB訪問で得た情報を整理し、自分の言葉でまとめる最終ステップです。この振り返りが、今後の自己分析やエントリーシート、面接対策に活きてきます。
【準備編】OB訪問の具体的な流れとやるべきこと
ここからは、各ステップで「具体的に何をすべきか」を詳しく解説していきます。まずは「準備編」として、OB訪問が実現するまでのステップ1から3を見ていきましょう。
この準備段階を丁寧に行うことが、OB訪問全体の成否を分けるといっても過言ではありません。
ステップ1:目的の明確化と自己分析|何を知りたいか考える
なんとなくOB訪問をするのは非常にもったいないです。「この訪問を通じて何を得たいのか」という目的を具体的に設定しましょう。「事業内容について深く知りたい」「社風を肌で感じたい」など、目的によって質問内容も変わってきます。
自分の興味や強みを再確認する簡単な自己分析も行い、「なぜこの会社に興味があるのか」を自分の言葉で説明できるようにしておくと、訪問がより有意義なものになります。
ステップ2:訪問したいOB・OGを探す|4つの探し方
目的が明確になったら、話を聞きたいOB・OGを探しましょう。主な探し方は4つあります。まずは大学の「キャリアセンター」で卒業生名簿を相談するのが王道です。次に「ゼミや研究室の教授・先輩」に紹介してもらう方法も有効です。
また、最近では「OB訪問専用のアプリやサイト」で探す学生も増えています。最後に「親族や友人」など、身近な人脈を頼るのも一つの手です。自分に合った方法でアプローチしてみましょう。
ステップ3:メールでアポイントを依頼する【例文あり】
訪問相手が見つかったら、メールでアポイントを依頼します。相手は忙しい社会人ですから、件名だけで用件と差出人が分かるようにし、簡潔で丁寧な文章を心がけましょう。
自己紹介、連絡先を知った経緯、訪問したい理由を明確に伝え、候補日時を複数提示して相手に選んでもらうのがマナーです。自分の都合だけを押し付けるのではなく、相手の都合を最優先に考える姿勢が何よりも大切です。
件名:OB訪問のお願い(〇〇大学 社会学部 佐藤美咲)
株式会社〇〇
〇〇部 〇〇様
突然のご連絡失礼いたします。
私は、〇〇大学社会学部の佐藤美咲と申します。
大学のキャリアセンターにて〇〇様のことを知り、ぜひお話をお伺いしたく、ご連絡いたしました。
現在、〇〇業界を志望しており、特に貴社の「〇〇」という理念に強く惹かれております。そこで、〇〇様のお仕事内容や、働くうえでのやりがいなどについてお聞かせいただきたく、OB訪問のお時間をいただけないでしょうか。
来週以降で、もしご都合のよろしい日時がございましたら、30分ほどお時間をいただけますと幸いです。いくつか候補を挙げさせていただきます。
・7月16日(火)13:00〜17:00
・7月18日(木)終日
・7月19日(金)10:00〜15:00
もちろん、〇〇様のご都合に合わせて調整いたします。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。
————————————————–
佐藤 美咲(さとう みさき)
〇〇大学 社会学部 3年
携帯電話:090-0000-0000
メール:misaki.sato@xxxx.ac.jp
————————————————–
なぜあなたに連絡したのかという「経緯」と「理由」を具体的に書くことで、相手への誠意が伝わります。また、候補日を複数提示しつつも、相手に選択権を委ねる丁寧な姿勢が好印象に繋がります。
【実践編】OB訪問の具体的な流れとやるべきこと
アポイントが取れたら、いよいよ訪問の「実践編」です。ここではステップ4から6、つまり当日の準備から訪問直後のお礼メールまでの流れを解説します。
多くの学生が緊張する場面ですが、一つひとつのやるべきことをこなしていけば問題ありません。
ステップ4:企業研究と質問リストの作成|準備で差がつく
OB訪問は、調べても分からない「生の情報」を聞きに行く場です。企業の公式サイトに書かれていることを質問するのは失礼にあたります。最低限の企業情報は頭に入れたうえで、「自分はこう考えたのですが、実際はどうなのでしょうか?」という仮説を検証するような質問を準備しましょう。
質問は最低でも10個以上用意しておくと、会話が途切れる心配がなく安心です。質の高い質問は、あなたの熱意と知的な好奇心を示す絶好のアピールになります。
ステップ5:OB訪問当日の流れとマナー|受付から退室まで
当日は、約束の時間の5〜10分前には指定された場所に到着するようにしましょう。早すぎる到着はかえって迷惑になることもあるので注意が必要です。
受付から退室まで一連の流れをシミュレーションしておくと、当日の振る舞いがスムーズになります。感謝の気持ちを忘れず、ハキハキとした態度で臨みましょう。
ステップ6:当日中にお礼メールを送る|感謝を伝え次に繋げる
訪問が終わったら気を抜かずに、その日のうちに必ずお礼のメールを送りましょう。これは社会人としての必須マナーです。
感謝の気持ちはもちろん、「〇〇というお話が特に勉強になりました」のように、何が学びになったのかを具体的に伝えることが重要です。あなたの誠実さが伝わり、訪問してくれたOB・OGの方にも「時間を作って良かった」と思ってもらえるはずです。
【訪問後編】OB訪問の具体的な流れとやるべきこと
OB訪問は話を聞いてお礼を言ったら終わりではありません。最後の仕上げである「訪問後編」のステップ7があなたの就活を大きく前進させます。
このステップを疎かにせず、得たものを次に繋げましょう。

ステップ7:振り返りと情報整理|訪問を今後に活かす
訪問で聞いた貴重な話を、忘れないうちにノートやパソコンにまとめておきましょう。ただメモを書き写すだけでなく、「この話は自己PRに使えそうだ」「この情報は志望動機を深めるのに役立つ」といったように、今後の就活にどう活かすかを考えることが大切です。
複数のOB訪問をした場合は、情報を比較検討することで、その企業ならではの強みや特徴がより明確になります。この整理と分析が、あなただけの武器になるのです。
時期別!OB訪問のスケジュール感
ここまで7つのステップの流れを解説しましたが、「じゃあ、そのステップをいつやればいいの?」という疑問も湧いてきますよね。
ここでは大学3年生の時期別に、おすすめのスケジュール感を紹介します。これを参考に、あなた自身のOB訪問計画を立ててみましょう。
大学3年生の夏~秋:自己分析とOB探しを始める
この時期は就活の準備を始めるのに最適です。まずは自己分析や業界研究を進めながら、OB訪問の目的を明確にしましょう(ステップ1)。
夏休みなどを利用して、興味のある業界・企業のリストアップと、OB・OG探し(ステップ2)に着手できると、冬以降の活動がスムーズに進みます。まだ焦る必要はありませんが、早めにスタートを切ることで、余裕を持って準備ができます。
大学3年生の冬:OB訪問のピーク!集中的に行う
12月〜2月頃はOB訪問を最も活発に行うべき時期です。夏〜秋に見つけておいたOB・OGにアポイントを依頼し(ステップ3)、実際に訪問を重ねていきましょう(ステップ4・5)。
多くの学生がこの時期に動くため、早めに計画を立ててアポイントを取ることが重要です。複数の訪問から得た情報を比較・整理し(ステップ7)、自分の就活の軸を固めていきましょう。
大学3年生の3月以降:選考と並行し、最終確認で訪問
3月になると企業の採用広報活動が解禁され、就活もいよいよ本番です。この時期のOB訪問は志望度の高い企業の最終確認や、面接で話す内容を深めるために行うのが効果的です。
例えば、「一次面接を控えているのですが、〇〇様から見て、貴社が求める人物像についてアドバイスをいただけないでしょうか」といった、より具体的で実践的な質問ができます。選考の合間を縫って戦略的に活用しましょう。
OB訪問の流れに関するよくある質問(Q&A)
ここでは、OB訪問の流れに関して、多くの就活生が抱きがちな細かな疑問にお答えします。計画を立てる上での不安要素は、ここで全て解消しておきましょう。
Q1. オンラインでのOB訪問の流れは対面と違う?
また背景は無地の壁など、相手が集中できる環境を整えましょう。画面越しでは表情が伝わりにくいため、相槌を少し大きく打ったり、笑顔を意識したりするなど、対面の時以上にリアクションを大きくすることを心がけると良いでしょう。
Q2. OB訪問にかかる時間はどのくらい?
話が盛り上がったとしても終了時間が近づいたら「まもなくお時間ですので」と、こちらから話を切り上げる配慮が大切です。相手の時間を管理する意識を持つことで、計画性のある学生という印象を与えられます。
Q3. アポ依頼のメールが返ってこない時はどうすればいい?
それでも返信がない場合は催促と受け取られないよう、「先日はOB訪問のお願いでご連絡いたしました〇〇大学の〇〇です。ご多忙とは存じますので、もしご都合が悪いようでしたら気兼ねなくお申し付けください」のように、相手を気遣う一文を添えて、再度連絡してみても良いでしょう。それでも返信がなければ今回は縁がなかったと切り替える潔さも必要です。
OB訪問の流れを理解して、計画的に就活を進めよう
今回はOB訪問の全体の流れを7つのステップに分けて、計画の立て方と合わせて解説しました。全体像が見えれば、いつ、何をすべきかが明確になり、漠然とした不安も解消されたのではないでしょうか。
OB訪問はただやみくもに行うのではなく、しっかりとした計画に基づいて進めることで何倍も有意義なものになります。この記事を参考にあなた自身のOB訪問計画という名の「時系列ガイド」を作成し、自信を持って就活の第一歩を踏み出してください。

