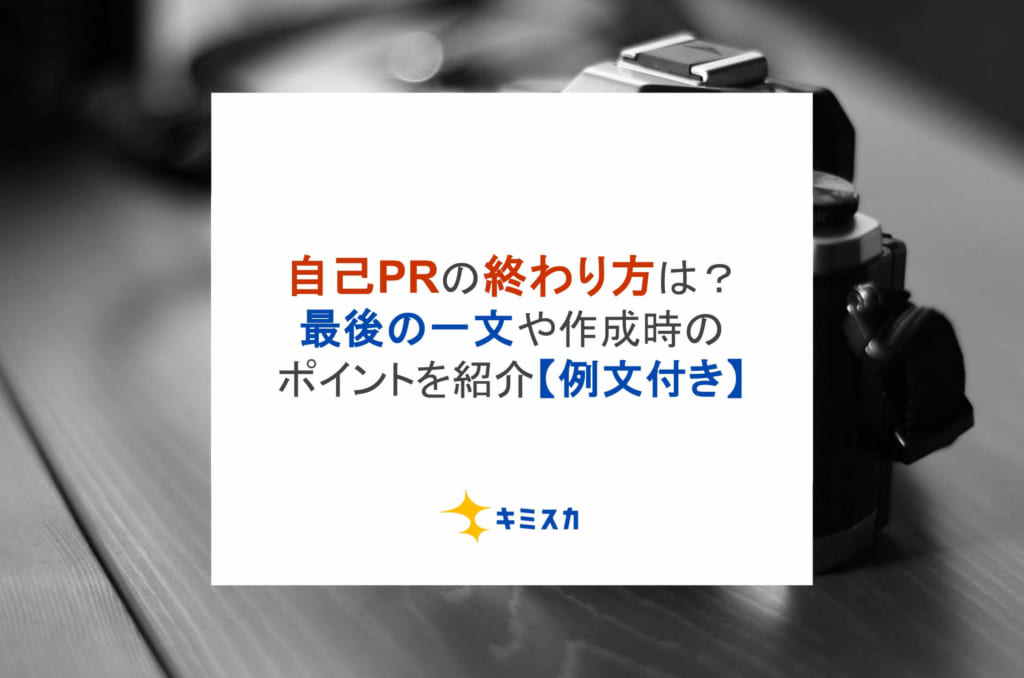
「自己PRの終わり方がわからない」「自己PRの締めくくりは何を話せばよいの?」
自己PRでアピールしたい強みや長所は見つかったものの、自己PRの終わり方に悩んでしまい、なかなか仕上げられずにいる就活生も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、自己PRの終わり方を例文付きで3パターン紹介します。あわせて自己PRの終わり方で意識したいポイントや、避けるべき終わり方についてもまとめました。
自己PRの終わり方・締め方の作成で悩んでいる就活生は、ぜひ本記事を参考にしてください。
自己PRの終わり方が分からない就活生へ
自己PRは自分の強みやスキルをアピールする場ですが、それだけでは効果的なアピールとはいえません。自己PRで重要なことは、「一緒に働きたい」と思ってもらうことです。
つまり、自己PRは「この学生と働きたい」「採用メリットがある」と感じさせる終わり方を意識することで、高評価を得られるアピールとなります。具体的な結びに関しては、次の章をご確認ください。
【例文あり】自己PRの終わり方3パターン
ここからは、自己PRの終わり方を3パターン紹介します。最後の一文の例文を作成したので、自己PRの終わり方に悩んでいる学生はぜひ参考にしてみてください。
なお、例文では書類選考用に「貴社」と書いていますが、面接で話す際は「御社」と使い分けるようにしましょう。
企業に貢献できること
自己PRの終わり方の1パターン目は、企業に貢献できることをアピールする結び方です。ES(エントリーシート)や面接では、企業に採用メリットを感じてもらう必要があります。企業に貢献できることを最後の一文に組み込むことで、あなたが入社するメリットを感じてもらえるでしょう。
私が貴社(面接の場合は御社)に入社しましたら、○○○○(過去の出来事)の経験を生かしてお客様とのコミュニケーションを一番に考えた営業に努め、顧客満足度の向上に貢献したいです。
入社後の決意
自己PRの終わり方の2パターン目は、入社後の決意を述べる結び方です。入社できたら何に力を注ぎたいのか、どのようなキャリアを思い描いているのかなど、入社後の自分の姿を伝えることで社員として働くイメージをもってもらえます。
私が貴社に入社しましたら、販売の現場で業務を担い、いずれは新商品の開発に携われるような社員へと成長したいと考えております。
強みや長所
自己PRの終わり方の3パターン目は、自分の強みや長所で結ぶ方法です。自己PRの最初にアピールした強みや長所を最後に繰り返し述べることで、あなたの良いところを強調できます。
私のこの〇〇という強みを生かして、貴社の〇〇(部署名や業務内容など)で活躍したいと考えております。
自己PRの終わり方で意識したいポイント5つ

自己PRの終わり方を3パターン紹介しましたが、いずれかのパターンをただ真似すればよいわけではありません。
ここで紹介する自己PRの終わり方で意識したいポイントを参考に、あなたの良さや強みが的確に伝わる自己PRに仕上げましょう。
企業が求める人物像を意識する
自己PRに限らず、ESや面接の質疑応答で意識したいことは企業が求める人物像です。企業がどのような人材を求めているか把握し、それに自分がマッチしていることをアピールできなければ効果的なアピールとはいえません。
例えば、歴史を重んじる企業の面接を受けた際に、「私のチャレンジ精神を生かして、どんどん新商品を開発したいです」と述べた場合、自社には合わないと判断される可能性があります。どのパターンの終わり方を選ぶにしろ、企業が求める人物像を意識することが重要です。
伝えたい要素を絞る
貴重なアピールの機会を無駄にしたくないと思い、複数の強みや長所をアピールする学生がいますが、その方法はおすすめできません。一度にたくさんのアピールをしてしまうと、何を伝えたいのか分かりにくくなったり、印象に残りにくくなったりします。
自己PRの結びに内容を詰め込むことは避け、最もアピールしたいことを終わりにもってくるようにしましょう。
しっかりと言い切る
例えば、「と思います」「かもしれません」のような中途半端な終わり方は避けるべきです。きちんと言い切ることで、あなたのアピールに説得力が生まれます。
企業が学生に求めていることは、爽やかさや元気さ、前向きな姿勢です。自信のない姿を見せるのではなく、入社したいという熱意を見せましょう。
PREP法で構成する
PREP(プレップ)法とは、結論から始まり結論で終わる文章構成方法です。伝えたいことが相手に伝わりやすくなる文章構成として、ビジネスの場を中心に広く用いられています。
具体的には、「結論→理由→具体例→結論」の順番に進む手法です。就活の質疑応答は、すべてPREP法で構成することをおすすめします。
嘘はつかない
自己PRの終わり方が分からないからといって、嘘をついたり、誇張したりするのはやめましょう。大抵の場合、嘘や誇張表現は見破られます。運よく見破られなかったとしても、入社後のミスマッチにつながるため避けるべきです。
とくに学歴やアルバイト歴、資格に関する嘘は経歴詐称となります。また、成績や出席日数に関する嘘は成績証明書でバレるため注意が必要です。嘘をついて選考通過を目指すのではなく、自分らしさを評価してもらうことを意識しましょう。
【強み別】自己PRの終わり方例文5選
自己PRの終わり方を、強み別に分けて紹介します。自分の強みとしている例文を参考に、自己PR作りを進めましょう。
向上心
私は常に成長を求め、自ら学び続ける向上心を持っています。大学ではマーケティングを専攻し、ゼミ活動の一環として地域企業の商品プロモーションに携わりました。初めは知識不足で思うような成果を出せませんでしたが、独学でSNSマーケティングの書籍を読み込み、実践を重ねた結果、ターゲット層に適した広告戦略を提案し、前年対比120%の売上向上に貢献しました。
この経験から、新しい知識を積極的に吸収し、それを実践に活かす力が身につきました。貴社でも現状に満足せず、常に学び、挑戦を続ける姿勢で貢献していきます。
継続力
私は一度決めたことを最後までやり抜く継続力が強みです。大学では英語力を高めるため、毎日30分のオンライン英会話を3年間継続しました。最初は思うように話せず苦労しましたが、学習方法を工夫しながら続けた結果、TOEICスコアを400点から800点へと伸ばすことができました。
この経験から、困難に直面しても諦めず、継続的な努力を重ねることで成果を生み出せることを学びました。貴社においても、粘り強く取り組み、長期的な成果につなげられるよう尽力いたします。
柔軟性
私は状況に応じて柔軟に対応し、最適な方法を模索できる力があります。大学ではイベント運営サークルに所属し、学園祭の企画を担当しました。しかし、当初の計画は天候不良で実施が困難になり、急遽、屋内開催へと変更せざるを得ませんでした。そこで私はチームと協力し、レイアウトや演出を工夫することで、来場者満足度を維持しながら成功へと導きました。
この経験から、想定外の状況でも冷静に判断し、最適な解決策を見出す力を身につけました。貴社でも環境の変化に適応し、柔軟な発想で貢献していきます。
計画性
私は目標達成のために計画を立て、着実に実行する力があります。大学では資格取得を目指し、半年間で簿記2級に合格しました。最初に試験日から逆算し、週ごとの学習計画を作成。効率的に学ぶために重要ポイントを整理し、毎日の勉強時間を確保しました。途中で予定通りに進まないこともありましたが、その都度スケジュールを見直し、柔軟に調整したことで、無理なく目標を達成できました。
この経験から、計画的に行動しつつ、状況に応じて修正する力が身につきました。貴社でも業務を的確に進め、成果につなげられるよう尽力いたします。
責任感
私は最後まで責任を持って物事に取り組む力があります。大学では学生広報チームのリーダーとして、オープンキャンパスの運営を担当しました。初めての経験で不安もありましたが、参加者にとって有意義なイベントにするため、事前準備から当日の進行まで細部にこだわりました。特にトラブルが発生した際には冷静に対応し、チームメンバーと協力して迅速に解決。結果として、前年よりも多くの参加者から高評価を得ることができました。
この経験を通じて、周囲を巻き込みながら責任を果たす力を培いました。貴社でも任された業務に誠実に向き合い、期待に応えられるよう尽力いたします。
これは避けたい!自己PRの終わり方NGパターン
最後に、自己PRの終わり方で避けるべきパターンを見ていきましょう。以下の3パターンの終わり方は高評価につながりにくいので、最後の一文を考え直すことをおすすめします。
一貫性がない
例えば、自己PRでアピールした強みやスキルとはかけ離れた終わり方など、全体を通して見たときに一貫性のなさが浮き彫りになる結びは避けるべきです。一貫性のないアピールは説得力が低く、嘘をついているのではないかと思われる可能性があります。
自己PRの終わり方を考える際は、アピールに一貫性があるかどうかを確認しましょう。
根拠がない
やる気や決意をアピールしたいからといって、最後の一文に根拠のないアピールをもってくるのはおすすめできません。例えば、「必ず○○万円売り上げます」「○○人の接客をこなします」など、達成できるかどうか分からないアピールは評価されにくいばかりか、仕事を軽く考えているとマイナスの印象を与えてしまう可能性もあるでしょう。
企業に貢献できることや入社後の決意で終わる場合は、具体的な数字は出さず、今後努力していきたいことを中心に述べることをおすすめします。
ありがちな定型文
せっかくの自己PRをありがちな定型文で終わらせてしまうのは、もったいないので避けましょう。例えば、「一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします」「どんな仕事でも頑張ります」など、業界・企業問わず使い回せる定型文を用いると、志望度が低いと思われてしまうかもしれません。
企業は自社にマッチした学生を求めています。自己PRの終わり方を考える際は、企業ごとに終わり方を変えるべきでしょう。
自己PRの終わり方は3パターンが基本
自己PRの終わり方は、企業に貢献できること・入社後の決意・強みや長所の3パターンが基本です。また、どのパターンの終わり方を選んだとしても、「一緒に働きたい」と思ってもらうことを意識してみましょう。
自己PRは数ある質疑応答のなかでも重視されるため、最後の一文にはこだわりたいところです。終わり方で評価に差が出るケースも少なくないので、定型文で終わらせようとせず、企業が求める人物像を意識した終わり方を考えてみてください。

