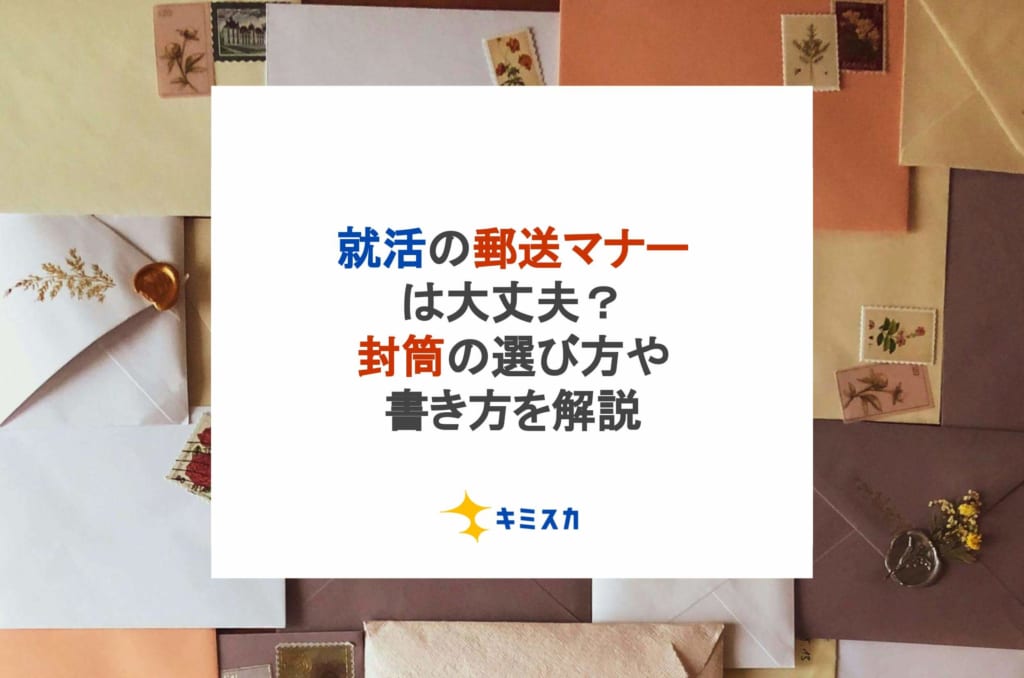
就活では履歴書やエントリーシートといった各種書類を郵送する機会が多々あります。しかし、「どんな封筒を選べばいいの?」「宛名はこれで合ってる?」など、封筒の準備や書き方に悩む就活生も多いのではないでしょうか。
この記事では、就活における郵送マナーの基本である封筒の選び方から、表面・裏面の正しい書き方、書類の入れ方、郵送方法、さらには郵送前の最終チェックリストやよくある質問まで、分かりやすく徹底解説します。社会人としての第一歩を気持ちよく踏み出すためにも、正しい封筒マナーを身につけましょう。
就活で使う封筒の選び方|サイズ・色・購入場所
まずは、就活関連の書類を郵送する際に必要な封筒の選び方を見ていきましょう。封筒の大きさと色、そしてどこで購入できるかを確認し、封筒を購入する際の参考にしてみてください。第一印象を左右することもあるので、適切なものを選びましょう。
1. 封筒の適切なサイズは角形2号
就活に関する書類は、A4サイズの書類を折らずにそのまま入れられる角形2号(角2)の封筒で郵送するのが基本です。履歴書やエントリーシートはクリアファイルに入れてから封筒に入れるのがマナーなので、A4サイズ対応の角形2号が最適です。
これより小さいサイズの封筒だと、書類を折らなければならず、採用担当者に手間をかけさせてしまう可能性があります。
2. 封筒の色は白色が基本
就活の各種書類の郵送に用いる封筒の色は、白色が最もフォーマルで丁寧な印象を与えられます。茶色の封筒も市販されていますが、これらは主に事務的な用途で使われることが多く、重要な書類を送る就活の場面では避けるのが無難です。
白色の封筒は清潔感があり、中身の書類も透けにくいため、安心して使用できます。
3. 就活用封筒はどこで買える?
角形2号の白い封筒は、身近な場所で購入できます。文房具店はもちろん、コンビニエンスストア、100円ショップ、大きめのスーパーマーケット、郵便局の窓口、インターネット通販などでも取り扱いがあります。
特に文房具店やネット通販では種類も豊富で、ある程度の枚数をまとめて購入するのにおすすめです。 就活では複数の企業に応募することが一般的なので、少し多めに用意しておくと安心です。
就活における封筒の書き方【表面編】
封筒を選んだら、次は表面の書き方です。企業の担当者に失礼なく、かつ正確に届けるための重要なポイントです。一般的に就活に用いられる縦書きの和封筒を例に、項目ごとに丁寧に確認していきましょう。黒色の油性ボールペンを使用するのが基本です。

1. 企業の郵便番号|算用数字で正確に
まずは、企業の郵便番号を記入します。封筒の右上に、横書きで算用数字(1, 2, 3…)を使って正確に書きましょう。 郵便番号の記入欄が封筒に印刷されている場合はその枠内に、ない場合は右上に「〒」マークを付けずに数字のみを記入します。 番号を間違えると配達が遅れる原因になるため、必ず事前に確認してください。
2. 企業の住所|都道府県からビル名まで略さず
次に、企業の住所を郵便番号の下に記入します。都道府県名から書き始め、ビル名や階数まで省略せずに正確に記載しましょう。 住所が長く一行で収まらない場合は、二行に分けて書きますが、その際、二行目は一行目よりも一文字分程度下げて書き始めるとバランスが良く見えます。 アラビア数字ではなく漢数字(一、二、三…)を用いるのがより丁寧な印象です。
3. 宛名|会社名・部署名・担当者名と敬称
続いて、封筒の中央やや右寄りに宛名を記入します。宛名は住所よりも一回り大きな文字で、はっきりと書きましょう。会社名は「(株)」などと略さず、「株式会社○○」と正式名称で記載します。
部署宛ての場合は「人事部 御中」、担当者名が分かっている場合は「人事部 ○○様」とします。「御中」と「様」は併用できないため注意が必要です。 担当者名が不明な場合は「採用ご担当者様」と記載するのが一般的です。
株式会社〇〇
人事部 御中
株式会社〇〇
人事部 〇〇様
株式会社〇〇
採用ご担当者様
4. 「応募書類在中」|赤ペンで左下に記載
封筒の表面左下に、赤色の油性ボールペンで「応募書類在中」と記入し、その周りを四角い枠で囲みます。これは、企業側が他の郵便物と区別しやすくするための大切な記載です。 手書きに自信がない場合は、「応募書類在中」のスタンプを利用しても問題ありません。 文房具店や100円ショップなどで手に入ります。スタンプを使用する場合も、色は赤色を選びましょう。
就活における封筒の書き方【裏面編】
封筒の表面を書き終えたら、次は裏面です。裏面には差出人である自分の情報を正確に記載します。誰から送られてきた書類なのかを明確にするために、丁寧な記入を心がけましょう。こちらも黒色の油性ボールペンを使用します。
1. 自分の郵便番号・住所・氏名を書く位置
封筒の裏面中央より左側に、自分の郵便番号、住所、氏名を記入します。郵便番号は封筒の継ぎ目の左側、住所はその下に、氏名はさらにその下に記載するのが一般的です。 大学名、学部、学科名も忘れずに氏名の左横に少し小さめに書き添えましょう。 住所は都道府県から、マンション名や部屋番号まで正確に記載してください。
2. 投函日|提出日の日付を左上に
封筒の裏面左上に、書類を投函する日付または提出する日付を漢数字で縦書きで記入します。「令和六年五月十三日」のように和暦で書くのが一般的です。 この日付は、送付状に記載する日付と統一するようにしましょう。 空欄のまま提出するのはマナー違反となるため、忘れずに記入してください。
3. 封じ目には「〆」マークを忘れずに
書類を封筒に入れ、のり付けをしたら、封じ目の中央に黒色の油性ボールペンで「〆」マークを記入します。この「〆」マークは「封緘(ふうかん)」と呼ばれ、「確かに封をしました」「途中で誰にも開封されていません」という意味を示す大切な印です。
「×」と間違えないように注意しましょう。「封」や「緘」という漢字一文字でも構いませんが、「〆」が最も一般的です。
就活書類を封筒に入れる際のマナーと手順
封筒の準備と記入が終わったら、いよいよ書類を封入します。ただ入れるだけでなく、企業側に失礼なく、かつ書類を良い状態で読んでもらうためのマナーがあります。正しい手順とポイントを押さえておきましょう。
1. 送付状(添え状)を同封する
応募書類を郵送する際は、必ず送付状(添え状)を同封しましょう。送付状とは、誰が誰に何を何枚送ったのかを伝えるための挨拶状のようなものです。 送付状があることで、採用担当者は同封書類の内容をすぐに把握でき、丁寧な印象も与えられます。
・日付(投函日)
・宛先(企業名、部署名、担当者名)
・差出人情報(大学・学部・学科名、氏名、住所、電話番号、メールアドレス)
・件名(例:選考応募書類のご送付について)
・頭語と結語(拝啓・敬具など)
・本文(応募の旨、同封書類の一覧など)
・同封書類名とその部数(記書きで箇条書き)
2. 書類はクリアファイルに挟んで保護
用意した応募書類と送付状は、そのまま封筒に入れるのではなく、無色透明で新品のクリアファイルに挟んでから封入しましょう。 これにより、郵送中に書類が折れ曲がったり、雨などで濡れたりするのを防ぐことができます。
採用担当者が書類を取り出す際にも扱いやすくなります。柄付きや色付きのクリアファイルは避け、シンプルなものを選んでください。
3. 書類を入れる正しい順番
クリアファイルに入れる書類の順番も大切です。一番上に送付状、次に履歴書、エントリーシート、その他企業から提出を求められている書類(成績証明書、卒業見込証明書など)の順で重ねます。
採用担当者が上から順番に確認しやすいように配慮することがポイントです。 すべての書類をクリアファイルにまとめたら、封筒の表面から見て書類の表が上になるように入れましょう。
就活で使う封筒の郵送方法と切手の知識
書類を封筒に入れ終えたら、いよいよ郵送です。しかし、ただポストに投函すれば良いというわけではありません。適切な郵送方法を選び、正しい料金の切手を貼ることが重要です。ここで失敗しないための知識を身につけましょう。

1. おすすめの郵送方法と料金比較
就活の書類を送る際は、基本的には「普通郵便」で問題ありません。しかし、企業への到着確認をしたい場合や、より確実に届けたい場合は「特定記録郵便」や「簡易書留」を利用することも検討しましょう。
特定記録郵便は、引き受けの記録が残り、配達状況をインターネットで確認できるため、到着確認をしたい場合に便利です。 簡易書留は、引き受けと配達のみを記録し、万一の事故の際には損害賠償もあります。速達は締切間近の最終手段ですが、余裕を持った提出を心がけましょう。
・普通郵便:最も安価。追跡なし、補償なし。
・特定記録郵便:普通郵便料金+160円。追跡あり、補償なし。
・簡易書留:普通郵便料金+350円。追跡あり、補償あり(上限5万円)。
2. 切手の料金はいくら?正しい貼り方
角形2号の封筒でA4書類を送る場合、重さによって郵便料金が変わります。送付状と応募書類数枚、クリアファイルを含めると、50gを超えることが多いでしょう。
一般的な重さである50g超~100g以内であれば、定形外郵便物(規格内)として140円切手が必要です(2024年5月現在)。 不安な場合は郵便局の窓口で重さを測ってもらい、正確な料金の切手を貼りましょう。料金不足は失礼にあたるため、切手は多めに貼るか、窓口で正確な料金を支払うのが確実です。 切手は封筒の表面左上に、複数枚貼る場合は縦に並べて貼るのが一般的です。
就活の郵送で失敗しないための注意点
封筒の準備から郵送まで、いくつかの注意点があります。これらを押さえておくことで、採用担当者にマイナスな印象を与えるリスクを減らすことができます。細部まで気を配り、丁寧な対応を心がけましょう。
1. 筆記用具は黒色の油性ボールペンで
封筒の宛名書きや裏面の差出人情報、送付状などは、必ず黒色の油性ボールペンを使用しましょう。 水性ペンや消せるボールペンは雨などで滲んだり、摩擦で消えたりする可能性があるため避けるべきです。
また、サインペンやマジックはインクが裏写りしたり、文字が太すぎて読みにくくなったりすることがあるため不向きです。ボールペンの太さは0.7mm~1.0mm程度が見やすくおすすめです。
2. 読みやすい丁寧な字を心がける
封筒の文字に限らず、就活関連の書類はすべて丁寧な字で書くことを心がけましょう。字の上手い下手よりも、一字一字心を込めて丁寧に書かれているかどうかが重要です。
採用担当者は多くの書類に目を通すため、読みにくい文字や雑な印象を与える文字はマイナスイメージにつながりかねません。時間をかけて、ゆっくりと正確に記入しましょう。
3. 封筒ののり付けはスティックのりが基本
封筒を閉じる際は、液体のりや両面テープ、スティックのりを使用します。中でもスティックのりは、シワになりにくく綺麗に仕上がるためおすすめです。 液体のりはつけすぎると封筒が波打ったり、はみ出して汚れたりする可能性があるので注意が必要です。
両面テープも綺麗に貼れますが、粘着力が強いものは一度貼ると剥がしにくいことがあります。セロハンテープでの封緘は見た目が悪く、ビジネスマナーとして不適切なので避けましょう。
郵送前に確認!就活封筒の最終チェックリスト
書類をポストに投函する前に、もう一度最終確認をしましょう。うっかりミスで選考のチャンスを逃すことがないよう、以下の項目を一つひとつチェックしてください。このひと手間が、あなたの就活をサポートします。
1. 宛先・差出人情報に誤りはないか
企業の郵便番号、住所、会社名、部署名、担当者名(敬称含む)に間違いや省略がないか、再度確認しましょう。同様に、自分の郵便番号、住所、氏名、大学・学部・学科名も正確に記載されているかチェックします。 特に会社名は「株式会社」の位置(前株か後株か)や、「様」と「御中」の使い分けは間違えやすいポイントです。
2. 「応募書類在中」の記載は完璧か
封筒の表面左下に、赤色のペンで「応募書類在中」と記載し、定規などを使って四角い枠で囲んでいるか確認しましょう。 この記載は、企業側が重要な書類であると一目で認識するために非常に重要です。 スタンプを使用した場合も、インクがかすれていないか、曲がっていないかなどをチェックしてください。
3. 切手の料金と貼り方は適切か
郵送物の重さに応じた正しい金額の切手を貼っているか確認しましょう。料金が不足していると、企業に届かなかったり、企業側が不足分を支払うことになったりして大変失礼です。 不安な場合は、郵便局の窓口で計測してもらうのが最も確実です。 切手は封筒の表面左上に、曲がったり剥がれたりしないようにしっかりと貼りましょう。
4. 書類の入れ忘れ・順番は大丈夫か
送付状、履歴書、エントリーシートなど、企業から指示された書類がすべて揃っているか、クリアファイルに入っているか、そして正しい順番で入っているかを確認します。 特に指定書類の漏れは選考に大きく影響する可能性があるため、細心の注意を払いましょう。 提出前に募集要項を再確認することも大切です。
5. 封はしっかりされているか
封筒ののり付けが剥がれていないか、しっかりと封がされているかを確認しましょう。郵送中に封が開いてしまうと、中の書類が紛失したり、汚損したりする可能性があります。 のり付け後、封じ目の中央に「〆」マークを記入したかも忘れずにチェックしてください。
就活の郵送封筒に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、就活の郵送封筒に関して学生からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。細かな疑問点を解消し、自信を持って郵送準備を進めましょう。知っておくと役立つ情報ばかりなので、ぜひ参考にしてください。
1. 角形2号以外の封筒ではダメ?
就活書類の郵送には、A4サイズの書類を折らずに入れられる角形2号の封筒を使用するのが絶対的なマナーです。 これより小さい封筒で書類を折って送付すると、採用担当者に手間をかけさせ、配慮が足りないという印象を与えかねません。
角形2号の封筒はコンビニや100円ショップでも手軽に入手できますので、必ず用意しましょう。
2. 字が下手でも選考に影響する?
字の上手い下手そのものが直接的に選考結果を左右することは少ないですが、雑に書かれた文字は「丁寧さに欠ける」「志望度が低いのでは」といったマイナスな印象を与える可能性があります。
大切なのは、上手さよりも丁寧に書こうとする姿勢です。一字一字心を込めて、読みやすい文字を心がけることが重要です。どうしても気になる場合は、ペン習字などで練習するのも良いでしょう。
3. のり付けはセロハンテープでも良い?
封筒ののり付けにセロハンテープを使用するのは避けましょう。セロハンテープは剥がれやすく、見た目も安っぽいため、ビジネスマナーとして不適切とされています。
スティックのりや両面テープ、液体のりを使用するのが基本です。特にスティックのりはシワになりにくく、綺麗に仕上がるためおすすめです。液体のりを使用する場合は、つけすぎに注意しましょう。
4. 封をした後に開封してしまったら?
書類の入れ忘れや書き損じに気づき、一度封をした封筒を開封してしまった場合は、その封筒は使用せず、新しい封筒に書き直して再封入するのがマナーです。
開封した跡が残っている封筒は見た目が悪く、雑な印象を与えてしまいます。手間はかかりますが、新しい封筒を用意して、気持ちよく提出できるようにしましょう。
5. 茶封筒は絶対に使ってはいけない?
就活の応募書類を送る際には、白色の封筒を使用するのが一般的であり、最も丁寧な印象を与えます。茶封筒は事務的な用途で使われることが多く、重要な書類を送る就活の場面では、白色の封筒が無難であり、避けるべきとされています。
どうしても白色の封筒が手に入らないといった特別な事情がない限り、白色を選びましょう。
6. 縦書きではなく横書き封筒はあり?
就活の応募書類を送る場合、一般的には縦書きの和封筒を使用します。企業によっては横書きの封筒でも受け付けてくれる場合もありますが、特に指定がない限りは、伝統的でフォーマルな印象のある縦書きの和封筒を選ぶのが無難です。 宛名や差出人の書き方も縦書きが基本となります。
7. 郵送の締切は必着?消印有効?
郵送の締切には「必着」と「消印有効」の2種類があります。「必着」は、その期日までに企業に書類が到着している必要があることを意味します。「消印有効」は、その期日までに郵便局で受付印(消印)が押されていれば良いという意味です。 どちらの指定かしっかり確認し、締切に余裕をもって郵送しましょう。特に「必着」の場合は配達日数も考慮する必要があります。
8. 手渡しする場合の封筒マナーは?
会社説明会や面接などで応募書類を直接手渡しする場合も、封筒に入れて持参するのがマナーです。この際、封筒の表面に宛名は書かず、左下に赤字で「応募書類在中」と記載します。
裏面には自分の住所・氏名・大学名などを記載します。 手渡しの場合、封筒の封はせず、すぐに書類を取り出せる状態にしておくのが一般的です。 担当者に渡す直前に封筒からクリアファイルごと取り出し、封筒の上に重ねて両手で渡しましょう。
9. 書き間違えたら修正液を使っても平気?
封筒の宛名書きなどで書き間違えてしまった場合、修正液や修正テープを使用するのは絶対に避けましょう。 公的な書類やビジネス文書において修正液などを使用するのはマナー違反とされています。
間違えてしまった場合は、手間でも新しい封筒に一から書き直すのが鉄則です。予備の封筒をいくつか用意しておくと安心です。
10. 郵送事故で書類が届かない場合は?
万が一、郵送事故で書類が企業に届かない、または大幅に遅延する可能性もゼロではありません。このような事態を避けるため、また万が一の際に追跡できるように、「特定記録郵便」や「簡易書留」といった記録が残る方法で郵送することを検討しましょう。
もし締切日を過ぎても到着確認ができない場合は、正直に企業に連絡し、指示を仰ぐのが賢明です。
就活の封筒マナーを押さえて好印象を目指そう
就活における書類の郵送は、企業との最初の接点となることもあり、封筒の選び方や書き方といったマナーは非常に重要です。
本記事で解説したポイントを一つひとつ確認し、丁寧な準備を心がけることで、採用担当者に良い印象を与え、自信を持って就職活動を進めることができるでしょう。これらの郵送マナーは社会人になってからも役立つ知識ですので、ぜひこの機会にしっかりと身につけてください。

